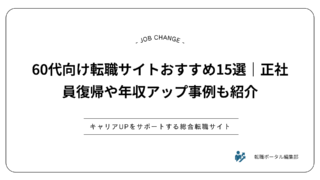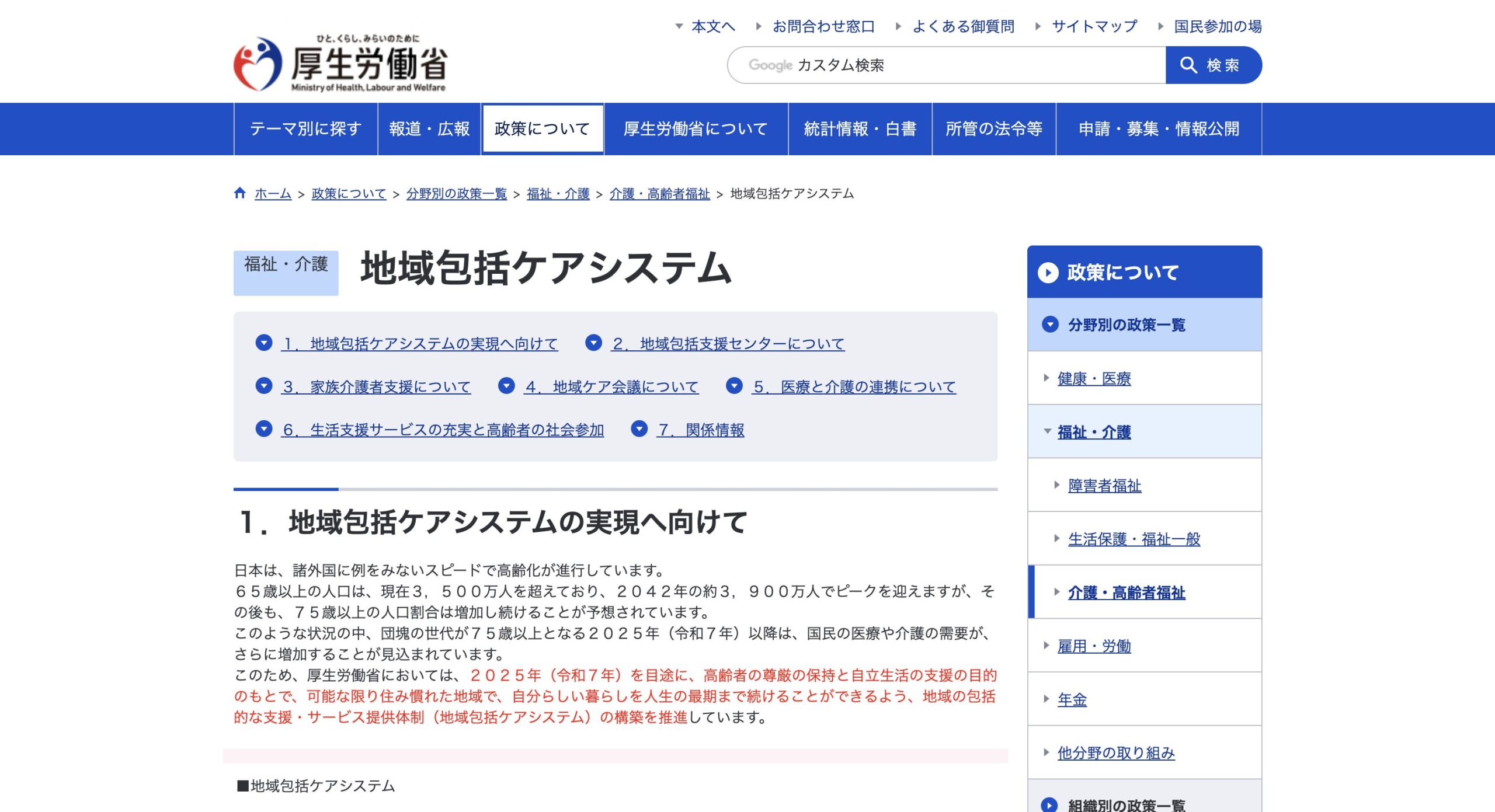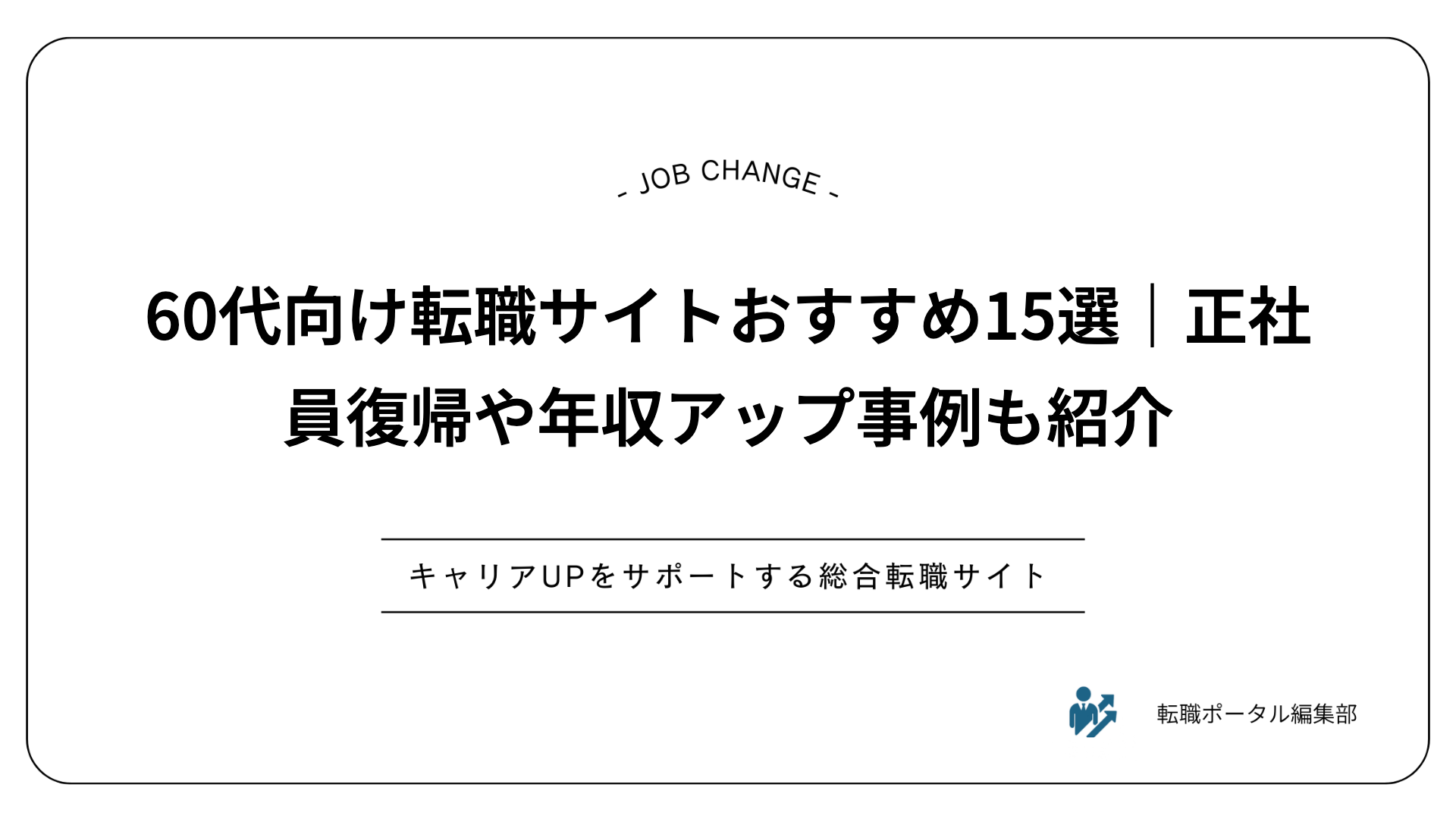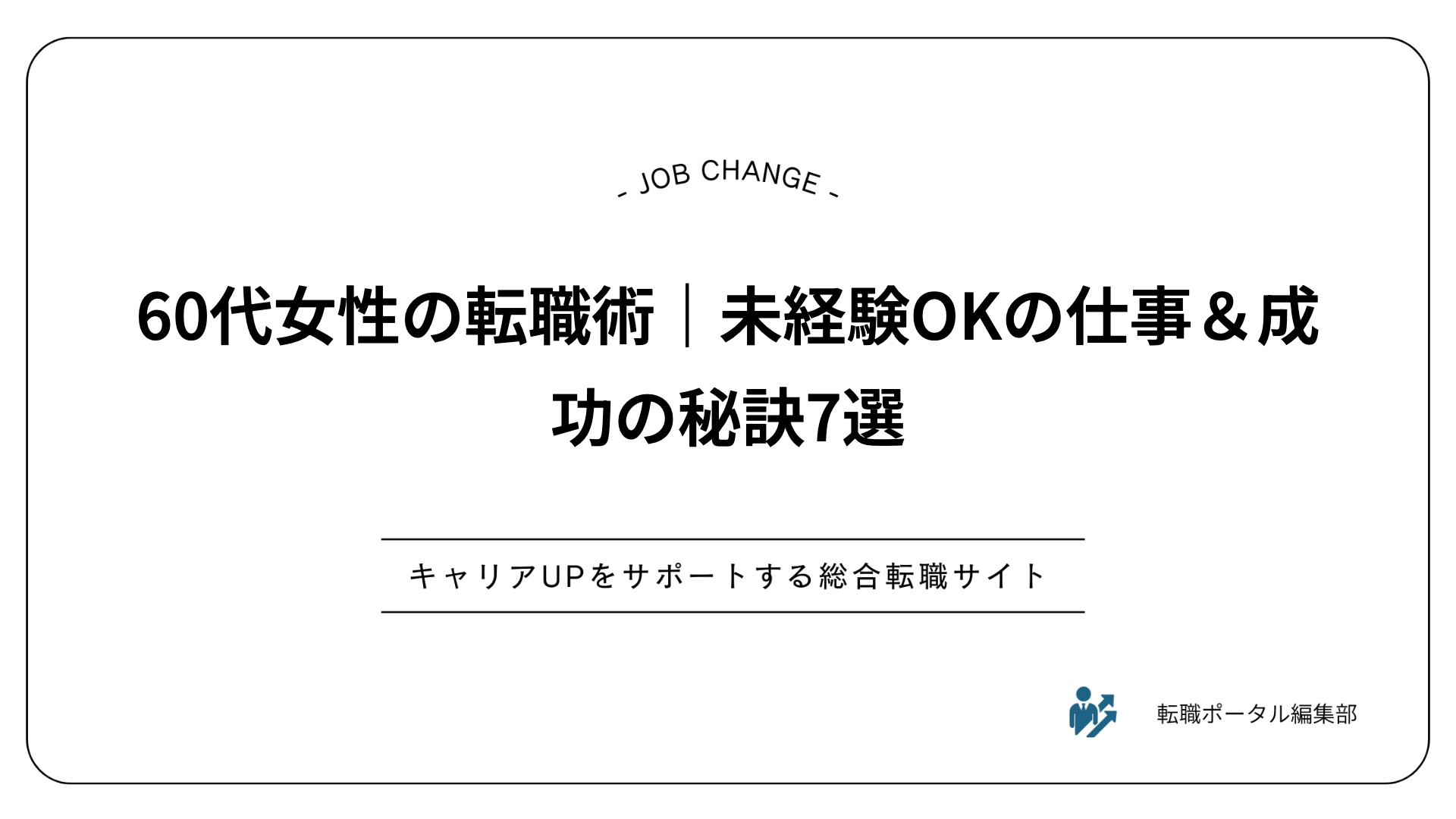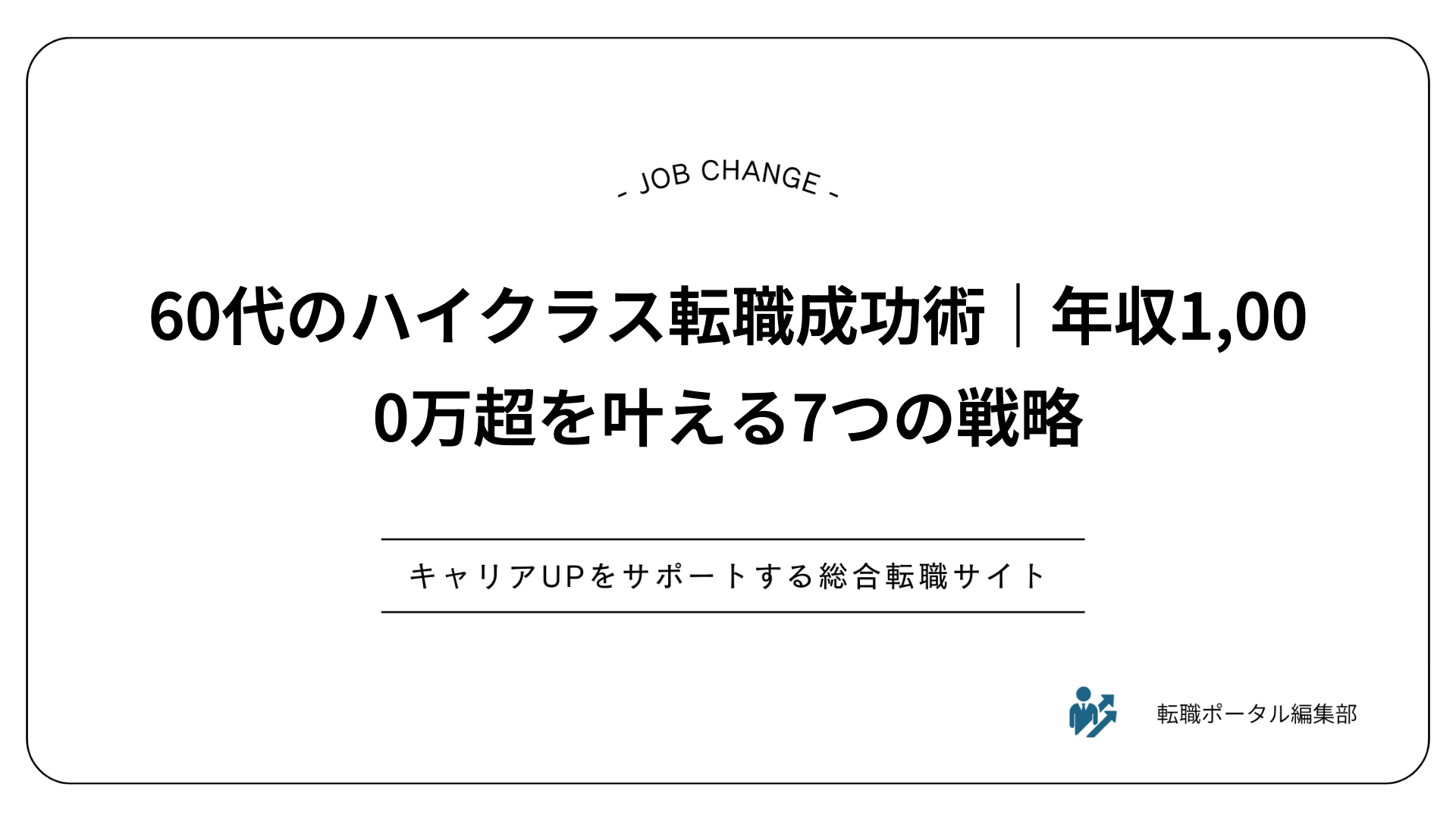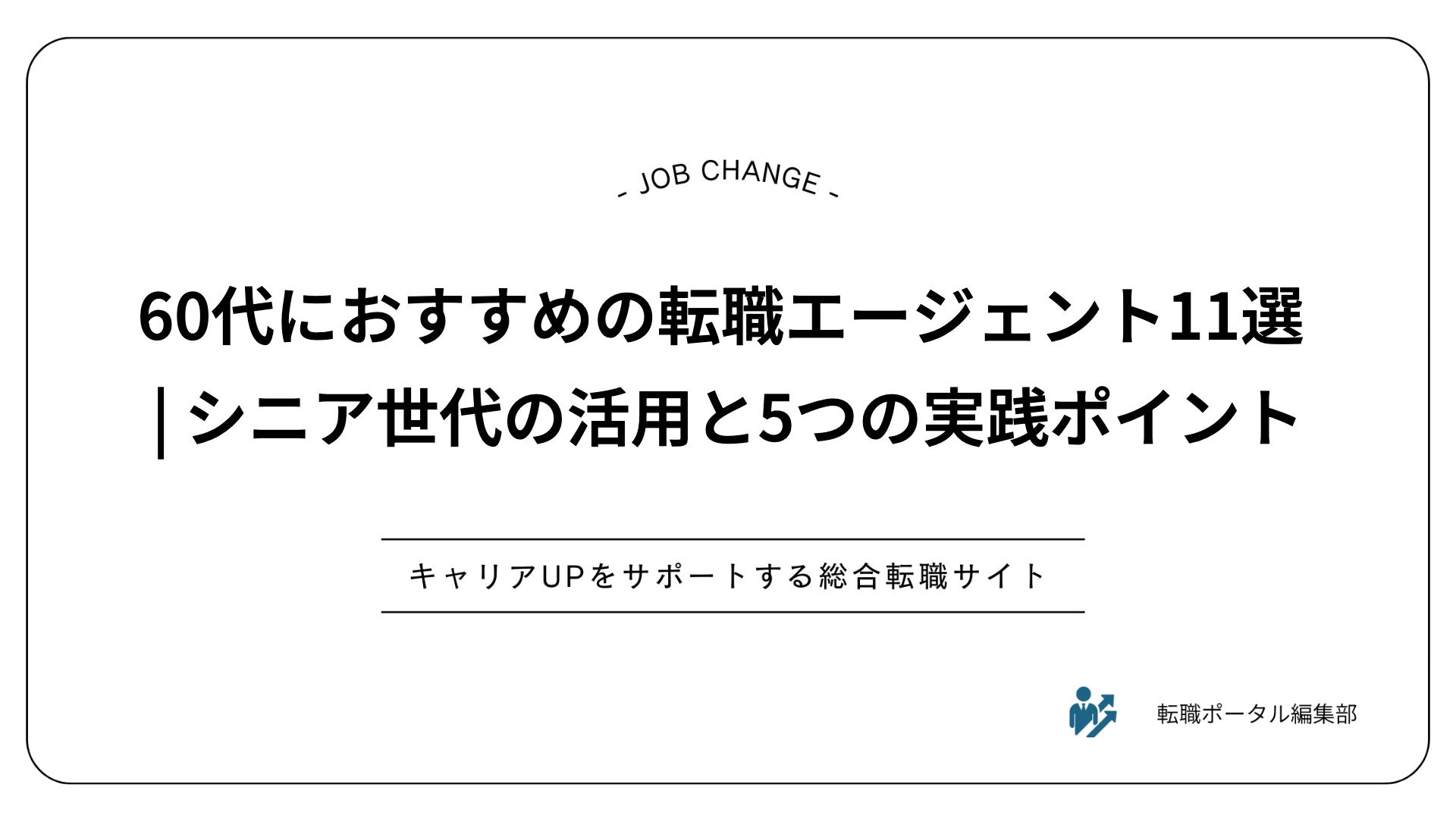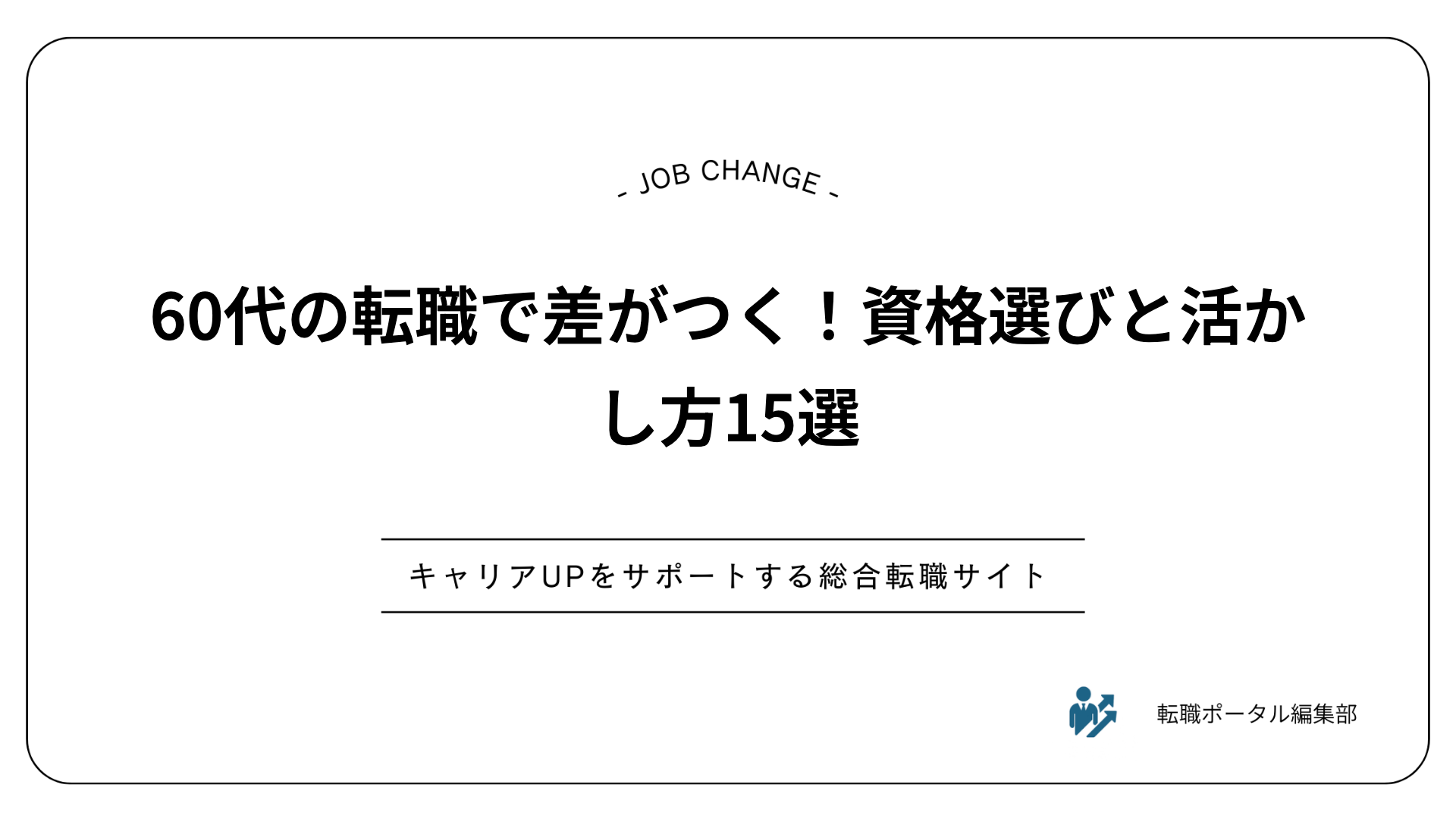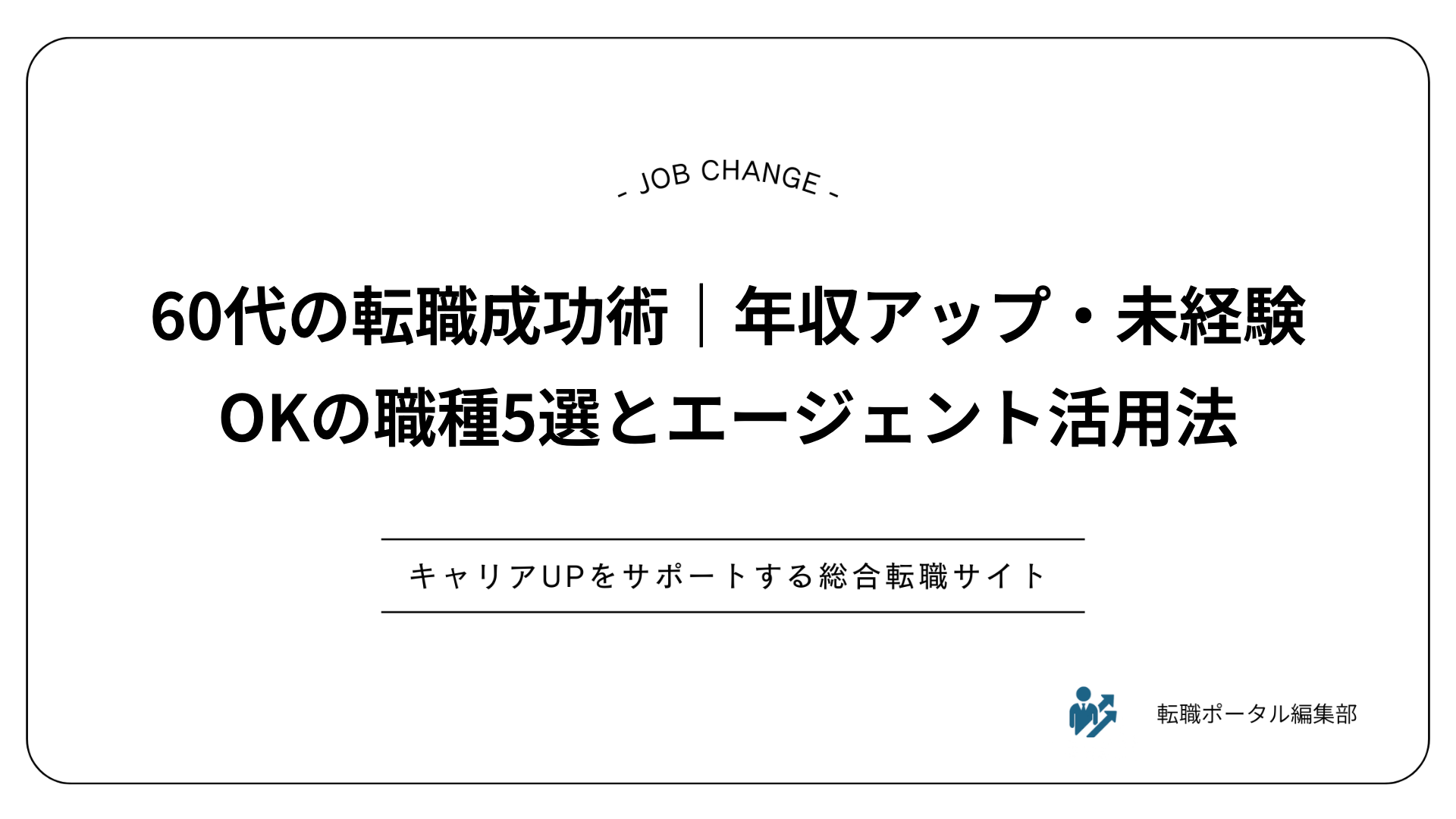60代転職の現実と成功法|年収ダウンを防ぐ11の戦略
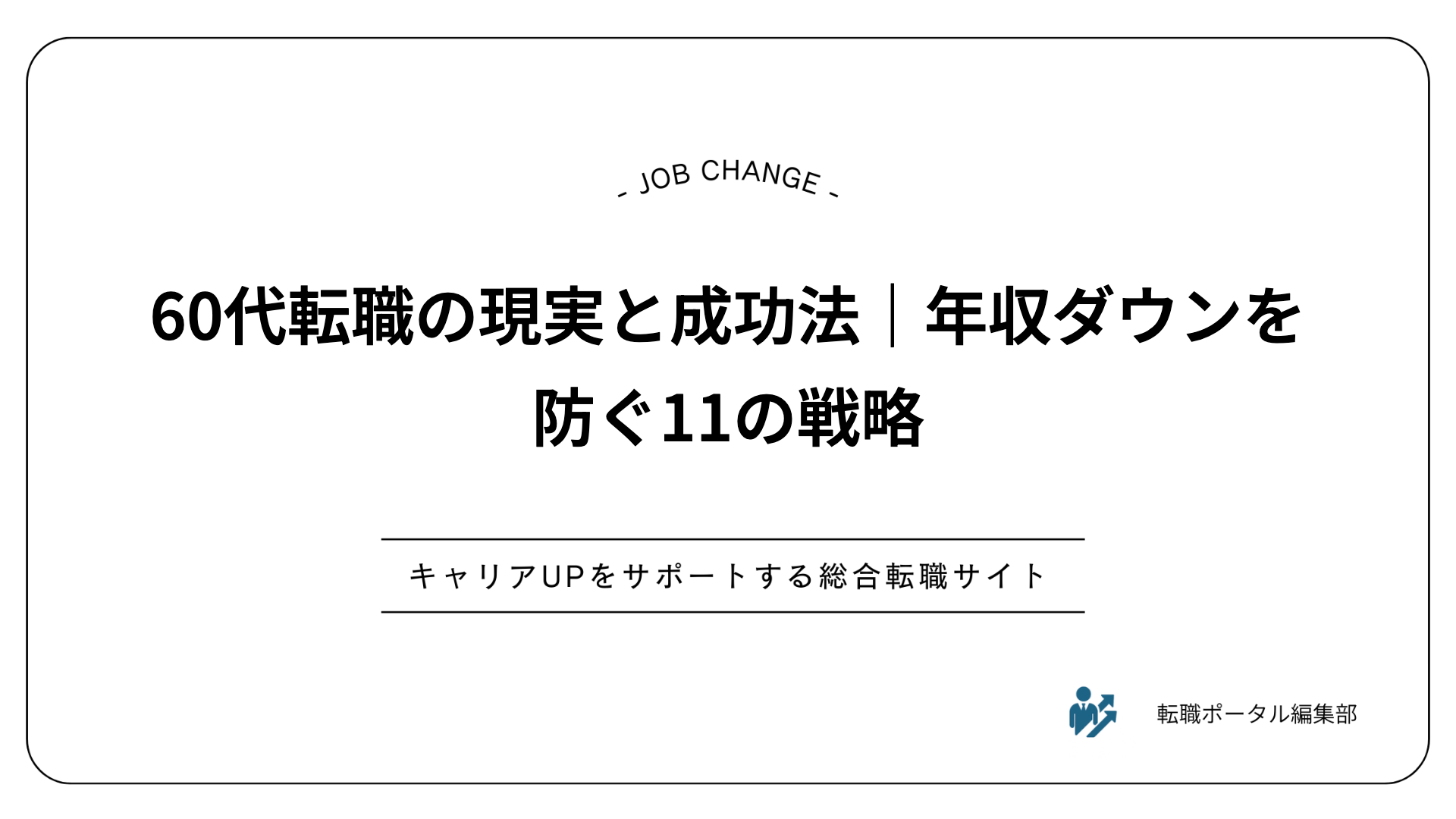
「60代での転職って本当にできるの?」
「年収がガクッと下がるって聞いたけど生活は大丈夫?」そんな不安を感じていませんか?
実際、60代の転職市場は若い世代とは大きく異なり、求人の内容や採用基準、年収水準にも現実的なギャップがあります。
しかし、しっかりと情報を集めて戦略的に動けば、納得のいく仕事と働き方を見つけることは十分に可能です。
この記事では、以下のような疑問に答えながら、60代の転職を現実的かつ前向きに進める方法を解説しています。
- 60代で採用されやすい仕事や業界は?
- 年収を下げずに転職するにはどうすればいい?
- 再雇用や副業など、他の働き方との違いは?
- 実際に成功した人はどうやって動いたの?
- 税金や年金への影響はどうなる?
60代だからこそできる仕事や選択肢を知って、自分らしいセカンドキャリアを築いていきましょう。
転職市場の現実と動向(60代)
最新統計で見る求人数と採用率

60代の転職市場は、数値で見るとその厳しさが明確になります。
厚生労働省の「高年齢者雇用状況報告」では、60歳以上を雇用する企業は増加していますが、正社員採用や長期的なキャリア形成の機会は限られています。
- 有効求人倍率は全体平均よりも低水準
- 雇用形態の大半が非正規で、正社員登用はごく一部
- 形式上の年齢制限撤廃と、実態とのギャップが存在
「求人数はあるが、希望条件に合う職は少ない」と感じる背景には、こうした数字の裏付けがあります。
まずは、現実を正確に捉えることが、戦略的な転職活動の第一歩です。
高年齢者雇用安定法の影響と年齢制限撤廃の流れ
2021年の改正で「70歳までの就業機会の確保」が企業の努力義務となりました。
この法改正はシニア層の就業促進を目的としていますが、現場ではまだ「年齢による選別」が根強く残っています。
特に民間企業では、即戦力や若手育成とのバランスを理由に、60代以上の採用に慎重なケースが多いのが実情です。
たとえば書類選考では、若年層に比べて明らかに通過率が低く、仕事内容も選択肢が限られる傾向があります。
一方で、制度を活用して採用されたケースも増えており、「どう活用するか」が大きな分かれ目になっています。
60代が直面する代表的な課題

60代の転職で直面する課題には、体力・スキル・評価基準といった側面が複雑に絡み合っています。
- 健康面の不安や体力の限界
- ITスキルや最新業務知識の不足
- 採用時に年齢を理由とした無意識のバイアス
これらの課題は、戦略的に準備することで克服できるものも少なくありません。
「無理かもしれない」ではなく、「どう備えるか」という視点が重要になります。
転職を考える主な理由と背景
定年後の収入維持と年金不足
60代で転職を検討する方の多くが、年金だけでは生活が厳しいという不安を抱えています。
公的年金の受給開始年齢が原則65歳になった現在、60〜64歳の間には収入の空白期間が生まれがちです。
この「収入の谷間」を埋めるために、働き続ける必要性を感じる人が増えています。
- 年金支給額だけでは生活費が足りない
- 住宅ローンや子の教育費が残っている
- 老後資金を貯めるための就労継続
年金制度だけに依存せず、自力で収入を得る手段として「転職」は現実的な選択肢のひとつです。
「本当に今から働き口が見つかるのか…?」という不安があっても、行動すれば道は開けます。
役職定年や給与ダウンへの対策
多くの企業では50代後半から60歳前後にかけて「役職定年制度」が適用され、これにより給与が大幅に下がるケースが少なくありません。
たとえば、部長職から一担当者へ降格となり、責任は軽くなる一方で、報酬も30〜50%減となる事例もあります。
この現実を前にして「このまま社内に残るより、別の道を探したい」と感じる人が増加しています。
転職によって再びキャリアを活かせるポジションに就いたり、条件の良い再雇用先を見つけたりする動きも活発です。
年収ダウンを黙って受け入れるのではなく、「再スタート」の選択肢を持つことが老後の安心につながります。
健康・働き方の見直しニーズ

60代になると、体力面や健康への意識が大きく変化します。
「通勤が辛い」「長時間勤務が続けられない」「ストレスの少ない仕事をしたい」といった理由から、より自分に合った働き方を求める人が多くなります。
- 週3〜4日勤務や短時間シフトへのニーズ
- 在宅や地域限定の働き方を希望
- 自身の生活リズムを重視した職場選び
このような変化に対応するためには、「自分の健康状態と相談しながら選べる仕事」を探す視点が欠かせません。
働くことが「負担」になるのではなく、「生活の一部」として継続できる環境を整えることが大切です。
社会貢献ややりがいを求めるケース
60代の転職理由には、収入目的だけでなく「人生の最終ステージに意味ある仕事をしたい」という思いも多く見られます。
退職後、地域活動や福祉分野に関わる仕事に就いたり、後進育成やNPO活動に従事したりする人も増えています。
これらは「金銭報酬」よりも「やりがい」や「感謝」に価値を見出す働き方です。
人生100年時代、セカンドキャリアとして「社会とのつながり」を重視する働き方は、精神的な充実にもつながります。
「仕事=お金」の枠を超えた転職理由があることも、60代ならではの特徴です。
介護・ライフスタイルの変化に対応

60代になると、親の介護や配偶者の病気、自身の健康など、家庭環境が大きく変化する時期でもあります。
これまでのようにフルタイム勤務が難しくなったり、勤務地の柔軟性が求められるようになるケースも多いです。
- 親の介護でフルタイム勤務が困難になった
- 配偶者との生活リズムに合わせた働き方を希望
- 自宅近くやリモートワークの仕事を探している
こうした背景から、柔軟なシフト制や短時間勤務、在宅勤務などを条件とする求人に関心が集まっています。
転職先を選ぶ際は「仕事内容」だけでなく、「働き方の自由度」にも注目することが重要です。
年収変化の現実と防ぐための戦略
シニア求人の給与帯と職種別モデル
60代の転職では、年収が大きく下がる傾向にあるのが現実です。
厚生労働省のデータによると、60〜64歳の平均年収は約330万円、65歳以上では約270万円程度にまで下がります。
特に非正規雇用では、時給1,000〜1,200円台の仕事が主流となり、月収15万円を下回ることも少なくありません。
- 警備・清掃・介護:月収12〜18万円が相場
- 事務・販売補助:時給1,100円前後
- 管理職経験者の再就職:契約社員で年収300〜450万円
年収水準は「前職の経験・スキル」と「職種の人手不足度」に強く左右されます。
希望年収を保ちたい場合は、自分のキャリアが評価される職種を狙う必要があります。
実績・スキルを評価させる交渉術
60代の転職では、年齢だけで判断されないためにも「実績やスキルをどう伝えるか」が重要になります。
特に中小企業やベンチャー企業では、即戦力や実務経験に価値を見出す傾向が強いため、過去の成果を「数字」と「事例」で明示することが効果的です。
- 売上やコスト削減などの定量的成果を具体的に示す
- マネジメント経験や部下育成の成果を事例で語る
- 業務改善やプロジェクト推進などの役割を強調する
また、面接時の言葉遣いや態度も評価対象になります。
柔軟性・謙虚さ・成長意欲を見せることで「扱いやすいシニア」という印象を与えることができ、採用確度も高まります。
「どうしても年齢がネックになるのでは…?」という不安を、実績と姿勢で覆すことができるのです。
再雇用・独立・副業との収入比較

60代の収入維持には、「再雇用」「独立」「副業」など複数の選択肢があります。
それぞれの特徴と収入目安を比較しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
- 再雇用制度:月給20〜25万円前後、役職なし・昇給なしが多い
- 独立・顧問契約:実力次第で年収300〜800万円も可能だが、不安定さも伴う
- 副業・在宅ワーク:月数万円の収入を積み重ねるタイプが主流
再雇用は安定を求める方向け、独立は人脈やスキルが強みの方向け、副業は時間を調整しながら働きたい人向けです。
「収入+やりがい+生活スタイル」の3点から総合的に判断することが、満足のいく働き方選びにつながります。
向いている仕事・業界一覧
経験を生かすハイクラスポジション
60代でも過去のキャリアや専門性を活かせる「ハイクラスポジション」の求人は存在します。
特にマネジメントや技術職など、後進育成や顧問的な役割が期待される職種では、年齢よりも「経験値」が重視される傾向があります。
たとえば中小企業の事業再構築支援や、業務プロセスの最適化、人事・労務管理のアドバイスなどで活躍する事例も豊富です。
このようなポジションを目指す際には、求人サイトだけでなく「シニア特化型エージェント」や人脈を活用した直接応募が効果的です。
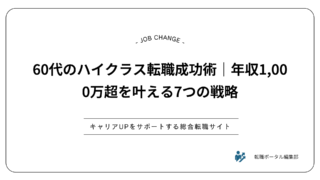
活用すべき「シニア特化エージェント」は以下の記事でまとめています↓

体力負担が少ないサービス・事務系

体力に不安がある方には、比較的負担の少ない仕事が人気です。
- マンション管理人や施設の受付
- データ入力・経理補助などの事務職
- 小売店の品出し・レジ対応(短時間勤務)
これらの仕事は未経験でも始めやすく、勤務日数や時間を柔軟に選べる求人も多いため、働き方の自由度を重視する方に向いています。
「体は無理なく、でも社会と関わり続けたい」というニーズを叶える手段として注目されています。
人手不足業界(介護・警備・清掃など)
慢性的な人手不足が続く業界では、60代以上の採用も積極的です。
- 介護職:初任者研修など資格取得支援が充実
- 警備:研修制度あり、未経験歓迎の求人が豊富
- 清掃:短時間・週2〜3日の勤務も可能
これらの業界は、働き手の確保が最優先課題のため、年齢よりも「やる気」「継続意欲」が重視される傾向があります。
「60代でも歓迎」と明記された求人が多く、選考時に年齢で不利を感じにくい点も魅力です。
在宅・リモートでできる仕事
近年では、60代でも在宅で働ける環境が整いつつあります。
特にコロナ以降、非対面型の業務に対応できるスキルを持つ人材へのニーズが高まりました。
データ入力、テープ起こし、文章の校正・添削、オンライン接客サポートなどが代表例です。
自宅で無理なく働きたい、通勤が困難という方には「在宅勤務可能」な求人を探すことが、新たな可能性を広げます。
成功までの準備ステップ
キャリア棚卸しと市場価値の確認

60代での転職成功には、自身の経験・スキルを冷静に見つめ直す「キャリアの棚卸し」が不可欠です。
過去の職務経歴を振り返り、どんな業務で成果を出したか、どんな役割を担ってきたかを具体的に整理しておきましょう。
- 経験職種・年数・実績を一覧化
- 得意分野と他者と差別化できる強みを言語化
- 市場での評価軸に合うスキルかをチェック
ミイダスなどの市場価値診断ツールを活用すれば、自分に合った職種やポジションの傾向も把握できます。
自分の価値を理解し、それを正しく相手に伝える準備が転職活動の基盤となります。
リスキリングと資格取得の方法
60代の転職では「学び直し=リスキリング」が成功率を左右します。
特に未経験職種への挑戦や、IT・介護・事務系の仕事を希望する場合は、最低限の資格やスキル証明が必要になるケースが多いです。
たとえば以下のような資格は、短期間かつ低コストで取得でき、60代でも評価されやすいです。
- 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
- 簿記3級・FP3級などの基礎資格
また、最近では「シニア向け職業訓練校」や「公共職業訓練」が全国で開講されており、無料または低額で受講可能です。
学び直しに遅すぎることはありません。「今からでもできること」に目を向ける姿勢が求められます。
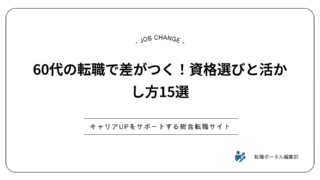
履歴書・職務経歴書ブラッシュアップ

採用担当者が最初に目にする書類だからこそ、「60代らしい強み」を明確に伝えることが大切です。
職務経歴書では単なる年表ではなく、職務ごとの成果や実績、得意領域を分かりやすく記載しましょう。
たとえば「営業」だけでなく「新規開拓に強みがあり、前年比120%の成果」「部下10名の育成を3年間担当」といった具体性があると説得力が増します。
また、履歴書には柔軟性や協調性、継続勤務への意欲も記載すると良いでしょう。
書類の印象で「堅い・古い」と思われないように、最新のフォーマットやPC作成の文書で整える工夫も必要です。
健康管理と働き方シミュレーション
60代以降の働き方では、健康状態が長期的な就労の可否を左右します。
- 定期的な健康診断を受ける
- 長時間勤務や夜勤が可能かを判断する
- 無理のない通勤・勤務日数を想定する
求人票だけでなく、職場見学や就労体験制度を活用し、実際の働き方をイメージしてみることも有効です。
「働けるか」ではなく「続けられるか」を基準に、無理のない働き方を設計していきましょう。
求人・転職サービスの賢い選び方
公的サービス(ハローワーク・シルバー人材など)
60代の転職活動では、民間サービスだけでなく公的機関の活用も非常に有効です。
- ハローワーク:地域密着型で職業相談・紹介・職業訓練などが無料
- シルバー人材センター:短期・単発・軽作業系の仕事を紹介
- 地域包括支援センター:介護職志望者への支援も対応
特にシルバー人材センターでは、「収入よりも社会参加を重視した働き方」が中心となっており、週2〜3回の無理のない勤務を希望する方に人気です。
「まずは少しだけ働きたい」「仕事を通じて健康を維持したい」といった方にとって、最初の一歩として活用しやすいのが特徴です。
シニア特化型転職エージェント活用術
60代の転職支援に特化したエージェントを活用することで、ミスマッチの少ない求人に出会える可能性が高まります。
一般的なエージェントと異なり、「シニアの希望条件や不安点」に寄り添ったサポートを受けられる点が大きな魅力です。
たとえば、FROM40やマイナビミドルシニアなどは、シニア向けの求人掲載に特化しており、非公開求人や独占案件も豊富です。
また、書類添削や模擬面接、就業後のフォローまで支援が手厚いため、「転職が初めてで不安」という方でも安心して利用できます。
年齢による書類落ちを防ぐためにも、プロのサポートを活用しましょう。
オンライン求人サイトとスカウトの使い分け
現在は、60代向けの求人もインターネットで簡単に検索・応募ができる時代です。
- ミドルシニア求人に特化した求人サイト
- スカウト機能で企業からの直接オファーを受けられるサービス
- 職歴・希望条件を登録するだけで自動的に求人を提案
スカウト型のサービスは、受け身で待ちながら複数社の反応を比較できるのが強みです。
反面、応募数が増えると情報管理や対応が煩雑になるため、自分のペースに合ったサービス選びが重要です。
おすすめの転職サイト・エージェントは以下の記事でも解説しているので参考にしてください↓

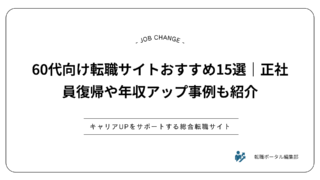
企業への直接応募と人脈活用

60代だからこそ活かせるのが「過去のつながり」や「前職での人脈」です。
かつての取引先や元上司、同僚からの紹介で再就職が決まったケースも多く、「信頼できる人物」として評価されやすいのが利点です。
また、中小企業では求人広告を出さずに直接応募を受け付けているケースもあるため、企業のホームページからの応募も一つの手です。
「求人が出ていないから諦める」のではなく、「自ら声をかけてみる」姿勢が、思わぬチャンスを引き寄せることもあります。
体験談に学ぶ成功・失敗事例
年収アップに成功したハイクラス転職
60代で年収アップを実現した成功例は、「専門性」と「即戦力性」を活かしたケースが中心です。
たとえば、大手メーカーを早期退職後、中小企業の技術顧問に転職した男性は、過去の開発経験と人脈を武器に、年収600万円超を実現しました。
また、営業職出身の女性がシニア層向け商材を扱う企業で顧客対応を任され、成果に応じてインセンティブが支給される仕組みにより前職より年収増となった事例もあります。
「年齢=不利」というイメージにとらわれず、自分の強みを活かせる職場に出会えたことが成功の要因です。
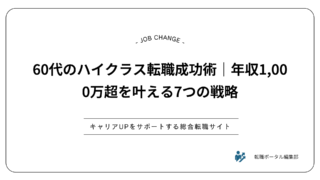
給与ダウンでも満足度が高い再雇用例
再雇用制度で年収は下がったものの、働きやすさや人間関係の良さから「働き続けてよかった」と感じる人も多くいます。
- 業務内容が負担なく、体に無理がかからない
- 人間関係が良好でストレスが少ない
- 通勤が短時間で家庭との両立がしやすい
「年収がすべてではない」という判断で、QOL(生活の質)を重視した選択は、精神的な満足度が高いのが特徴です。
ライフスタイルに合わせた働き方が実現できるかどうかが、再雇用を成功させる鍵になります。
書類通過率を高めたシニアの工夫

年齢を理由に書類選考が通らないと悩む方は多いですが、工夫次第で改善できます。
例えば、志望動機で「年齢による懸念」に先回りして触れ、「柔軟性があり、若手とも積極的に協働できる姿勢」をアピールしたことで、通過率が倍増したケースがあります。
また、職務経歴書での実績をグラフや箇条書きで整理することで、視覚的にわかりやすくなり評価された事例もあります。
「自分を魅力的に見せる工夫」を怠らないことが、60代の転職における書類通過の鍵です。
社会保険・税金のチェックポイント
再就職後の厚生年金と在職老齢年金
60代で再就職する場合、「厚生年金」と「在職老齢年金」の関係を正しく理解しておくことが重要です。
在職中でも年金を受給できるケースはありますが、給与や年金の合計額が一定の基準を超えると、年金が一部支給停止となる可能性があります。
- 60〜64歳:28万円を超えると支給額が減額される
- 65歳以上:47万円が基準となり、超過分に応じて減額
この制度は「働くほど損をする」と誤解されがちですが、長期的には厚生年金の受給額が増えるため、トータルで見ればプラスになるケースが多いです。
働く意欲があるなら「減額」を理由に機会を逃さないことが大切です。
雇用保険・失業給付の取り扱い

60代でも退職後の一定条件を満たせば、雇用保険の「基本手当(失業手当)」を受給することができます。
受給には以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
- 退職時に就労意思と能力がある
- 就職活動を継続していること
受給期間は最長で150日(自己都合退職)〜330日(会社都合退職)とされ、年齢によって加算もあります。
ただし、自己都合退職では待機期間が発生するため、ハローワークでの事前相談が重要です。
医療費・介護保険料への影響
再就職による収入増加は、住民税や介護保険料、医療費の自己負担割合にも影響を与える可能性があります。
特に65歳以降は、前年の所得に応じて医療費負担が1〜3割に変動し、高額療養費制度の上限額も増加する点に注意が必要です。
また、介護保険料も所得に連動して増加するため、想定より手取りが減るケースもあります。
収入と社会保険料・税金の関係は複雑なため、転職前にシミュレーションしておくことが安心につながります。
転職以外の働き方と選択肢
フリーランス・顧問・業務委託
近年、60代でフリーランスとして働く人が増えています。
特に「経験」や「人脈」が強みとなる顧問・コンサル型の働き方は、企業側にもニーズがあり、短時間・高単価での契約が可能です。
- 週2日稼働で月収20〜30万円の業務委託例
- 専門性が活かせる分野(法務・財務・開発支援など)に強み
- 定年後に元の会社や取引先と契約するパターンも多数
ただし、収入の安定性や社会保険の自己負担といったデメリットもあるため、生活設計とのバランスを見ながら進めましょう。
副業・兼業で収入を補う方法
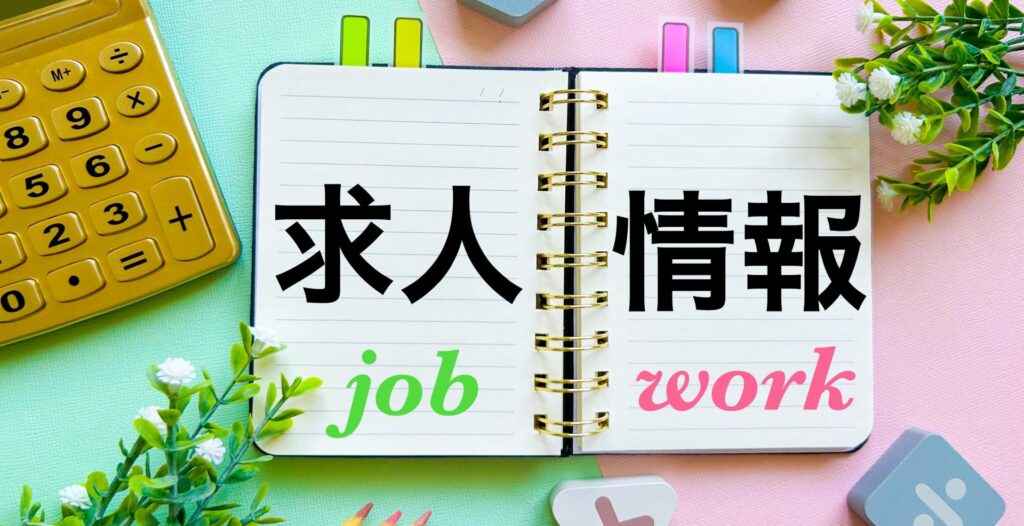
働き方の自由度が高まった今、「フルタイムではなく副業で収入を補う」という選択も現実的です。
具体的には、以下のような副業が60代からの挑戦として人気です。
- スキルシェア(文章添削、写真販売、通訳など)
- 配達・軽作業(Uber Eats、ポスティングなど)
- ハンドメイドやせどりなど在宅で完結する作業
月3万〜5万円の収入を目標とするなら、時間も体力も過度に使わずに継続できます。
「生活費をすべて稼ぐ」というよりは、「足りない分を補う」スタイルが無理なく続けるコツです。
現職での再雇用・嘱託制度活用
今の職場での再雇用や嘱託制度は、もっともスムーズに継続就業ができる選択肢です。
社内の業務内容や人間関係に慣れていることから、60歳以降の不安が少なく、引き続き働きたい人には向いています。
ただし、待遇は下がるケースが多く、以下のような制限もあります。
- 雇用は1年更新などの有期契約
- 昇給・賞与は対象外の場合が多い
- 仕事内容が大幅に変更されることもある
制度の内容は企業によって異なるため、事前に確認し、希望と合致するかどうかを見極めることが大切です。
成功へ導くチェックリスト
応募前に確認したい5項目
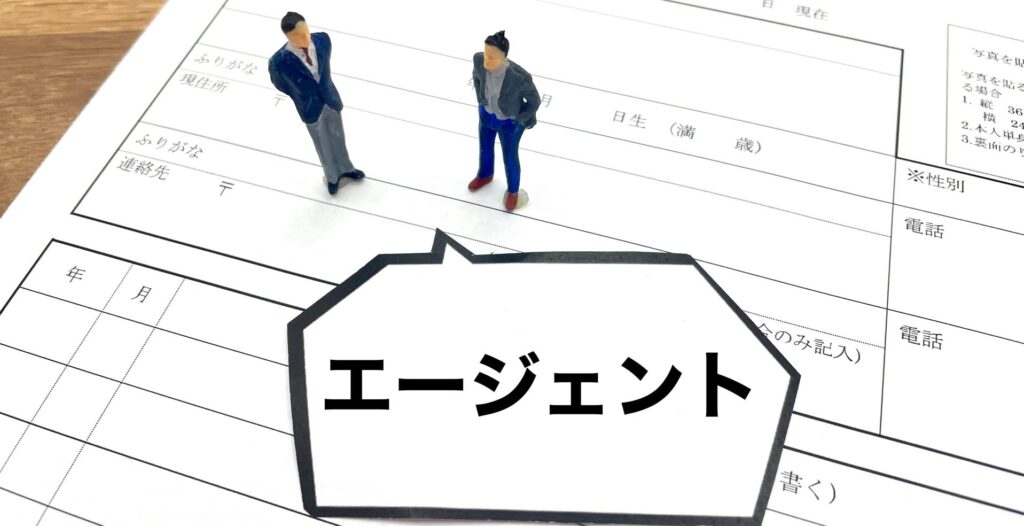
60代での転職を成功させるには、「応募前の確認作業」が何より重要です。
応募書類を送る前に、以下の5項目を自問してみましょう。
- 希望条件と求人内容が一致しているか
- 勤務時間・場所・体力面に無理がないか
- 職場の年齢構成や雰囲気が合いそうか
- 長期的に働ける環境か
- 社会保険・給与体系の説明が明確か
「とにかく応募数を増やせばいい」という戦略は、シニア層には不向きです。
少数精鋭で、確度の高い応募を心がけましょう。
面接前後の最終確認ポイント
面接前後には、企業の姿勢や条件を見極めるためのチェックが欠かせません。
面接当日には以下の点に注目してみましょう。
- 年齢に対する偏見のない姿勢か
- 業務説明が具体的で曖昧でないか
- 想定外の業務を押しつけられそうか
また、面接後に感じた違和感は見逃さないこと。
たとえ内定が出ても、「続けられるかどうか」を基準に冷静に判断しましょう。
入社後3ヶ月の定着アクション
転職後の最初の3ヶ月は、「職場に馴染めるか」を左右する大事な期間です。
以下のような行動を意識すると、スムーズな定着につながります。
- 周囲と積極的に挨拶・コミュニケーションをとる
- 自分の役割を明確に理解し、責任を果たす
- 改善点や違和感をメモしておく(無理をしすぎない)
60代での新しい環境は不安もありますが、「聞く姿勢」「受け入れる柔軟さ」がある人は好印象を持たれやすいです。
「早く成果を出そう」と焦らず、まずは信頼を築くことが何よりのスタートです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 60代でも正社員になれますか?

可能性はゼロではありませんが、非常に限定的です。
多くの場合は契約社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用が中心になります。
ただし、専門職や管理職経験を活かした再就職では、正社員採用の可能性が残されている分野もあります。
「正社員でなければダメ」と考えず、柔軟な働き方を取り入れる視点が重要です。
Q2. 60代からの資格取得は意味がありますか?
はい、意味あります。
- 就きたい職種が資格を必要とする場合は必須
- 面接時に「意欲の証明」として評価されやすい
- 就労支援制度や補助金でコスト負担を抑えられる
特に介護・事務・IT関連などの実務系資格は、転職後にすぐに活かせることが多いため、年齢に関係なく効果的です。
Q3. 面接で年齢を理由に不採用になることはありますか?

表向きは年齢差別は禁じられていますが、実態としては年齢を理由にした選考が行われるケースも少なくありません。
そのため、面接時には「年齢=扱いづらい」という先入観を払拭するために、協調性・柔軟性・健康状態などを自分からアピールしておくことが有効です。
また、過去の職歴を謙虚に話す姿勢も評価されやすくなります。
Q4. 転職活動がうまくいかないときの対処法は?
60代は「量より質」が鍵になります。
- 応募先の条件と自分の強みのミスマッチを見直す
- 求人の探し方を「エージェント活用」や「人脈紹介」に広げる
- 応募書類や面接対策を専門家に添削してもらう
応募の数に一喜一憂せず、戦略的に「合う企業」を見極める視点が大切です。
Q5. 転職するタイミングで年金はどうなりますか?
就業状況や収入によって、在職老齢年金の支給が停止・減額されることがあります。
しかし、厚生年金への再加入により将来の受給額が増えるケースもあるため、単純に「損」とは言えません。
年金と収入の兼ね合いは複雑なので、年金事務所での事前相談が安心です。
まとめ:60代転職は現実を知り戦略で勝つ
60代での転職は、たしかに現実的な壁が多く存在します。
しかし、今は多様な働き方や支援制度が整備されつつあり、「準備」と「情報収集」次第で道は大きく拓けます。
本記事で紹介したように、60代転職の成功の鍵は以下の4点です。
- 市場の現実を知ったうえで自分に合った戦略を立てる
- 「年収」「働き方」「やりがい」のバランスを見極める
- 健康管理とスキルアップを並行して進める
- 信頼できる支援サービスを上手に活用する
年齢を理由に諦めるのではなく、「人生後半のキャリアをどう生きたいか」を見つめ直すことこそが、60代転職の第一歩です。
現実を直視しながらも、ポジティブな未来設計を描いて、納得のいくセカンドキャリアを実現していきましょう。
60代からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
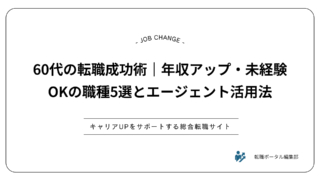
60代の転職におすすめのエージェント・サイトはこちら↓