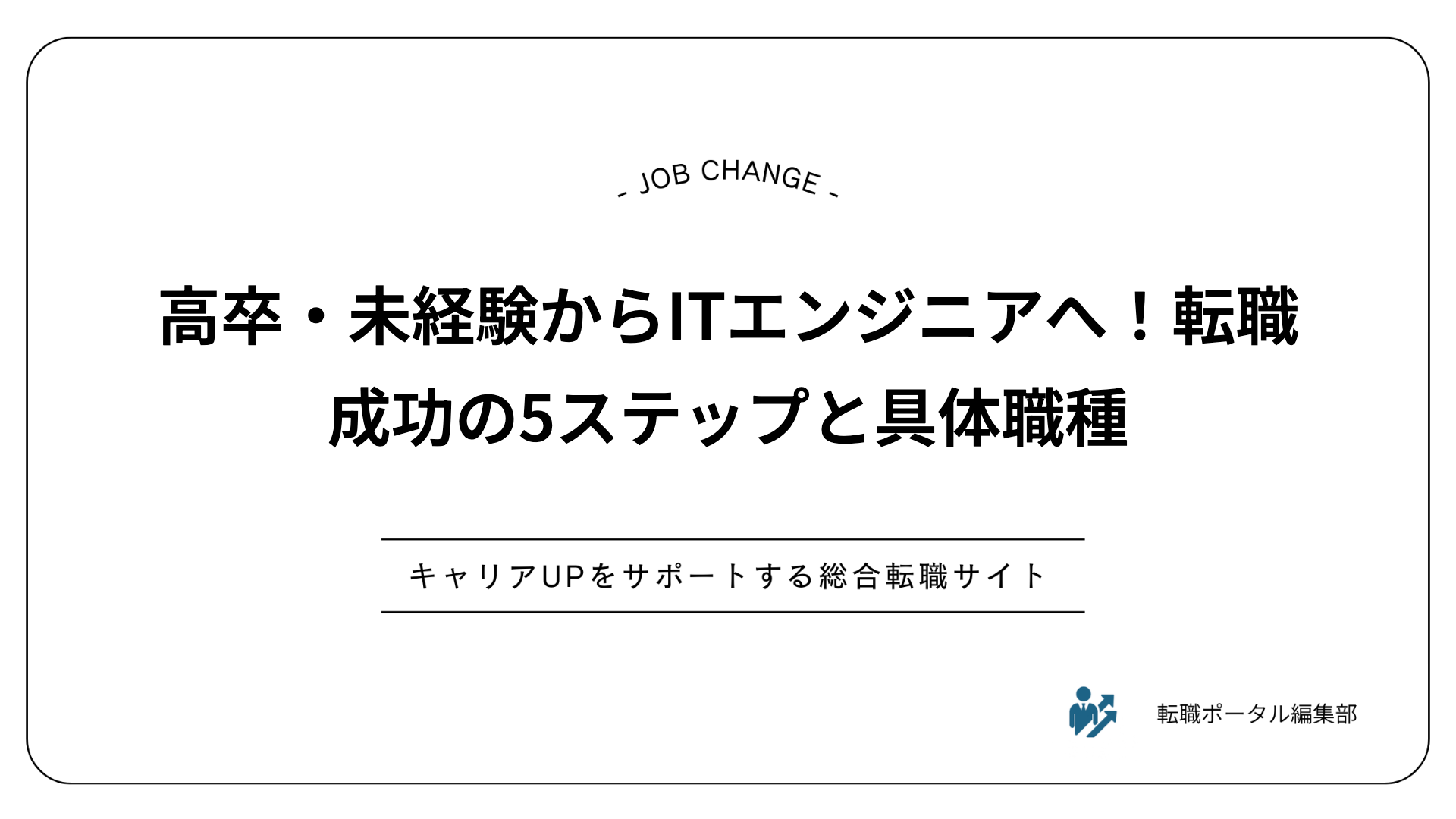エンジニア管理職への転職成功ガイド|年収相場・スキル・事例10選
「プレイヤーとしての限界を感じ始めている」「技術だけでキャリアを伸ばすのが不安」「でも管理職になるのは少し怖い」——そんな思いを抱えていませんか?
エンジニアとして経験を積んできたからこそ、次のステージとして“管理職”という選択肢が視野に入るのは自然なことです。
しかし一方で、マネジメントに必要なスキルや適性、転職市場での評価ポイントなど、わからないことが多くて踏み出せない人も多いはず。
この記事では、エンジニアが管理職へとキャリアチェンジする際に必要な情報を網羅的に整理しています。
- スペシャリストと管理職の違い・判断軸
- 最新の転職市場動向と年収相場
- 管理職に必要なスキルと行動例
- 成功事例・未経験からのステップアップ方法
- 転職エージェント活用や資格・学習法まで
「自分にマネジメントが向いているのか?」「転職するならどんな準備が必要か?」という疑問を、この記事を読むことでクリアにできるはずです。
エンジニア管理職とは何か?役割とキャリアパスの全体像
技術スペシャリストと管理職の違いを明確に理解する
エンジニアとしてのキャリアを積むなかで、多くの人が「スペシャリスト」か「管理職」かという分岐点に立ちます。
この2つは同じ技術領域にいながらも、果たす役割や求められるスキル、成果の評価軸が根本的に異なります。
- 技術スペシャリスト:技術の深掘りやアーキテクチャ設計、課題解決に集中
- 管理職:チームの成果最大化や人材育成、プロジェクト推進などを担う
- 評価軸の違い:前者は「技術成果」、後者は「組織成果」が基準
例えばスペシャリストは、「設計が正しいか」「コードの品質が高いか」といった観点で評価されます。一方、管理職は「チームでプロジェクトを成功に導いたか」「育成・連携に貢献したか」が重視されます。
どちらが優れているという話ではなく、自身の志向や価値観、将来の目標に沿って選ぶべき選択肢です。
「マネジメントに向いているのか?」と悩む方は、この違いを知ることで、自分に合った方向性が見えてくるでしょう。
管理職が企業に求められる背景と期待される成果
管理職が企業から求められるようになった背景には、チーム開発の拡大と技術の複雑化があります。
かつては一人のエンジニアが設計から運用まで担当することもありましたが、今では役割が細分化され、調整力と推進力を持つマネージャーの存在が欠かせません。
企業が期待する管理職の成果には、以下のようなものがあります。
- ビジネス要件を技術言語に翻訳し、現場に落とし込む
- リソース配分・スケジュール調整による進捗管理
- メンバーのモチベーションを維持し、離職率を下げる
実際、10名以上の開発チームになると、調整力や対人能力がチームの成果に直結します。放任主義ではプロジェクトは進まず、逆に過干渉でもメンバーの自立心を奪ってしまいます。
そのバランスを見極め、チームに最適な「環境づくり」を行うことが、現代のエンジニア管理職に求められるミッションです。
エンジニアが管理職を目指すメリットとデメリット
管理職というポジションには、大きなチャンスと同時に特有の負担がついてきます。
たとえば収入や発言権が上がる一方で、コードを書く時間は減り、業務のストレスは増える傾向にあります。
- 年収が上がる、昇進の機会が広がる
- 事業に深く関わり、意思決定に参加できる
- マネジメント経験が将来の転職市場で武器になる
一方で、「人を動かす」立場になることで対人ストレスが増し、技術的な最前線から離れてしまう懸念もあります。
たとえば、「今後もコードを書き続けたい」「自分の手でシステムを作りたい」と思っている人にとっては、管理職になることがキャリア満足度を下げる要因になりかねません。
重要なのは、自分の価値観と照らし合わせて判断することです。肩書きや収入だけで選ぶのではなく、「何を実現したいのか」にフォーカスすべきでしょう。
転職市場の最新動向と年収相場
需要が高い業界・職種と求人の探し方
近年、エンジニア管理職のニーズは急速に高まっています。
結論から言うと、特に以下の業界でエンジニア管理職の求人が活発です。
- 自社プロダクトを持つSaaS企業
- DXを推進する大企業のIT部門
- 開発体制を内製化するスタートアップ
その背景には「開発組織の拡大」と「技術内製化の潮流」があります。外注から自社開発へと移行する企業が増える中、技術と組織の両方に精通した人材が強く求められているのです。
求人の探し方としては、以下の方法が有効です。
- ビズリーチやJACなどのエグゼクティブ向け転職サイトを活用
- 管理職ポジションに強い転職エージェントに登録
- LinkedInやX(旧Twitter)などSNSでのダイレクトスカウトに対応
特に年収1,000万円以上のポジションは、一般求人サイトには出回らず、非公開で水面下に動いているケースが多いため、信頼できる人材紹介会社とのつながりを持つことが鍵となります。
「求人が見つからない」と感じている方も、実は非公開求人にアクセスできていないだけかもしれません。
エンジニアリングマネージャー/EMの年収レンジと交渉ポイント
エンジニアリングマネージャー(EM)の年収は、企業規模や職務内容によって大きく異なりますが、一定の相場感を知っておくことは転職時に非常に重要です。
結論として、EMの年収レンジは以下のとおりです。
- スタートアップ:600万〜900万円
- メガベンチャー・SaaS企業:800万〜1,200万円
- 外資系・大手上場企業:1,200万〜1,800万円以上
給与水準は、担当するエンジニア数や管理の範囲(ピープルマネジメントかプロジェクトマネジメントか)によっても変動します。また、報酬交渉の際には「技術力」ではなく「組織運営や成果創出力」を軸にアピールすることが重要です。
交渉ポイントとしては以下のような観点が挙げられます。
- 過去のチームサイズとマネジメント実績
- プロジェクトの成功例とその定量的成果(KPI、売上貢献など)
- エンジニアの定着率向上や育成施策の実施経験
企業は「この人に任せればチームが回る」という信頼を重視します。自己PRの際は、具体的な事実と数値を交えて提示することで、年収の上振れも十分に狙えます。
未経験から管理職候補で採用されるケースと条件
実務経験がない状態でも、管理職候補として採用される事例は確実に存在します。
その多くは、「将来の幹部人材を育てたい」という企業の長期的視点によるものであり、特に以下のような人物が歓迎されやすい傾向があります。
- リーダー経験はないが、業務改善提案や後輩指導の実績がある
- 論理的思考力・抽象化力に優れ、事業理解が早いタイプ
- IT以外の分野でマネジメントやプロジェクト推進経験がある
このような人材は「将来伸びる」「スケーラビリティがある」と評価され、現場リーダーからマネージャーへの昇格前提で採用されるケースも珍しくありません。
一方で、即戦力マネージャーではないため、採用されるポジションは「プレイングリーダー」や「チームリーダー見習い」からのスタートとなることが多いです。
未経験からでも十分に狙えるポジションですが、応募時には「なぜ自分が将来的にマネジメントに向いているのか」「どんな成長シナリオを描いているのか」を明確に伝えることが鍵になります。
管理職に求められるスキルセットと適性
テクニカルスキルのアップデートと“手を動かす”バランス
エンジニア出身の管理職にとって、「技術力を維持しながらチームを導く」というバランス感覚が非常に重要です。
現場から完全に離れてしまうと、技術的な意思決定に説得力を持たせにくくなります。一方で、自らがプレイヤーとして動きすぎると、本来のマネジメント業務が後回しになってしまう危険もあります。
たとえば、コードレビューには関わるが実装はメンバーに任せる、技術選定やアーキテクチャ設計には関与しつつ、手は動かさないといったスタンスが効果的です。
新しい技術のキャッチアップも継続し、自分自身が技術的に「信用できる存在」であり続けることが、チーム全体の技術レベルを底上げすることにもつながります。
マネジメントスキルとリーダーシップの具体的行動例
管理職には、スケジュール管理や進捗確認といったオペレーション面だけでなく、チームの心理的安全性やモチベーションにも配慮したマネジメントが求められます。
- 1on1ミーティングを活用してメンバーの悩みを拾う
- チーム内での成功体験や失敗を言語化して共有する
- 失敗を許容する文化をつくり、挑戦を後押しする
また、リーダーシップは「引っ張る力」ではなく「信頼される姿勢」から生まれます。自分が率先して行動し、困難な状況でも淡々と立ち向かう姿がメンバーの信頼を生むのです。
マネジメントは学習よりも実践がものを言う分野。大小問わず成功と失敗の経験を積み重ね、自分なりの“スタイル”を磨いていくことが重要です。
ビジネス視点・コミュニケーション力・意思決定力を高める方法
エンジニアとしては優秀でも、ビジネス視点が欠けていると管理職としては評価されにくいものです。マネジメント層には、収益構造や事業戦略に基づいた意思決定が求められます。
そのためには、数字に強くなることが第一歩です。PL(損益計算書)やKPIレポートを読む習慣をつけ、会議では収益・コスト・投資対効果といった言葉を自然に使えるようにしておきましょう。
さらに、組織の中で影響力を持つにはコミュニケーション力も不可欠です。論理的な説明、傾聴姿勢、ファシリテーション能力など、多方面のスキルが求められます。
これらの力は一朝一夕では身につきませんが、意識して場数を踏むことで着実に磨かれていきます。
転職成功までのステップと準備
自己分析でキャリアゴールを設定し成果を棚卸しする
管理職への転職を成功させるためには、まず「自分はどんなマネージャーになりたいのか」を明確にする必要があります。
キャリアゴールを設定する際は、以下の2つの観点で整理してみましょう。
- どんな組織や事業領域でマネジメントをしたいのか
- 自分の強みを活かせるチーム規模やフェーズはどこか
この方向性を明確にしたうえで、これまでの成果を「数字」「影響」「役割」に分けて棚卸ししておくと、応募書類や面接で説得力のあるアピールができます。
たとえば、「メンバー3名をリードし、6カ月間で開発スピードを20%向上させた」など、成果はできる限り定量化して表現しましょう。
職務経歴書・履歴書で実績とマネジメント経験を伝える書き方
管理職への転職では、単なる業務経験ではなく「どんなチームをどう導いたか」を明示することが重要です。
職務経歴書では、プロジェクトごとの役割・体制・成果に加えて、以下のような観点を盛り込むと高評価につながります。
- チーム構成(人数・スキル構成)と自身のポジション
- マネジメントした業務の範囲(採用、評価、予算など)
- 定量的成果(例:納期遵守率、売上向上、離職率改善など)
また、職務経歴書と合わせて「マネジメントスタイルの特徴」や「再現性のある行動」も伝えておくと、自分の人物像がより明確になります。
面接で評価される成果指標の提示と組織改善エピソード
管理職ポジションの面接では、「チームをどう動かし、どんな成果を出したか」が問われます。
重要なのは、単なる業務説明ではなく、成果を示す“数値”と“課題解決プロセス”を明確に語れることです。
たとえば以下のようなエピソードが高く評価されやすいです。
- リリース遅延が続いていたチームにアジャイルを導入し、平均納期を30%短縮
- 1on1とフィードバック制度を整備し、エンジニアの離職率を半年で半減
- 開発とビジネス部門の対立を改善し、社内プロジェクトのリードタイムを40%改善
これらはすべて「課題→取り組み→成果」のストーリー構成で語ると、面接官にも伝わりやすくなります。
特にEMやVPoEポジションでは、「成果を再現可能にする能力」が重視されるため、単発の成功よりも“再現性あるマネジメント手法”として語る視点が求められます。
タイプ別の転職事例とキャリアシナリオ
Web系スタートアップでEMに就いた事例
30代前半のAさんは、受託開発企業でリードエンジニアとして経験を積んだ後、自社開発スタートアップに転職。入社1年後にはエンジニアリングマネージャー(EM)としてチームを統括する立場に就任しました。
当初はプレイヤー業務との両立に苦戦しましたが、徐々に1on1を通じたチームビルディングと採用活動に注力し、開発スピードの安定化とエンジニアの定着率向上を実現。
事業成長に伴い組織が拡大する中で「技術と人の両輪を支える存在」として評価され、現在はCTO直下で全体設計と技術組織づくりに携わっています。
「成長環境に飛び込んで、求められる役割に柔軟に応じた結果、自然とキャリアが拓けた」と語っています。
大企業社内SEからIT戦略マネージャーへ昇格した事例
Bさんは40代前半。これまで10年以上にわたり、メーカー系大企業の情報システム部門で社内SEとして勤務していました。
業務改革プロジェクトで現場ヒアリングから要件定義、ベンダーコントロールまで主導した経験を買われ、グループ全体のIT戦略を担うマネージャーへと昇進。
「技術的な深さは限定的でも、業務プロセスの理解力と現場巻き込みのスキルが評価された」と本人は振り返ります。
現在は複数のプロジェクトを横断的にマネジメントし、社内DXの中心的存在として活躍中です。
メーカー系エンジニアが開発部門長にキャリアチェンジした事例
Cさんは30代後半。製造業のソフトウェア開発部門に在籍し、長年ハードと連動する組み込み系の開発を担当していました。
若手の育成や部門間調整を積極的に担っていた姿勢が評価され、社内公募制度を活用して開発部門長に抜擢。
「コードを書くのが好きだったが、チームが成果を出す構造を作る面白さに目覚めた」と語ります。
現在はプロジェクトマネジメントだけでなく、中長期の技術方針や採用戦略にも携わり、プレイヤーから“経営に近い技術責任者”への道を歩んでいます。
未経験から管理職を目指すロードマップ
小規模チームの技術リーダー経験を積むステップ
管理職未経験者が最初に目指すべきポジションは、「3〜5人規模のチームリーダー」です。
いきなり10人以上の組織を任されるケースはまれであり、まずは少人数のチームをまとめる経験を積むことが、スムーズなマネジメントキャリアの第一歩になります。
- タスク管理や進捗確認の習慣をつける
- 日報や1on1などで信頼関係を構築する
- トラブル時に冷静に対応し、振り返りを促す
この段階では、「自分が動く」よりも「他人を動かす」ことの難しさを体感できるでしょう。初期のつまずきも貴重な財産になります。
小さな成功体験を積みながら、徐々にメンバー数や担当領域を広げていくのが現実的な成長ステップです。
社内昇格と社外転職の選択肢を比較する
管理職を目指すルートは、大きく「社内で昇格する」か「社外に出て転職する」かの2パターンに分かれます。
社内昇格のメリットは、信頼関係や業務知識がある状態からスタートできる点です。特に人材育成に力を入れている企業では、研修やフォロー体制が整っており、段階的にマネジメントを学ぶことができます。
一方、社外転職は新しい環境でリセットされた評価を得られるチャンスがあります。これまでマネジメント機会が与えられなかった場合でも、意欲と適性を示せば「管理職候補」として採用される可能性もあるのです。
どちらを選ぶにせよ、「なぜ管理職を目指すのか」「どのように組織に貢献できるか」を明確に持っておくことが、次のチャンスにつながります。
メンター・コーチを活用してスキルギャップを埋める
未経験から管理職を目指す上で、周囲の支援を得ながらスキルを補完する姿勢は非常に効果的です。
- 社内のマネージャー経験者に定期的な相談をする
- オンラインで外部のメンターやキャリアコーチを活用する
- 業界コミュニティや勉強会に参加し、視野を広げる
実際に活躍しているマネージャーの行動や思考を観察することで、自分に足りない視点や振る舞いが明確になります。
独学では気づきにくい課題も、他者からのフィードバックによって解像度が高まり、成長のスピードも加速します。
資格取得と学習で転職を有利にする方法
プロジェクトマネージャ/ITサービスマネージャなど国家試験の活用
エンジニア管理職を目指すうえで、国家資格の取得は一定の信頼性を得る手段として有効です。
とくに情報処理技術者試験の中でも、以下の資格はマネジメント系職種において高い評価を得やすい傾向にあります。
- プロジェクトマネージャ試験(PM)
- ITサービスマネージャ試験(SM)
- システムアーキテクト試験(SA)
これらの資格は、業務遂行能力や理論的知識だけでなく、ドキュメント構成力や論理思考も求められるため、「マネジメントスキルの証明」として有効です。
特に大手企業やSIer業界では、書類選考の段階で資格保有者が有利になるケースもあります。
MBA・ビジネススクール・オンライン講座の選び方
よりビジネス寄りの視点を育てたい方には、MBAやビジネススクール、マネジメント向けオンライン講座の活用が効果的です。
特に以下のようなニーズを持つ方に向いています。
- 事業計画・PL/BSなどファイナンス基礎を体系的に学びたい
- 社外でのネットワーク形成や視座を広げたい
- 将来的にCxOレベルを目指している
国内外のMBAスクールはもちろん、Udemyやグロービス学び放題などオンライン学習プラットフォームでも、リーダーシップやロジカルシンキング、経営戦略といったマネジメント系講座が豊富に提供されています。
「資格よりも実践型の学びがしたい」と考える方には、こうしたサービスが向いているでしょう。
最新技術トレンドを追うための情報収集術
管理職であっても、最新の技術トレンドを理解しているかどうかでメンバーからの信頼は大きく変わります。
毎日コードを書く必要はありませんが、「世の中で今何が起きているか」を把握することは欠かせません。
情報収集には以下のような方法が有効です。
- QiitaやZennなどの技術ブログで実務に近い知見を得る
- TechCrunchやGigazineで業界全体の動向をチェック
- ポッドキャストやYouTubeで通勤時間に情報をインプット
特にAI、DevOps、セキュリティ、クラウド領域など、組織課題と密接な分野は優先的にキャッチアップしておくと、経営との会話でも説得力を持てます。
転職エージェント・求人サイトの効果的な活用法
管理職・エグゼクティブ特化型エージェントの選定基準
管理職ポジションを狙う場合、通常の求人サイトだけでは十分な情報にアクセスできないことが多いため、エグゼクティブ特化型の転職エージェントを活用することが重要です。
特化型エージェントを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- ハイクラス・管理職に特化している(例:JAC、ビズリーチ)
- 非公開求人の保有比率が高い
- 担当コンサルタントの業界理解が深い
面談では希望ポジションだけでなく、「マネジメント経験の再現性」や「どの規模感で活躍できるか」まで含めて相談すると、マッチ度の高い求人紹介が受けられます。
短期転職だけでなく、中長期視点でのキャリア設計に寄り添ってくれるかも、重要な判断基準です。
エージェント面談で確認すべき評価基準と非公開求人情報
転職エージェントとの初回面談では、こちらが質問する姿勢を持つことで、より有益な情報を引き出せます。
特に以下のような質問を事前に用意しておくと効果的です。
- 企業が管理職採用で重視している評価ポイントは何か
- 現場マネージャーと経営陣、どちらが採用決定権を持つか
- 非公開求人のうち、裁量や意思決定権が大きいポジションはあるか
また、募集背景や前任者の退職理由など、求人票だけでは分からない「裏情報」を丁寧に聞き出すことで、転職後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
エージェントとの信頼関係が築ければ、他候補より早く好条件案件を紹介されることもあります。
複数サービス併用でスカウト機会を最大化するコツ
管理職転職では、「受け身で待つ」だけでなく「機会を広げる」姿勢が重要です。複数のエージェントサービスやプラットフォームを併用することで、思わぬスカウトや非公開案件との出会いが生まれます。
おすすめの併用戦略は次のとおりです。
- ビズリーチ・リクルートダイレクトスカウトなどスカウト型を登録
- JACなどハイクラス転職に強いエージェントと面談
- LinkedInで職歴を整え、企業人事からの直接アプローチも狙う
ただし、過剰な登録で情報が錯綜しないよう、やり取りを一元管理できるスプレッドシートなどを活用して、状況を整理することをおすすめします。
「良い求人が来るかどうか」は運に見えますが、「準備しておくかどうか」は自分次第です。
よくある悩みとQ&A
「管理職になりたくない」場合のキャリアオプション
すべてのエンジニアが管理職を目指す必要はありません。中には「人を動かすより、自分でコードを書いていたい」「評価や人事に関わりたくない」という人も多くいます。
そうした場合でも、専門性を極めて評価されるキャリアは確かに存在します。
- テックリードやアーキテクトなど、技術特化型の上位職
- 専門領域に特化したコンサルタントや研究開発職
- フリーランスや副業型エンジニアとして技術力で稼ぐ道
組織によっては、スペシャリストにもマネージャーと同等の等級・報酬体系を用意しているケースもあります。
自分にとって「心地よく成果を出せるポジション」はどこかを見極めることが、長く満足度の高いキャリアを築くポイントです。
35歳以上・マネジメント経験なしでも転職できるか
35歳を過ぎてマネジメント経験がない場合でも、転職は十分可能です。ただし、ポテンシャルだけでは難しく、「再現性ある実績」と「将来像の具体性」が求められます。
たとえば、以下のようなアプローチが有効です。
- 業務改善やチーム支援でリーダーシップを発揮した実績を整理する
- マネジメントスクール受講や社内プロジェクト参画など、自発的な取り組みを示す
- 「なぜ今マネジメントを目指すのか」「将来的にどうなりたいのか」を明確に語れるようにする
また、スタートアップや成長企業では、「柔軟に育成したい」「文化をつくれる人材を採用したい」という理由から、年齢よりも志向性やフィット感を重視する傾向があります。
年齢がハンデになることはあっても、「できない理由」にはなりません。
地方在住エンジニアがリモートで管理職を目指す方法
近年はフルリモートで働ける企業も増え、地方在住エンジニアにも管理職の道が開かれています。
ポイントは、物理的距離を「不利」にしないための工夫です。
- 日報・週報や1on1を活用し、常にメンバーと接点を持つ
- SlackやZoomでのリアルタイムな意思疎通を意識的に強化する
- 成果を言語化・可視化する習慣を持つ
また、フルリモート体制を前提にしたマネジメント経験は、今後さらに市場価値が高まる分野でもあります。
東京に出ずとも、全国の企業に貢献できるマネージャーとしてのキャリアは、現実的な選択肢になりつつあります。
まとめ:エンジニア管理職転職は“技術×組織”でキャリアを広げる選択
エンジニアとして培ったスキルを軸にしながら、組織全体の成果に貢献する——それが管理職への転職で得られる最大の価値です。
なぜなら、管理職は単なる“上位職”ではなく、「技術を理解しながら人を動かす」という複合スキルを持つ専門職であり、現代の開発組織には欠かせない存在だからです。
- スペシャリストとの違いを理解し、自分に合ったキャリア判断ができる
- マネジメントスキル・ビジネス視点・意思決定力など多面的な能力が求められる
- 年収アップや裁量権の拡大といった待遇面のメリットも大きい
- 未経験でもステップを踏めば十分に管理職を目指せる
- エージェントや学習サービスを活用することで転職成功率を高められる
つまり、管理職転職とは「過去の経験を活かし、未来の影響力を広げる」挑戦です。
今のポジションに違和感がある、成長の限界を感じている、もっと組織に影響を与えたい——そう感じたら、一歩踏み出してみてください。あなたのキャリアには、まだまだ広がる可能性があります。