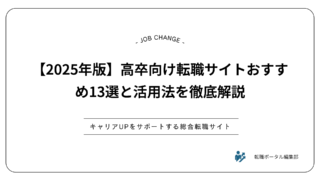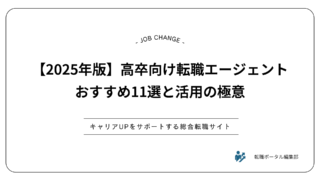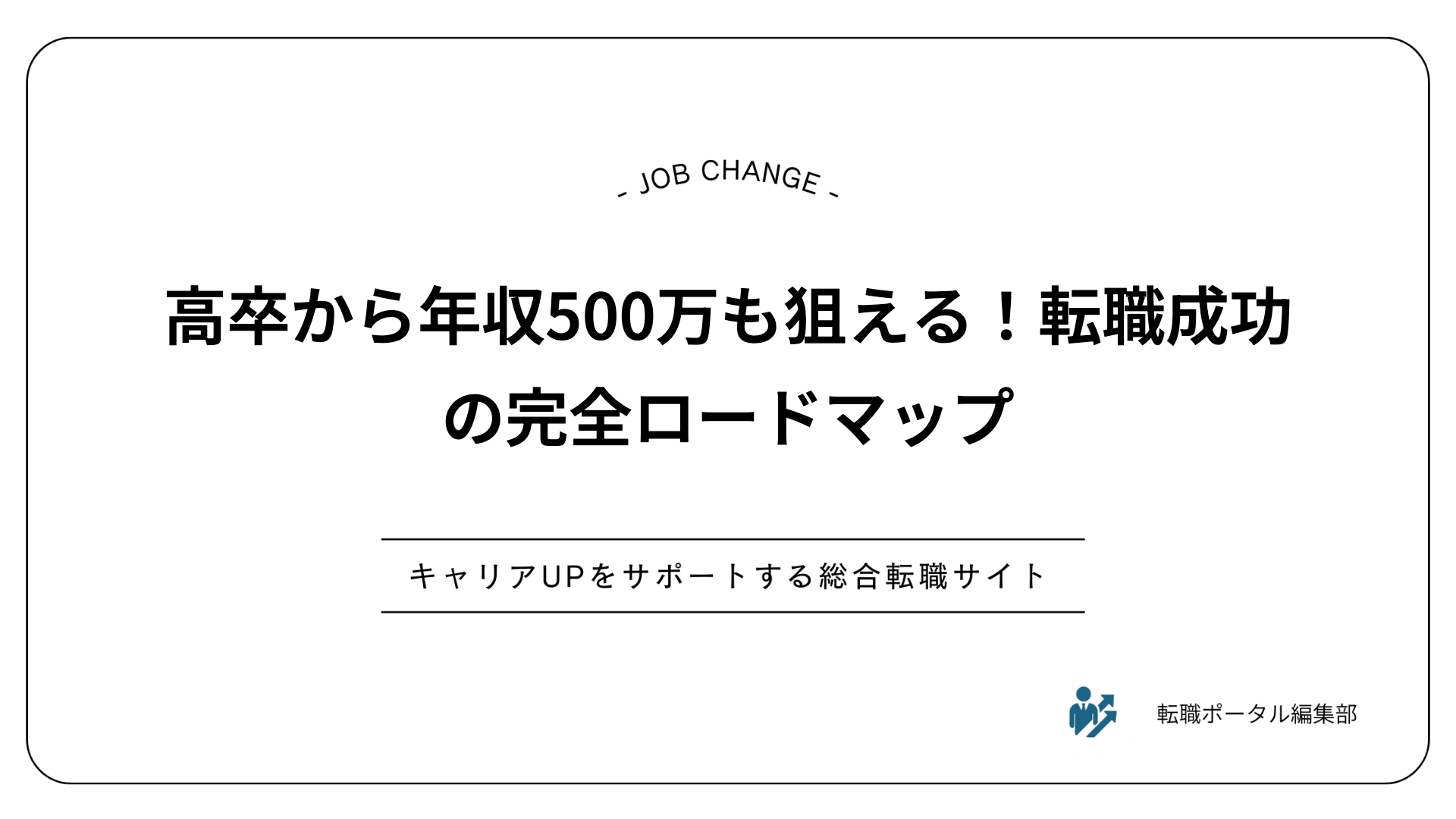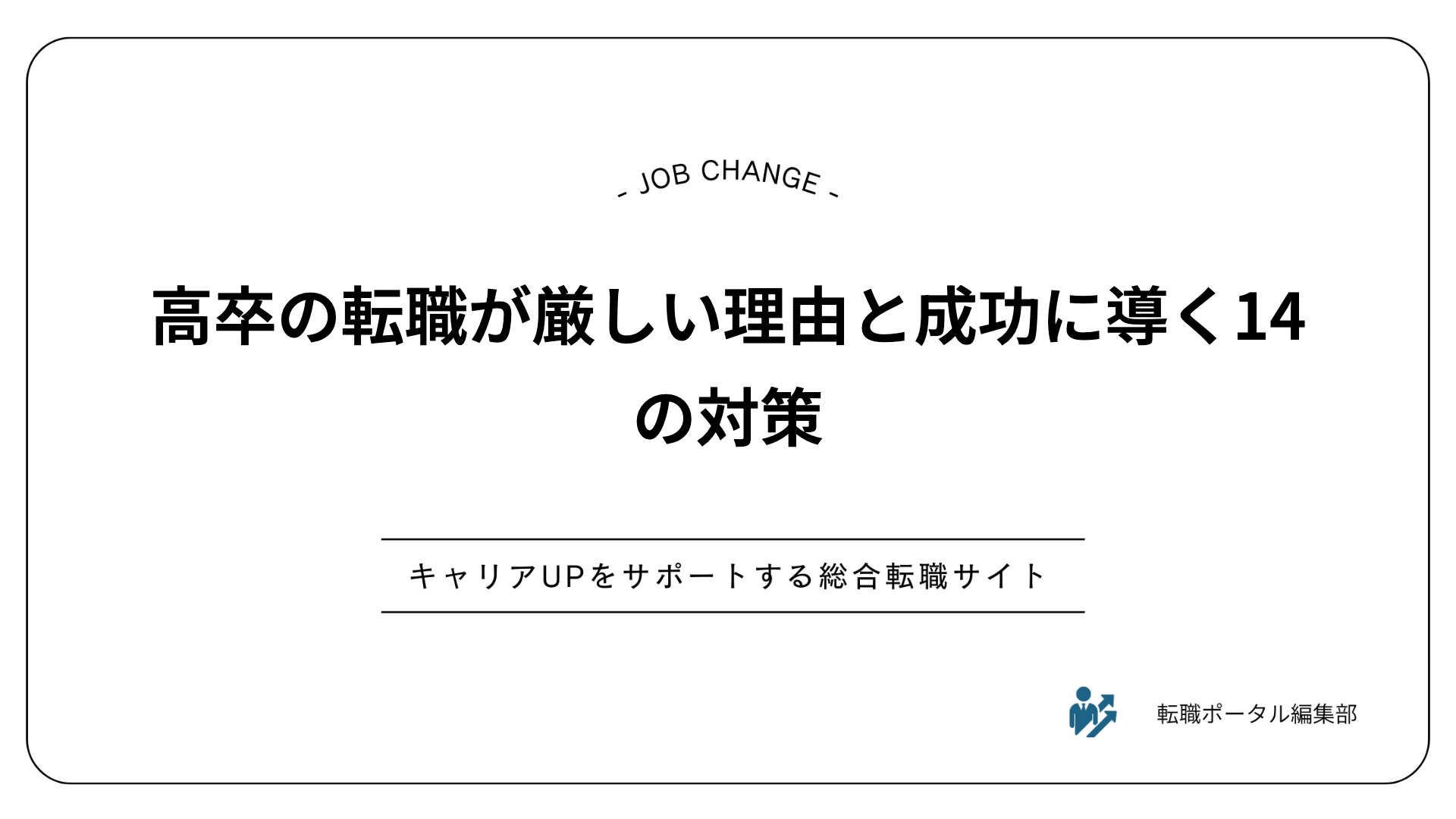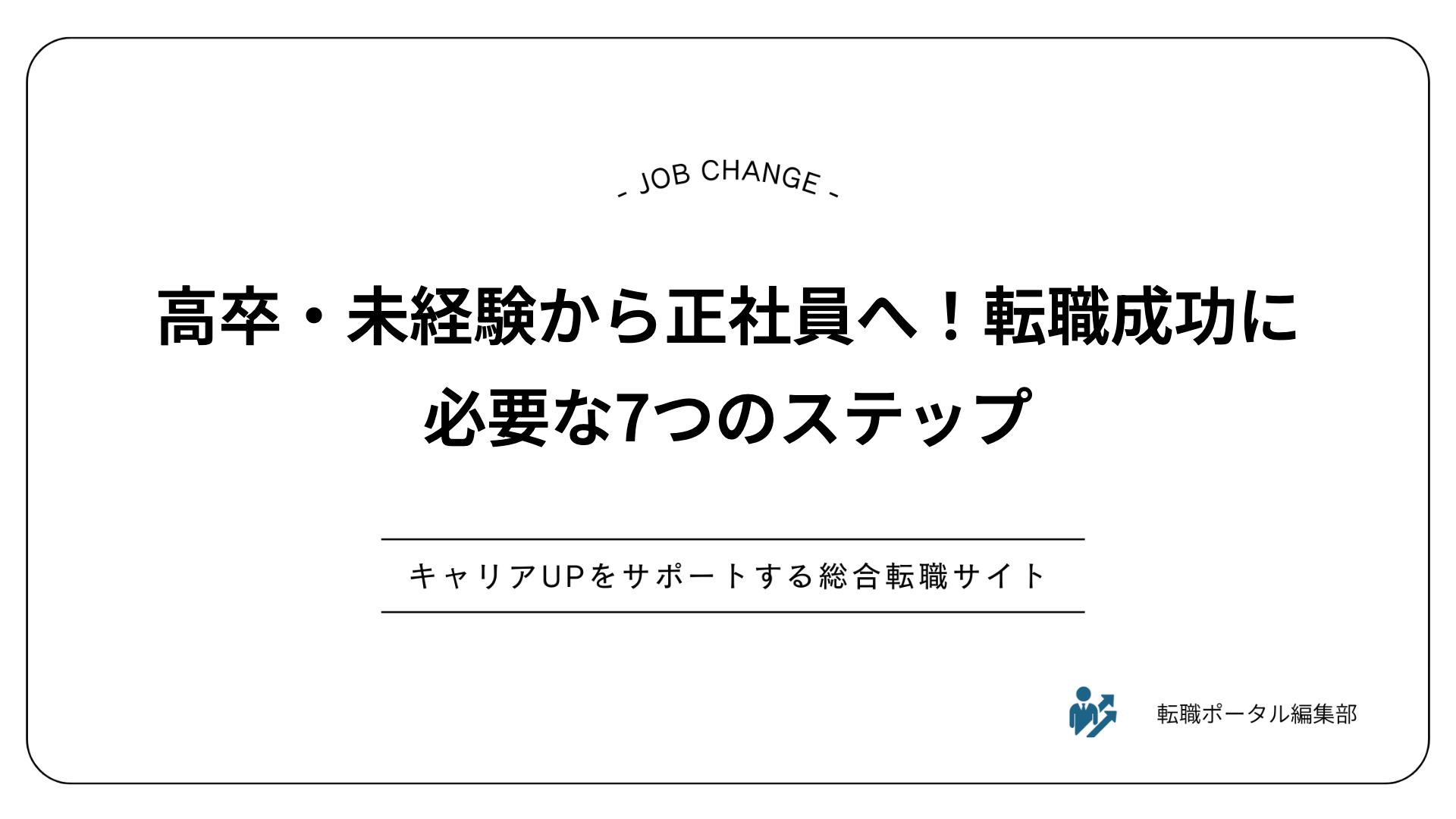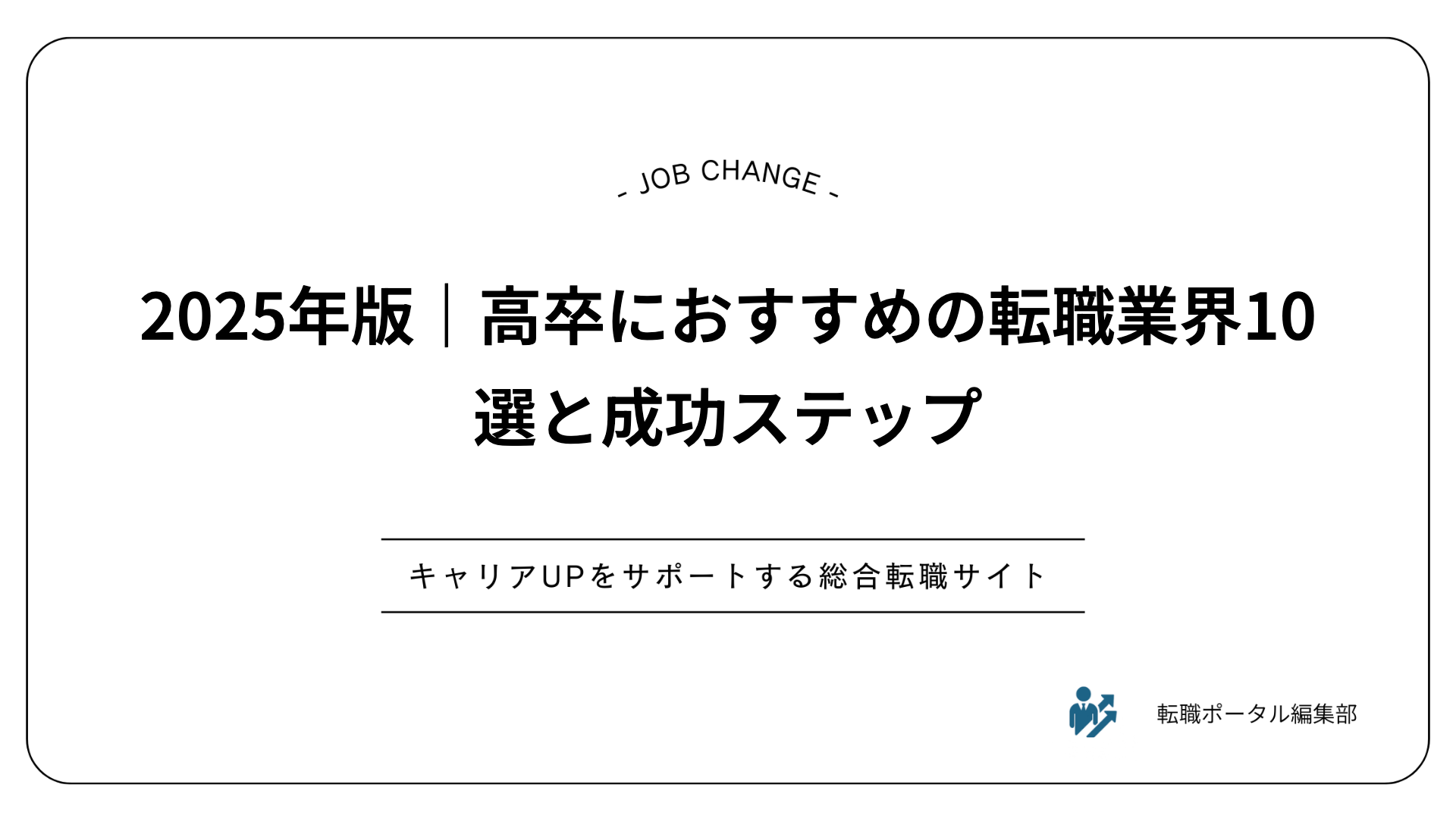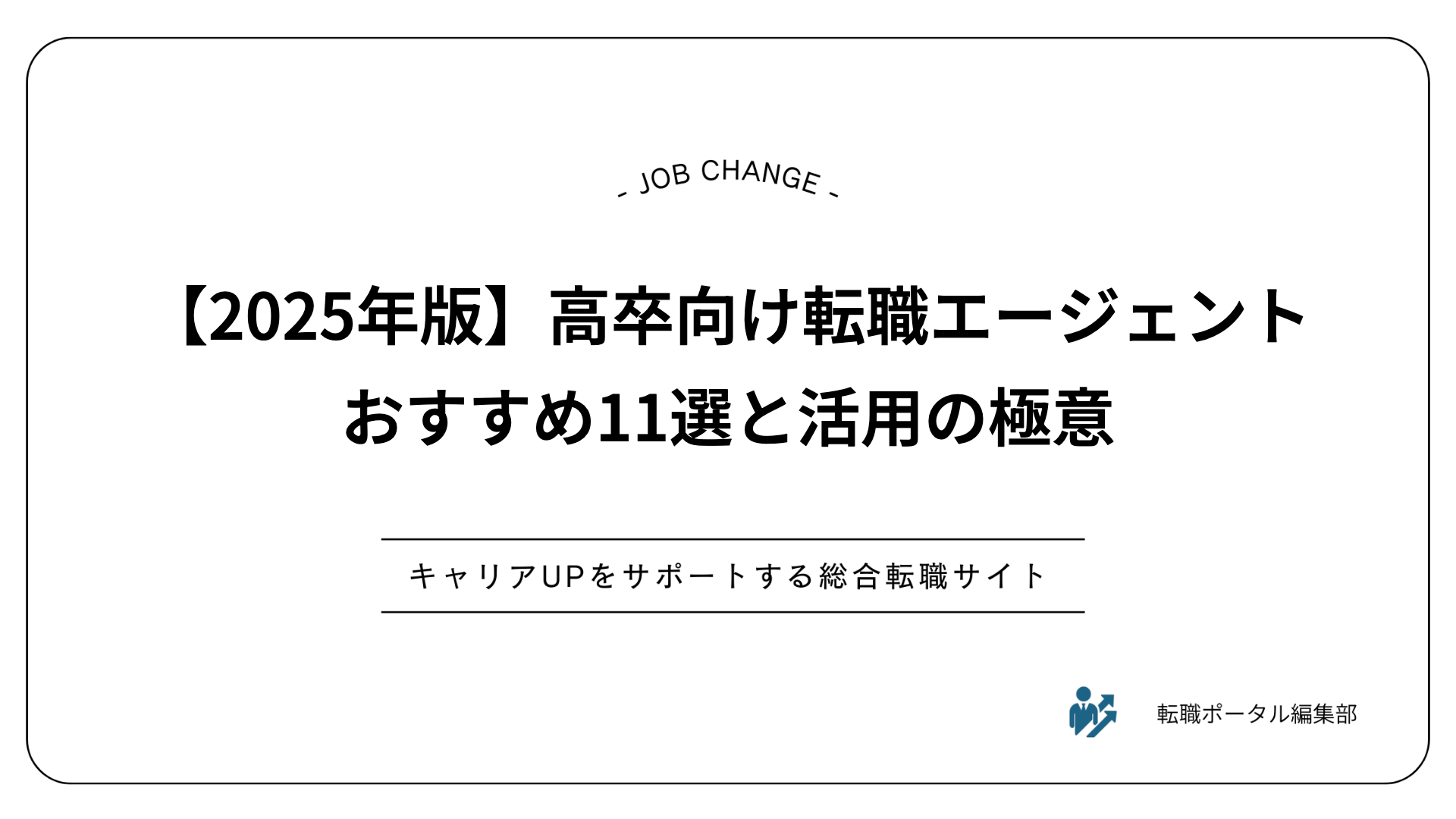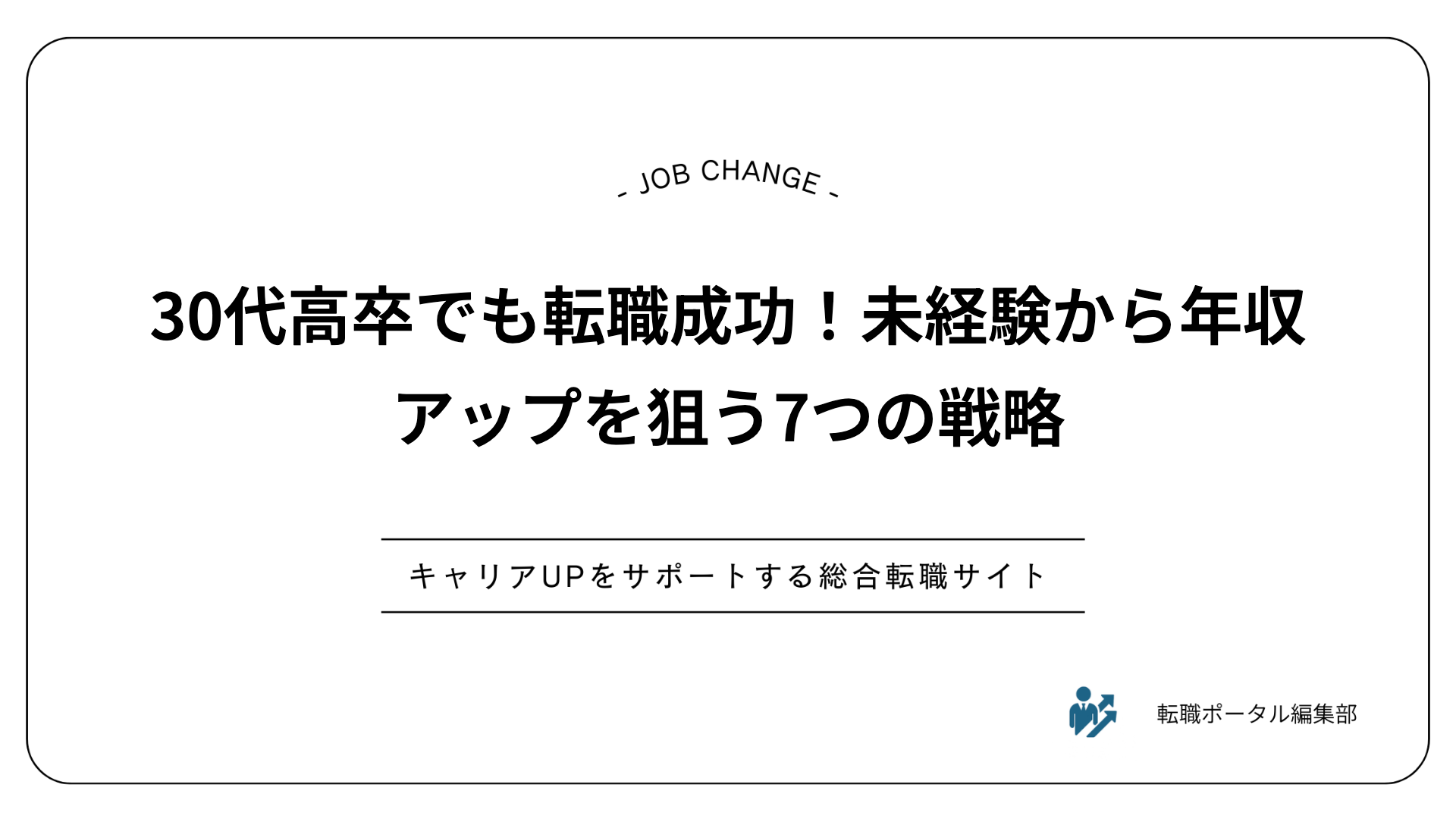高卒から公務員へ転職するための7ステップ|年齢制限・試験対策・職種一覧を完全解説
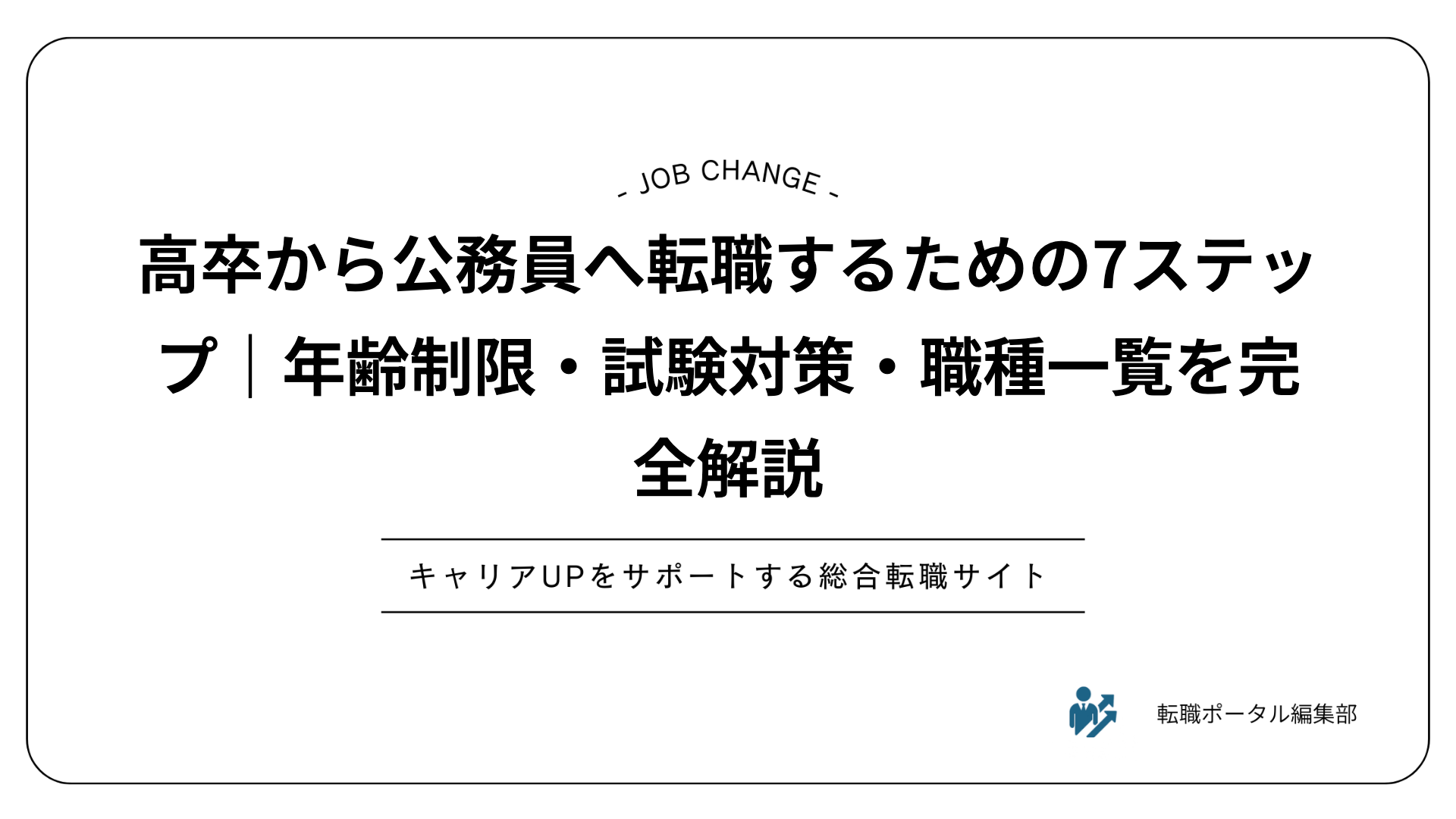
「高卒でも公務員になれるのかな…」
「年齢がネックで諦めるべき?」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、高卒からでも公務員へ転職する道はしっかりと用意されており、受験区分や試験対策を正しく押さえることで誰でも目指すことが可能です。
この記事では、次のような疑問や不安に丁寧に答えていきます。
- 高卒で受けられる公務員試験の条件や年齢制限は?
- 国家公務員・地方公務員・公安系などの違いがわからない
- 高卒でもキャリアアップできる?給与はどれくらい?
- 試験勉強は独学で通用するの?予備校って必要?
- 実際に転職した人の体験談が聞きたい
「安定した職に就きたい」「将来の不安を減らしたい」と感じている方にこそ、公務員転職という選択肢を知ってほしい——そんな思いでこの記事をまとめました。
読み進めることで、自分に合った受験区分や職種、対策方法がきっと見つかります。
高卒でも公務員へ転職できる?基本条件と年齢制限
公務員試験に学歴制限はあるのか

結論から言えば、公務員試験において「高卒だから受けられない」ということはありません。
公務員試験では主に「学歴」よりも「受験資格となる年齢」や「区分」が重要視されるため、高卒でも適切な区分を選べば十分に受験可能です。
実際に国家公務員や地方公務員には高卒区分(一般職)や社会人経験者採用などの枠が設けられており、毎年多くの高卒者が採用されています。
「高卒だから不利なのでは…」と不安に感じる方もいますが、面接ではこれまでの経験や志望動機、やる気などが重視されるため、学歴のみで判断されることはありません。
つまり、学歴で悩む必要はありません。重要なのは、自分に合った受験区分を理解し、準備を進めることです。
高卒枠・社会人経験者枠の違いと選び方
高卒で公務員を目指す場合、主に「高卒区分」と「社会人経験者枠」のどちらかから受験することになります。
- 高卒区分:高校卒業程度の学力が対象。年齢制限は18〜21歳程度が一般的。
- 社会人経験者枠:一定の職歴が必要。年齢制限はおおむね30代半ばまで。
- 選び方のポイント:20代前半までなら高卒枠、社会人歴が3年以上なら社会人経験者枠を検討。
社会人経験者枠では、民間企業での実務経験やコミュニケーション能力が重視される傾向があります。
一方で高卒区分では、筆記試験の得点が合否に大きく影響しますので、どちらを選ぶかによって対策の方向性も変わります。
「どの枠が自分に合っているか分からない…」という場合は、各自治体や官庁の募集要項を確認し、条件や試験内容を比較してみましょう。
年齢上限と例外規定をチェックしよう

公務員試験には、年齢制限が設けられているのが一般的です。多くの試験では「18歳以上、29歳以下」などといった上限があります。
- 国家公務員一般職(高卒区分):21歳未満(例年)
- 地方初級(高卒区分):18歳〜30歳未満の自治体もあり
- 社会人経験者採用枠:原則30〜40歳まで受験可能
ただし、自治体によっては例外規定を設けている場合もあります。
たとえば「職歴〇年以上であれば35歳まで応募可能」といった条件が加わるケースです。
こうした例外に該当することで、年齢が30代でもチャンスが広がる場合があるため、最新の募集要項を必ず確認することが大切です。
「もう年齢的に遅いのでは…?」と不安な方も、例外規定や社会人枠の存在を知れば、道は開けてきます。
高卒から目指せる公務員の主な職種一覧
国家公務員一般職(高卒区分)で担う業務内容
国家公務員一般職(高卒区分)は、国の行政機関において事務処理や調査補助、窓口対応などを行うポジションです。
主に各省庁の地方支分部局(税務署、労働基準監督署、運輸局など)で働くことになります。
担当する業務は多岐にわたり、たとえば労働局では雇用保険の申請業務、運輸支局では自動車登録の受付などが挙げられます。
採用後はOJTで業務を学びながら、実務経験を積んでいきます。昇任制度も整っており、将来的には主任や係長といった役職も目指せる点が魅力です。
「現場で人と接する仕事がしたい」「事務職として安定して働きたい」という方におすすめの職種です。
地方公務員(都道府県・市区町村職員)の仕事と魅力
地方公務員は、住民に最も身近な行政サービスを提供する存在です。
高卒で受験できる職種には、一般事務、学校事務、技術職(土木・建築など)などがあります。
地域の役所や教育委員会などで勤務し、住民票の発行、税金の徴収、道路の補修など、地域社会を支える幅広い業務を担当します。
地方ごとの事情や文化に密着した業務が多く、「地元に貢献したい」「安定した環境で長く働きたい」といった思いを持つ人に人気の職種です。
また、比較的ワークライフバランスが取りやすく、育児や介護との両立を考える方にも向いています。
公安系公務員(警察官・消防官・自衛官など)の特徴
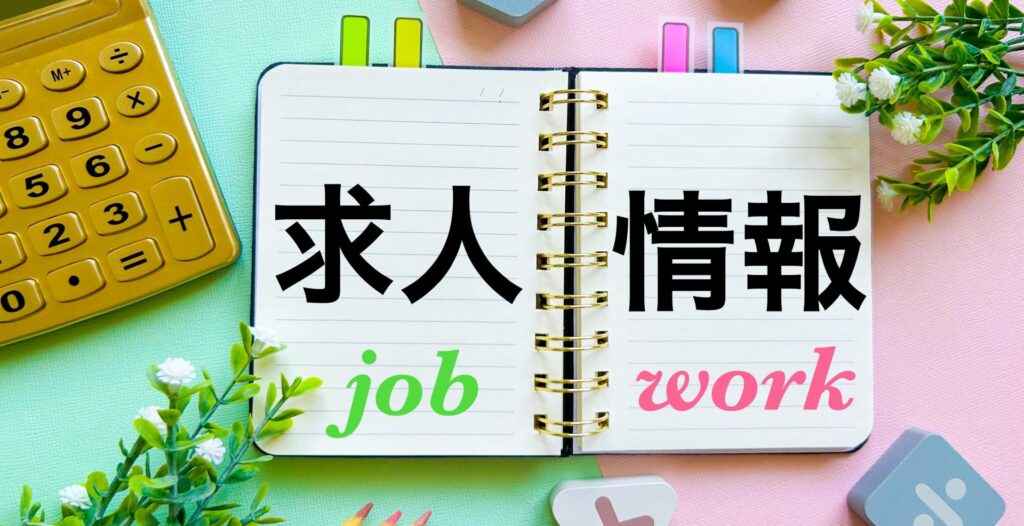
公安系公務員とは、人々の生命・財産・安全を守る使命を担う職種です。高卒者が目指せる主な職種には、警察官、消防官、自衛官などがあります。
- 警察官:交通取締りや地域パトロール、事件捜査などに従事
- 消防官:火災現場や救急出動、災害対応が中心
- 自衛官:国防や災害派遣などの活動に従事
これらの職種は体力と精神力が求められますが、その分やりがいや社会的意義は非常に大きいです。
また、給与や退職金が比較的高水準であること、若いうちから安定した収入が得られる点も魅力の一つでしょう。
「人の役に立ちたい」「体を動かす仕事がしたい」という人にはぴったりの選択肢です。
技術系・専門職系で活かせる資格とスキル
高卒でも、特定のスキルや資格を活かせる技術職・専門職を目指すことができます。
たとえば土木、建築、電気、機械などの技術系や、情報処理、化学分析などの職種があります。
これらの職種では、高校や専門学校で学んだ技術や資格(第二種電気工事士、測量士補など)がそのまま評価対象になります。
専門性が高いため、試験の難易度は一般事務よりも高くなりますが、業務の希少性や人材不足の影響から採用枠が安定している点が特長です。
また、職務経験を積むことで管理職や上級職への昇進も目指せるため、「手に職をつけて安定したキャリアを築きたい」という方には理想的な道といえるでしょう。
資格やスキルを活かしたいけど、どの職種があるのかわからない…そんなときは過去の採用実績や自治体の職種案内を確認してみましょう。
高卒公務員の給与・昇進モデルとキャリアパス
初任給・年収水準と大卒公務員との比較

高卒公務員の初任給は、おおむね月給16〜18万円程度からスタートします。
地域手当や扶養手当、住居手当などの支給により実際の月収はこれより高くなることが多いです。
年収ベースでは、1年目で250万〜300万円程度が一般的です。賞与(期末・勤勉手当)は年2回支給され、安定した収入が魅力です。
一方、大卒公務員は初任給が19〜21万円前後とやや高めですが、その差は年次が進むごとに縮まる傾向にあります。
昇任や評価によって個人差も出てくるため、学歴による給与差は「初任給レベルではあるが、生涯賃金では努力次第で逆転可能」ともいえます。
昇給ペースと昇進試験の仕組み
公務員の給与体系は、毎年一定の昇給があり、評価によって昇給額に差がつきます。
平均的には年に約3,000〜5,000円のベースアップが見込まれます。
- 評価制度:勤務評価に基づき、昇給幅に差がつく
- 昇進:主任→係長→課長補佐→課長など段階的に昇任
- 昇進試験:一部自治体や省庁では管理職登用にあたり試験が実施される
高卒からでも、実績や人間関係、マネジメント能力などが認められれば、係長・課長といった役職を目指すことが可能です。
「高卒だから昇進できないのでは?」と心配する必要はなく、むしろ現場経験を積んだ職員ほど信頼されやすい傾向があります。
福利厚生・ワークライフバランスの実情
公務員の大きな魅力の一つが、充実した福利厚生と安定した働き方です。
厚生年金、公務員共済、育児休暇、介護休暇、定期昇給などがしっかり整備されています。
有給休暇も取りやすく、勤務時間も基本的に8:30〜17:15と一定しているため、プライベートの時間を確保しやすい点も好評です。
また、近年はテレワークやフレックスタイム制度を導入する自治体も増えており、柔軟な働き方が可能になっています。
「育児と両立したい」「残業の少ない仕事がいい」そんな希望を叶えられるのが公務員という働き方の強みです。
高卒で公務員になるメリット・デメリットを徹底比較
公務員ならではの安定性と社会的信用

高卒で公務員になる最大のメリットは、なんといっても「安定した雇用と収入」です。
景気の影響を受けにくく、リストラや解雇のリスクがほとんどないため、将来設計が立てやすい職業といえます。
- 定期昇給・賞与がある
- 退職金制度が整っている
- 共済組合など福利厚生も充実
- 住宅ローンや賃貸審査でも信頼されやすい
「安定した仕事に就きたい」「家族を安心させたい」という方には、まさに理想的なキャリアパスです。
昇給スピードやキャリアアップ面でのギャップ
一方で、高卒公務員には「昇進の壁」を感じる場面もあります。
特に大卒者が多く配属される部署では、学歴による初期配置の差が昇進に影響することもあるからです。
とはいえ、それはあくまで一部の傾向に過ぎず、現場での実績や対人スキルが重視される場面も多くあります。
近年は「人物重視・成果重視」の人事制度を取り入れる自治体も増えており、学歴にとらわれずキャリアアップできる環境が整いつつあります。
「努力しても大卒には勝てないのでは?」と感じたら、早めに係長・主任試験に挑戦してみるのも一つの方法です。
民間企業への転職・スキル汎用性の課題

公務員として長年働くと、民間企業で評価される「実務スキル」や「マネジメント経験」が不足してしまうというデメリットもあります。
特に、役所の独自ルールや文化に慣れきってしまうと、転職時に苦労する可能性があります。
- ITや営業などのスキルが民間では求められる
- 公務員特有の手続き重視の仕事は汎用性が低い場合も
- 転職活動に慣れていないため書類作成や面接対応に苦戦しやすい
そのため、在職中に資格取得や副業経験を積むことで「外でも通用する力」を養っておくと安心です。
「万が一の転職にも備えておきたい…」そんな方はスキル習得の準備を今から始めておきましょう。
転職成功までのステップとスケジュール
試験区分別の出願時期・試験日程
公務員試験は区分ごとに日程が異なるため、まずは受験したい職種のスケジュールを把握することが重要です。
- 国家公務員一般職(高卒区分):例年6月に公告、9月に一次試験
- 地方初級:多くの自治体で6〜7月に募集、9〜10月に筆記試験
- 社会人経験者枠:募集は秋〜冬が中心(例:10月出願、12月試験)
自治体や官庁によって日程や実施方式が異なるため、必ず公式ホームページで確認してください。
「うっかり出願期限を逃してしまった…」という事態を防ぐには、早めに試験カレンダーを作成しておくと安心です。
退職から入庁までのタイムラインを逆算する
現在の職場を退職して公務員に転職する場合、「退職→試験→合格→入庁」までの流れを事前に逆算しておく必要があります。
なぜなら、公務員試験には半年〜1年かかるケースもあり、無計画に退職すると「収入が途絶えてしまう」リスクがあるからです。
- 筆記・面接の準備期間:3〜6ヶ月
- 試験〜合格発表:1〜2ヶ月
- 内定〜入庁まで:翌年4月など
スムーズな転職を実現するには、「現職の退職時期をいつにするか」「貯金や生活費をどう確保するか」もあわせて検討しておきましょう。
在職中に受験・合格し、翌年4月に入庁というスケジュールが理想です。
受験案内・募集要項の情報収集方法

受験する職種が決まったら、まず確認すべきは「受験案内」と「募集要項」です。
これらは試験区分や出願方法、試験科目、年齢条件などが詳細に記載されています。
入手方法は以下の通りです。
- 国家公務員:人事院または各省庁の公式サイト
- 地方公務員:都道府県・市区町村の人事委員会やHP
- 公安系:警察・消防の採用サイトまたはリクルーター窓口
募集時期が限られているため、定期的にチェックする習慣をつけておくと有利です。
「サイトが見づらくて探せない…」という方は、各自治体の採用TwitterやLINE公式アカウントなども活用すると、情報を見逃しにくくなります。
合格率を高める公務員試験勉強法
数的処理・文章理解の効率的学習テクニック
公務員試験において「数的処理」と「文章理解」は得点源となる重要科目です。特に数的処理は出題数が多く、苦手意識を持つ人も少なくありません。
まずは毎日コツコツと解く習慣をつけ、反復練習で解法パターンを身につけましょう。
- 数的処理は「解き方」を覚えることが最優先
- 最初は時間を気にせず丁寧に解く
- 慣れてきたら制限時間を設けて練習
文章理解では、現代文読解と英語の読解スピードを上げることがポイントです。
速読トレーニングや要点把握力を鍛えることで、限られた時間内でも正確に解けるようになります。
「数的処理が苦手で不安…」という方は、出題パターンを覚えることから始めてみましょう。最初は解けなくても、続ければ必ず伸びてきます。
過去問演習と模試活用のベストプラクティス

本番の出題傾向を掴むには、過去問演習が最も有効な学習方法です。
特に同じ職種・区分の過去3〜5年分は、繰り返し解いて傾向と頻出テーマを体で覚えましょう。
- 1回解くだけでなく、2〜3周して定着させる
- 「なぜ間違えたか」をノートに記録する
- 模試で本番と同じ緊張感を体験する
模試は自分の実力を客観的に知る良い機会です。受験前に1〜2回は受けておくと、時間配分や集中力の持続なども確認できます。
「模試で点が取れなくて不安…」という方も、間違いから学ぶことが大切です。本番までに修正すれば大丈夫です。
面接・適性検査対策で押さえるポイント
筆記試験を突破しても、最終的に合否を分けるのは面接や適性検査です。
特に面接では「志望動機」「自己PR」「これまでの経験」など、個人の姿勢が問われます。
模範解答を丸暗記するのではなく、自分の言葉で語れるように何度も練習しましょう。
また、公安系では性格診断や適性検査の比重も高く、事前対策が必要です。
日常生活での判断力や倫理観、責任感なども評価対象となるため、普段から「どう行動するか」を意識して過ごすことが面接対策にもつながります。
「面接で緊張してしまう…」という方は、話す内容を箇条書きにして整理してから声に出して練習してみましょう。
予備校・通信講座・独学それぞれの選び方
予備校を利用するメリット・デメリット
公務員試験対策において予備校を利用する最大のメリットは、「学習環境の整備」と「プロの指導が受けられる安心感」です。
- わからない点をすぐに質問できる
- 学習ペースを管理してくれるカリキュラム
- 面接対策や模擬面接のサポートがある
一方で、費用が高額(10〜30万円)になりがちな点や、通学に時間がかかる場合もある点には注意が必要です。
自分一人ではなかなか学習が進まないという人にとって、予備校は非常に心強い選択肢になるでしょう。
通信講座で学ぶ場合の費用とサポート内容

通信講座は、時間や場所に縛られずに学習を進めたい人におすすめの方法です。
スマホやパソコンで動画講義を受けられるため、仕事や家事の合間でも効率的に学習を進めることができます。
受講料は予備校より安く、5〜15万円程度が相場です。
また、近年の通信講座は質問サポートや添削指導、模擬試験の受験制度なども充実しており、通学型に劣らないクオリティになってきています。
「コストを抑えつつもプロの指導が欲しい」という人には、通信講座が最適です。
独学派が失敗しないための参考書リスト
独学での公務員試験対策は、費用が最も安く済むというメリットがありますが、正しい教材選びと学習計画がカギになります。
- 『畑中敦子の数的推理・判断推理シリーズ』(LEC出版)
- 『速攻の時事』(実務教育出版)
- 『スーパー過去問ゼミ』(実務教育出版)
- 『クイックマスター』(TAC出版)
まずは出題傾向を把握するために過去問を1冊解いてみて、自分の苦手科目を特定するのが効果的です。
独学は孤独になりがちですが、SNSや掲示板、YouTubeなどを活用して情報交換すると、モチベーション維持にもつながります。
「どの教材から始めればいいのかわからない…」という方は、書店で立ち読みして自分に合ったものを選ぶと安心です。
高卒から公務員へ転職した先輩たちの体験談
20代で地方公務員へ転職したケース

20代前半で民間企業から市役所職員へ転職したAさんは、事務職として日々窓口対応や書類作成業務を担当しています。
転職理由は「将来への不安」と「地元で長く働きたい」という思いからでした。
彼は高卒後、販売職として働いていましたが、労働時間の長さやキャリアの不透明さに悩み、公務員試験に挑戦。
半年間の独学と通信講座の併用で一次試験に合格し、面接では「現職での接客経験」をアピールポイントとして伝えたところ、高評価を得て採用されました。
現在は「休日も安定して取れて、収入も安定。家族との時間も増えた」と、満足度の高い生活を送っています。
民間企業から国家公務員一般職へ転職したケース
Bさんは20代後半、建設業界の営業職から国家公務員(一般職・高卒区分)に転職しました。
- 営業時代の経験で得た「傾聴力・調整力」が面接で高評価
- 試験勉強は平日の仕事終わり+週末に集中
- 家計管理のため、コストを抑えて独学中心で対策
入庁後は運輸局に配属され、現在は窓口対応や許認可手続き業務を担当。
役所内の雰囲気に驚きつつも、「落ち着いて長く働ける」と公務員としての仕事にやりがいを感じています。
「安定した働き方を求めているなら、公務員への転職は本当におすすめ」と語っています。
公安系公務員に転職した女性のケース
Cさんは高卒で民間の事務職を経験後、消防官へ転職した女性です。
体力的なハードルはあったものの、学生時代の運動部経験を活かし、半年間のトレーニングと筆記対策に集中。
試験では体力試験も無事クリアし、面接では「女性ならではの視点で地域の安全に貢献したい」という想いを伝え、採用されました。
消防署配属後は救急業務を中心に従事し、周囲からの信頼も厚く、職場でも女性職員のロールモデルとして活躍しています。
「男女問わず、やりたい気持ちがあれば必ず道は拓ける」と、今は後輩の指導にも力を入れています。
よくある質問(FAQ)
高卒公務員試験の倍率はどのくらい?

試験区分や自治体によって異なりますが、高卒区分の公務員試験の倍率はおおむね3倍〜10倍程度といわれています。
- 地方初級:3〜6倍程度が一般的
- 国家一般職(高卒区分):5〜10倍前後
- 社会人経験者枠:少数精鋭の採用で10倍以上になるケースも
筆記試験のウエイトが高いため、事前の対策次第で十分に合格を狙える範囲です。
「高倍率で不安…」という方も多いですが、実際には受験者の中には記念受験や準備不足の人も多く、きちんと対策すれば十分にチャンスはあります。
30歳を過ぎても高卒区分で受験できる?
基本的に高卒区分は「21歳以下(または22歳未満)」といった年齢制限があるため、30歳を過ぎた方は対象外となることが多いです。
しかし、「社会人経験者枠」や「民間企業等職務経験者採用枠」であれば、30代半ば〜40歳程度まで受験可能なケースがあります。
特に自治体によっては柔軟に年齢制限を設けているところもあるため、募集要項をこまめにチェックすることが重要です。
「年齢制限で諦めそう…」という方も、社会人枠の存在を知れば希望が見えてくるはずです。
高卒で公務員になって後悔しないためのポイントは?

公務員としての仕事に向き合う姿勢と、将来を見据えたキャリア設計が後悔しないためのカギです。
高卒で入庁すると、周囲に大卒者も多く、最初はギャップを感じるかもしれません。
しかし、長期的には勤務年数や実績が重視されるため、焦らず自分のペースで成長することが大切です。
- 積極的に学び、資格取得にも挑戦する
- 上司や先輩との信頼関係を築く
- 業務以外の場面でも視野を広げる
「キャリアの天井があるのでは?」と不安に思う方もいますが、努力次第で昇進も可能です。
自分の目標と価値観を見極めることが、公務員人生を豊かにする第一歩となります。
まとめ:高卒から公務員へ転職するなら「制度理解×対策」が成功のカギ
高卒から公務員への転職は、年齢制限や受験区分を正しく理解し、対策をしっかり行えば十分に可能です。
特に「安定した職を得たい」「地元で長く働きたい」「民間経験を活かしたい」と考える人にとって、公務員は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
本記事で紹介したポイントを押さえることで、転職成功への道筋が見えてきます。
- 高卒でも年齢や受験区分を選べば幅広い職種を目指せる
- 国家・地方・公安・技術職など多様な公務員キャリアが存在
- 昇進・昇給制度も整っており、大卒との差は努力で埋まる
- 試験対策は筆記・面接・適性検査まで幅広く計画的に
- 予備校・通信・独学など自分に合った学習法を選ぶのが成功の近道
「高卒だから」と不安に思う必要はありません。重要なのは、自分に合った区分と対策方法を選び、最後まであきらめずに取り組むことです。
この記事を参考に、あなたの転職が実りある一歩になることを願っています。
高卒からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
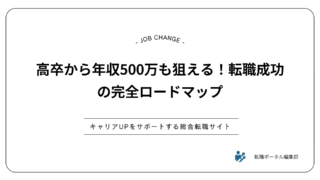
高卒の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓