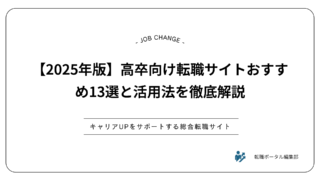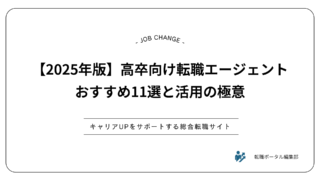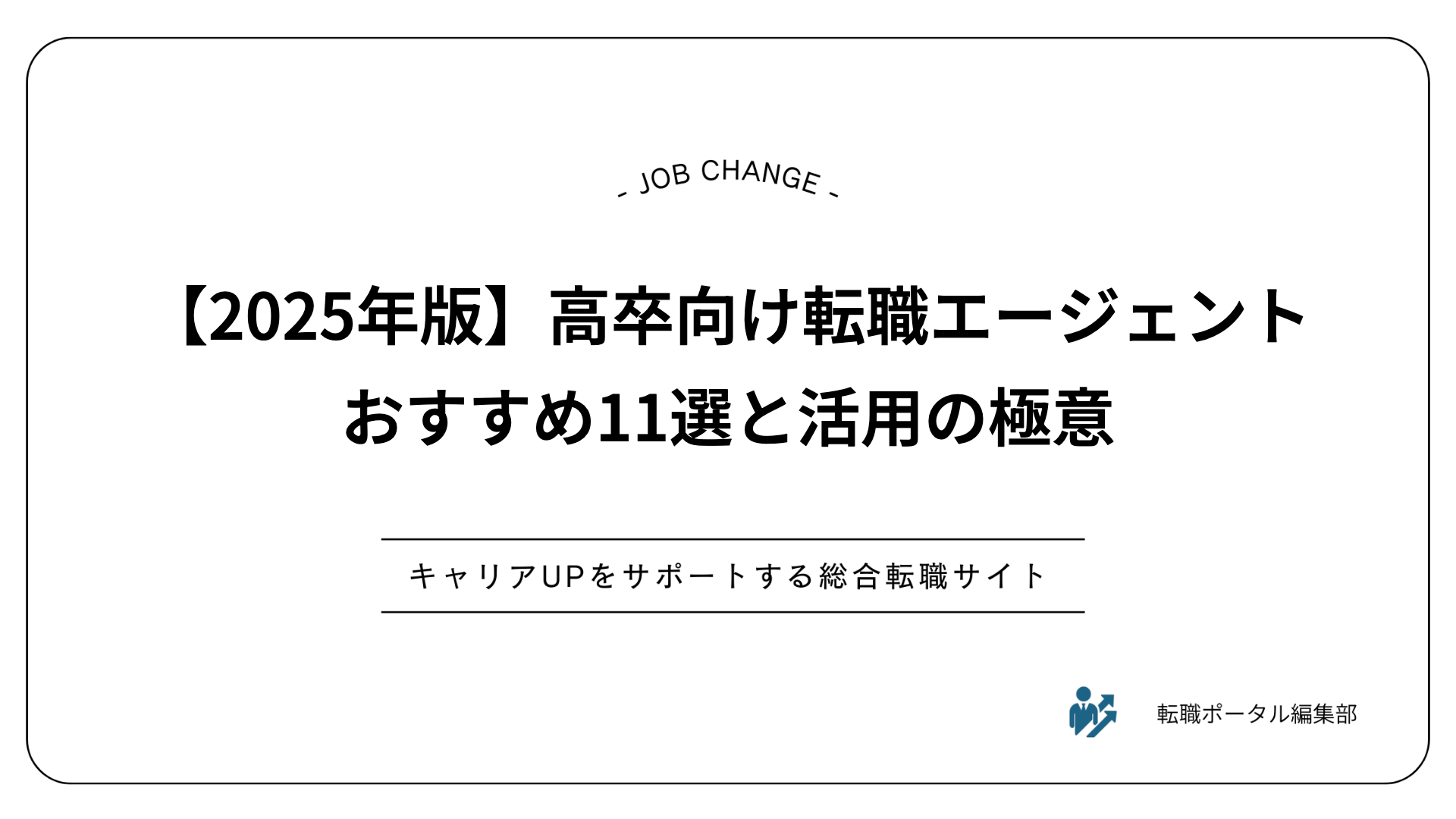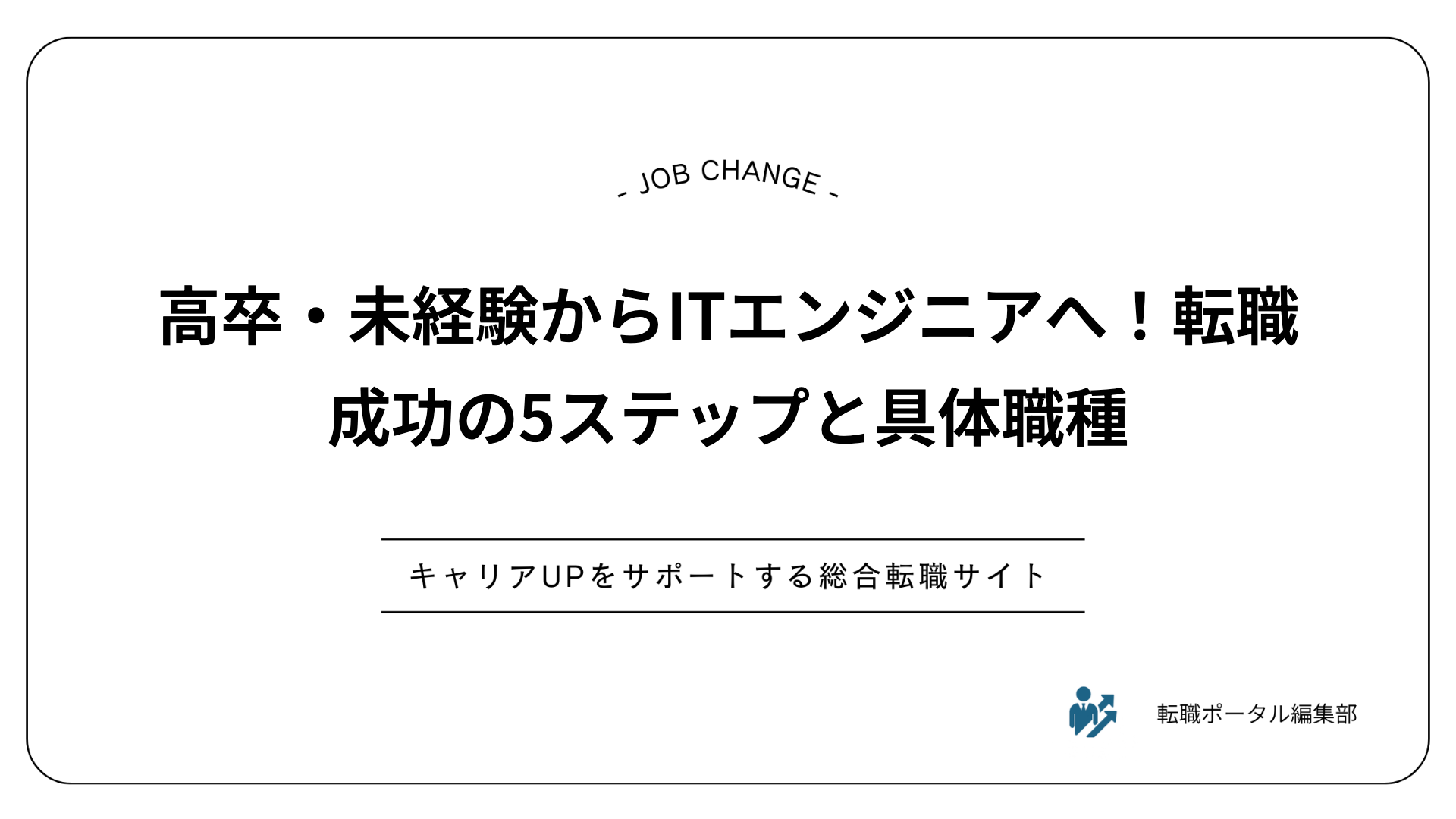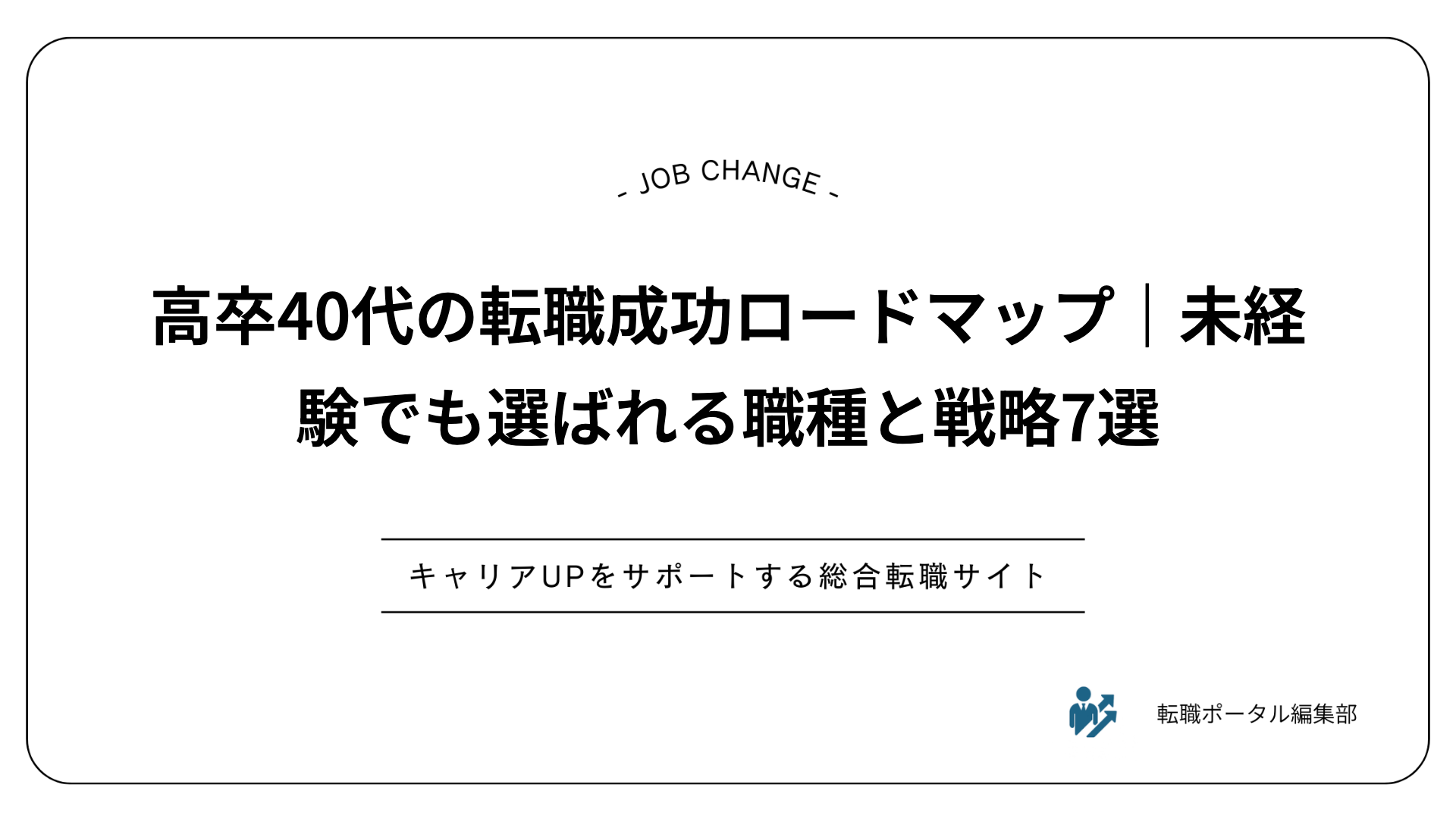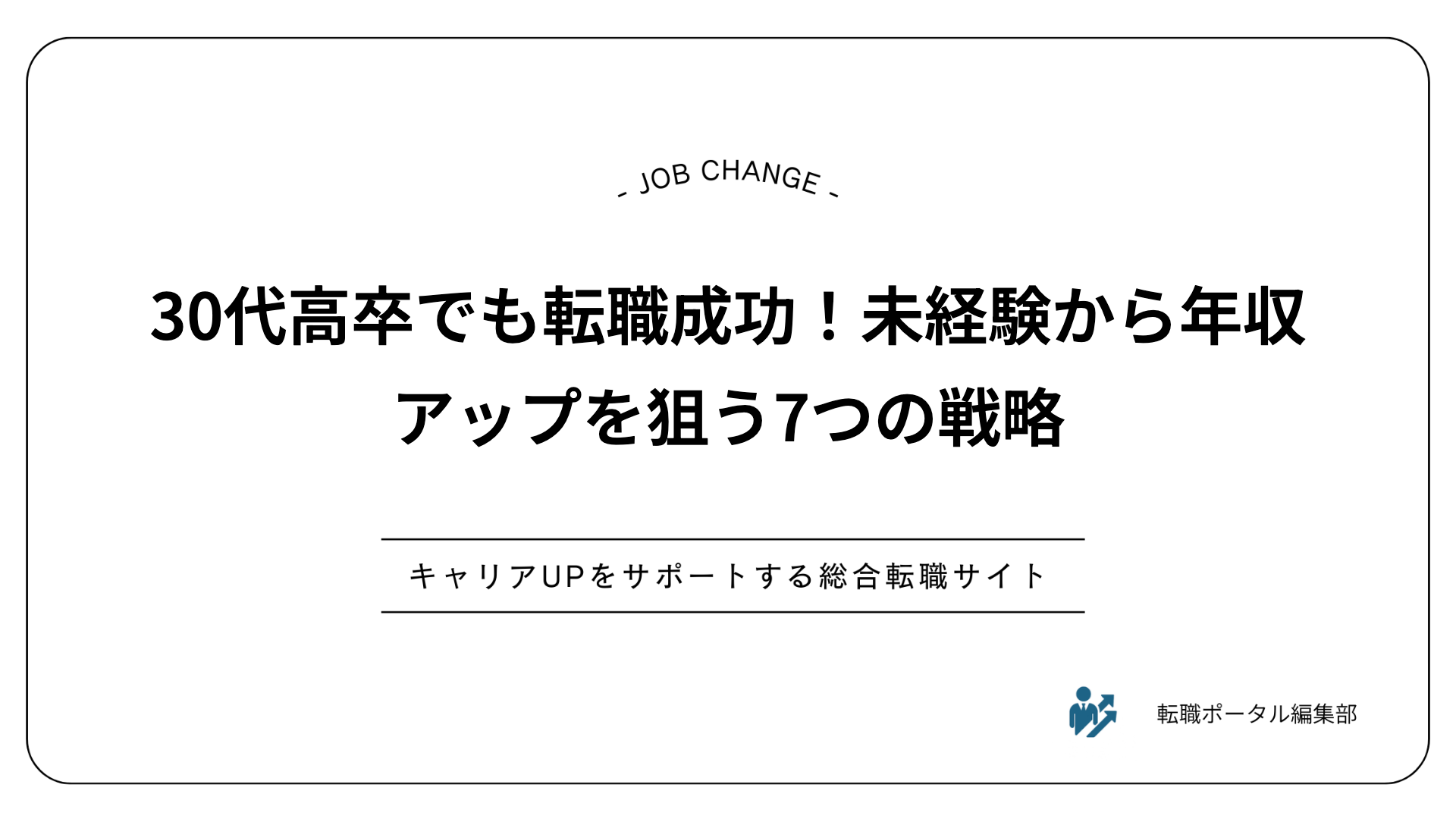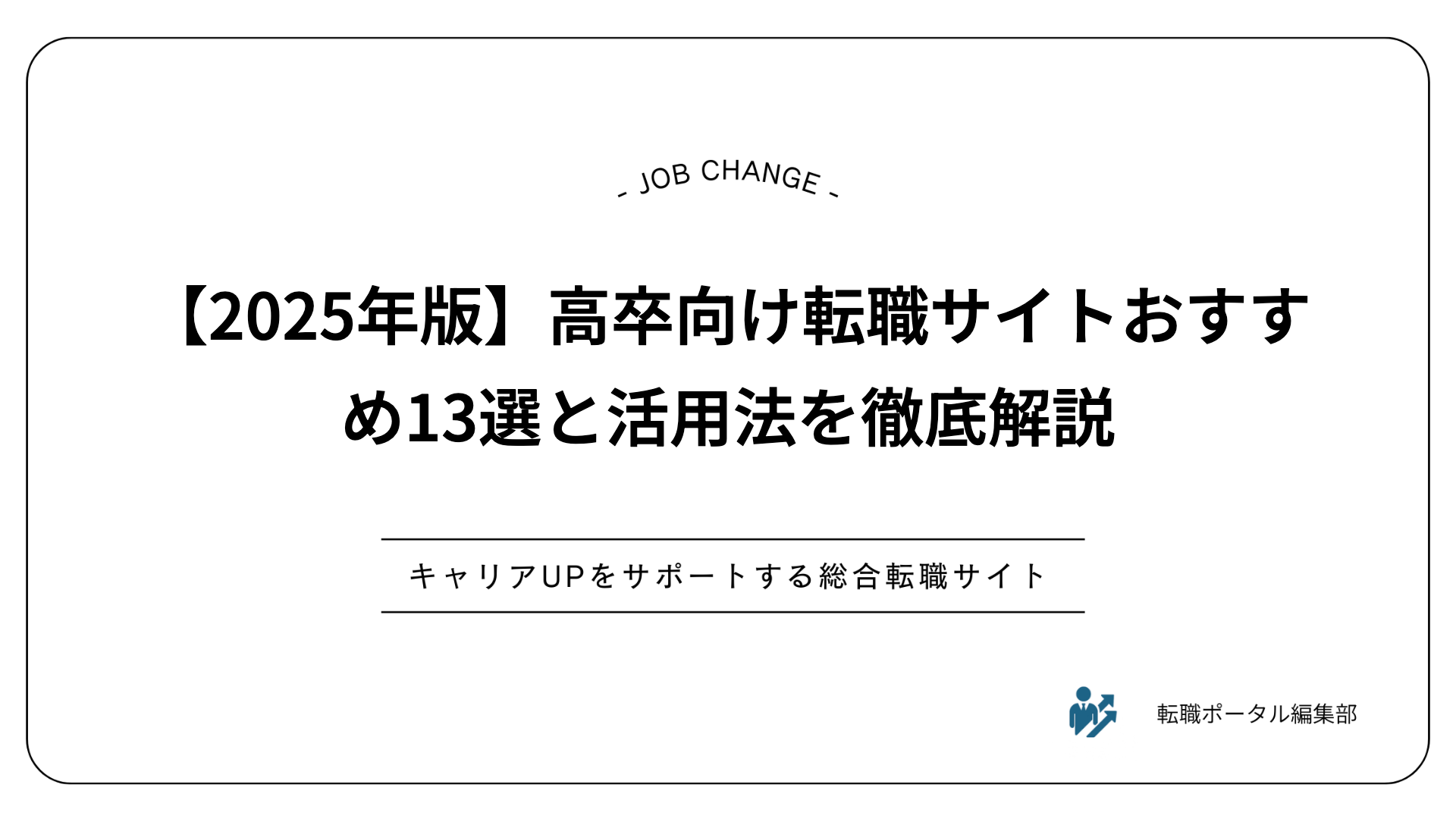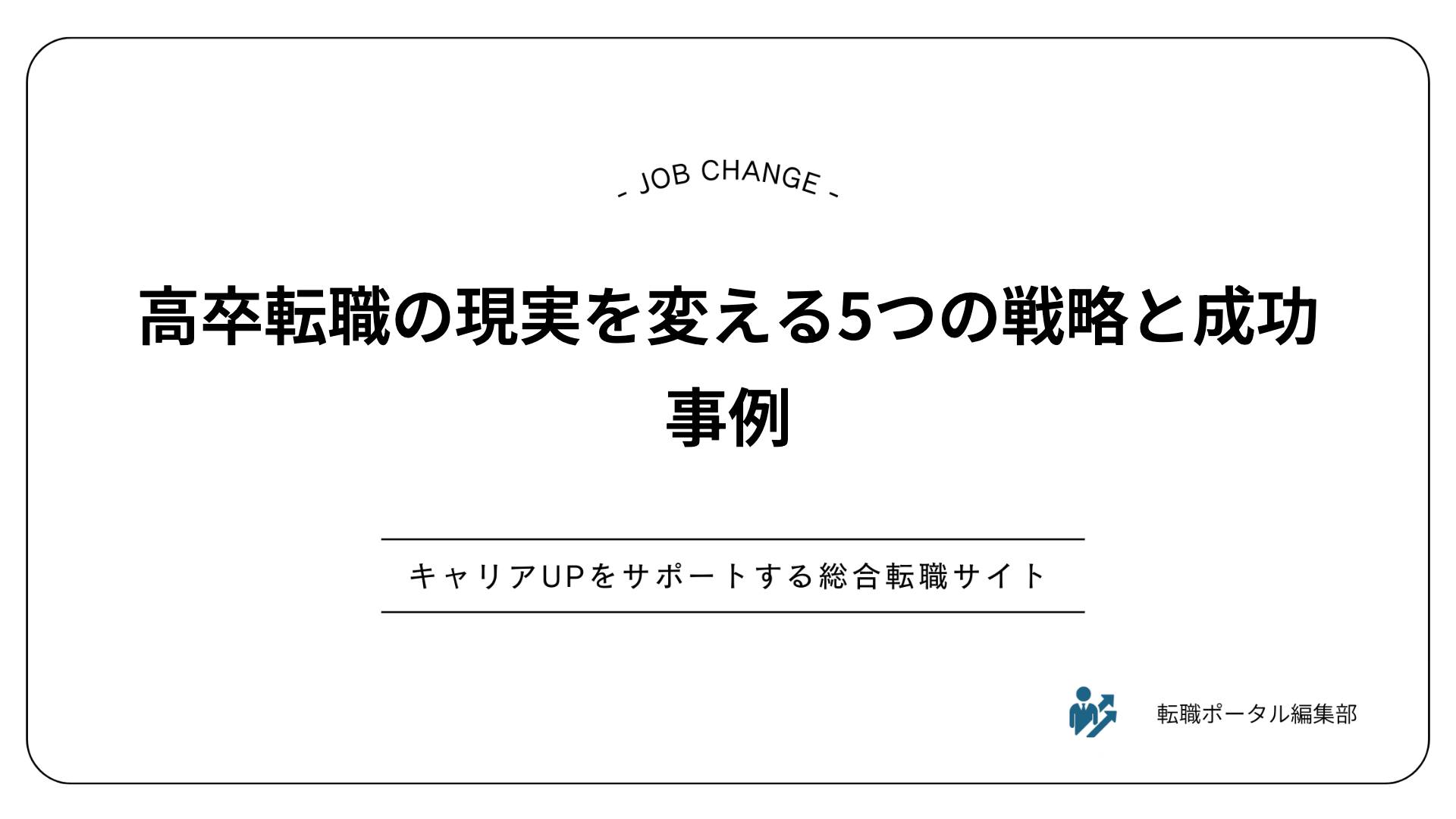高卒の転職に強い!資格選びと成功戦略18選
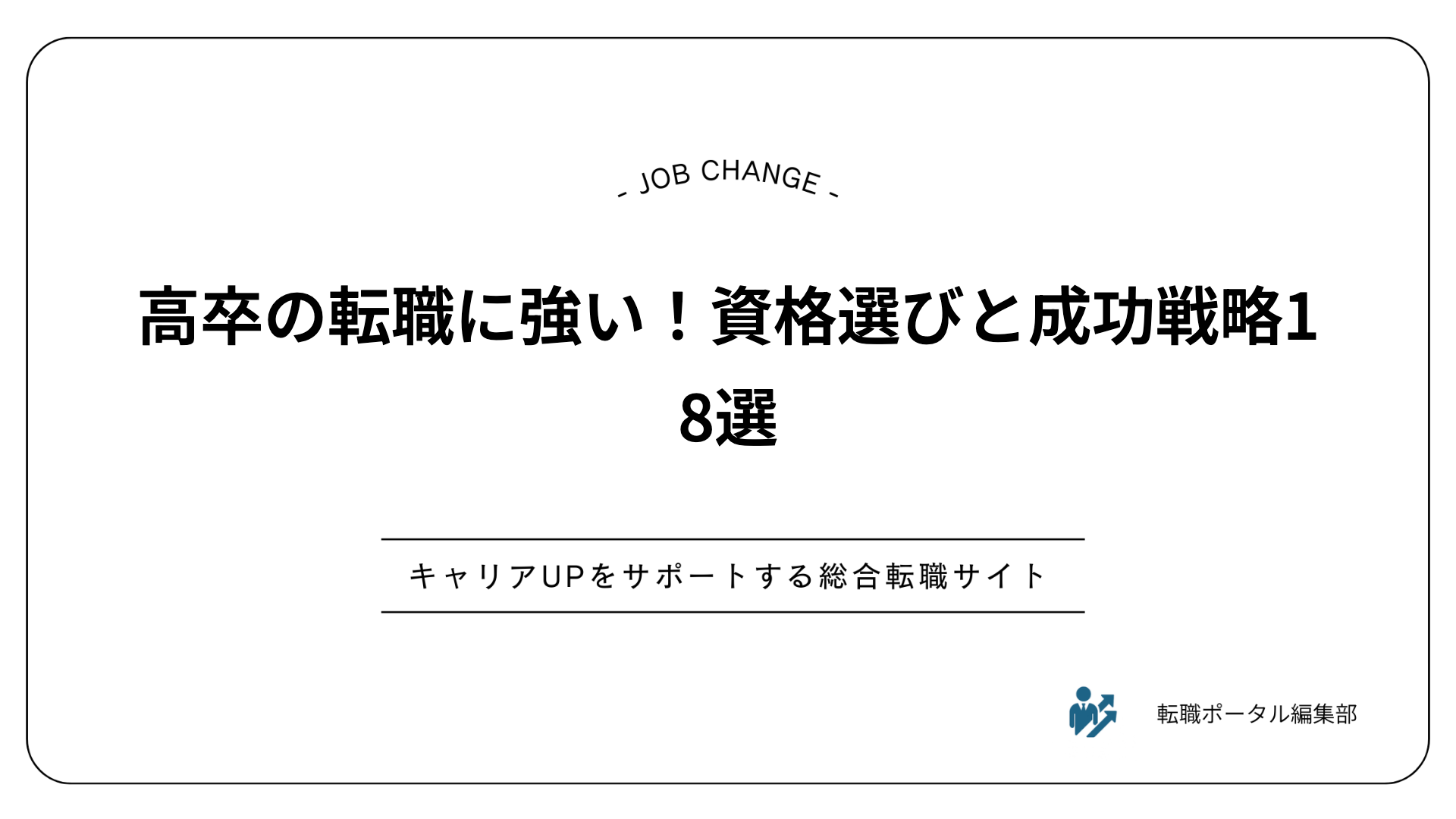
「高卒だから転職が不利かもしれない」
「資格がないと採用されにくいのでは…」
そんな不安を抱えていませんか?
確かに、高卒での転職は大卒と比べて応募できる求人が限られていたり、選考で不利に感じる場面もあるかもしれません。
しかし、状況は変えられます。あなたが本気で新しいキャリアに踏み出したいと考えているなら、「資格」を活用することでチャンスは大きく広がります。
この記事では、高卒の方が転職で有利になるために必要な資格や選び方、効果的な勉強法まで網羅的に解説します。
たとえば、次のような悩みや希望をお持ちの方に役立つ内容です。
- 未経験から専門職に転職したい
- 収入を上げたいけど学歴に自信がない
- 安定した職場で長く働きたい
- 自分に合った資格がわからない
- 仕事と勉強を両立できるか不安
ひとつでも当てはまるなら、ぜひ最後まで読んでみてください。あなたの転職成功に直結するヒントが見つかるはずです。
高卒が資格を取得すると転職で有利になる理由
応募条件を満たせる求人が増える

資格を持つことで、応募できる求人の幅が広がります。これは、高卒者にとって非常に大きな利点です。
企業によっては、特定の資格が応募条件になっていることがあります。
たとえば、不動産や介護、運送業界などでは、資格の有無が採用の前提になるケースも少なくありません。
資格を取得することで、これまで挑戦できなかった求人にもエントリーできるようになり、転職市場での選択肢が大きく広がります。
「高卒だからチャンスが少ない…」と感じているなら、まずは資格取得から始めてみると可能性が大きく広がるかもしれません。
スキルと努力を客観的に証明できる
資格は、あなたの知識や努力を第三者が認める「公式な証明書」として機能します。
学歴では見えにくいスキルや学習意欲を採用担当者に伝える手段として、資格は非常に有効です。
- 基本情報技術者:IT分野の基礎知識を持つ証明
- 簿記検定:経理や会計処理の理解を示す
- FP技能士:お金に関する幅広い知識を持つことを示す
未経験の業界や職種に応募する際にも、「しっかり学んでいる姿勢」が伝われば、ポテンシャルを評価してもらいやすくなります。
「学歴に自信がないけど頑張りたい」そんな方こそ、資格取得でチャンスを掴めます。
年収アップや資格手当につながる

資格には「収入アップ」のチャンスも含まれています。特定の資格を持つことで、基本給が上がったり、資格手当が支給されることも珍しくありません。
たとえば不動産業界の宅建士、介護業界の介護福祉士、電気関連の電気工事士などは、その代表例です。
資格によっては、月数千円〜数万円の手当が付く場合もあり、年収換算で見ると大きな違いになります。
「収入を少しでも上げたい」「生活にゆとりを持ちたい」と考えている方は、資格をひとつの武器として検討してみてはいかがでしょうか。
「資格って本当に収入に直結するの?」と疑問に思うかもしれませんが、求人票や転職サイトを見ると、手当が明記されている職種は多くあります。
未経験分野へのキャリアチェンジがしやすい
資格は、新しい業界への第一歩として非常に有効です。
- ITパスポート → 未経験からIT事務へ
- 介護職員初任者研修 → 福祉業界の入口に最適
- 登録販売者 → ドラッグストアでの採用に有利
たとえば、IT業界に興味がある方が、基本情報技術者を取得すれば「基礎がある」と評価されやすくなります。
これにより、未経験でも採用される可能性が高まります。
キャリアの選択肢を広げたいと考えているなら、まずは興味のある分野で使える資格から始めてみるのがよいでしょう。
「未経験じゃ無理では?」と不安な方もいると思いますが、資格があることで面接官に「真剣に取り組んでいる」と伝えることができます。
資格選びのポイント
仕事で活かせるかどうか
結論から言うと、「実務で使える資格」を選ぶことが転職成功のカギです。
資格の中には知識が身につくものの、業務に直結しないものもあります。
せっかく時間とお金を使って勉強するなら、転職先の職種や業界で活用できるものを選びましょう。
たとえば、経理職を目指すなら簿記、IT職なら基本情報技術者、販売職なら登録販売者やMOSが有力です。
実際にどんな仕事に就きたいかを明確にすることで、必要な資格が自然と見えてきます。
「何から手をつけていいかわからない…」という方は、まず興味ある職種の求人をチェックして、求められている資格を確認してみましょう。
国家資格と民間資格の違い

資格には「国家資格」と「民間資格」の2種類があり、目的によって選び方が変わります。
- 国家資格:国が法律で定めた資格で、社会的信頼性が高い(例:宅建士、行政書士、介護福祉士)
- 民間資格:企業や団体が独自に認定している資格(例:MOS、ITパスポート、日商簿記)
国家資格は取得難易度が高めですが、職務独占や名称独占の効力があるため、キャリアに直結しやすいです。
一方、民間資格は比較的取得しやすく、スキルの証明や就職の足がかりとして有効です。
どちらを選ぶべきか迷ったら、将来的に独立したいなら国家資格、早く転職結果を出したいなら民間資格がひとつの目安になります。
取得難易度と学習コスト
資格取得には時間や費用がかかります。自分の状況に合わせて、無理なく続けられるものを選ぶことが重要です。
- FP3級やMOS:学習期間1〜2ヶ月、初心者向け
- 簿記2級やITパスポート:2〜3ヶ月で取得可能
- 宅建士や基本情報技術者:3〜6ヶ月の計画的な学習が必要
仕事と両立しながら学ぶ場合、1日30分でも良いので無理なく続けられる資格を選びましょう。
勉強の習慣がつくことで、モチベーションも維持しやすくなります。
「途中で挫折しないか不安…」という方は、まずは難易度の低い資格から始めて「合格体験」を積み重ねるのも有効です。
将来性・需要が高い分野か

今後の社会で求められるスキルが身につく資格を選ぶことも、転職を成功させるポイントです。
特に注目されているのは以下の分野です。
- IT・DX系:AI・セキュリティなどのニーズが拡大(ITパスポート、基本情報技術者)
- 福祉・医療系:高齢化社会により需要が安定(介護福祉士、医療事務、登録販売者)
- ライフプラン系:お金に関する知識が役立つ(FP技能士、簿記)
10年後にも需要が見込まれる分野を意識することで、「長く使えるスキル」を身につけることができます。
「今の流行りだけで選んで大丈夫かな?」と迷う場合は、複数の資格を組み合わせることで、より安定した転職戦略が立てられます。
高卒におすすめの国家資格
宅地建物取引士(宅建士)
宅建士は、不動産業界で必須とされる国家資格です。とくに不動産売買・賃貸の仲介業務では、法律上「宅建士の配置」が義務付けられています。
そのため、宅建資格を持っているだけで不動産会社からのニーズが非常に高く、転職時のアピール材料として有効です。
試験の出題範囲には法令や税制などが含まれますが、学歴による受験制限はなく、高卒でも十分に合格可能です。
「未経験でも不動産業界に挑戦したい」という方には、まさにぴったりの資格です。
行政書士
行政書士は、法律に関する書類作成や手続きを代行できる国家資格で、個人開業も可能な「士業」のひとつです。
- 高卒でも受験可能で、学歴に関係なくチャレンジできる
- 独立・開業が可能で自由な働き方も目指せる
- 企業の総務・法務部門でも重宝される
「将来的に独立も視野に入れてキャリアを築きたい」「法務分野に強くなりたい」という方におすすめです。
基本情報技術者
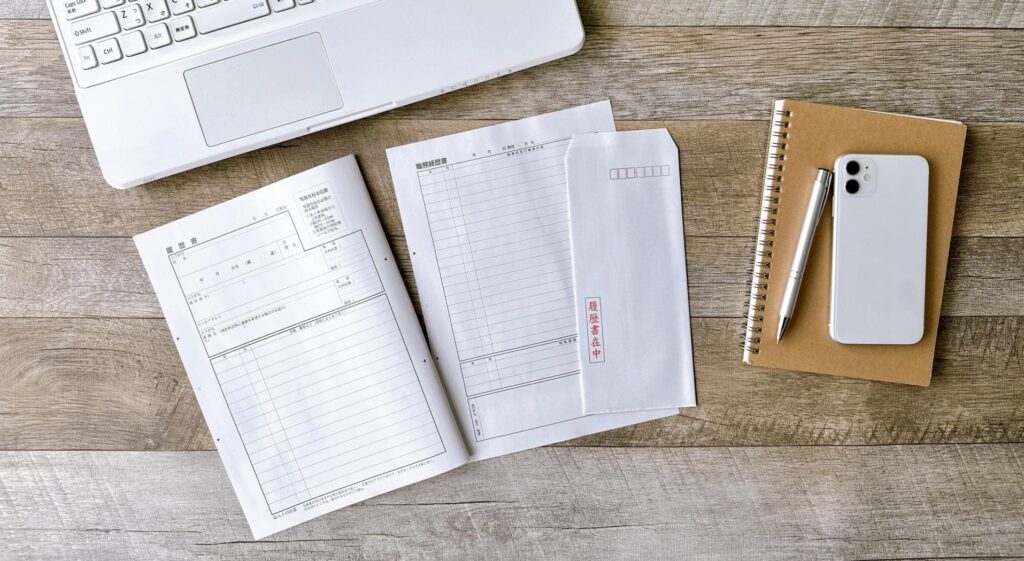
IT業界を目指すなら、まず取得しておきたいのがこの資格です。
経済産業省が認定する国家資格で、プログラミングやネットワーク、データベースなどの基礎知識が問われます。
高卒でIT分野に興味がある方は、独学または通信講座での対策が現実的です。難易度は中級程度ですが、合格すれば履歴書の印象が格段にアップします。
「将来性のある業界に入りたい」「デジタルスキルを身につけたい」方に最適です。
危険物取扱者(乙種四類)
ガソリンスタンドや工場、化学系企業で働くうえで重宝されるのが危険物取扱者の資格です。
- 日常生活に身近な危険物を取り扱える
- 試験内容は物理・化学の基礎が中心
- 求人条件として指定されることが多い
「ものづくり系」「工場勤務」などを希望する高卒者には、まず取得しておきたい実用的な資格といえるでしょう。
介護福祉士

介護福祉士は、介護職で唯一の国家資格であり、福祉業界でのキャリアアップに欠かせません。
実務経験が3年以上必要ですが、介護職員初任者研修→実務者研修→介護福祉士というルートで段階的にステップアップできます。
福祉業界は人手不足で常に求人があり、安定した収入と職場を求める方には非常に向いています。
高卒から福祉業界で長く働きたい、将来は施設長などの管理職を目指したい方にはおすすめの資格です。
登録販売者
ドラッグストアや薬局で医薬品を販売できる「準薬剤師」とも言える資格です。第一類を除く市販薬(風邪薬・胃薬など)の販売が可能になります。
- 都道府県認定の公的資格で信頼性が高い
- 筆記試験のみで取得可能
- 安定性の高いドラッグストア業界で評価される
「安定して働ける職場が良い」「接客+専門知識を活かしたい」方にはとくにおすすめです。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)
FP技能士は「お金に関する知識」を体系的に学べる国家資格で、保険・金融・不動産・年金など多岐にわたる分野を網羅しています。
高卒者でも受験可能で、3級→2級と段階的にステップアップできる点も魅力です。
銀行や保険会社、不動産会社などでの活躍に直結するほか、家計管理やライフプランにも役立つため、汎用性の高い資格です。
「将来は金融系も検討したい」「お金の知識を武器にしたい」という方にはぴったりでしょう。
第二種電気工事士

電気設備の工事・保守に関わる国家資格で、特にビル管理・工場・電気関連企業などで求められる場面が多い資格です。
- 筆記と技能試験の2ステップで取得可能
- インフラ業界での安定した需要
- 独立・開業にもつながるスキル
「実務スキルで強みを作りたい」「現場で活躍したい」という方は、ぜひ挑戦してみてください。
高卒におすすめの民間資格
MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
MOSは、WordやExcelなどのMicrosoft Office製品の操作スキルを証明する資格です。
事務職や営業アシスタントなど、パソコンを使う職種全般で役立つため、特に高卒の転職市場では即戦力のアピールにつながります。
- 試験は随時実施されており、受験しやすい
- Word・Excel・PowerPointなどの科目別に取得可能
- 実務スキルとして企業評価が高い
「パソコン操作に自信がないけど事務職に就きたい」方に最適なスタート資格です。
日商簿記検定

簿記は、経理や会計の基礎を学ぶ資格で、特に日商簿記は企業からの認知度が高く、経理職や事務職を目指す際に有利です。
3級であれば初心者でも取り組みやすく、2級まで取れば即戦力として高評価されることもあります。
会計知識はどんな業種にも活かせるため、「数字に強い人材」として差別化を図ることができます。
「安定した事務職に就きたい」「将来は経理にキャリアチェンジしたい」方におすすめです。
ITパスポート
ITパスポートは、ITの基礎知識を証明する国家レベルの民間資格で、IT業界はもちろん、一般企業の事務職でも評価されます。
- 情報セキュリティやネットワークの基礎が身につく
- 就職・転職活動の際に「ITに強い」印象を与えられる
- 独学でも合格可能で、試験もCBT方式で手軽
「今後はIT業務にも関わりたい」「社内でデジタル化に対応できる人材になりたい」という方にぴったりの資格です。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
医療事務は、病院やクリニックの受付・会計業務などを担当する職種で、特に女性に人気の高い分野です。
中でも「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)」は、民間資格の中でも信頼性が高く、多くの医療機関で採用要件として扱われています。
働き方に柔軟性があり、パートや時短勤務などライフスタイルに合わせて働きたい方にもおすすめです。
調剤事務管理士技能認定試験

この資格は、調剤薬局における受付業務やレセプト(調剤報酬請求)作成を行うための知識を証明するものです。
- 女性を中心に需要が高い
- 医療事務よりも試験難易度が低め
- 資格があると即戦力として採用されやすい
未経験から医療業界に関わりたい方や、安定性を重視した転職を考えている方に向いています。
介護職員初任者研修
介護業界に入門するための最初の資格で、以前の「ホームヘルパー2級」に相当します。
資格を取得することで、施設だけでなく訪問介護の仕事にも携われるようになり、職域が広がります。
実務経験を積んでいけば、介護福祉士へのステップアップも可能なため、長期的なキャリア形成にもつながります。
「人の役に立ちたい」「社会的意義のある仕事をしたい」方に適しています。
TOEIC Listening & Reading Test

TOEICは、英語のリスニング・リーディング力を数値化する民間試験で、多くの企業が英語力の指標として活用しています。
- スコア600以上で事務職や貿易関連でも有利
- グローバル企業・外資系企業での応募資格になることも
- 資格手当や昇進条件に設定されている企業もある
英語が得意な方や、語学力を活かした仕事に挑戦したい方には、非常に価値の高い資格です。
年代・キャリア別のおすすめ資格戦略
十代〜二十代向け:職種選択の幅を広げる基礎資格
若いうちは経験が少ない分、資格で自分の可能性を広げることが大切です。
社会人経験が浅いからこそ、「職種に縛られない汎用スキル」や「ポテンシャルを示せる資格」を選ぶとよいでしょう。
- ITパスポート:どんな職種でも役立つITの基礎
- 簿記3級:数字に強い印象を与える
- MOS:事務系スキルの基礎を習得
将来どの業界に進むか迷っているなら、まずはこれらの資格で自分の適性を探ることから始めてみましょう。
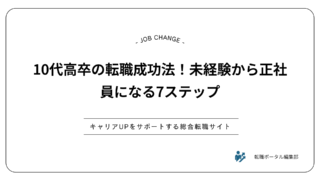
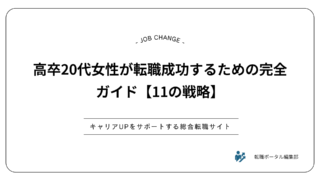
三十代向け:キャリアアップ・独立につながる資格
30代は「実務経験+専門スキル」で差をつけやすい年代です。
転職市場では即戦力が求められるため、より専門性の高い資格でキャリアアップや独立を視野に入れた戦略をとりましょう。
- 宅建士:不動産業界での昇格や独立に有利
- FP2級:保険・不動産・金融業界で評価が高い
- 第二種電気工事士:技術系職種で独立も可能
これまでの経験に「資格」という証明を加えることで、選ばれる人材になれます。

女性向け:ライフイベントと両立しやすい資格

結婚・出産など、ライフステージの変化に備えて、柔軟な働き方が可能な資格を選ぶこともポイントです。
家庭と仕事を両立したい方には、短時間勤務や在宅ワークができる業界・職種で活かせる資格が向いています。
- 医療事務:パートや時短勤務が可能
- 調剤事務管理士:未経験でも就職しやすい
- MOS:在宅事務や派遣での活用も可
将来のライフスタイルを見据えて、安定した資格を早めに取得しておくと安心です。
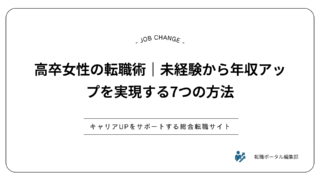
資格取得のステップ
自己分析でキャリアビジョンを明確にする
資格取得を成功させるには、まず「なぜその資格が必要なのか」を明確にすることが大切です。
自分のキャリアの方向性や興味のある分野を整理することで、勉強のモチベーションを保ちやすくなります。
- 将来どんな仕事に就きたいかを考える
- どんな働き方をしたいのかをイメージする
- その職種に必要なスキルや資格を洗い出す
「何となく人気があるから」ではなく、「自分に必要だから」と納得して選ぶことで、学習に対する意欲も持続しやすくなります。
学習計画とスケジュールの立て方

資格取得には、継続的な勉強が必要です。短期で成果を出すためにも、現実的で継続可能な学習スケジュールを作りましょう。
最初に試験日から逆算して、1週間ごと・1ヶ月ごとの目標を立てると進捗管理がしやすくなります。
特に仕事や家事と両立する場合は、「毎日30分」などの小さな習慣を作ることが合格への近道です。
「途中で挫折しそう…」という不安があるなら、週1回の振り返り日を設けるだけでもリズムが整います。
独学・通信講座・スクールの選択基準
勉強方法には大きく分けて3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の性格や生活リズムに合ったものを選びましょう。
- 独学:コストが安いが、情報収集や計画管理が必須
- 通信講座:サポート付きで効率的に学べる、費用は中程度
- スクール通学:質問しやすく仲間もできる、費用は高め
「独学に自信がない」「時間管理が苦手」という方は、通信講座の活用が特におすすめです。
試験直前期の勉強法とメンタル管理
試験が近づくにつれ、焦りや不安が出やすくなります。そんな時期こそ、正しい勉強法とメンタルの整え方が合否を分けます。
復習中心の学習に切り替え、過去問や模擬試験を使って実戦形式に慣れることが重要です。
メンタル面では、「完璧を求めすぎない」「わからない問題は飛ばす」などの柔軟さが必要です。
緊張するのは当然なので、深呼吸や散歩などで心身をリセットする習慣も取り入れてみましょう。
資格以外にアピールできるポイント
実務経験とポータブルスキル

資格だけでなく、これまでの職務経験や「どこでも活かせるスキル」も重要なアピール要素です。
- コミュニケーション力:接客・営業・チーム業務で培われた経験
- 問題解決力:トラブル対応や改善提案の経験
- PCスキル:Excelやメール対応などの事務処理能力
高卒でも、現場で積み上げた経験や汎用的なスキルをしっかり言語化できれば、資格がなくても評価されることがあります。
「経験が浅いから…」と不安に感じる方こそ、今までの仕事を棚卸ししてみることをおすすめします。
面接で評価される主体的な学び姿勢
採用担当者が注目するのは「どれだけ資格を持っているか」だけでなく、「なぜそれを取ろうと思ったのか」「どんな姿勢で学んでいるか」です。
たとえ未経験でも、資格取得に向けた努力や継続的な学びをアピールできれば、大きなプラス評価につながります。
「将来こうなりたいからこの資格を勉強した」「仕事の幅を広げたくて勉強している」という動機を、自分の言葉で語れるように準備しておきましょう。
成果を示すポートフォリオや実績

目に見える成果や実績を示せると、説得力が一段と増します。
- Excelで作成した資料や業務改善の報告書
- 接客や営業での「売上貢献」や「表彰履歴」
- ブログやSNSなど、自発的に発信した活動
たとえ資格が未取得でも、こうしたアウトプットがあることで、「実力を証明できる人材」としての印象が強くなります。
「ポートフォリオって難しそう…」と感じた方も、まずは過去の成果を時系列でメモすることから始めてみてください。
高卒転職と資格に関するよくある質問
資格なしでも転職は可能か
結論から言えば、資格がなくても転職は可能です。ただし、選べる職種の幅や企業の選考通過率は、やはり資格がある場合と比べて狭まる傾向があります。
とはいえ、以下のようなポイントをアピールできれば、資格がなくても高く評価されることもあります。
- 前職での実務経験や業務成果
- コミュニケーション力・柔軟性などの対人スキル
- 学ぶ意欲や仕事への前向きな姿勢
未経験職種への挑戦であっても、「資格は現在取得中」といった姿勢を伝えるだけでも印象は変わってきます。
在職中に資格勉強を両立するコツ
働きながらの勉強は決して楽ではありませんが、工夫次第で十分に両立可能です。
- 通勤時間を音声学習にあてる
- スキマ時間にアプリや動画で学習
- 土日はまとめて過去問に取り組む
最も大切なのは「完璧を目指しすぎず、コツコツ続ける」ことです。無理のない目標設定で、継続しやすい仕組みを作りましょう。
「続けられるか不安…」という方は、勉強日記やSNSでの発信など、モチベーション維持の仕組みを取り入れてみてください。
複数資格の優先順位の付け方
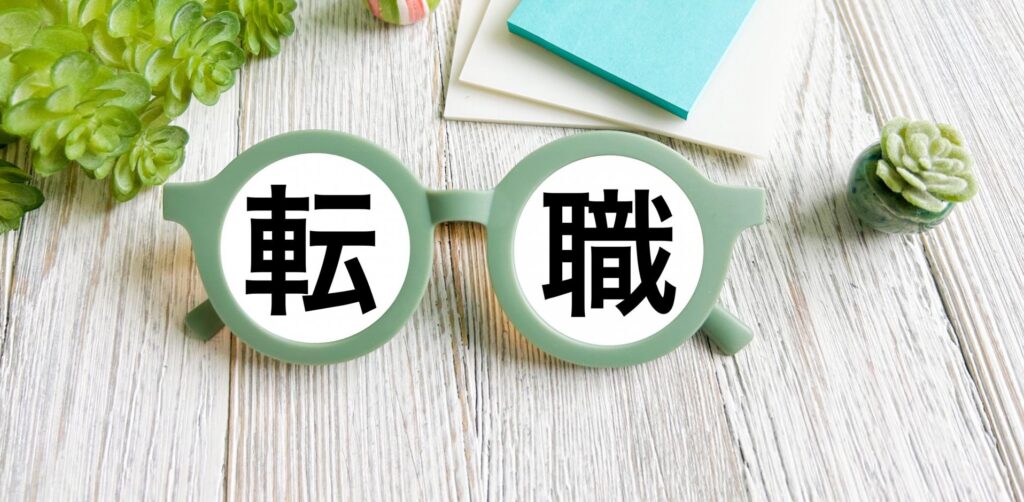
複数の資格に興味がある場合、まずは「目的」と「効果の即効性」で優先順位をつけるのがおすすめです。
たとえば、転職を急いでいるなら短期間で取得可能な資格から、将来独立を目指すなら難易度は高くても専門性の高い資格を優先しましょう。
また、以下のような観点も参考になります。
- 希望職種で必要とされる資格か
- 取得にかかる時間と費用
- 転職活動のスケジュールとのバランス
「どれも大事に思える…」という場合は、まず最も汎用性が高い資格から始めると、次の選択にもつながりやすくなります。
まとめ:資格は高卒の転職を加速させる最強の武器
資格取得で高卒の転職に差をつけよう
高卒であっても、適切な資格を取得することで、転職市場での立場を大きく改善できます。
実際に、資格があることで応募できる職種が広がり、面接での説得力も増し、さらには年収アップや手当の対象になることも多くあります。
- 応募条件を満たせる求人が増える
- スキル・努力を客観的に示せる
- 資格手当や年収アップが見込める
- 未経験分野へのキャリアチェンジに役立つ
- 職場・ライフスタイルに合わせた柔軟な資格選択が可能
だからこそ、高卒の方こそ「資格」という武器を活用して、自分のキャリアを主体的に切り開いていくべきです。
「学歴がないから…」と悩む前に、まずは一歩、資格取得から踏み出してみましょう。
キャリアゴールから逆算して行動を始めよう

どの資格を選ぶか迷ったときは、「将来どうなりたいか」を起点に考えることが大切です。
今すぐ転職したいのか、将来独立したいのか、安定した働き方を優先したいのかによって、最適な資格は変わってきます。
ゴールを明確にすることで、やるべきことも、学ぶべき知識も、無駄なく見えてきます。
今日がそのスタート地点です。ぜひ今この瞬間から、自分にとって最適な一歩を踏み出してみてください。
高卒からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
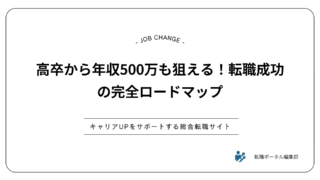
高卒の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓