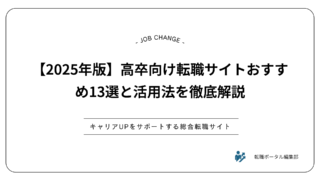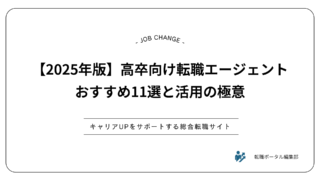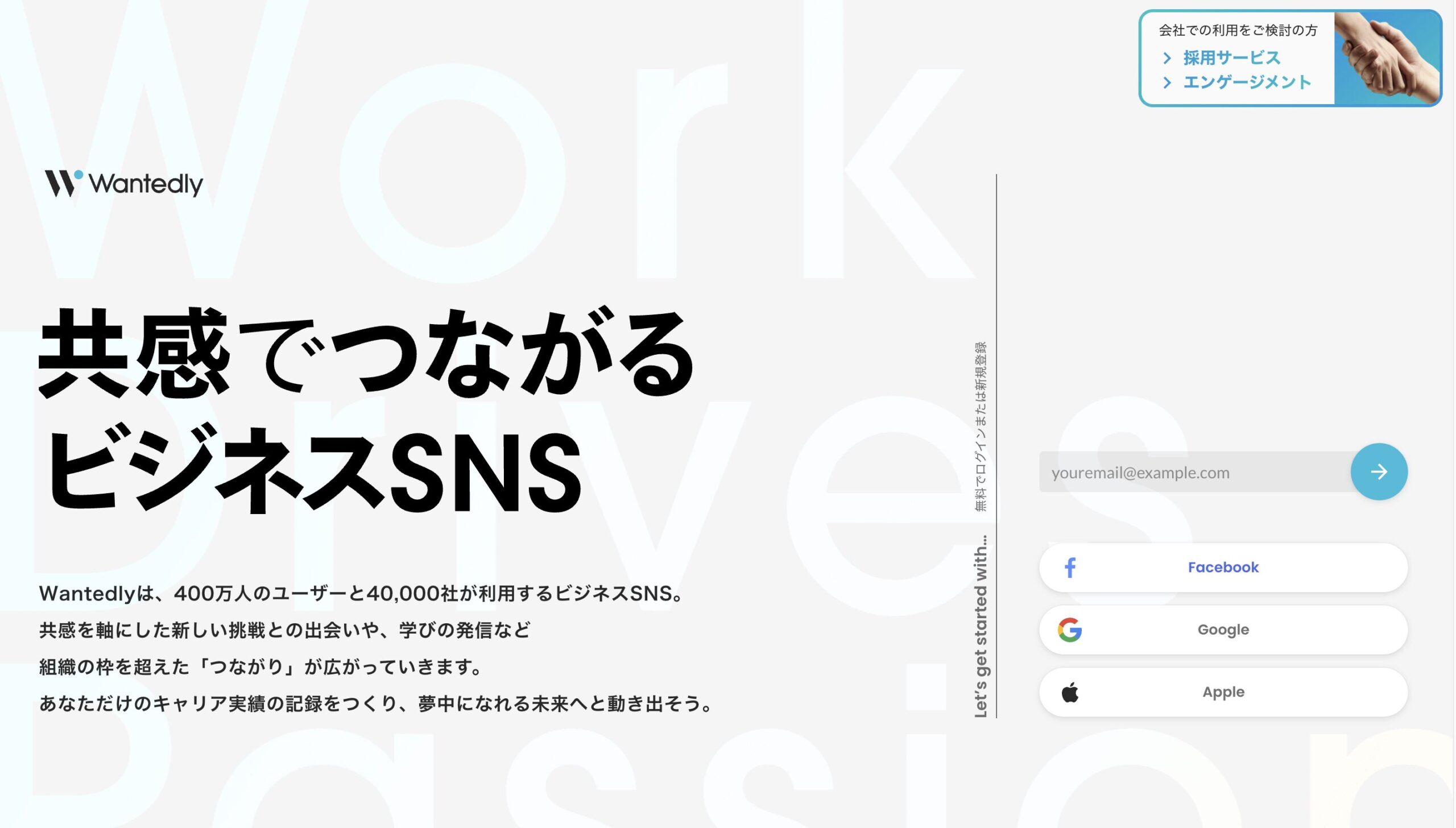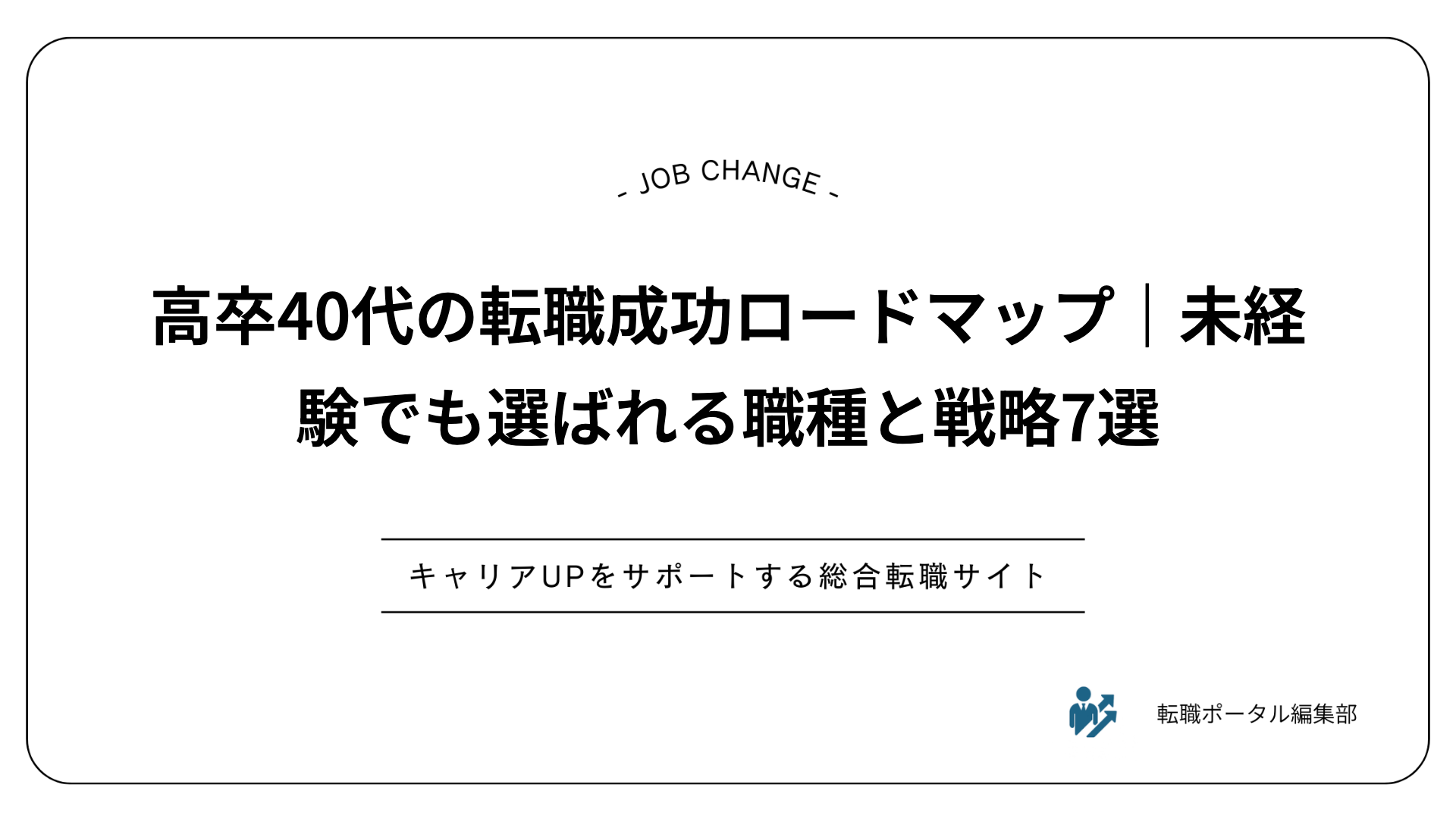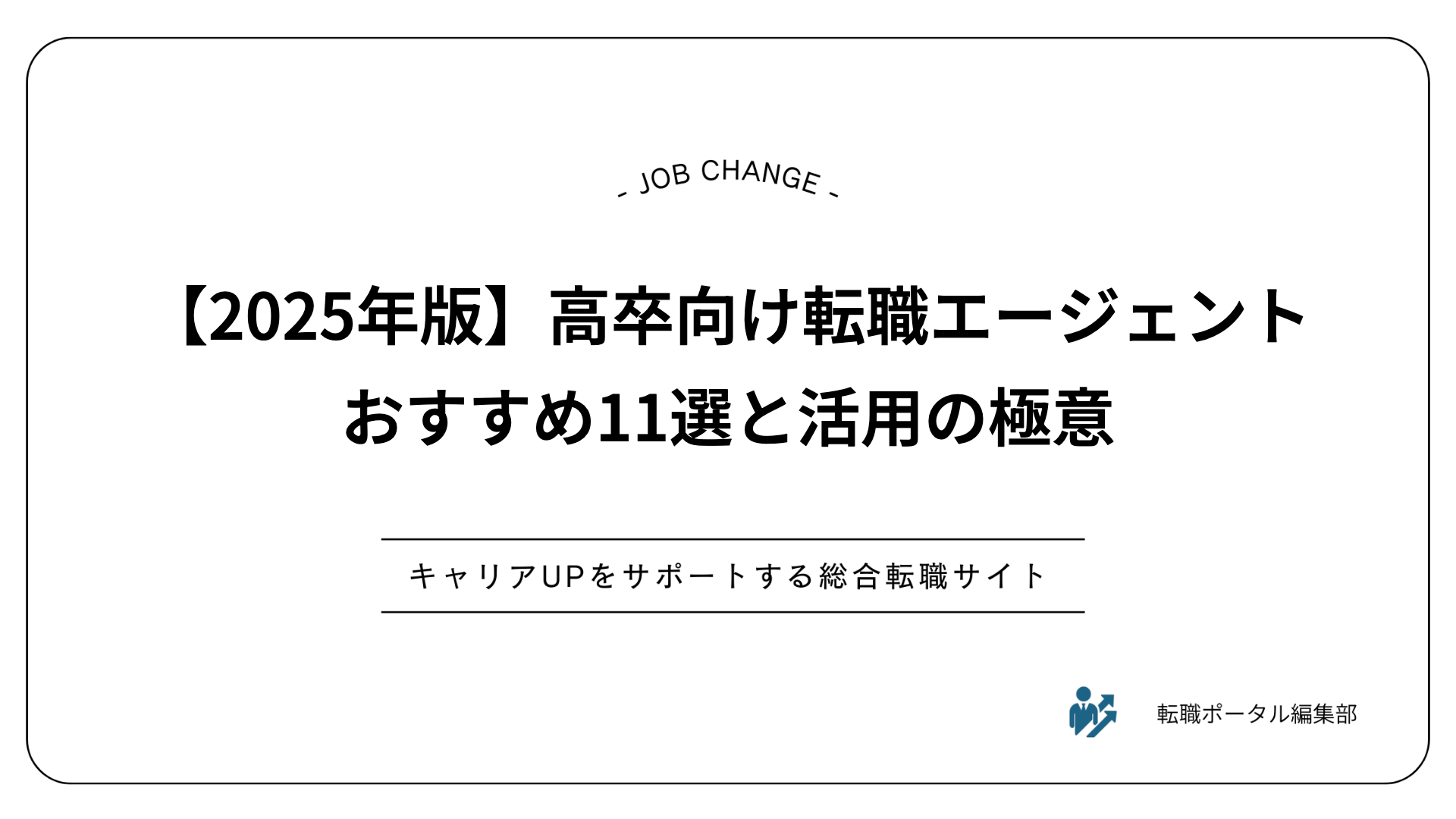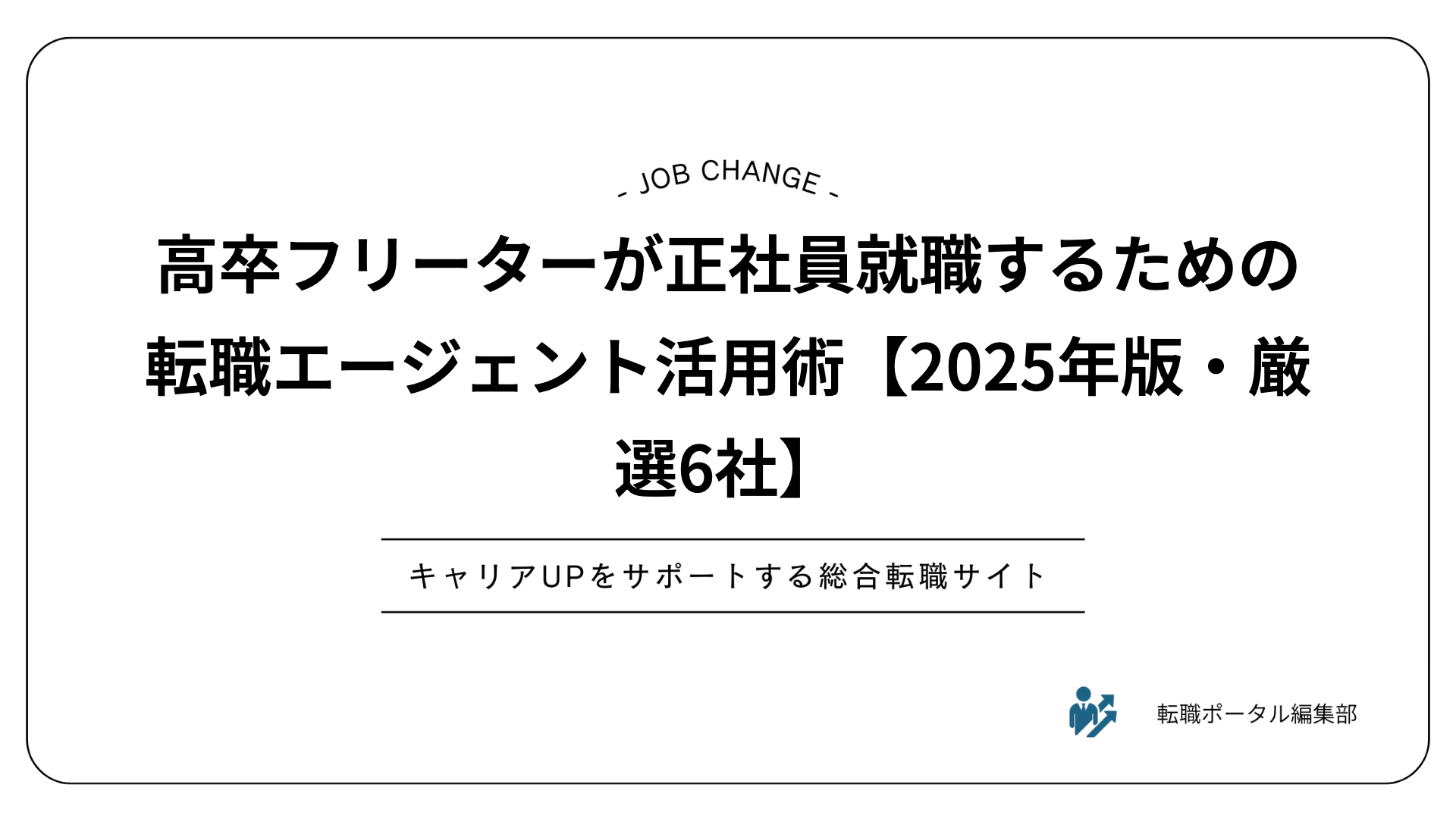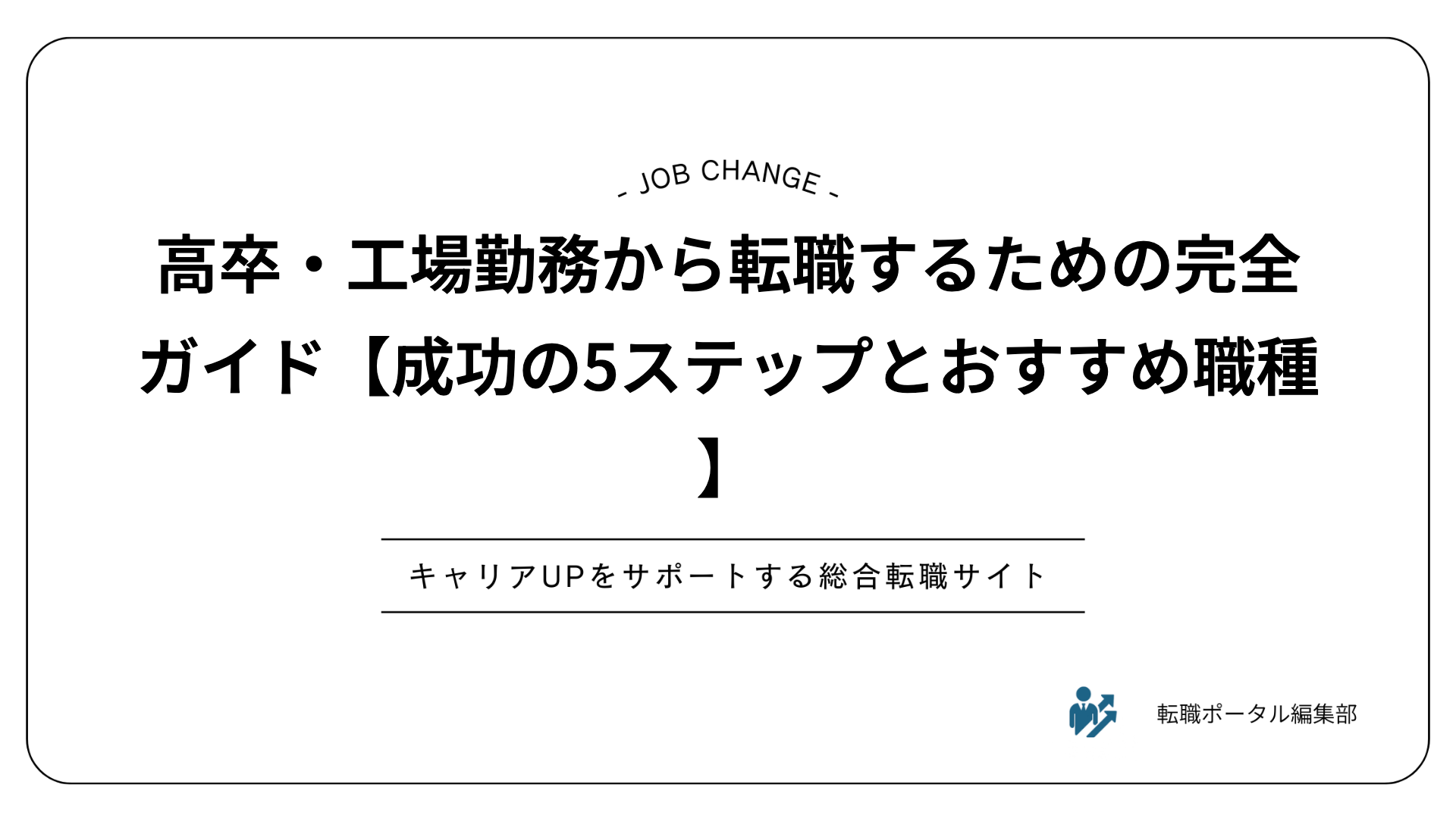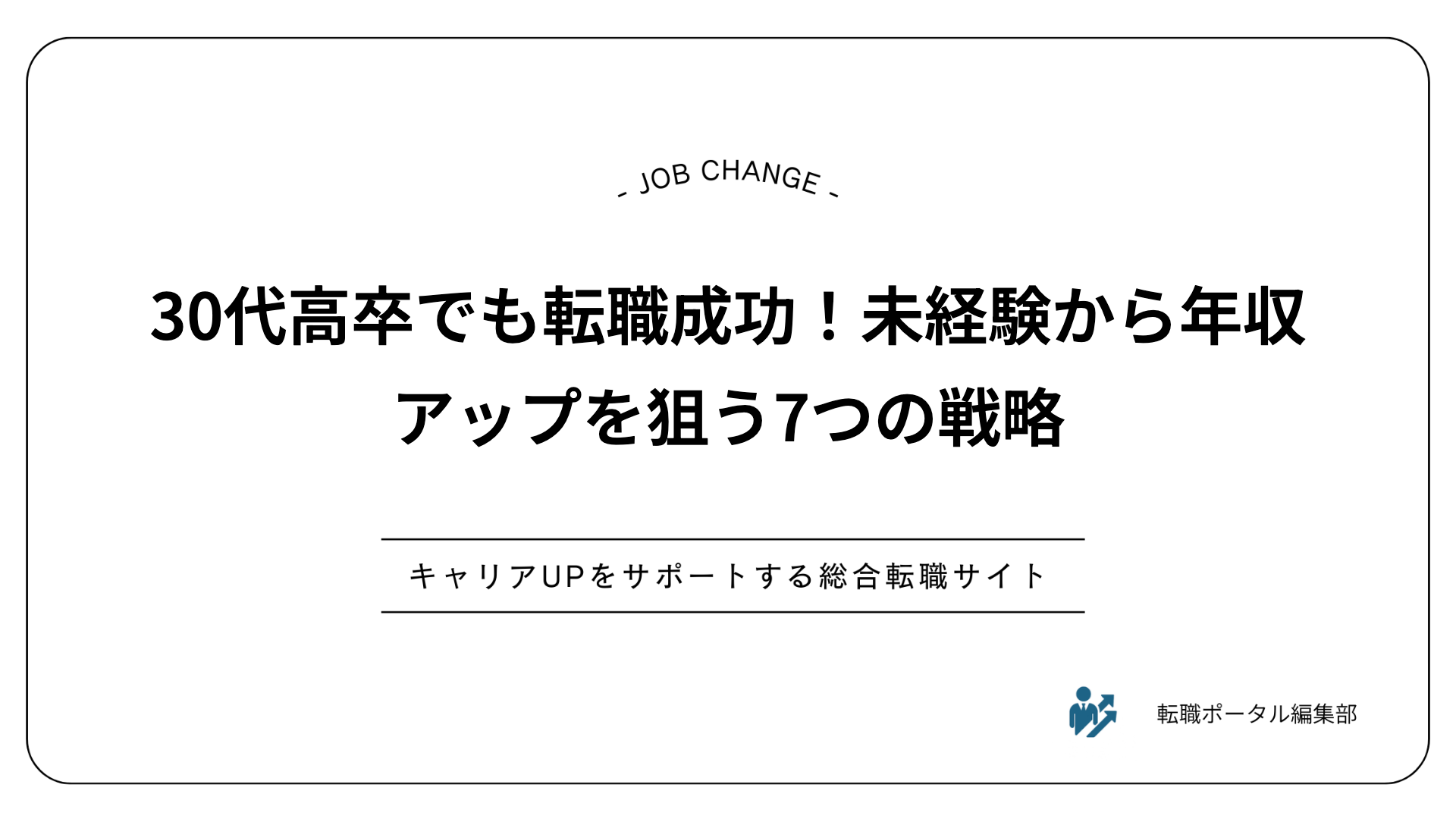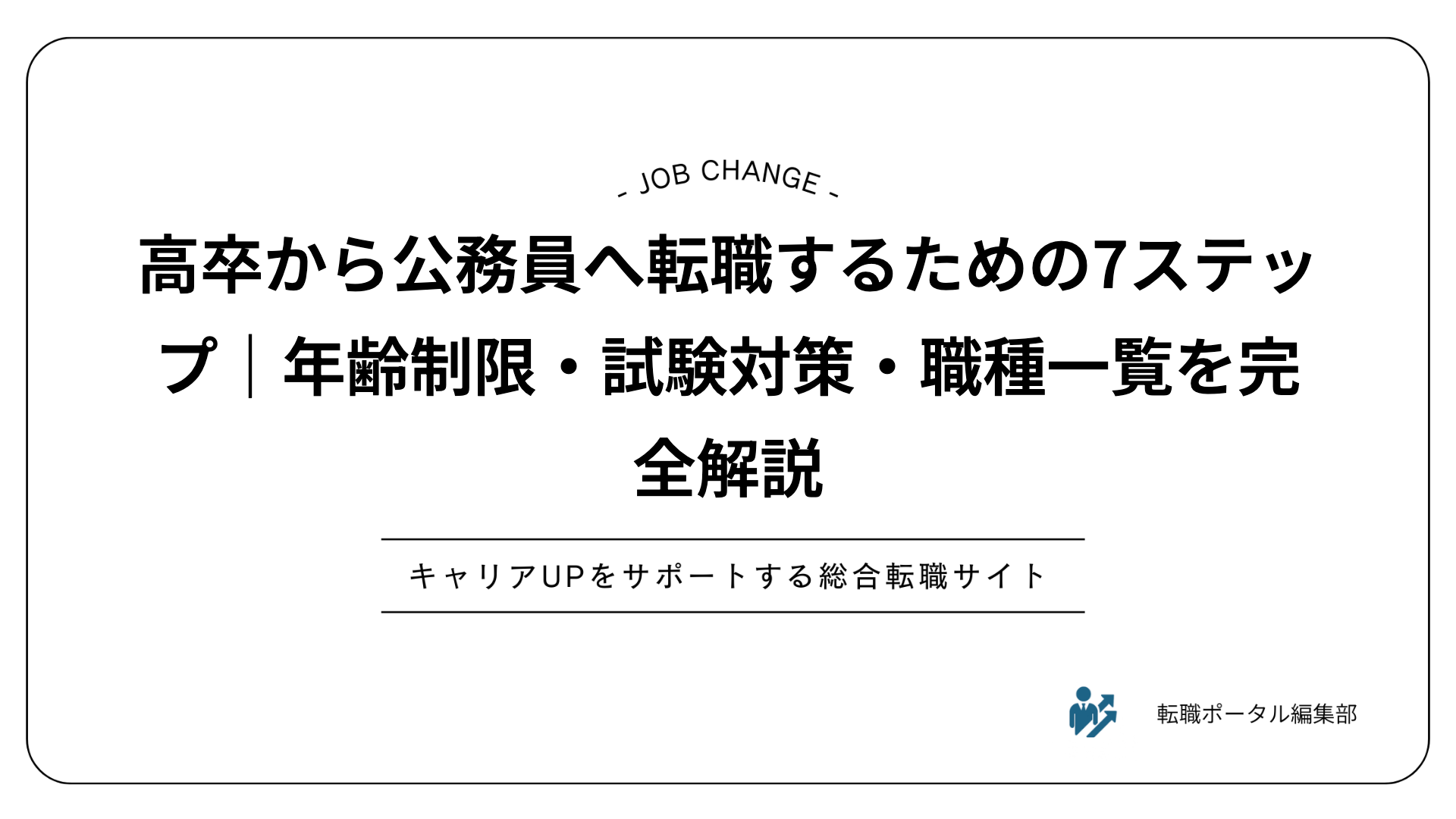高卒から年収500万も狙える!転職成功の完全ロードマップ
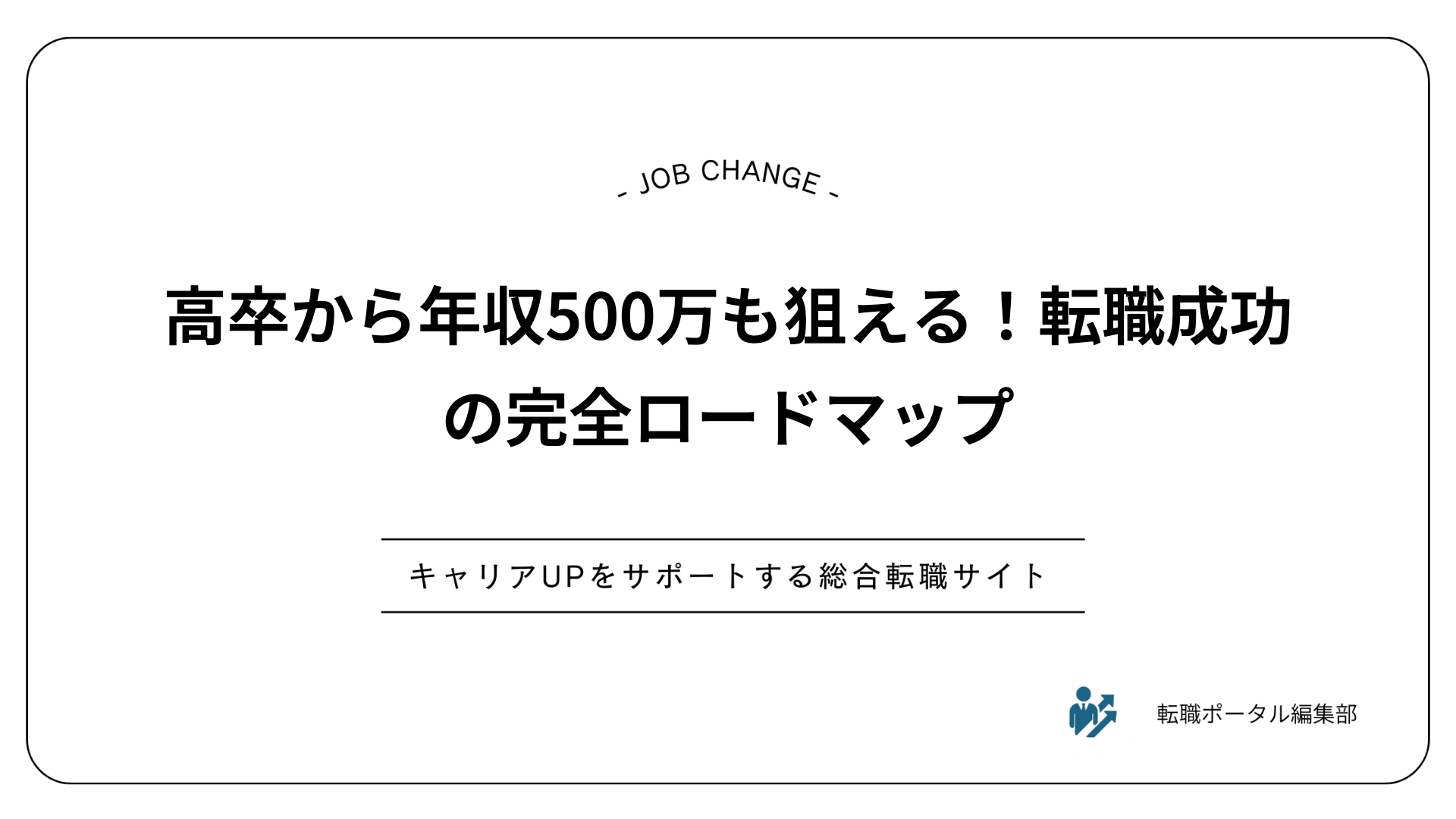
「高卒だと良い仕事に就けないのでは?」「年収がずっと低いままなのでは?」──そう感じて転職に不安を抱えている方は少なくありません。
確かに、学歴によって選考が制限される企業があるのは事実です。しかし、今の転職市場では“学歴よりも実力”を評価する企業が増えつつあります。
正しい情報と準備を重ねれば、高卒からでも希望のキャリアを実現することは十分可能です。
この記事では、高卒者が転職で直面する現実と課題を紐解きながら、成功するために必要な知識と行動ステップを解説しています。
- 学歴の壁をどう乗り越えるか
- どんな業界・職種が高卒者に向いているのか
- 年収を上げるために必要な準備とは
- 高卒でも応募できる企業の探し方
- 実際に年収アップに成功した転職事例
「自分でもできるかも」と思えるようになる情報が詰まっています。まずはこの記事を読んで、転職活動の第一歩を踏み出してみませんか?
高卒が転職で直面しやすい現実と課題
学歴フィルターが残る企業が多い背景

高卒者が転職を検討する際、最初に直面するのが「学歴フィルター」です。
これは応募条件に大学卒以上と明記している企業が多く、高卒者が書類審査の段階で不利になりやすい現実を指します。
この背景には、日本企業が長年「学歴=能力」と評価してきた文化が根強く残っていることが挙げられます。
しかし、すべての企業が学歴フィルターを設けているわけではありません。
特に中小企業やベンチャー企業、実力主義の業界では、学歴よりも実務経験やスキルを重視する傾向が強まっています。
- 求人票に「学歴不問」と記載のある企業を狙う
- 職務経歴書で成果や実績を具体的にアピールする
- 転職エージェントを活用し、企業側に学歴以外の魅力を伝えてもらう
「学歴に自信がないから…」と尻込みする必要はありません。自分の強みを活かせる企業に目を向ければ、転職のチャンスは確実に広がります。
求人数・選択肢が限定される理由と対処法
高卒者の転職活動では、応募できる求人が限られているという課題に直面します。
実際、求人票に「高卒可」と明記された案件は、全体の中でもごく一部に留まっているのが現状です。
その背景には、企業側が学歴で業務適応力や将来性を判断しやすいという意識が根強くあるからです。
特にホワイトカラーや総合職では、「大卒以上」を条件とする傾向が強く、高卒者は書類選考の段階で不利になることが少なくありません。
とはいえ、高卒可の求人には明確な強みもあります。たとえば人手不足の業界では実務経験を重視し、柔軟な採用方針を取っている企業も多数存在します。
特に中小企業や成長中の企業では、実績やポテンシャルに注目してくれるケースが増えています。
初任給・年収格差を示す最新データ

高卒と大卒の間には、依然として賃金の格差が存在します。厚生労働省の2024年データによると、初任給の差は次の通りです。
- 高卒:約18.5万円
- 短大卒:約20.5万円
- 大卒:約23.5万円
このような差は年次が上がるにつれて広がる傾向があり、昇格や役職への登用にも影響を及ぼすことがあります。
しかし、必ずしも高卒だから年収が上がらないわけではありません。
特に実力主義の業界や、インセンティブのある営業職、または資格によって給与水準が大きく変わる業界では、学歴に関係なく年収アップが見込めます。
さらに、転職を戦略的に活用し、実績を積みながら条件の良い企業へ移ることで、段階的に年収を引き上げることも十分に可能です。
離職率の高さが採用に与える影響
高卒者は「離職率が高い」というイメージを持たれやすく、それが採用選考で不利になることもあります。
実際、厚労省の統計によると、高卒で就職した人のうち約35%が3年以内に退職しているとされています。
この数字だけを見るとネガティブな印象を受けますが、離職の背景には「企業とのミスマッチ」「働き方の不一致」「教育体制の不備」など、環境要因があるケースが大半です。
採用側の懸念を払拭するには、転職理由や離職の経緯をポジティブに伝えることが不可欠です。
また、次の職場での継続意欲を示すことも信頼を得る上で重要です。
- 「どんな職場を望んでいるか」「なぜその企業を志望するのか」を具体的に語る
- 資格取得やスキル習得など、自らの成長を示す取り組みを強調する
過去の離職を「失敗」としてではなく、「学びと再挑戦の機会」として捉える姿勢が、次の採用へとつながります。
データで読み解く高卒者の転職市場動向
求人数と採用率の最新統計
近年の雇用情勢を見ると、高卒者の転職市場には徐々に追い風が吹きつつあります。
厚生労働省の「一般職業紹介状況」によると、2024年の高卒者向け求人数は前年よりも約5%増加しており、採用ニーズは着実に回復傾向にあります。
とくに製造・物流・建設・サービス業界を中心に、人手不足の深刻化が影響しており、経験や学歴よりも「やる気」や「定着率」を重視する企業が増加しています。
さらに、第二新卒(卒業後3年以内)に関しては、ポテンシャル採用の枠が広がり、書類選考の通過率も高まっている傾向があります。
求人数の増加は歓迎すべき動きですが、人気業界に応募が集中することで競争率も上がるため、「自分に合う仕事」「長く続けられる職場」を見極める目が重要です。
業界・職種別に異なる学歴要件

業界や職種によって、学歴に対する要求度合いには大きな違いがあります。
たとえば公務員や大企業の総合職、金融・コンサル業界などでは、今でも「大卒以上」が応募条件になっていることが少なくありません。
一方で、実務重視・人手不足が深刻な業界では、高卒者でも積極的に採用されています。具体的には以下のような分野が該当します。
- 建設・土木・運輸などの現場職
- 介護・保育・サービス業などの人材需要が高い業界
- 営業職や販売職など成果型の職種
また、IT業界でも一部職種(テスター、コーディング業務など)においては、学歴よりもスキルや実務経験を重視する傾向が強まっています。
年代別(20代・30代以降)の転職成功率
高卒者の転職成功率は、年齢によっても大きく異なります。
一般的に若いほどポテンシャル採用が通りやすく、職歴や経験に関係なく「伸びしろ」を評価してもらいやすい傾向があります。
たとえば20代前半であれば、「第二新卒」として企業が積極的に採用しているゾーンです。
この年代では、やる気や成長意欲を重視した面接が中心となり、過去の離職歴やスキル不足も大きな障壁にはなりません。
一方、30代以降になると、「何ができるか」「どんな実績があるか」といった実務経験が問われやすくなります。
企業側も即戦力を求める傾向が強くなるため、未経験職種への転職はやや難易度が上がります。
しかし、30代・40代でもチャンスがないわけではありません。
年齢を重ねても、自己分析やスキルアップを怠らず、着実に準備をすることで、納得のいく転職を実現できます。

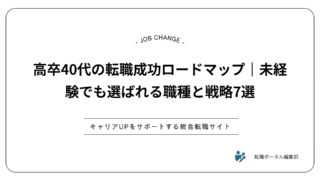
転職を成功に導く事前準備
自己分析で強みとキャリア軸を明確にする方法

転職を成功させるためには、まず「自分を知る」ことが最優先です。
特に高卒の方は、学歴ではなく「強み」や「価値観」をもとに職場を選ぶことが重要になります。
自己分析では、これまでの経験を振り返りながら、自分が得意なこと・楽しかったこと・評価されたことを棚卸ししてみましょう。
具体的には次のようなステップを踏むと効果的です。
- 過去の仕事やアルバイト経験で「成果を出した場面」を洗い出す
- その時の行動や考え方から「自分の強み」を言語化する
- 今後の仕事に対して「何を重視するか」(働き方・環境・収入など)を明確にする
このようにキャリア軸がはっきりすれば、面接での一貫性も生まれ、企業からの信頼度が高まります。
なんとなく転職するのではなく、「自分に合った職場」を選ぶためにも、自己理解を深めておくことが欠かせません。
評価されやすい資格・スキルアップの選び方
高卒者が転職で評価を得るうえで、資格やスキルの有無は大きな武器になります。
特に「未経験可」と記載された求人でも、関連資格を持っていることで内定率が大幅に上がることは少なくありません。
ただし、資格なら何でも良いというわけではありません。以下のような観点で選ぶのがおすすめです。
- 業界ニーズが高く、転職に直結しやすいもの(例:簿記、宅建、ITパスポート)
- 業務に役立ち、即戦力として評価されやすいもの(例:フォークリフト、介護初任者研修)
- 未経験でも短期間で取得可能なもの(例:MOS、販売士)
また、オンライン講座や通信教育などを活用すれば、働きながらでも無理なくスキルアップが可能です。
「資格=やる気の証明」として見られることも多いため、取得するだけで選考にプラスに働くことがあります。
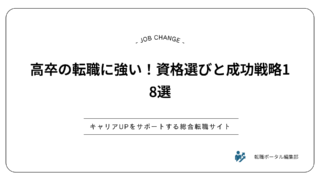
学歴をカバーする履歴書・職務経歴書の書き方
高卒の方が転職活動を進める際、履歴書や職務経歴書の工夫が選考突破のカギを握ります。
学歴の欄で不利に見える分、他の部分で「この人と会ってみたい」と思わせる工夫が必要です。
ポイントは「学歴に触れすぎないこと」ではなく、「経験や実績で補うこと」です。以下のような記載を意識しましょう。
- 職務経歴は時系列で簡潔に、成果を具体的に記載(例:〇〇業務にて売上前年比120%達成)
- 工夫や改善を行った経験を数値やエピソードで補足
- 自己PR欄では「仕事に対する考え方」や「継続力・責任感」をアピール
また、転職回数が多い場合でも「なぜ辞めたか」より「何を得て、次にどう活かすか」の視点で伝えることが重要です。
事実を正直に書きつつも、ポジティブな未来につなげる内容を意識しましょう。
面接で光るエピソードのつくり方

高卒であっても、面接で印象を残すことは十分に可能です。
むしろ、実務経験や人柄を評価する中途採用の場では、「話の内容」が選考結果を大きく左右します。
そのため、面接では「誰でも話せる自己紹介」ではなく、「あなたしか語れないエピソード」を用意しましょう。以下の手順で準備するのがおすすめです。
- 過去の職場やアルバイトで困難を乗り越えた経験を振り返る
- その場面で「自分がどんな行動をしたか」「どんな結果を得たか」を整理
- その経験から得た学びや価値観を伝える
たとえば、「忙しい時期でも残業を引き受けて感謝された経験」や「ミスをフォローし信頼を得たエピソード」などは、実直な姿勢を伝える材料になります。
準備された具体例があるだけで、面接官の印象は大きく変わります。
「この人と一緒に働きたい」と思わせるためにも、自分の言葉で語れる経験を用意しておきましょう。
高卒におすすめの業界・職種と避けたい業界
実力主義で学歴を問わない業界
高卒でも評価されやすい業界の共通点は「実力主義」であることです。
年功序列ではなく、成果や貢献度を軸に評価される職場では、学歴の有無が昇進や年収に直結しません。
特に以下の業界は、高卒でも成果次第で大きく飛躍するチャンスがあります。
- 営業職(不動産・人材・広告など)
- 運送・物流業界(リーダー・管理職登用が早い)
- 建設・施工管理(現場経験がそのまま昇進に直結)
これらの業界では、数字や現場対応力が成果として可視化されるため、実務経験を積めば「肩書き」に関係なく上を目指せる環境が整っています。
若手を積極採用する人手不足業界

日本の労働人口は年々減少しており、人手不足が深刻化している業界では、若手人材の採用に力を入れています。
学歴よりも「長く働いてくれそうな人材かどうか」が重視される傾向が強まっています。
代表的なのは以下のような業界です。
- 介護・福祉業界(未経験でも研修体制が充実)
- 飲食・サービス業(シフト制で柔軟に働ける)
- 製造業(簡単な作業から始めてキャリア形成が可能)
これらの業界では研修や資格取得支援など、育成に力を入れている企業も多く、高卒でもスタートしやすい環境があります。
「未経験OK」や「学歴不問」の求人が目立つのもこの分野です。
年収アップが狙える職種
高卒からでも年収アップを目指せる職種は複数ありますが、共通するのは「スキルが収入に直結すること」です。
特に成果報酬型の職種では、学歴に関係なく高年収を実現することが可能です。
中でも狙い目となるのは以下の職種です。
- 法人営業(インセンティブあり)
- 施工管理・電気工事士(資格で年収上昇)
- プログラマー・ITエンジニア(実力次第で年収600万円超も)
これらの職種に共通するのは「成果主義」「スキル評価」「昇進のスピードが早い」といった特徴です。
未経験から挑戦できる求人も増えているため、将来性を見据えて狙ってみる価値は十分にあります。
学歴重視の傾向が強い業界
一方で、高卒者にとって挑戦のハードルが高い業界もあります。
とくに金融業界やコンサル、総合商社などは、学歴を足切り条件として用いる傾向が今も根強く残っています。
新卒採用において「大卒以上」が当たり前とされるこれらの業界では、中途採用でも「前職の役職や大卒資格」が問われるケースが一般的です。
また、公務員や大企業の事務職でも、「高卒枠」が少なく、競争率が高いのが現状です。
そのため、これらの業界を目指す場合は「資格取得」「職歴構築」「経験による実績蓄積」など、長期的な戦略が必要になります。
最初から避けるのではなく、回り道をしながら挑戦できる道を探る姿勢が大切です。
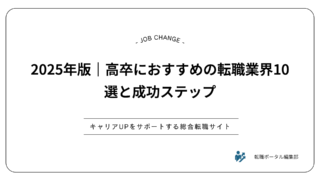
転職エージェント・求人サイトの選び方と活用法
総合型と特化型――それぞれのメリット

転職活動において、転職エージェントを活用することは非常に効果的です。
特に高卒の方にとっては、自分では探しきれない求人に出会えるチャンスを広げる手段でもあります。
転職エージェントには「総合型」と「特化型」の2種類があり、それぞれに異なる特徴とメリットがあります。
- 総合型:幅広い業界・職種をカバーし、求人の選択肢が豊富
- 特化型:特定の業界や属性(若手向け、高卒向けなど)に強く、マッチング精度が高い
たとえば、初めての転職で自分の適性がわからない場合は総合型エージェントで多様な求人を比較するのが有効です。
一方で、IT・建設・介護など「行きたい業界が決まっている」場合は、特化型を活用した方が効率的に進められます。
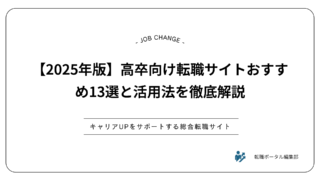
高卒向けおすすめ転職エージェント比較
高卒の方に特におすすめできる転職エージェントは、未経験歓迎や学歴不問の求人に強く、サポート体制が充実しているものが中心です。
以下はその一例です。
- 就職カレッジ(ジェイック):正社員経験がない人にも対応。研修付きで未経験者の就職に強い。
- DYM就職:高卒・第二新卒向けに特化。紹介先は正社員限定でサポートも丁寧。
- ハタラクティブ:20代向けだが高卒者の支援実績も多数あり、書類通過率が高い。
これらのエージェントでは、履歴書の添削や面接対策まで一貫した支援が受けられるため、初めての転職でも安心して取り組むことができます。
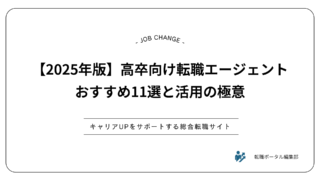
内定率を高めるエージェント活用術

転職エージェントを効果的に使うには、受け身ではなく「積極的に動く」姿勢が重要です。
単に求人を紹介してもらうだけでなく、自分の希望や不安をきちんと伝えることで、より的確なサポートを受けられます。
エージェントとの連携で成果を出すためには、次の3点を意識しましょう。
- キャリアカウンセリングで「軸」を明確に伝える
- 紹介された求人にはなるべく早く反応し、意欲を示す
- 不安な点や条件面は遠慮せず相談する
また、1社だけでなく複数のエージェントを併用することで、情報の偏りを防ぎ、選択肢を広げることができます。
転職活動は一人で抱え込むと疲れがちですが、プロの力を借りれば精神的な安心感も得られます。
「信頼できる担当者」と出会えるかどうかも、転職成功の大きなポイントです。
高卒から大企業・公務員へ挑戦するステップ
必要な経験・資格と応募ルート
高卒でも大企業や公務員を目指すことは可能です。ただし、学歴に代わる「武器」として経験や資格の有無が問われることが多くなります。
たとえば、大企業の中途採用では職種によっては「即戦力」を求める傾向があり、以下のような実績があると有利です。
- 現職での成果(営業成績、リーダー経験など)
- 業界に特化した資格(例:電気工事士、建築施工管理技士)
- 社会人としてのマナーや継続力が伝わる経歴
公務員については、高卒枠の採用試験が各自治体や国で設けられており、年齢制限の範囲内(多くは29歳以下)であれば受験可能です。
試験科目は筆記・作文・面接が中心で、対策をすれば十分に合格を狙えます。
高卒だからといって選択肢が狭まるわけではありません。
むしろ、現場での実績や堅実なキャリアがあれば、企業や行政も評価してくれる土壌は広がっています。
キャリアアップが期待できる社内制度
学歴に関係なく、入社後にキャリアアップを目指せる制度を整えている企業も増えています。
とくに大企業や安定志向の強い中堅企業では、以下のような仕組みが用意されています。
- 職能資格制度:能力と役職に応じて昇格できる
- 社内公募制度:部署異動や昇進を自ら手を挙げて応募できる
- 研修制度:資格取得支援やeラーニングなどの教育環境
こうした制度を活用すれば、高卒であっても管理職や専門職へのキャリアアップが現実的になります。
ポイントは「制度があるかどうか」だけでなく、「実際に活用されているか」を確認することです。
口コミサイトや社員インタビューを参考にし、制度が形だけになっていない企業を選ぶことが重要です。
難関選考を突破する対策ポイント

大企業や公務員の選考では、他の転職よりも倍率が高く、選考も厳しくなる傾向があります。そのため、入念な準備と対策が必要不可欠です。
まず履歴書・職務経歴書では、定型的な表現ではなく「自分の強み」と「その企業でどう活かすか」を明確に書きましょう。企業研究も欠かせません。
面接では、以下のような視点を重視して準備しましょう。
- なぜその企業・自治体を志望するのか(志望動機)
- 過去の経験から何を学び、どう成長してきたか
- 入社後にどんな貢献ができるか
また、公務員試験であれば過去問を繰り返し解くこと、模擬面接を受けて話し方や受け答えを磨くことも重要です。
難関な選考であっても、事前準備を重ねれば突破のチャンスは十分にあります。「高卒だから無理」と思い込まず、着実な対策で差をつけましょう。
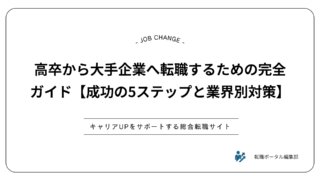
地域別転職戦略とリモートワーク活用
大都市圏と地方で異なる求人動向
転職市場は、都市部と地方で大きく傾向が異なります。都市部では業種・職種ともに選択肢が多く、専門性や高年収を狙える求人も豊富です。
一方で地方は、求人の数こそ少ないものの、採用条件が柔軟で未経験から挑戦しやすいという利点があります。
たとえば、以下のような特徴があります。
- 大都市圏:IT、金融、コンサルなどの専門職が豊富
- 地方:介護、建設、製造など人手不足の業界が多い
リモートワークの普及により、地方に住みながら都市部の仕事を受けるという働き方も広がっています。
居住地にとらわれないキャリア設計が可能な時代です。
地方在住でも狙えるリモート求人の探し方

地方在住でもチャンスが広がる今、フルリモート求人は有力な選択肢です。
特にIT系やWeb関連業種では、業務が完全にオンラインで完結するため、勤務地を問わない求人が増えています。
こうした求人を探すには、以下の方法が効果的です。
- 「リモート」「在宅」などのキーワードで求人検索を行う
- ReworkerやRemote Workなど専門サイトを活用する
- Wantedlyなどベンチャー求人に強いサービスを併用する
ただし、自己管理能力や成果への意識が求められるため、応募書類や面接で「仕事の進め方」や「過去の実績」を具体的に伝えることが大切です。
U・Iターン転職を成功させるコツ
地元に戻るUターンや、新天地に移住するIターンは、ライフスタイルの見直しを兼ねた転職として人気が高まっています。
とくに結婚・出産・介護などのライフイベントを機に地方への転職を選ぶ人が増加しています。
成功させるには、生活と仕事の両面から計画的に動くことがポイントです。
たとえば、移住支援を活用すれば金銭面の負担も軽減できますし、企業によっては住宅補助などがある場合もあります。
また、U・Iターンに特化した転職フェアや自治体の無料相談会を活用するのもおすすめです。
- 事前に地域の生活費や交通環境を調査する
- 現地企業の文化や待遇を把握しておく
- 長期的に働く意欲を企業に伝える
地方転職は、単なる引っ越しではなく「働き方の再設計」です。生活環境や将来の家族設計も視野に入れたうえで、転職活動を進めましょう。
よくある質問と転職成功事例
何歳まで転職は可能か
高卒の転職において、「何歳までがチャンスか?」という疑問はよく挙がります。
結論から言えば、年齢による制限は一概にはなく、年代ごとに評価されるポイントが異なるだけです。
20代であれば「伸びしろ」や「意欲」が重視され、30代以降では「実務経験」や「成果」が評価される傾向があります。
40代・50代でも、専門スキルやリーダー経験を活かせる職種ではニーズがあります。
年齢を気にするよりも、自分の強みを活かせる職場を見極めることが重要です。
未経験でも採用されるための工夫

未経験職種への転職は、高卒者にとって大きなチャンスです。
しかし、経験がない分、採用担当者に「安心して任せられる人材か」をどう伝えるかが重要です。
採用を勝ち取るには、以下のような工夫が効果的です。
- 「なぜその職種に興味を持ったのか」を明確に伝える
- 業界研究や資格取得など、事前準備を行っていることを示す
- 過去の職務やアルバイト経験から共通するスキルをアピールする
たとえば、営業職未経験でも接客や販売経験があれば「顧客対応力」「コミュニケーション力」といったスキルは応用可能です。
このように過去の経験を「どう活かせるか」という視点で伝えると、未経験でも前向きに評価されます。
また、「自ら学ぶ姿勢」や「長く働く意欲」を明確に伝えることで、採用側の不安を払拭することができます。
在職中と離職後、どちらで活動すべきか
転職活動は「在職中に行うべきか」「離職してから行うべきか」で迷う方も多いですが、一般的には在職中に活動を始めるのが安全です。
なぜなら、収入がある状態であれば精神的にも余裕があり、じっくりと企業選びができるためです。
ただし、長時間労働や過度なストレスで活動時間が確保できない場合は、無理せず一度離職してから集中する選択もあり得ます。
離職期間中の印象を和らげるためには、以下のような工夫が有効です。
- 資格取得や職業訓練に通い、自己研鑽に取り組む
- 離職理由や再就職の目的をポジティブに伝える
いずれにしても、ブランク期間をネガティブに見せない工夫が大切です。自分に合ったタイミングと方法で、無理なく転職活動を進めましょう。
高卒から年収アップを実現した成功事例

高卒からの転職で年収アップを実現した人たちは、共通して「努力+戦略」を組み合わせています。たとえば、以下のようなケースがあります。
- 接客業から法人営業へ転職し、インセンティブで年収400万円以上に
- 物流倉庫スタッフから施工管理へ資格取得後に転身し、年収500万円を超える
- 独学でプログラミングを学び、IT企業に就職して2年で年収アップ
これらの事例に共通するのは、「目標設定」「継続した学び」「適切な業界選び」です。
最初から理想の年収でなくとも、地道なキャリア設計によって高収入に近づけるのが現代の転職環境です。
年収アップを目指すなら、「いま何ができるか」ではなく、「これから何を積み上げていけるか」を意識した行動が大切です。
まとめ:学歴にとらわれず「自分らしい転職」を叶えるために
高卒だからといって転職が不利になる時代ではありません。
もちろん、学歴が選考に影響する企業や職種があるのも事実ですが、それは一部に過ぎず、多くの企業では「経験」や「人柄」「意欲」を重視する方向にシフトしています。
この記事では、高卒者が転職で直面しやすい課題や、成功のための具体的な戦略について解説しました。
特に以下のポイントを押さえて行動すれば、学歴の壁を乗り越えて、理想のキャリアを築くことは十分に可能です。
- 自己分析で強みや希望条件を明確にする
- 学歴に代わる「資格」や「経験」を積極的にアピールする
- 面接では具体的なエピソードや成果をもとに説得力を持たせる
- 高卒向け転職エージェントやリモート求人などの支援を活用する
- 地方・大都市圏など地域ごとの求人傾向に合った戦略を立てる
転職活動は自分を見つめ直す大きなチャンスでもあります。
「高卒だから…」と制限をかけるのではなく、「どうすれば可能性を広げられるか」という前向きな視点で行動することが、成功への第一歩です。
まずは一歩踏み出すこと。情報を集め、相談し、準備を進める――その積み重ねが、あなたのキャリアを確かなものにしていきます。
高卒におすすめの転職サイト・エージェントはこちら↓