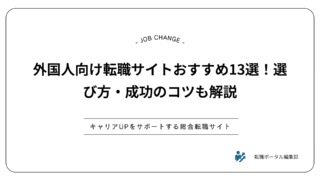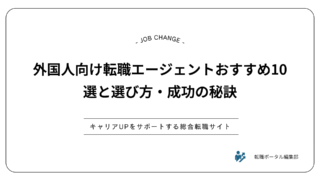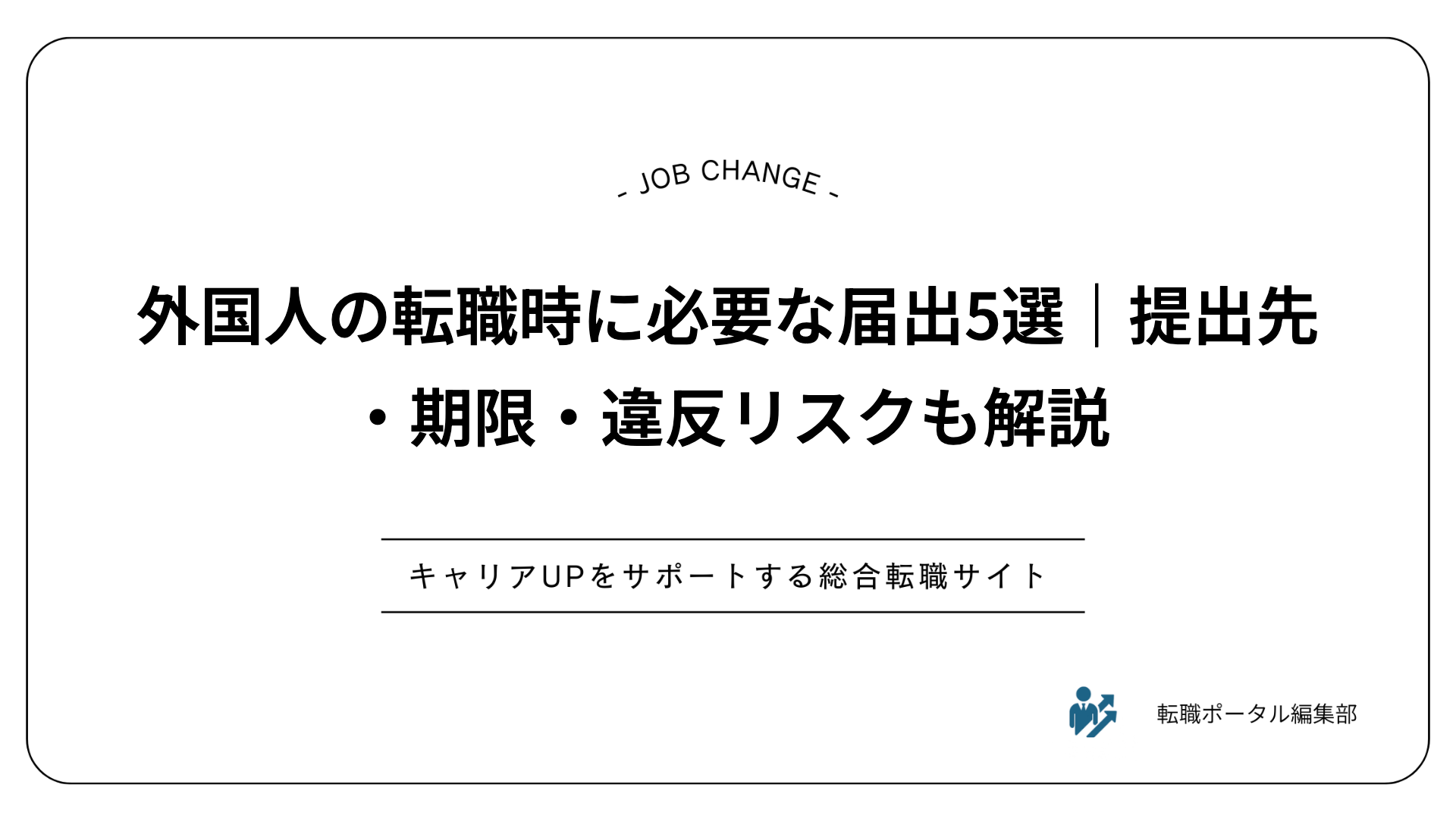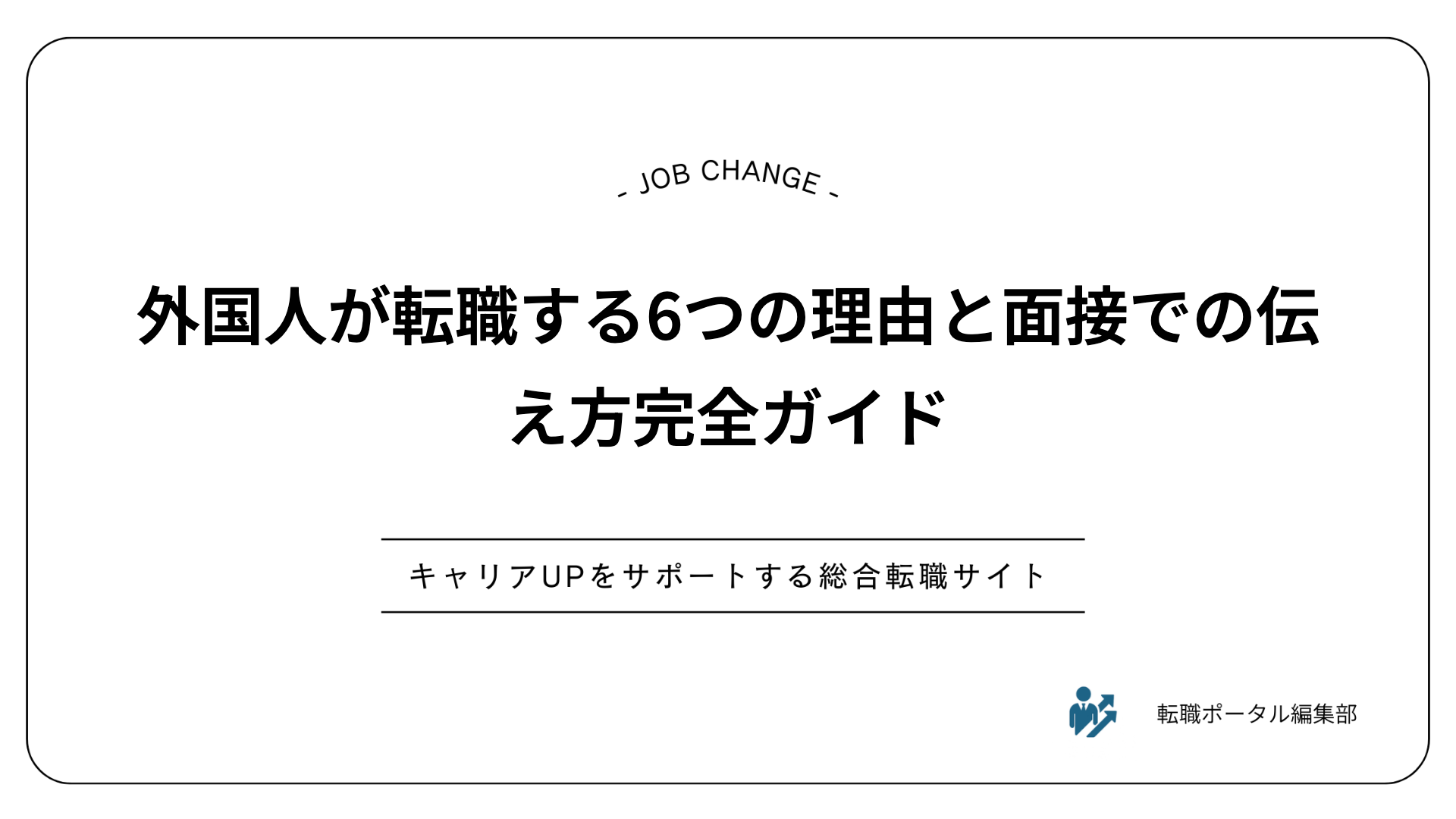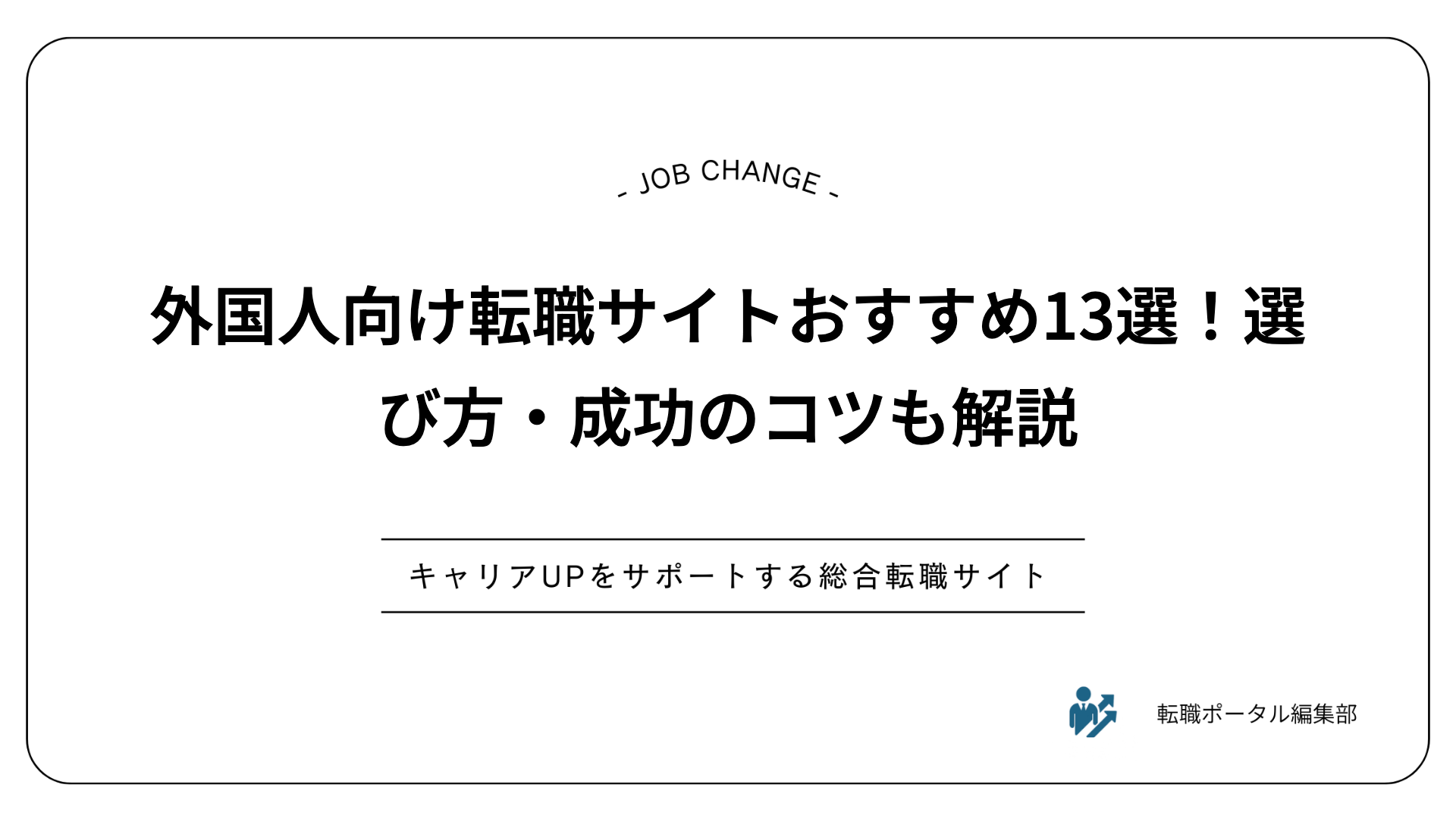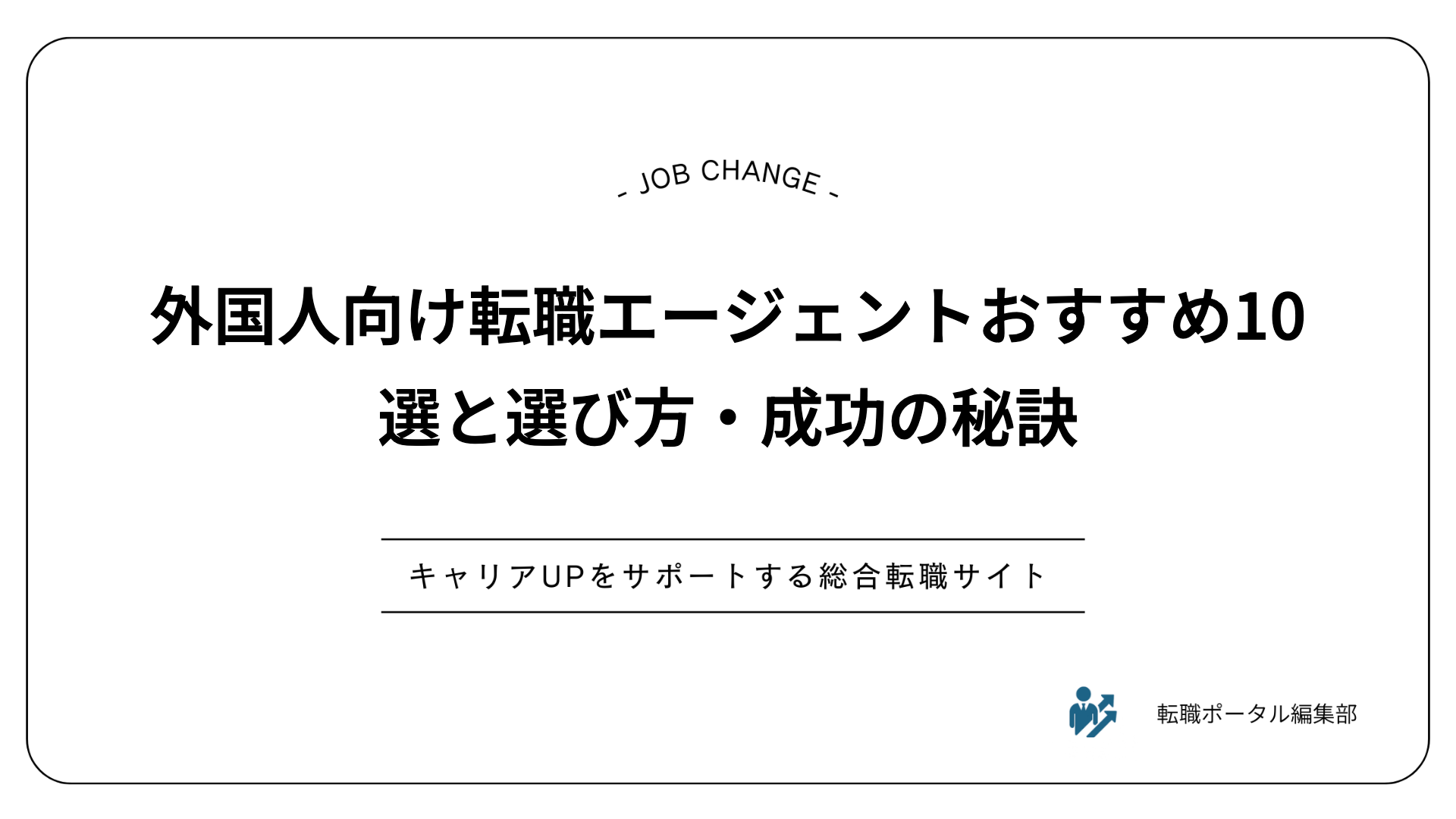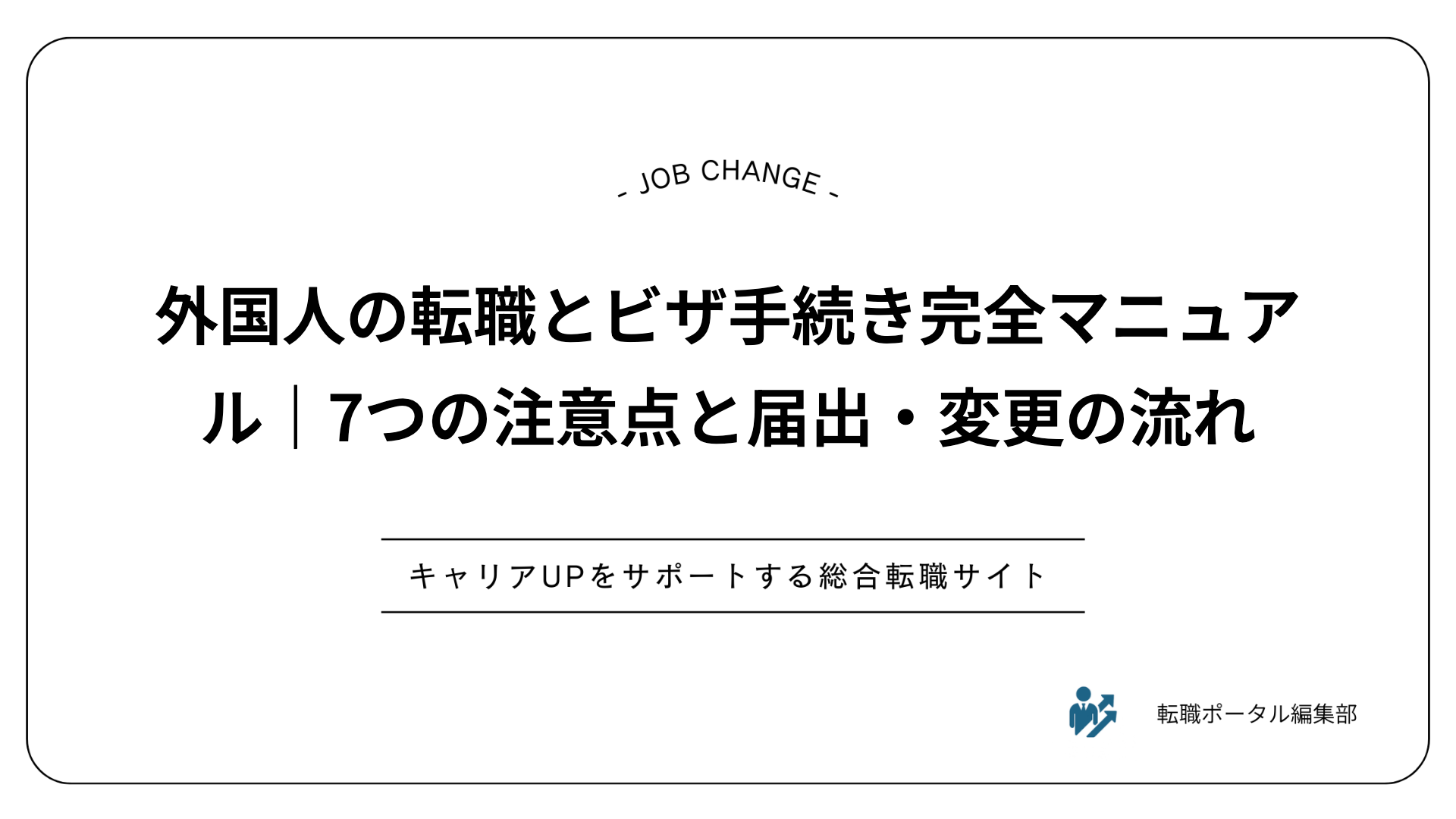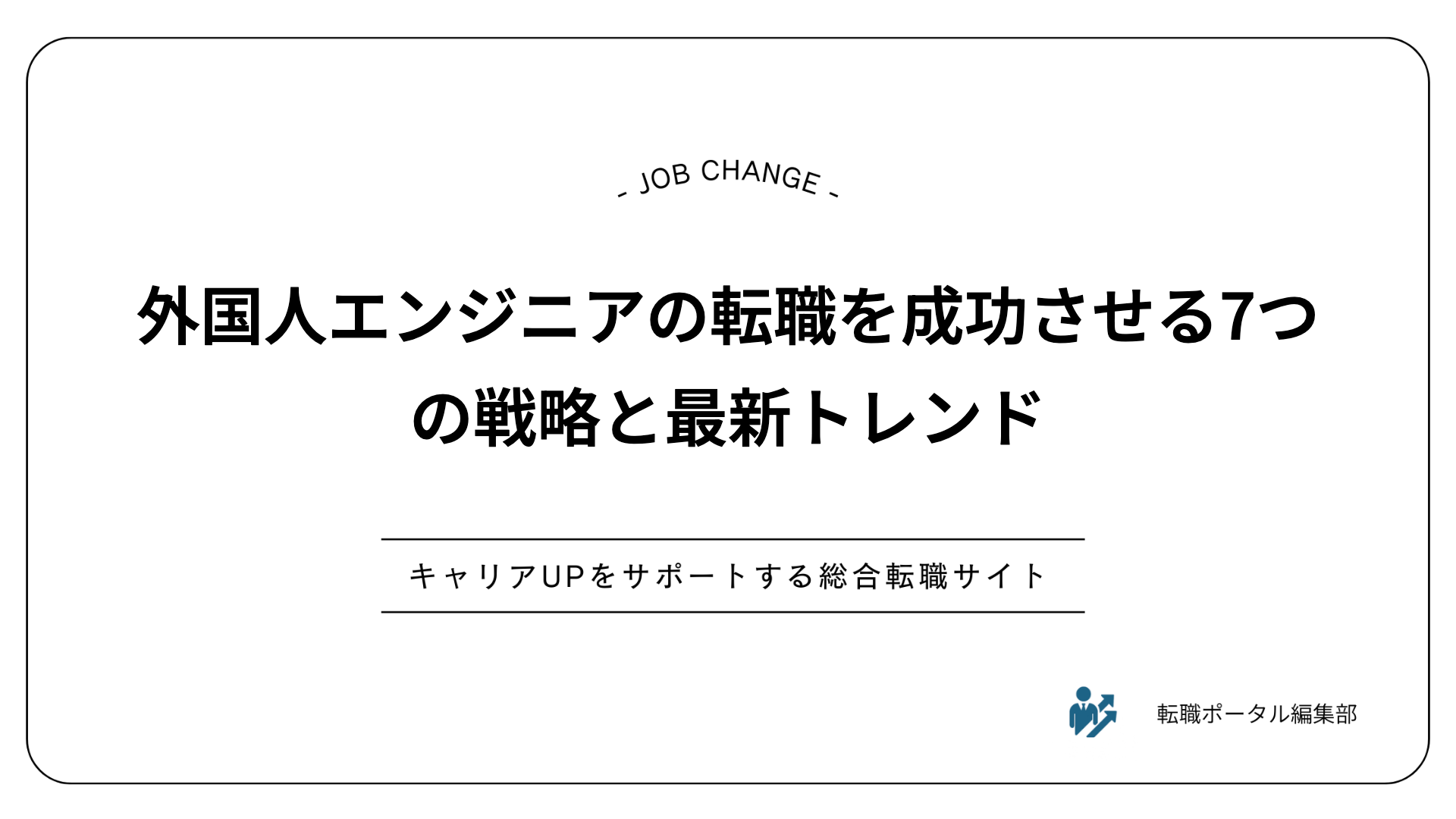外国人の転職が多い7つの理由と日本で成功する方法
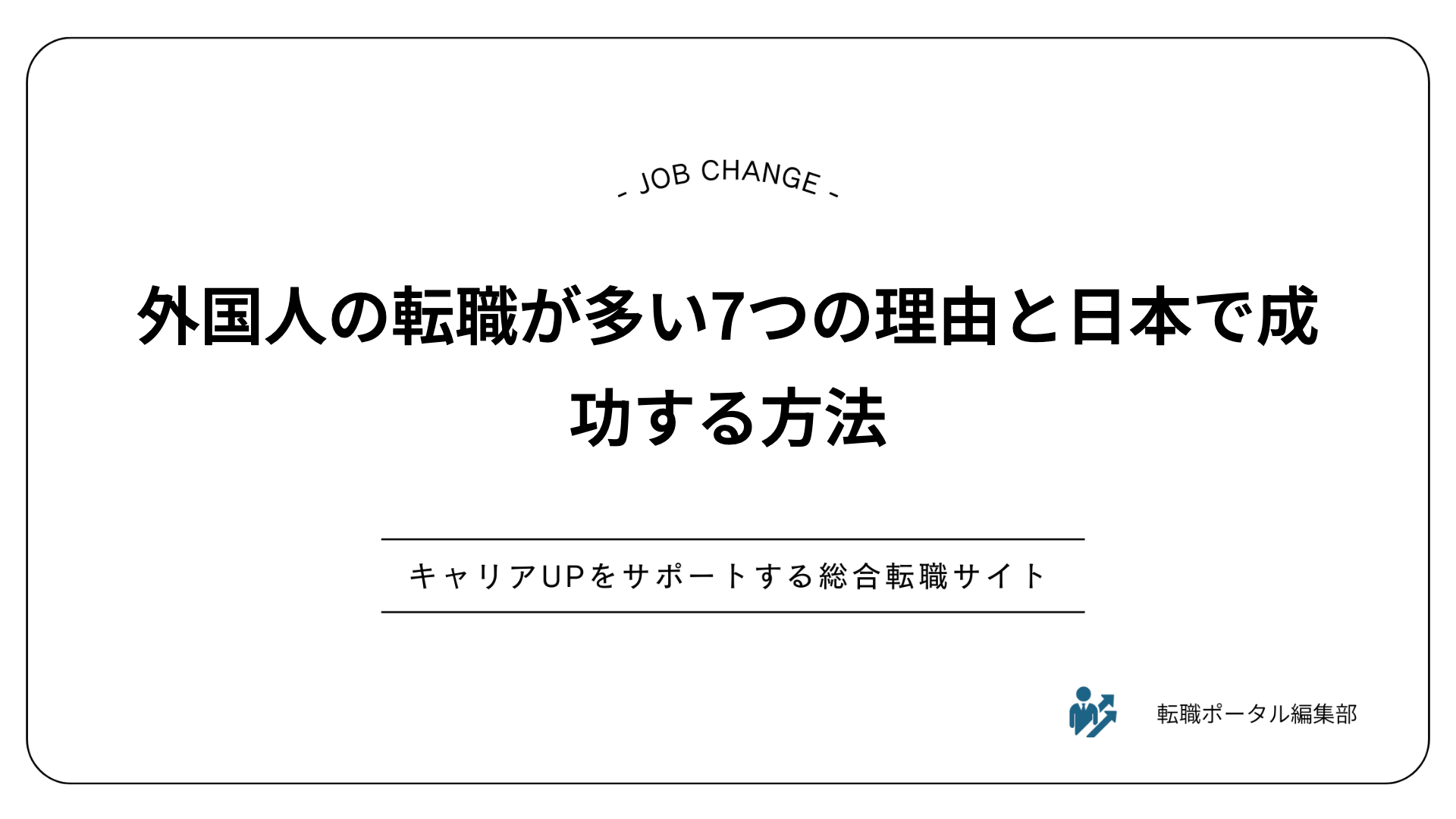
「外国人は転職が多いって本当?」「日本での転職って評価に響かないの?」——そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、海外ではキャリアアップのための転職が当たり前という国も多く、日本とのギャップに戸惑う外国人も少なくありません。
一方で、日本では転職回数が評価に影響する文化や制度が根強く、外国人にとっては転職をめぐる事情がやや複雑です。
この記事では、そんなモヤモヤを解消するために以下のような内容をわかりやすく整理しています。
- 外国人が転職を多くする理由と背景
- アメリカ・中国・ヨーロッパなど各国の転職観
- 日本での転職における注意点とビザの関係
- 転職が多い人が日本で成功するポイント
- 企業が外国人の定着率を高めるためにできること
転職を前向きに考えたい外国人の方、日本での採用やマネジメントに悩む企業担当者にとっても、きっと役立つはずです。
海外で転職が多いと言われる背景
実力主義・ジョブ型雇用が主流の国が多い
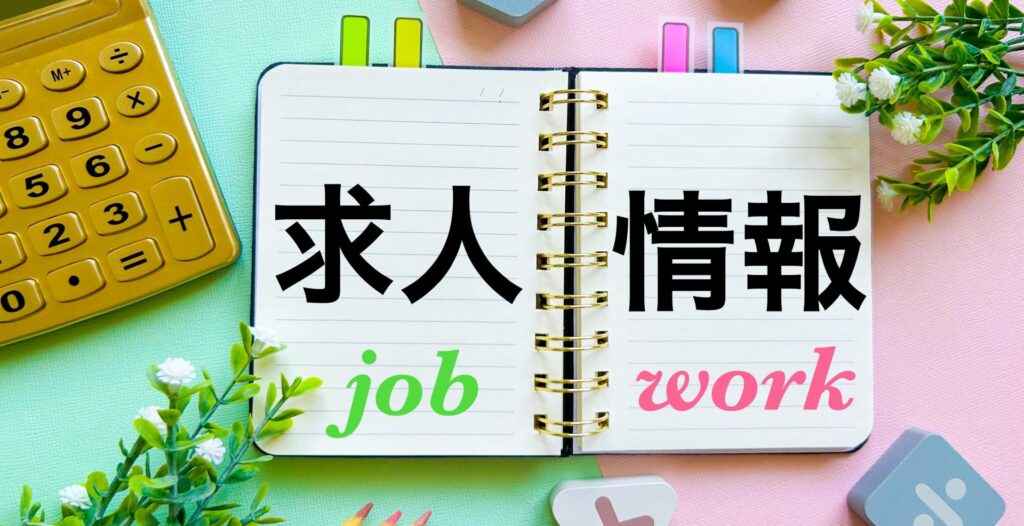
結論から言えば、海外で転職が多い背景には「実力主義」と「ジョブ型雇用制度」が深く関係しています。
これらの国々では、個人の能力や成果に応じてポジションや給与が決定されるため、より良い条件を求めて転職するのが一般的です。
- 職務記述書(ジョブディスクリプション)に基づき業務内容が明確に定義されている
- ポジションごとに求められるスキルや経験が異なるため、適切なマッチングが重視される
- 成果が認められない場合は別の企業へ移ることも自然な流れとされている
例えばアメリカやイギリスなどでは、同じ企業に長く勤めるよりも、スキルに合った仕事に乗り換えることでキャリアを形成していく文化があります。
「同じ会社に長く勤めることが美徳」とされる日本とは、根本的な雇用観が異なるのです。
給与アップやキャリアアップを目的とした転職文化
海外では「転職=ステップアップ」という考え方が根づいています。
特に欧米諸国では、転職によって給与や役職の向上を目指すのが一般的です。
たとえば、アメリカでは履歴書に過去の実績やスキルをしっかり記載し、それを武器により条件の良い企業に移るのが一般的です。
そのため、転職回数が多いこと自体が評価を下げる要素にはなりにくいのです。
日本における「転職=ネガティブ」の印象とは異なり、転職自体が自己成長の機会と見なされている点が大きな違いと言えるでしょう。
雇用流動性を促す法制度と社会的価値観

海外で転職が多い背景には、国の法制度や社会の価値観も関係しています。
特に雇用の自由度が高い国では、企業と従業員の関係が対等で、流動性のある労働市場が形成されています。
- 解雇規制が緩やかで、企業が柔軟に人材を入れ替えられる
- 失業保険や職業訓練制度などのセーフティネットが整っている
- 「転職=普通のこと」という価値観が広く共有されている
たとえば北欧諸国では、福祉制度が充実しており、一時的に失職しても生活が脅かされることは少ないため、キャリアチェンジへのハードルが低くなっています。
これにより、多くの人が自分のスキルや価値観に合った職場を探すことに積極的になれるのです。
制度と価値観の両面から支えられた流動的な労働市場が、転職の多さを後押ししているのです。
国別に見る平均転職回数と雇用慣行
アメリカ・カナダに見るキャリアビルディング型の転職
アメリカやカナダでは、転職はキャリア形成の一環として非常に一般的です。
たとえばアメリカ労働統計局(BLS)のデータによれば、平均的な労働者は20歳から50歳までに約12回の転職を経験しているとされています。
この背景には、成果主義に基づく昇進制度や柔軟な雇用文化があります。
- 転職によって給与が大きく増えることが珍しくない
- 職務ごとにキャリアのゴールが設計されており、自発的に職場を変えることが自然
- 企業も「転職は当然」という前提で人材確保・育成を行っている
また、ヘッドハンティングや転職支援サービスも活発で、自分に合った環境を見つけやすい環境が整っています。
これにより、個々人が主体的にキャリアの軌道を描くことができる社会が築かれているのです。
中国のポジティブ転職観と短い平均勤続年数
中国では若年層を中心に「転職は当たり前」という認識が広がっています。
特に都市部のホワイトカラー職では、平均勤続年数が3〜5年未満という調査結果もあり、転職を重ねることがキャリアアップに直結している風潮があります。
さらに、近年ではテック系やスタートアップ企業の台頭により、年功序列の概念が薄れ、「成果が出せる人材は高待遇で迎えられる」文化が加速しています。
新卒一括採用のような制度もなく、自らの能力でポジションを勝ち取る実力主義が基本となっているのが特徴です。
このような背景から、中国では転職がネガティブではなく、むしろ「より良い職場を目指す前向きな選択」として支持されているのです。
台湾・韓国などアジア諸国の転職事情

台湾や韓国といったアジアの先進国でも、近年は転職が一般化しつつあります。
特に台湾では、柔軟な働き方やスキル重視の風潮が高まり、転職を通じて年収や職務のレベルアップを図る人が増えています。
- 台湾の若者は「早期キャリア形成」を重視し、2〜3年単位で職場を変える傾向がある
- 韓国では、伝統的な終身雇用文化が残りつつも、IT業界や外資系を中心に転職が活発
- いずれの国でも「成果主義」が定着しつつあり、社内昇進より社外移動が有利な場面も
特に韓国では、大企業への就職が今も人気ですが、競争が激化するなかで、中小企業やスタートアップに活躍の場を求める若者も増えています。
アジアの中でも、グローバル化が進む都市部では、日本とは異なる転職観が育ってきているのが現状です。
ドイツ・イギリスなど欧州諸国のジョブチェンジ傾向
ヨーロッパでは、職業選択の自由やライフスタイル重視の考え方が根付いており、転職もその一環として捉えられています。
ドイツでは職業訓練制度(デュアルシステム)が整っており、若いうちから特定の職能を身につけるため、専門職への転職がスムーズです。
イギリスにおいても、「キャリアは企業に属するものではなく、個人が築くもの」とする考えが強く、ライフイベントに合わせた転職や職種変更が一般的です。
たとえば育児や介護を理由に一時離職し、その後再就職して全く異なる業種で働くといったケースも珍しくありません。
このように欧州諸国では、転職は単なる収入目的ではなく、「自分らしい働き方を実現するための手段」として自然に選ばれているのです。
外国人が日本で転職する際に直面する課題
転職回数が評価に影響する日本独自の慣行

日本では「転職回数が多い=定着力がない」という見方が根強く残っています。
そのため、外国人労働者にとっては、海外では一般的なキャリアアップ目的の転職であっても、ネガティブに評価されてしまうことがあります。
- 終身雇用の文化が根強く、長期勤務が「信用」の証とされる
- 転職理由が明確でないと、「問題のある人材」と誤解されやすい
- 職務内容よりも、会社名や在籍年数が重視されがち
このような背景から、転職を繰り返す外国人に対しては「すぐに辞めるのでは」という先入観を持たれる可能性があります。
したがって、職務経歴書や面接では「なぜ転職したのか」「どのような成果を出してきたか」を具体的に説明することが重要になります。
日本語能力とビジネスマナーのハードル
日本で働くうえで、日本語能力は依然として大きな壁です。
とくに転職活動においては、履歴書や職務経歴書の作成、面接での自己PRなど、日本語での高度なコミュニケーション力が求められます。
また、日本特有のビジネスマナーや職場の暗黙のルールを理解していないと、面接官に不安を与えてしまうこともあります。
たとえば「謙虚な態度」「空気を読む姿勢」「上下関係への配慮」など、海外では評価されにくい要素が、日本では重視される傾向があります。
このような文化的なギャップは、外国人にとって見えづらく、転職活動で不利になる原因の一つとなっています。
そのため、事前に日本のビジネスマナーを学ぶ、または専門家のアドバイスを受けることが成功への近道となるでしょう。
ビザ・在留資格と転職回数の関係
日本で働く外国人にとって、在留資格(ビザ)の要件は非常に重要です。
とくに「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ人が転職を繰り返す場合、その都度在留資格変更や就労資格証明の取得が必要になるケースがあります。
- 転職のたびに入管への申請が必要になることがある
- 頻繁な転職は「安定的な在留活動をしていない」と見なされるリスクも
- 企業がビザ更新のサポートに消極的になる可能性がある
また、在留資格の種類や取得時の条件によっては、転職によって「資格外活動」とみなされるおそれもあるため、注意が必要です。
そのため、転職前に入管や専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
安易な転職は、最悪の場合「在留資格の取り消し」や「更新不可」にもつながりかねません。
したがって、転職を考える際は、就労条件だけでなく「ビザとの整合性」も慎重に確認することが重要です。
永住申請・在留資格で転職回数が多い場合の注意点
永住許可に影響する評価ポイント

日本での永住許可を取得する際、転職回数は間接的に影響を及ぼす要素となります。
法務省のガイドラインでは「安定した収入」「継続的な就労活動」「素行が善良であること」などが重要視されています。
そのため、頻繁な転職や無職期間が長いと、「職業生活が安定していない」と判断されるリスクがあります。
- 在留中の収入が毎年安定しているかどうか
- 納税・保険料の支払いに滞りがないか
- 就労活動に一貫性があるかどうか
転職回数が多いこと自体がNGというわけではありませんが、「転職の理由が合理的か」「キャリアに一貫性があるか」が問われるのです。
そのため、永住申請を視野に入れるなら、収入証明や職務経歴の整合性をしっかりと準備しておく必要があります。
就労資格証明書など必要書類と手続き
転職をする際、就労資格の継続が認められているかどうかを確認するために、「就労資格証明書」の取得が推奨されます。
これは入管局に対して「転職先でも在留資格の活動内容と一致している」ということを示す重要な書類です。
- 転職後に提出することで、在留資格の更新・変更時の審査がスムーズになる
- 就労資格証明書の取得は義務ではないが、実務上ほぼ必須
- 申請には雇用契約書、履歴書、職務内容の説明書などが必要
特に永住申請時には、過去の職歴や在職証明をすべて整備しておくことが望ましいため、転職のたびに関連書類をきちんと保管しておくことがポイントです。
また、入管の指導に従い、適切な手続きを怠らないことで、将来的な永住申請時の信頼性にもつながります。
転職理由をポジティブに説明するコツ

永住申請においては、転職回数そのものよりも「転職理由の一貫性」が重視されます。
たとえば、同業界内でのスキルアップや、職務内容のステップアップであれば、審査官にも納得されやすい傾向があります。
逆に、「人間関係のトラブル」や「短期間での離職」が繰り返されていると、ネガティブな印象を与えやすいため注意が必要です。
- 「キャリア形成の一環としての転職」であることを明確にする
- 実績や成果を具体的に伝えることで、説得力を高める
- 職務経歴書や申請書類で「継続性」や「成長性」を打ち出す
また、職務内容が異なる場合でも、「なぜその職を選んだのか」「過去の経験がどのように活かされているか」を論理的に説明することで、一貫性を示すことができます。
単なる「転職の回数」ではなく、「転職によってどんな価値を積み上げてきたか」をしっかり伝えることが、審査通過への鍵となります。
具体的に面接時に伝える方法はこちら↓

転職回数が多い外国人のメリットとデメリット
スキルアップとネットワーク拡大のメリット
転職回数が多い外国人にとって、大きなメリットは「スキルの多様化」と「人的ネットワークの広がり」です。
異なる業界や職場を経験することで、専門知識だけでなく、柔軟な対応力や異文化適応能力が自然と身につきます。
- 複数の企業文化を経験することで、視野が広がる
- 転職を通じて、業界の最新動向や先端技術に触れやすい
- 人脈が広がり、新たなビジネスチャンスや紹介にもつながる
特にグローバルに活躍したい人にとって、これらの経験は非常に貴重です。
転職回数の多さが「経験豊富なプロフェッショナル」として評価されるケースも多く、戦略的に転職を重ねてきた場合はむしろ強みとして活かせるのです。
書類選考や面接で不利になるリスク
一方で、日本では転職回数が多いことがネガティブに受け取られる場面もあります。
特に書類選考の段階で「長続きしないのでは」「トラブルを抱えているのでは」といった懸念を持たれてしまうことがあります。
また、面接では「なぜ短期間で辞めたのか」「なぜその業界に移ったのか」といった質問に対し、説得力ある説明が求められます。
このようなリスクを避けるためには、職務経歴書で一貫性や成長のストーリーを意識的に描くことが重要です。
たとえ頻繁に職を変えていたとしても、「目的を持った転職」であることを明確に伝えれば、印象は大きく変わります。
転職歴がマイナスに働かないよう、事前準備とセルフブランディングが鍵となるでしょう。
雇用主側の教育コストと定着課題

企業側から見ると、転職回数が多い人材を採用することにはリスクも伴います。
たとえば、入社後すぐに退職してしまえば、教育にかけた時間やコストが無駄になってしまいます。
- 新人研修やOJTのコストが毎回かかる
- チームへの適応や文化理解に時間がかかる
- 短期間で離職されると、再び採用活動が必要になる
このため、企業は「定着率」や「長期的な貢献」に対する不安を抱くことがあります。
採用側の心理を理解しつつ、自身の「継続性」や「意欲」を具体的に伝えることが重要です。
また、「長く働く意思がある」「企業文化に共感している」といった姿勢を示すことも、採用担当者の不安を和らげるポイントになります。
企業が外国人の離職を防ぎ定着率を高める方法
キャリアパスを明確に提示する
外国人労働者が長く働くためには、「将来の見通し」が不可欠です。
そのため、企業側はキャリアパスを具体的に示すことが、離職防止につながります。
- 入社後3年以内の昇進モデルやジョブローテーション例を提示する
- スキルアップ研修や資格取得支援制度を案内する
- 目標設定と評価の仕組みを明文化し、将来のビジョンを共有する
「この会社にいればキャリアが築ける」と思える環境があれば、外国人にとっても定着の動機が強まります。
不透明な組織構造や曖昧な評価制度は、優秀な人材の流出を招く原因になりかねません。
公正な評価・報酬制度を整備する

外国人従業員の不満の一因として、「評価の不透明さ」や「日本人との格差」が挙げられます。
そこで重要なのが、実績に応じたフェアな評価と報酬制度です。
言語や国籍に関係なく、成果に対して正当な評価が得られる環境が整っていれば、外国人のモチベーションは大きく向上します。
たとえば、OKRやMBOといった目標管理制度を導入し、誰もが納得できる評価基準を設けるといった取り組みが有効です。
また、年功序列ではなく成果主義に近い制度設計を取り入れることで、多様な人材が活躍しやすい組織風土が育まれます。
文化的背景を理解したコミュニケーション
外国人との信頼関係を築くうえで、文化の違いへの理解は欠かせません。
たとえば、報連相の頻度、上下関係への考え方、言語的なニュアンスなど、日本人と異なる価値観を持っていることが多いためです。
- 多文化コミュニケーション研修を管理職向けに実施する
- 英語ややさしい日本語での情報共有を意識する
- 本人の母語が通じるサポートスタッフの配置を検討する
一方的に日本のやり方を押しつけるのではなく、歩み寄りの姿勢を見せることで、信頼感が生まれます。
小さな違いへの配慮が、離職率の低下につながるのです。
働きやすい就労環境と生活サポートを提供する
仕事だけでなく、生活面での支援も外国人の定着には重要です。
日本の行政手続きや住居探し、医療機関の利用など、外国人にとっては困難が多く、ストレスの原因になりがちです。
企業がこれらをサポートすることで、「この会社は信頼できる」と感じてもらいやすくなります。
たとえば、外国語対応の人事窓口、通訳付きの健康診断、銀行口座や携帯契約の手続きサポートなどが効果的です。
また、社内でのメンタルケアや生活相談窓口の設置も、安心して働ける環境づくりに寄与します。
就労支援と生活支援の両輪がそろって初めて、外国人が長期的に活躍できる職場になるのです。
転職回数が多い外国人が日本で成功するポイント
職務経歴書でキャリアの一貫性を示す

転職回数が多い場合でも、キャリアの一貫性を職務経歴書で丁寧に示すことで、評価は大きく変わります。
特に日本では「なぜその道を選んできたのか」というストーリーが重要視されます。
- 職種や業界に一貫した軸があることを明確に記載する
- 各職場での実績や貢献度を具体的な数値で示す
- 「転職の理由」と「次の職場で何を実現したかったか」をセットで説明する
これにより、ただの転職歴ではなく、「戦略的にキャリアを築いてきた人材」として評価されやすくなります。
日本企業は安定志向が強いため、「将来を見据えて積み重ねてきた経歴」であることを明確に伝えることが重要です。
面接でポジティブに転職理由を伝える
面接では、転職理由が特に重視されます。
ネガティブな印象を与えないよう、すべての転職において「目的」や「学び」を前向きに伝えることが求められます。
たとえば「上司との相性が悪かった」ではなく、「より挑戦的な環境を求めて転職した」といった表現に変えることで、受け手の印象が大きく変わります。
また、「今回の転職では長く働きたい」という意志を明確に伝えることで、企業の不安も和らげることができます。
転職歴が多くても、「次こそ定着したい」「この企業でキャリアを築きたい」という意欲を誠実に伝える姿勢が成功の鍵になります。
専門性を証明するスキルや資格を取得する

転職回数が多い外国人にとって、専門スキルや資格は「信頼性を補う材料」として非常に有効です。
特にIT、エンジニアリング、マーケティング、翻訳などの分野では、業界共通の資格や実務経験が客観的な強みになります。
- 日本語能力試験(JLPT)やビジネス日本語検定などの言語資格
- 業界ごとの国家資格やベンダー資格(例:簿記、基本情報技術者、TOEICなど)
- オンライン講座や研修を通じた最新スキルの習得
資格やスキルの取得は「成長意欲の証」としても評価されるため、採用側から見た安心材料になります。
「転職歴は多いが、確かなスキルがある」ことが証明できれば、むしろ即戦力として歓迎されるケースも多いのです。
データで見る世界の転職率と平均勤続年数
世界ランキングから読み解く平均勤続年数
世界各国の平均勤続年数を比較すると、その国の労働文化や雇用慣行の違いが浮き彫りになります。
たとえば、OECD(経済協力開発機構)の統計によると、日本の平均勤続年数は約12年と、加盟国の中でもトップクラスです。
一方、アメリカは4〜5年、韓国は6〜7年程度とされ、欧州各国でも7〜9年が平均的です。
- 日本:長期雇用前提の制度が根強く、勤続年数は長め
- アメリカ:ジョブホッピングが一般的で平均勤続年数は短い
- ドイツ:中小企業でも10年近い勤続年数を保っていることが多い
これらのデータからも、日本と他国とでは「定着」に対する価値観が大きく異なることがわかります。
日本で転職が少ないのは文化的背景だけでなく、制度や社会構造にも起因しているのです。
日本と海外の離職率比較
離職率とは、一定期間内に退職した人の割合を示す指標で、労働市場の流動性を測る指標にもなります。
厚生労働省のデータによれば、日本の年間離職率は平均約15%前後とされています。
一方、アメリカでは20〜25%に達する業界もあり、業種によっては30%を超えるケースもあります。
この違いは、企業と従業員の関係性や雇用契約の形式の違いに起因しています。
日本では正社員の解雇が難しく、終身雇用が前提のため離職率は低くなる傾向があります。
対して欧米では、「必要な時に必要な人を雇う」スタイルが一般的であるため、雇用の流動性が高く、離職率も高くなるのです。
離職率が高い=悪いというわけではなく、労働市場の柔軟性を表す一面でもあることを理解しておく必要があります。
業界別・職種別の最新転職動向
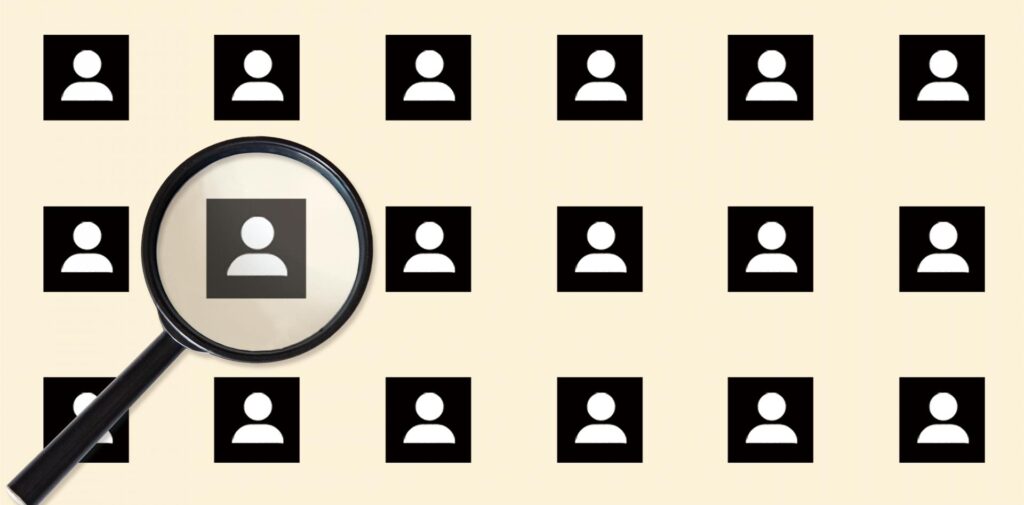
転職率は業界や職種によっても大きく異なります。
たとえばIT業界やスタートアップ、外資系企業では、転職が活発で離職率も高めです。
- IT・テック業界:変化が激しくスキルアップ志向も強いため、転職が頻繁
- サービス業:非正規雇用が多く、雇用期間が短いため離職率が高め
- 医療・福祉業界:需要は高いが、業務負担が重く離職者も多い
一方で、公務員や金融・インフラ業界などは比較的安定しており、勤続年数が長くなる傾向があります。
外国人労働者が転職を検討する場合は、自身のスキルや志向に合った業界の転職傾向も把握しておくとよいでしょう。
市場動向を知ることで、自分の転職活動の可能性や方向性をより具体的に描けるようになります。
まとめ:海外では転職は当たり前、日本企業はどう対応するか
結論として、世界的に見れば「転職が多いこと」はごく自然な現象であり、外国人にとってはキャリア形成の一部として一般的な行動です。
その理由は、実力主義・成果主義の雇用体系、法制度の柔軟性、社会的な価値観などに裏付けられています。
一方で日本では、転職回数が評価に影響したり、文化や制度面で障壁があったりと、外国人にとっては転職に慎重さが求められる場面もあります。
- 海外ではキャリアアップやスキルアップを目的とした転職が主流
- アメリカや中国などは平均勤続年数が短く、転職が文化として定着している
- 日本では「転職回数=マイナス評価」となりやすい文化がある
- 外国人が日本で転職する際は、ビザや評価基準への配慮が必要
- 企業はキャリアパスの明示や公正な評価制度の導入が定着率向上のカギ
だからこそ、外国人側も「転職理由の明確化」や「一貫性あるキャリア設計」を行い、企業側も「多様な価値観への理解」を深めていく必要があります。
双方が歩み寄ることで、外国人労働者がより活躍できる社会が実現するはずです。
外国人の転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
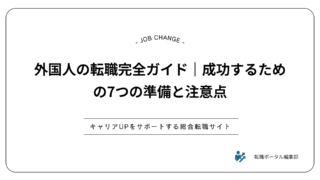
外国人の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓