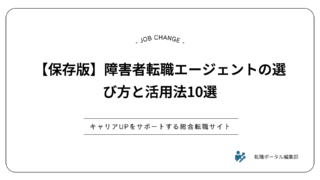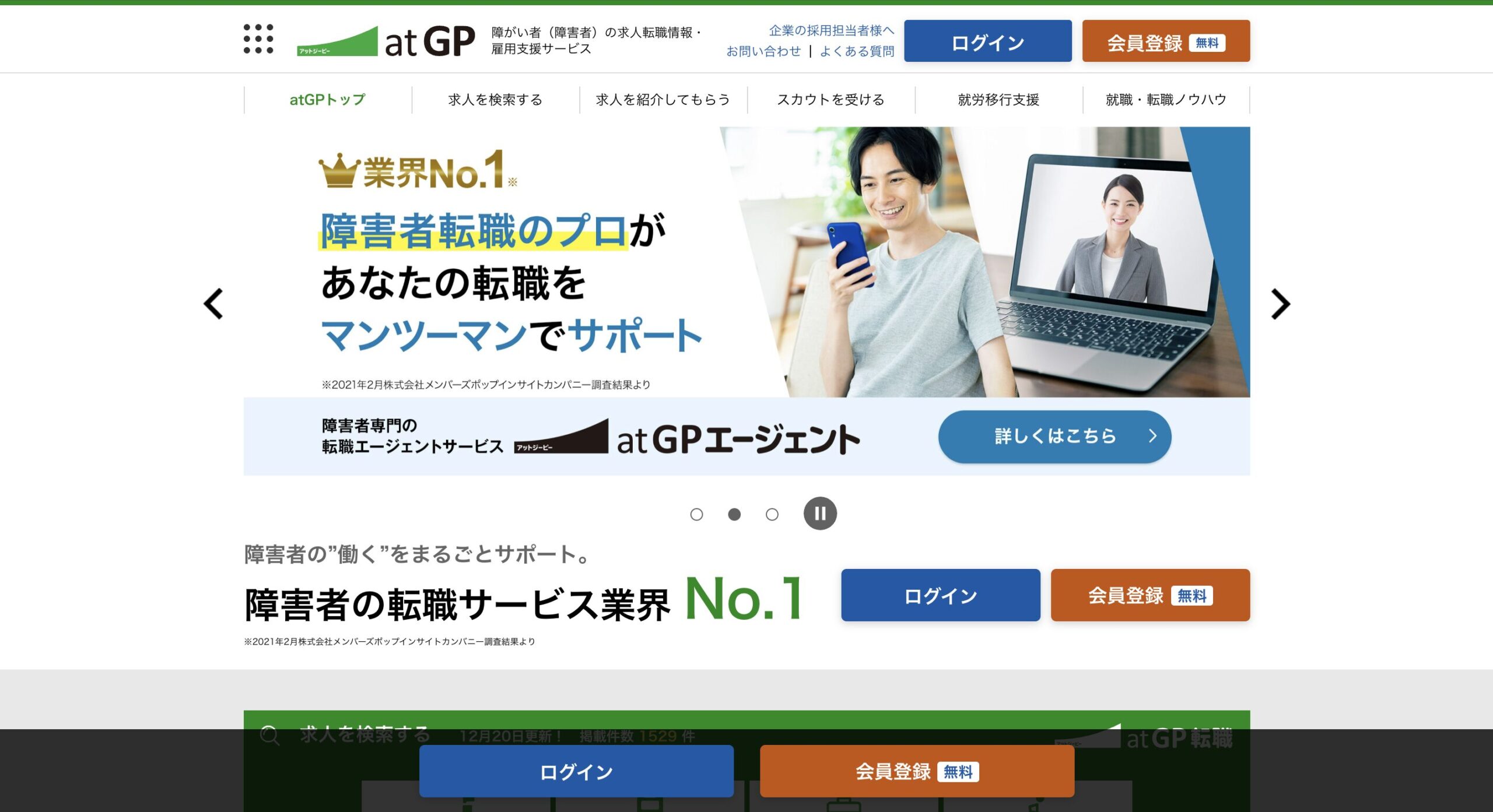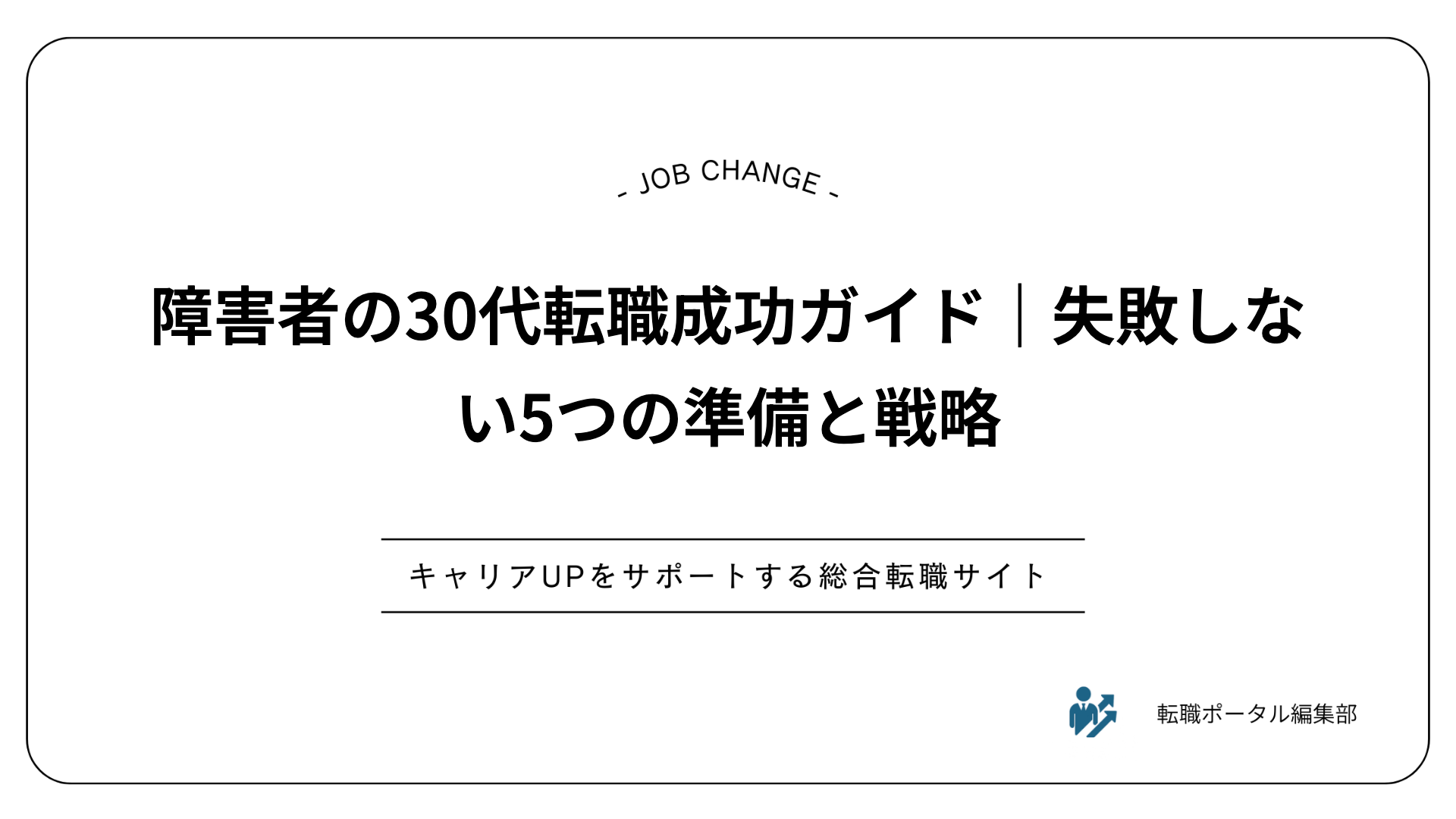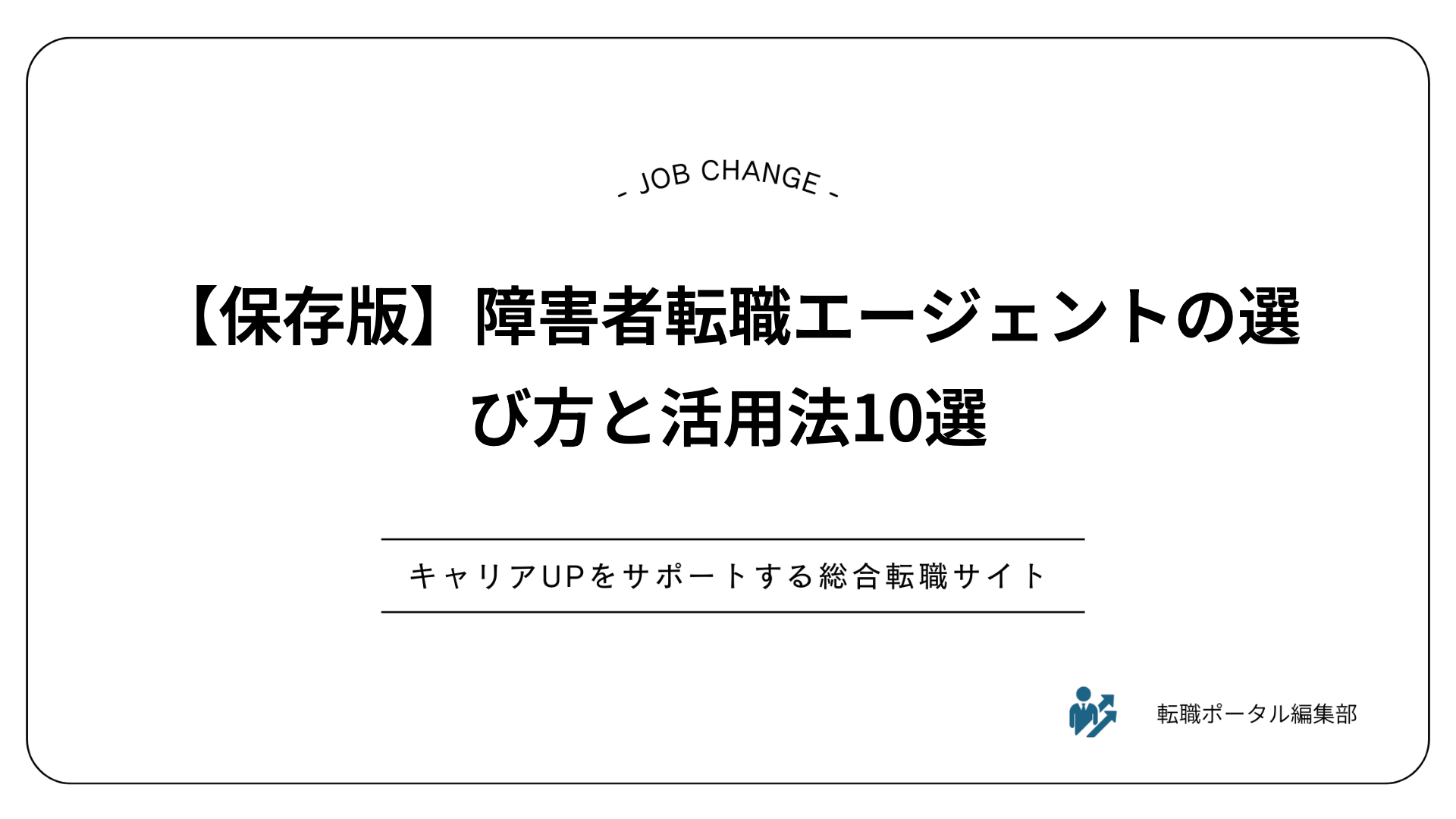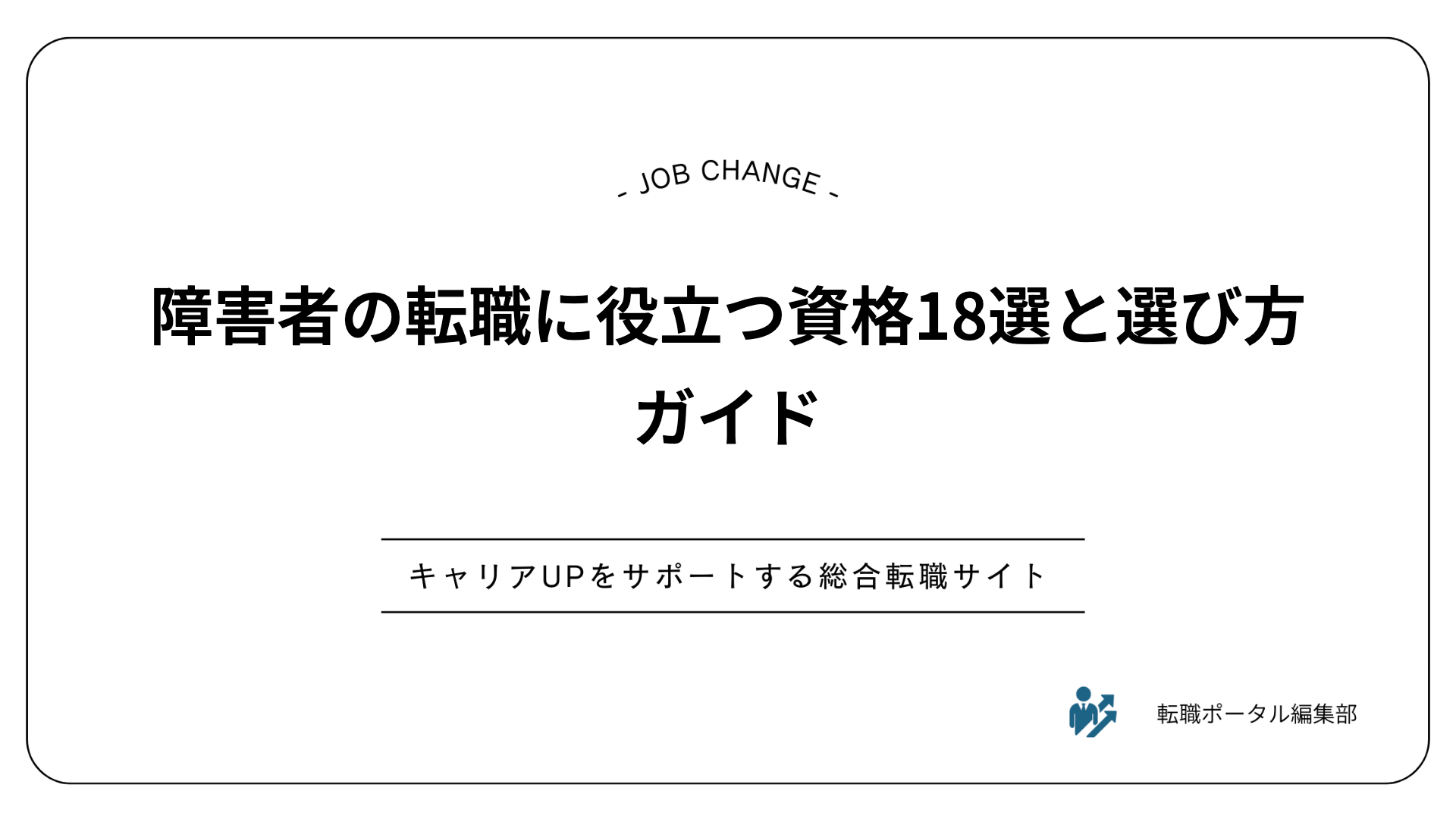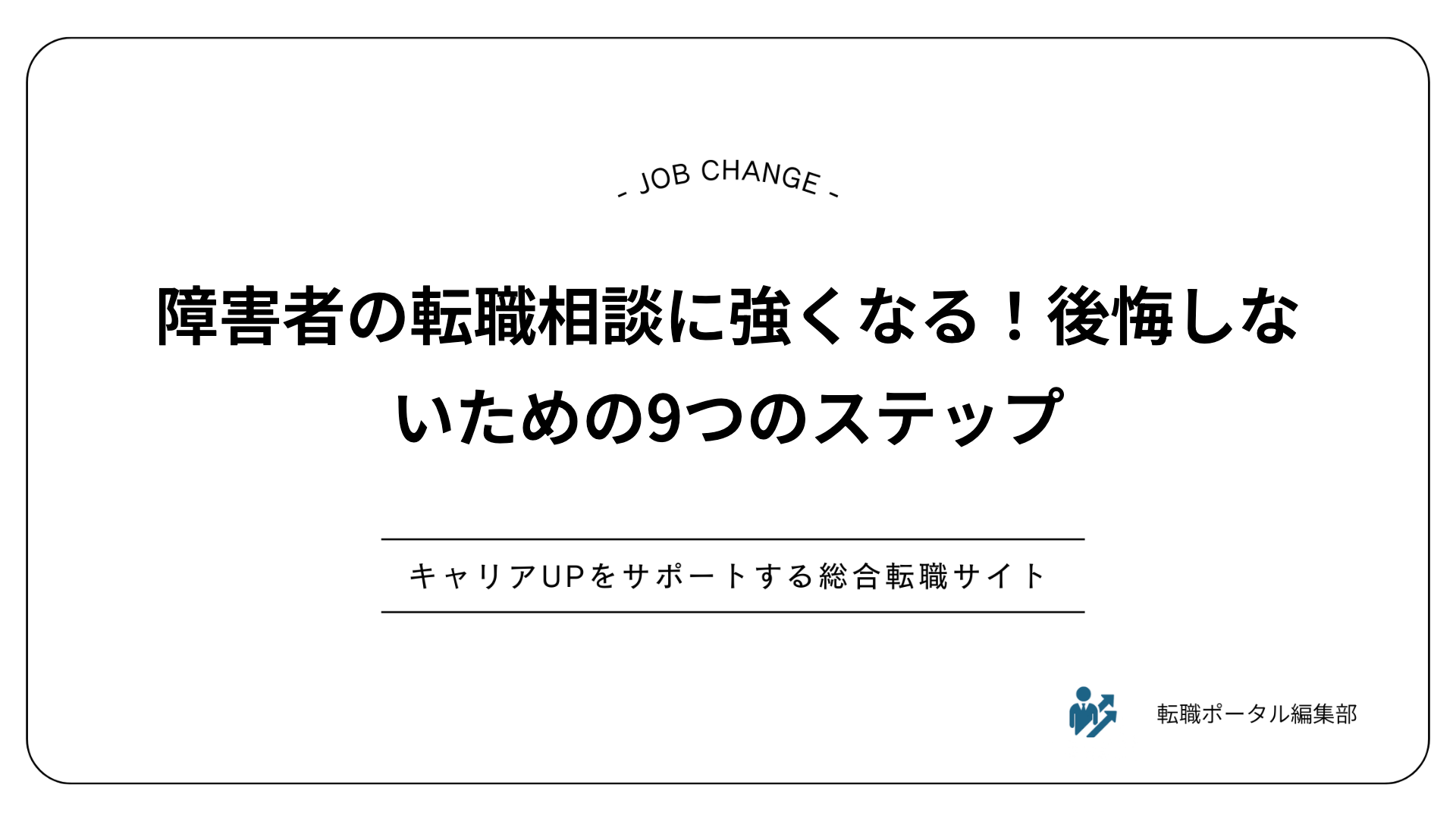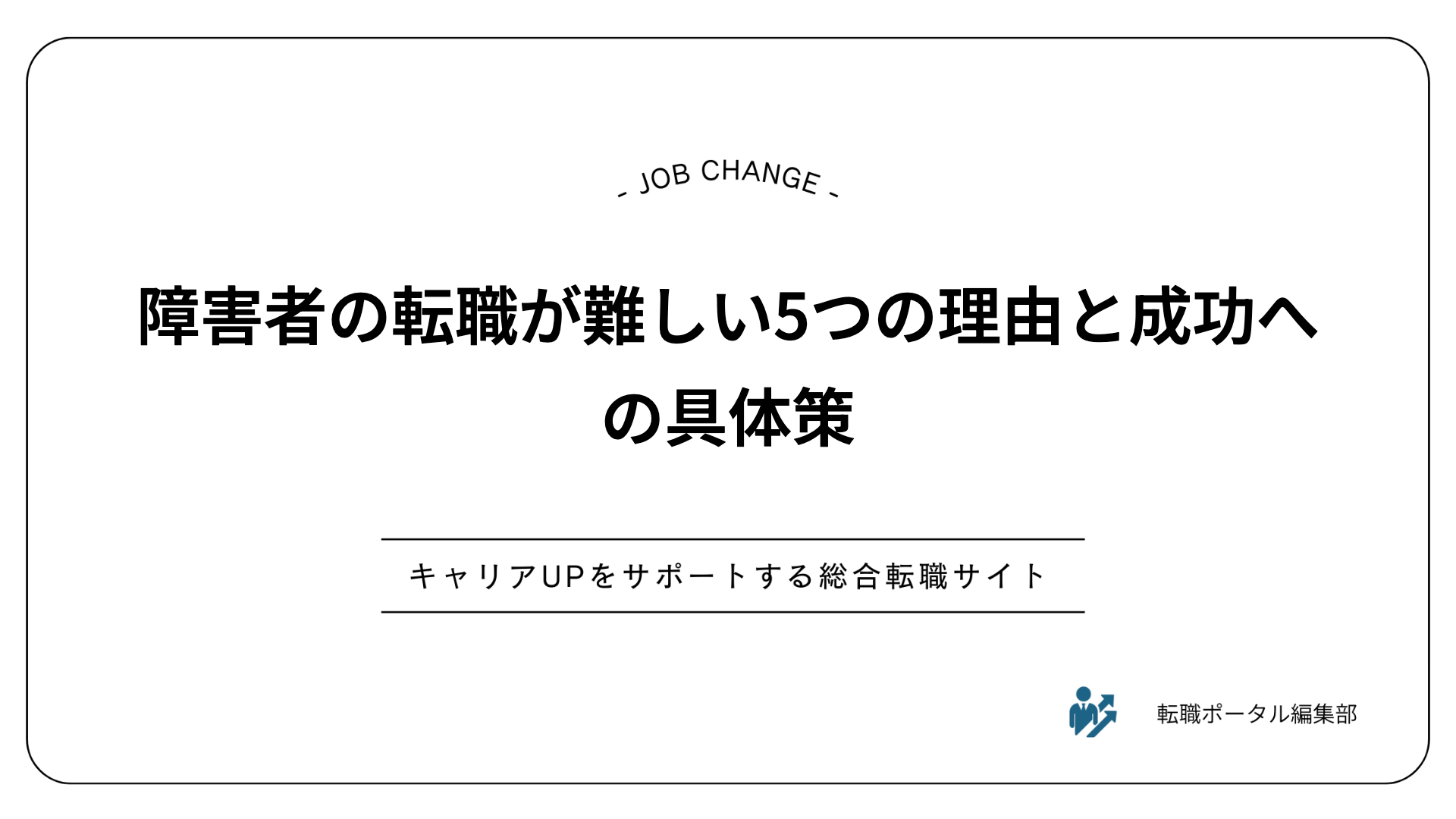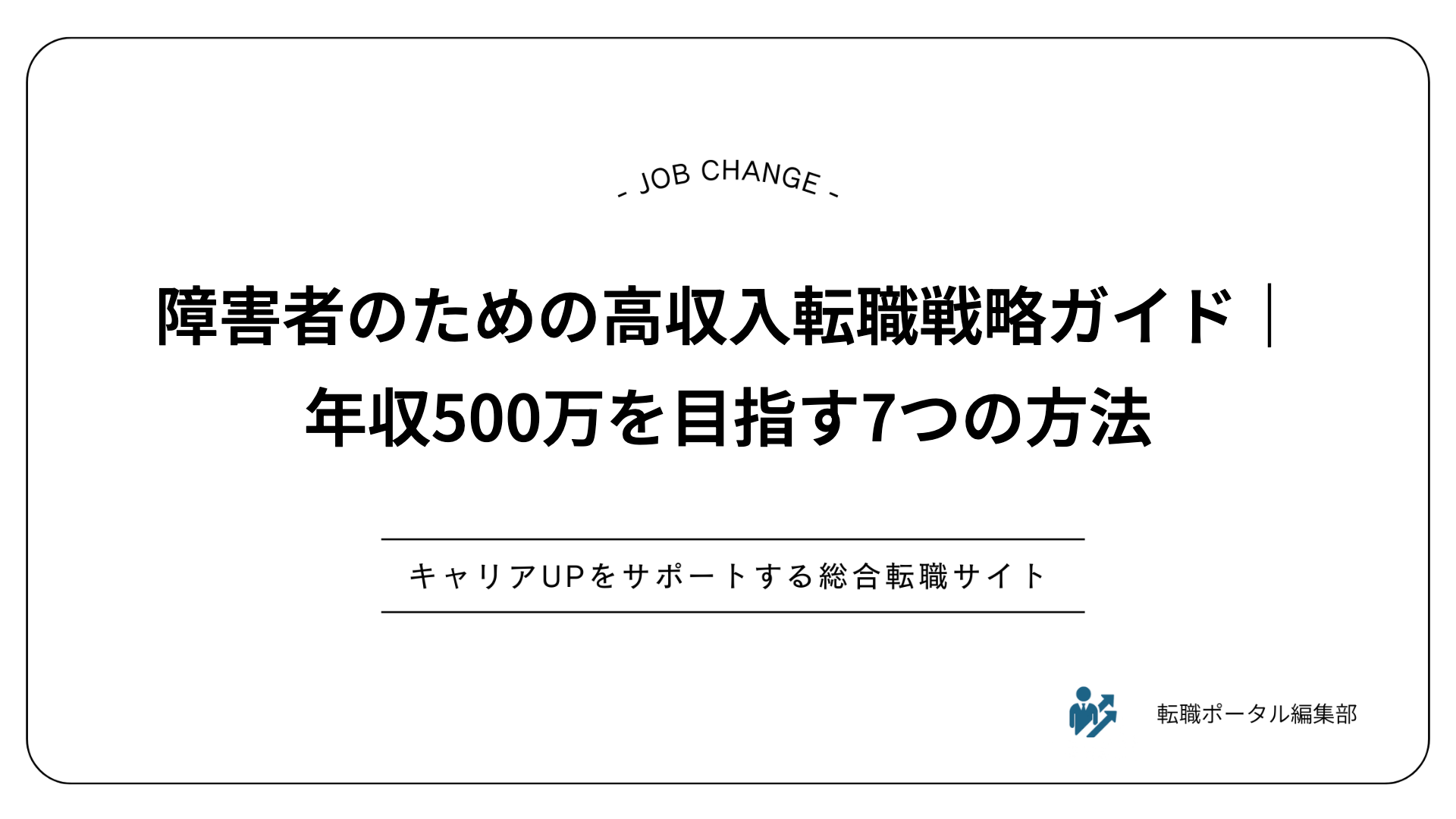障害者向け転職サイトおすすめ10選|選び方・比較・活用法を徹底解説
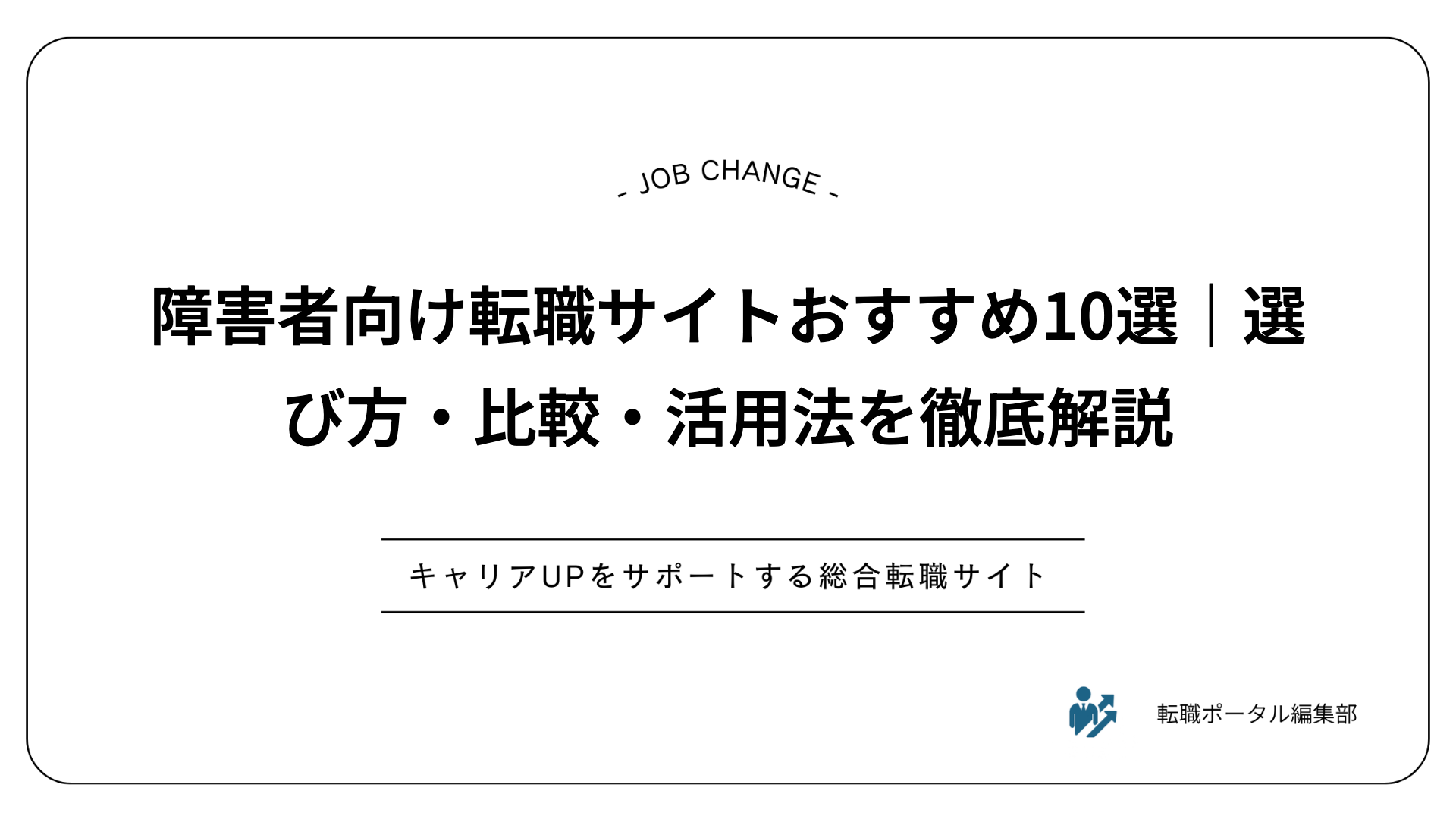
「障害があるけれど、ちゃんと働ける職場はあるのかな…」「どの転職サイトを使えばいいのか、正直よくわからない…」
障害者の転職活動には、情報の少なさや職場とのミスマッチなど、一般の転職以上に悩みや不安がつきまといます。
特に初めての転職やブランクがある方にとっては、どこから始めればいいのかさえ迷ってしまうものです。
この記事では、そんな方に向けて「障害者向け転職サイト」の基礎から活用法までを、わかりやすく丁寧に解説します。
- 障害者雇用の仕組みと転職市場の最新動向
- 自分に合った転職サイトの選び方
- おすすめの障害者転職サイトをタイプ別に紹介
- 転職活動の進め方や成功のポイント
- よくある疑問や不安への答え
あなたに合った働き方や環境は、きっと見つかります。ぜひ最後まで読んで、自分らしいキャリアの第一歩を踏み出してください。
障害者転職サイトとは?特徴と仕組み
障害者雇用枠と一般求人の違い

障害者転職サイトで紹介される求人には、障害者雇用枠として企業が設けた特別な募集が多く含まれています。
これは、障害者が安心して働けるように設計された制度です。
法律により、一定規模以上の企業は障害者を一定割合で雇用する義務があり、それに対応するための配慮や支援体制が整っています。
- バリアフリー設計や通院配慮のある職場
- ジョブコーチや専任の担当者による支援体制
- 体調や障害特性に応じた勤務形態の調整
一方、一般求人ではこれらの配慮が必ずしも期待できるとは限りません。
自分の状況や希望に合わせて、どちらの求人形態が適しているかを考えることが重要です。
「配慮のある環境で働きたい」と感じる方には、障害者雇用枠のある求人から始めるのが安心です。
転職サイトと転職エージェントの役割
障害者向けの転職支援には、大きく分けて「転職サイト」と「転職エージェント」の2つの仕組みがあります。
結論としては、サポート重視ならエージェント型の活用がおすすめです。
転職サイトは、求人情報の検索や応募を自分で進められるサービスです。
一方、転職エージェントは、専任のアドバイザーが付き、求人提案や書類添削、面接対策などをサポートしてくれます。
特に障害者向けの場合、障害内容や配慮事項を踏まえて求人を紹介してくれるエージェントの存在は、安心して転職活動を進めるうえで大きな味方となるでしょう。
「一人で進めるのは不安…」という方は、まずエージェントに相談してみるのが得策です。
最新の障害者転職市場動向

障害者の転職市場は、ここ数年で大きく変化しています。2021年以降、法改正や働き方改革の影響により、障害者雇用はさらに活発になっています。
特に注目すべきは、在宅勤務やテレワーク求人の増加です。身体的・精神的な負担を軽減しながら働ける環境が整いつつあります。
- 法定雇用率の段階的引き上げ
- 精神・発達障害者の雇用数の拡大
- テレワークを取り入れる企業の増加
これにより、「自分には無理かも」と思っていた方も、より現実的に働ける選択肢が広がっています。
時代の変化に目を向け、自分に合った働き方を探してみてください。
障害者転職サイトのメリット・デメリット
転職サイトを利用するメリット
障害者向けの転職サイトを活用する最大の利点は、自分のペースで情報収集や応募ができることです。
結論から言えば、手軽さと情報量の豊富さが大きな強みです。
まず、会員登録さえすれば、全国の求人情報をすぐに検索できます。
非公開求人や、障害特性に応じた詳細な条件検索も可能なサイトが多く、効率よく自分に合う仕事を見つけられます。
- 24時間いつでも求人検索・応募が可能
- 自分の希望に合った条件で検索できる
- 登録者限定の特典や非公開求人がある
忙しい中で転職活動を進めたい方、自分のペースでじっくり求人を見比べたい方には、特におすすめです。
「周囲に知られずに活動したい」という方にも、転職サイトは使いやすい選択肢です。
転職サイトのデメリットと注意点
転職サイトは便利な反面、デメリットも存在します。特に障害者向け求人を探すうえでは、「求人の質」と「応募後のサポート体制」に注意が必要です。
まず、サイトによっては企業からの情報提供が不十分で、実際の職場環境や配慮内容が見えにくいことがあります。
また、応募しても返信が遅かったり、書類選考の通過率が低かったりと、精神的な負担を感じやすい点も見逃せません。
さらに、サイトはあくまで「情報提供の場」であり、個別の相談や面接対策は自分で行う必要があります。
サポートが手薄な状態で進めると、思わぬミスマッチが起きることもあるのです。
「応募後に音沙汰がない…」「職場に配慮がなかった…」と後悔しないためにも、必要に応じて転職エージェントと併用するのがおすすめです。
障害者転職サイトの選び方
サポート体制とサービス内容を比較する

障害者転職サイトを選ぶ際、最も重視すべきは「どれだけサポートしてくれるか」です。
求人をただ紹介するだけでなく、就職活動全体をフォローしてくれるサービスがあるかどうかを確認しましょう。
- 履歴書・職務経歴書の添削サポート
- 障害特性に応じた面接対策
- 内定後の職場定着サポート
とくに精神障害や発達障害のある方は、就職後のフォローまで対応しているサイトを選ぶことで、安心して長く働ける環境が整います。
「一人で就活するのは不安…」という方には、専任アドバイザーがつくエージェント型のサービスが心強い味方になります。
求人情報の詳細度と検索機能をチェック
求人を探す際、情報の分かりやすさと検索のしやすさも重要な判断基準です。結論から言えば、「詳細な条件で絞り込みができるか」がポイントです。
良質な転職サイトでは、業種・職種・勤務地だけでなく、「配慮事項」「障害種別対応」「テレワーク可否」など、細かな条件で検索できる機能があります。
また、求人票には業務内容や配慮内容、社内サポート体制が具体的に書かれているかも重要です。情報が曖昧な場合、面接時の確認が必須となります。
「たくさん求人があっても、自分に合う仕事が見つからない…」と感じたら、検索機能と情報の質に注目してみてください。
年齢・障害種別に合ったサイトか確認する

障害者転職サイトは、それぞれ得意とする対象層が異なります。年齢や障害の種類によって、相性の良いサイトを選ぶことが重要です。
- 20代〜30代向け:キャリア形成重視、ポテンシャル採用が多い
- 40代以上:経験を活かせる求人や中高年向け支援があるサイト
- 精神・発達障害対応:専門カウンセラー常駐サイトも
サイトの公式ページにある「対応障害種別」や「利用者の声」などを確認し、自分と同じ背景を持つ人の実績があるかを見るのも参考になります。
「年齢的にもう難しいのでは…」と諦めず、自分の属性に合うサービスを見つけることで、選択肢はぐっと広がります。
地方求人や在宅勤務対応の有無を確認する
都市部以外に住んでいる方や、外出が難しい方にとって、「求人の地域性」や「在宅勤務の可否」は大きなポイントになります。
最近では、地方企業や在宅対応可能な求人も増えてきていますが、全てのサイトがそのような求人を扱っているわけではありません。
「全国対応」「在宅OK」「テレワーク可能」などのフィルターで検索できるか、またそれらの求人が実際にどれくらいあるかを事前に確認しておくことが大切です。
「通勤が不安で転職をためらっている…」という方も、リモート勤務対応の企業なら、無理なく働ける環境が見つかるかもしれません。
おすすめ障害者転職サイトランキング
総合型で求人が豊富なサイト
求人数の多さを重視するなら、総合型の障害者転職サイトが有力です。
さまざまな業界・職種・エリアの求人が掲載されており、幅広い選択肢の中から比較・検討できます。
- 全国対応の求人数が豊富
- 障害種別に関係なく多くの方が利用可能
- はじめての転職活動でも使いやすい設計
特に「dodaチャレンジ」や「atGP」は、登録後に非公開求人も紹介されるため、公開情報以上のチャンスが得られます。
「どのサイトに登録すればいいか迷う…」という方は、まずは総合型からスタートして、他のサイトと併用すると効率的です。
手厚いサポートが受けられるエージェント型サイト
サポートを重視するなら、エージェント型のサービスが最適です。
専任アドバイザーがヒアリングを行い、希望条件や障害特性にマッチした求人を提案してくれます。
応募書類の添削や模擬面接、入社後のフォローまで一貫して支援してくれるため、転職が初めての方やブランクがある方にも心強い存在です。
特に「エージェント・サーナ」や「ランスタッドチャレンジド」は、対応の丁寧さに定評があり、多くの利用者から高評価を得ています。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まず相談してみるだけでも大きな一歩になります。
IT・専門職に強いハイクラス向けサイト
スキルや経験を活かしたい方には、IT・専門職に特化した転職サイトがぴったりです。
こうしたサイトでは、高年収やフルリモート、キャリアアップに直結する求人が充実しています。
- エンジニア・デザイナー・マーケ職などが中心
- 年収500万円以上の求人も豊富
- スキル重視のため、学歴やブランクを問われにくい傾向
代表的なサービスには「LITALICOキャリア」や、障害者向け求人も掲載する「Green」などがあります。
「スキルを活かして自分らしく働きたい」という方は、こうした専門型サイトもぜひ検討してみてください。
地方・リモート求人に強いサイト
都市圏以外に住んでいる方や、通勤が困難な方にとって、地方対応や在宅勤務の求人を多く扱うサイトは非常に心強い存在です。
最近では、全国から応募可能な「フルリモート求人」や、「週数日出社のみ」といった柔軟な働き方を前提とした募集も増えています。
地方求人に強いのは「MyMylink(マイマイリンク)」、在宅案件を多く扱うのは「atGPジョブトレ IT・Web」などです。
「地方在住でも都心の企業で働きたい」「通院しながら在宅で働きたい」というニーズに対応できるサイトを選ぶことで、無理なく長く働ける職場に出会いやすくなります。
初めての転職をサポートする就労移行支援サービス連携サイト
就労経験が少ない方や、社会復帰を目指す方にとっては、就労移行支援と連携している転職サイトが安心です。
職業訓練や生活支援、就活準備まで一体的にサポートしてくれるため、自信を持って応募に臨めます。
- 職業訓練付きの求人紹介
- 生活・体調管理の相談も可能
- 定着支援で就職後の不安も軽減
「LITALICOワークス」や「ミラトレ」は、就労移行支援と求人紹介を組み合わせたサービスを提供しており、特に初めての転職者から人気があります。
「社会復帰が不安」「働くことにブランクがある」という方でも、一歩ずつ前に進める環境が整っています。
条件別に選ぶ障害者転職サイト
障害種別で選ぶ
障害者向け転職サイトの多くは、身体・精神・知的・発達など、障害種別ごとに得意分野があります。
自分の障害に対応した求人やサポート体制が整っているサイトを選ぶことで、安心して転職活動を進められます。
- 身体障害:バリアフリー職場、通勤配慮のある求人が多い
- 精神障害・発達障害:通院配慮、体調変動に理解のある職場が充実
- 知的障害:軽作業中心で継続支援のある求人に強み
サイトによっては、障害種別ごとに検索フィルターが用意されている場合もあります。
まずは自分の特性に対応しているかを確認し、サポート内容まで含めて比較するのがポイントです。
「精神障害に理解のある職場を探したい」など、具体的な希望がある場合は、専任アドバイザーのいるサイトがおすすめです。
年代別で選ぶ

年代によって適した転職支援の内容や、企業側の求めるスキルが異なるため、年齢に合ったサービスを選ぶことが大切です。
- 20代:未経験歓迎・ポテンシャル採用の求人が中心
- 30〜40代:実務経験を活かせるミドル向け求人が充実
- 50代以上:業務負担が軽く長期雇用を前提とした求人が多い
年齢による応募制限は原則ありませんが、企業側が想定する年齢層に合った求人を選ぶと、選考通過率も高まりやすくなります。
「この年齢で転職できるのかな…」と不安な方も、年齢別の支援に実績のあるサービスを使えば、自分に合った働き方が見つかるはずです。
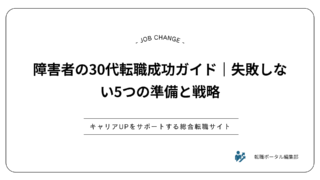
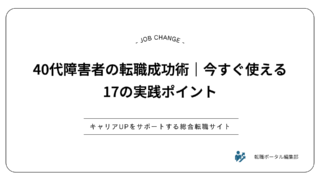
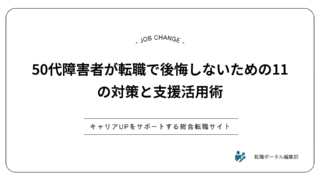
働き方別(在宅・時短・フルタイム)で選ぶ
障害の状況や家庭事情によっては、働き方の柔軟性が何よりも重要です。
障害者転職サイトの中には、在宅勤務・時短勤務など、働き方に特化した検索機能を持つサイトもあります。
最近では、「週3日からOK」「午前中のみ勤務可」「完全在宅」など、多様な働き方を想定した求人も増加中です。
こうした求人は競争率も高いため、希望の働き方が明確な方は、該当する条件に対応したサイトを優先的に利用するのがおすすめです。
「フルタイムは難しいけど、何か仕事がしたい」という想いを叶えるには、柔軟な働き方に強いサイトが最適です。
地域別で選ぶ

障害者向けの求人は、地域によって数や内容にばらつきがあります。そのため、自分が住むエリアに対応しているかを事前に確認することが大切です。
- 首都圏・関西圏:求人の数・種類ともに豊富
- 地方都市:自治体や地元企業と連携した求人が中心
- 過疎地・離島:在宅勤務案件を視野に入れるのが現実的
一部の転職サイトでは、都道府県別や市町村単位での検索が可能です。また、地域に根ざしたサポート拠点を持っているかどうかもチェックポイントです。
「地元で働きたい」「Uターン就職したい」など、地域にこだわりがある場合は、地方特化型のサービスを活用してみてください。
障害者転職サイトを活用する流れ
サイト登録とプロフィール作成
障害者転職サイトを利用する第一歩は、サイトへの無料登録です。
多くのサービスでは、メールアドレスや基本的な個人情報を入力するだけで、数分で完了します。
登録後は、自分の経歴や障害特性、希望条件を詳しくプロフィールに入力しましょう。
この情報をもとに、求人のマッチング精度が決まるため、なるべく正確かつ丁寧に記入することが重要です。
障害内容や必要な配慮事項などは、アドバイザーにのみ公開されるケースが多く、プライバシー保護も配慮されています。
「情報をどう書けばいいか不安…」という場合は、エージェント型サイトのアドバイザーに相談しながら進めると安心です。
求人検索と応募
プロフィールを入力したら、いよいよ求人検索に移ります。キーワードや勤務地、業種、障害配慮の有無などを条件に、自分に合った求人を探しましょう。
転職サイトによっては、検索結果に「障害者雇用枠」「在宅勤務対応」「精神障害配慮あり」などのラベルが付いており、視覚的にも選びやすくなっています。
- 条件を保存して新着求人を自動通知
- 気になる求人をお気に入り登録
- 応募前にエージェントが企業へ確認してくれる場合も
応募は1社ずつでも複数同時でも可能ですが、迷った場合はアドバイザーと相談しながら進めるのがおすすめです。
「自分に合う求人が見つからない…」という場合は、検索条件を少し緩めてみるのも一つの手です。
書類選考・面接対策
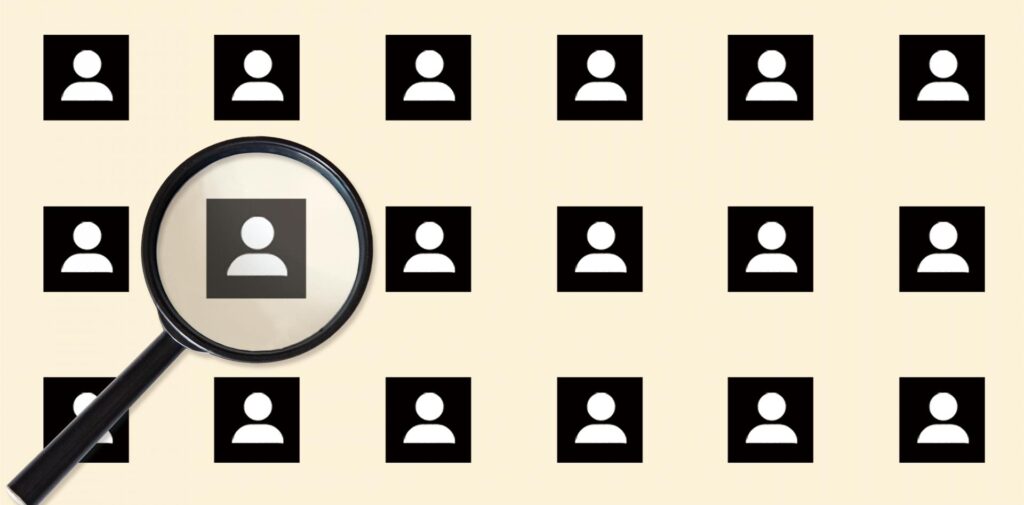
応募後は、企業による書類選考が行われます。通過した場合は、面接へと進みますが、このプロセスでは事前の準備が成功の鍵となります。
履歴書や職務経歴書には、障害の内容や必要な配慮についてどの程度記載するかが悩みどころです。
エージェントを活用すれば、書き方の例や企業ごとの傾向を教えてもらえるため安心です。
面接では、自己紹介や志望動機に加えて、配慮してほしいことや苦手な業務についても正直に伝えることが大切です。
「障害の話をどう切り出せばいいかわからない…」という場合は、模擬面接で練習することで自信が持てます。
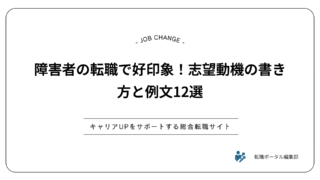
内定後のサポートと定着支援
内定が決まった後も、サポートは続きます。入社前には雇用条件の確認や、配慮事項の書面化、入社手続きのフォローなどが行われる場合が多いです。
また、就職後の「定着支援」も重要です。入社して数ヶ月以内に悩みが出やすいため、エージェントが企業と連携し、職場での状況を確認してくれます。
- 職場環境が合わないと感じた場合の相談窓口
- 勤務中のトラブルや不安を共有できる体制
- 必要に応じて業務調整や配置換えのサポート
「せっかく就職できたのに続けられるか不安…」という方も、こうした定着支援を活用することで、安心して働き続けられます。
障害者転職サイトを使って成功するコツ
複数サイトへの登録で選択肢を増やす

転職成功のコツは、1つのサイトに絞らず、複数の障害者転職サイトに登録することです。
なぜなら、サイトごとに取り扱っている求人やサポート内容が異なるからです。
あるサイトでは非公開求人として紹介される企業が、別のサイトでは一般公開されていることもあります。
また、アドバイザーとの相性も人によって異なるため、複数登録することで自分に合ったサービスに出会える可能性が高まります。
- 求人の比較がしやすくなる
- 異なるサポート体制を体験できる
- 複数のアドバイザーから意見がもらえる
「どこが一番良いのかわからない…」と悩んでいる方は、まず2〜3サイトに登録して、使いやすさや対応を比べてみるのが良いでしょう。
新着求人をこまめにチェックする
転職サイトでは、常に新しい求人が追加されていきます。希望に合った求人を見逃さないためにも、こまめなチェックが大切です。
特に人気のある企業や在宅勤務可能な求人は、応募が殺到してすぐに締め切られることもあります。
サイトによっては「新着求人通知」や「条件保存アラート」などの機能があるため、それらを活用して効率的に情報収集をしましょう。
「求人を見るのが面倒…」と感じる方も、通知機能を使えば、手間をかけずに最新情報をキャッチできます。
アドバイザーとのコミュニケーション術
エージェント型サービスを利用する場合、アドバイザーとのやりとりが成功の鍵を握ります。
結論としては、遠慮せず自分の希望や不安を率直に伝えることが大切です。
アドバイザーは多くの求職者を担当しているため、自分の状況を的確に伝えることで、よりマッチした求人を紹介してもらえます。
- 希望条件や譲れない点を事前に整理
- 障害内容と配慮事項を具体的に共有
- 不安な点や迷いがあれば早めに相談
「こんなこと聞いていいのかな?」とためらう内容でも、転職活動の一環として気軽に話してみましょう。
就労移行支援・公的機関の併用

転職サイトだけでなく、就労移行支援やハローワークなどの公的支援を活用することで、転職の成功率をさらに高められます。
就労移行支援事業所では、職業訓練や履歴書の添削、模擬面接などを行っており、就職後の定着支援も充実しています。
また、ハローワークの「障害者就業・生活支援センター」では、障害者専用の職業相談も可能です。
「転職サイトだけでは心細い…」と感じる方は、こうした支援を併用することで、より安心して就職活動を進めることができます。
よくある質問(FAQ)
障害者転職サイトとハローワークの違い
障害者転職サイトとハローワークは、どちらも障害者の就職を支援する機関ですが、目的やサービス内容に違いがあります。
転職サイトは主に民間企業が運営しており、インターネットを通じて求人情報を提供します。
対して、ハローワークは国の行政機関であり、対面相談や職業訓練などの公的支援が中心です。
- 転職サイト:非公開求人や在宅勤務など、柔軟な働き方に強い
- ハローワーク:地元企業や公的職業訓練に強く、職場実習もあり
どちらか一方に絞るのではなく、それぞれのメリットを活かして併用するのが理想的です。
精神・発達障害でも利用できる?

はい、精神障害や発達障害のある方でも、障害者転職サイトは利用可能です。実際、近年は精神・発達障害のある方の利用者が急増しています。
一部の転職サイトでは、精神障害や発達障害に特化した支援体制を整えており、専門のキャリアアドバイザーが在籍していることもあります。
「体調が不安定でも働ける職場が見つかるかな…」という不安がある方も、通院や体調変動に理解のある企業が増えている今、無理のない働き方が実現しやすくなっています。
企業に障害を開示するタイミングは?
障害の開示タイミングは非常に重要なポイントです。一般的には、「応募時」または「面接時」に開示するのが望ましいとされています。
転職サイトやエージェントを通じて応募する場合、あらかじめ開示したうえで配慮のある選考が行われることが多いです。
自分に必要な配慮をしっかりと伝えるためにも、書類や面接の段階で明確に開示することが、ミスマッチを防ぐコツです。
「伝え方に自信がない…」という場合は、アドバイザーに相談して、適切な説明の仕方を事前に練習するのが安心です。
内定後にサポートは受けられる?
多くの障害者転職サイトでは、内定後も「定着支援」という形でフォローが続きます。
職場で困ったことが起きた場合、アドバイザーが企業と連携して対応してくれるため、安心して働き続けられます。
特にエージェント型サービスでは、入社初日から数ヶ月間、定期的にフォローアップを行う体制が整っています。
「働き始めてからが不安…」という方にとって、入社後のサポートがあるかどうかは、転職サイト選びの重要な基準になります。
まとめ:障害者転職サイトを使いこなして、自分らしい働き方を見つけよう
障害者向け転職サイトは、キャリアの可能性を広げるための有効な手段です。
結論から言えば、「自分に合った転職サイトを賢く選び、活用することで、無理なく働ける職場と出会える可能性が高まる」ということです。
- 障害種別・年代・働き方別に特化した求人が探せる
- エージェント型サービスでは応募から入社後までサポートが充実
- 地方求人や在宅勤務など柔軟な働き方にも対応
- 複数サイトの併用で非公開求人や相性の良いアドバイザーに出会える
- 就労移行支援や公的機関を併用すれば転職活動を総合的に支援できる
だからこそ、「自分に合うサービスがわからない」「転職がうまくいくか不安」という方も、まずは一歩踏み出して登録してみることが大切です。
実際に使ってみることで、自分に必要な情報や支援が明確になっていきます。
障害があるからといってキャリアをあきらめる必要はありません。
適切な転職サイトと出会い、支援を受けながら、自分らしく働ける職場を一緒に見つけていきましょう。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
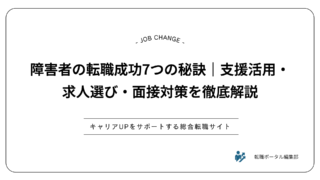
障害者の転職におすすめのエージェントはこちら↓