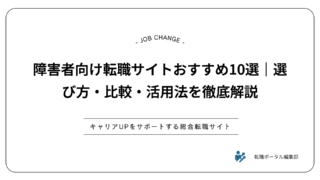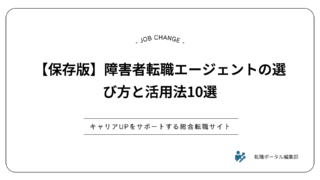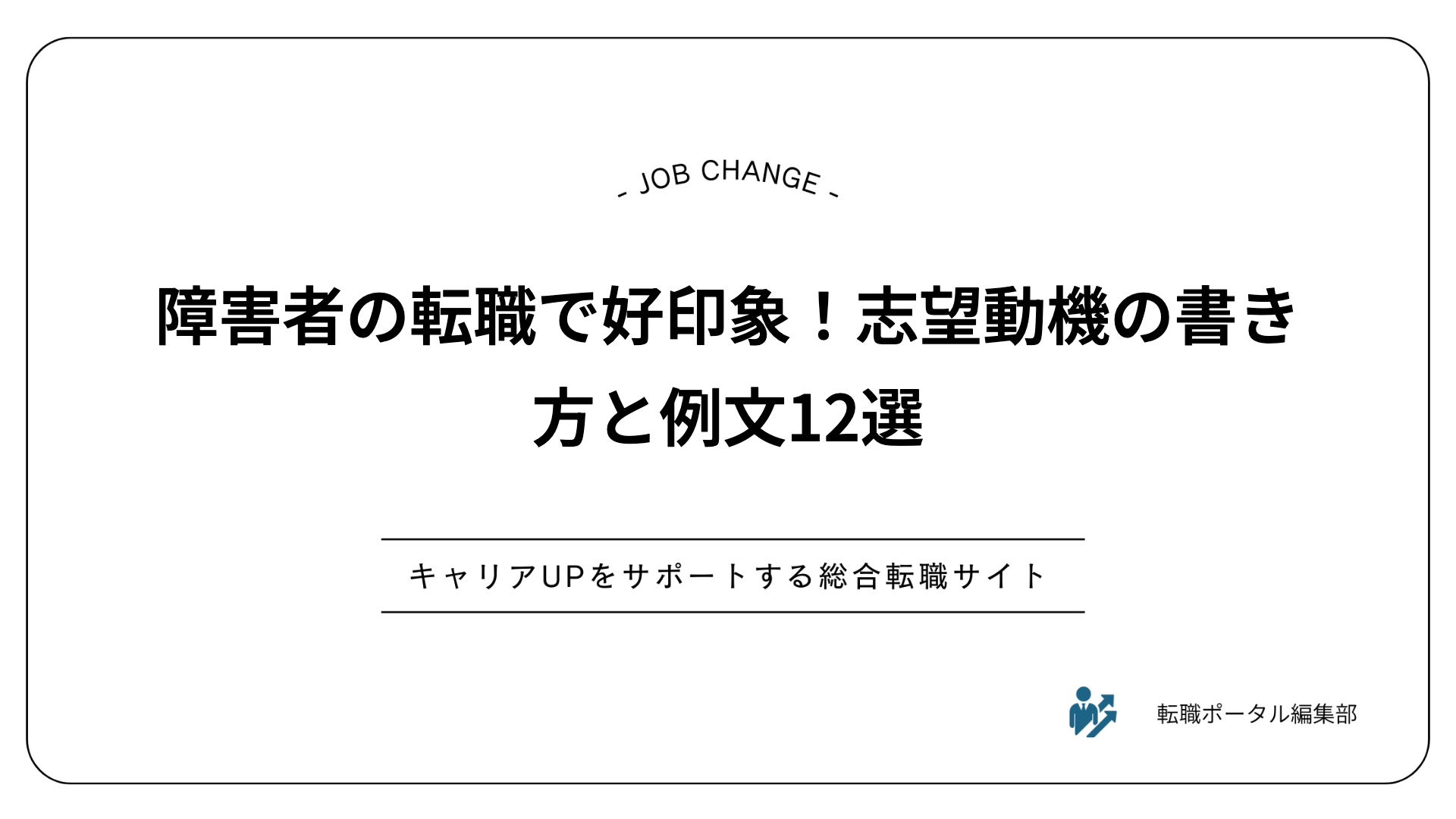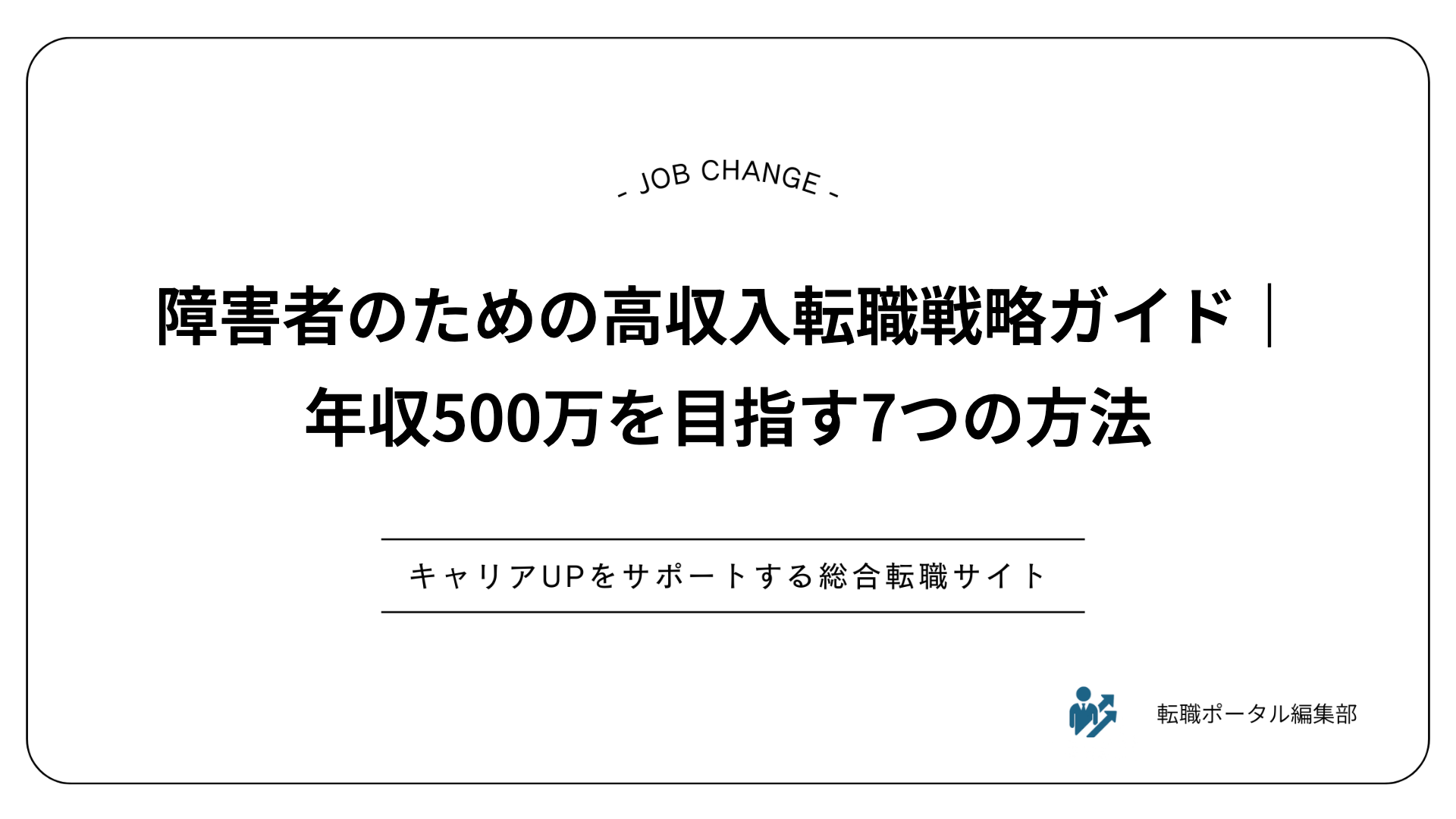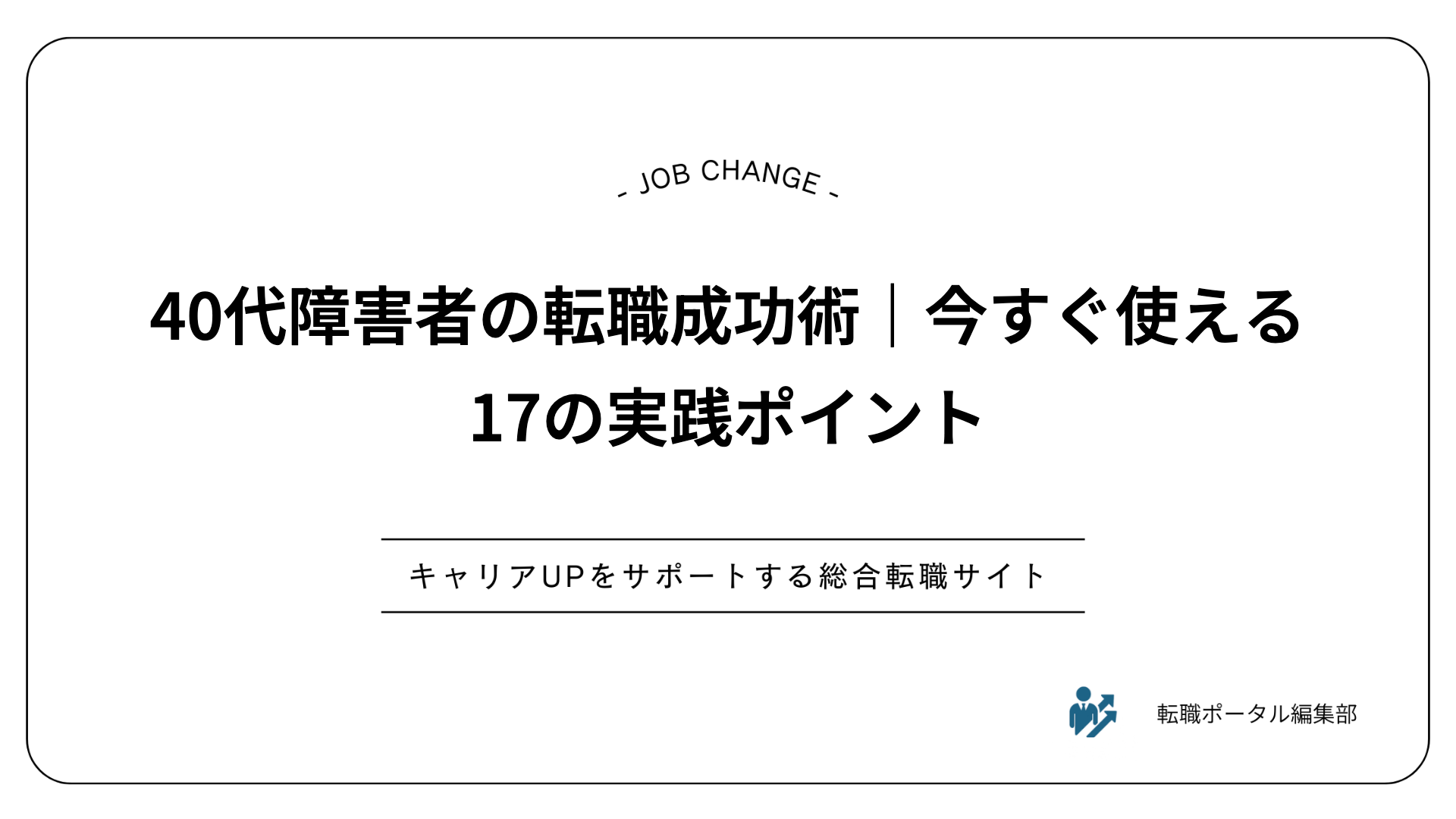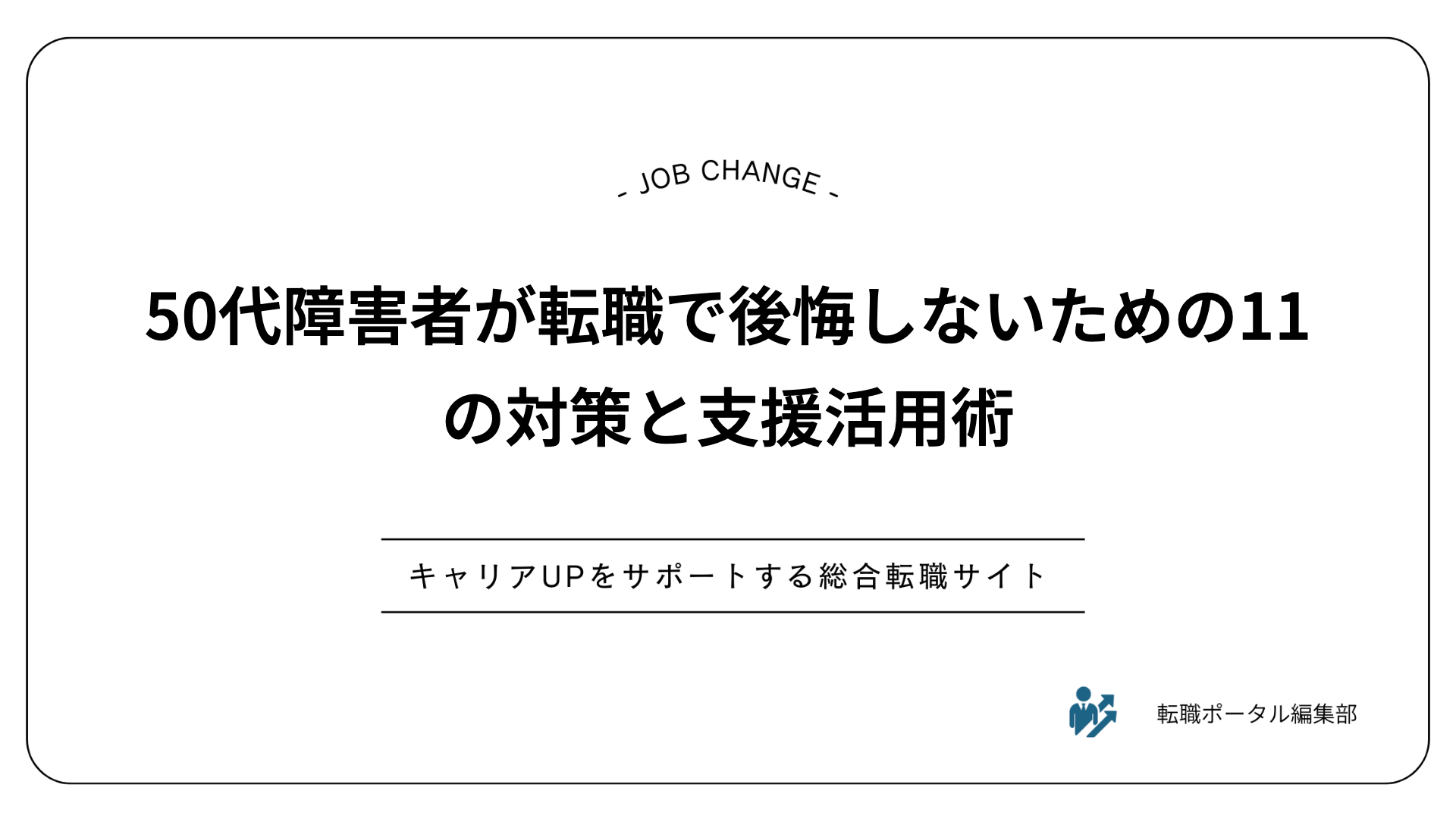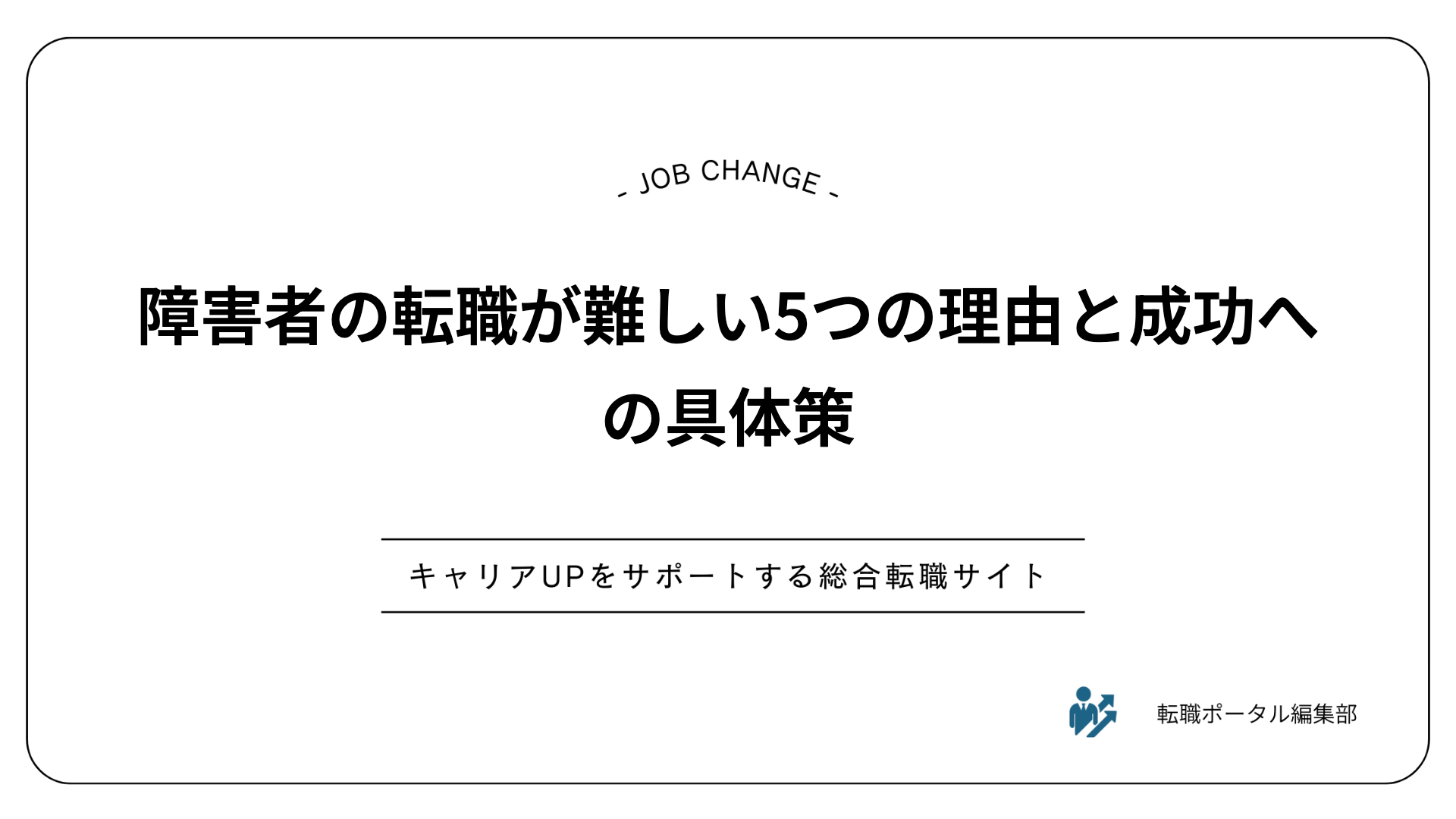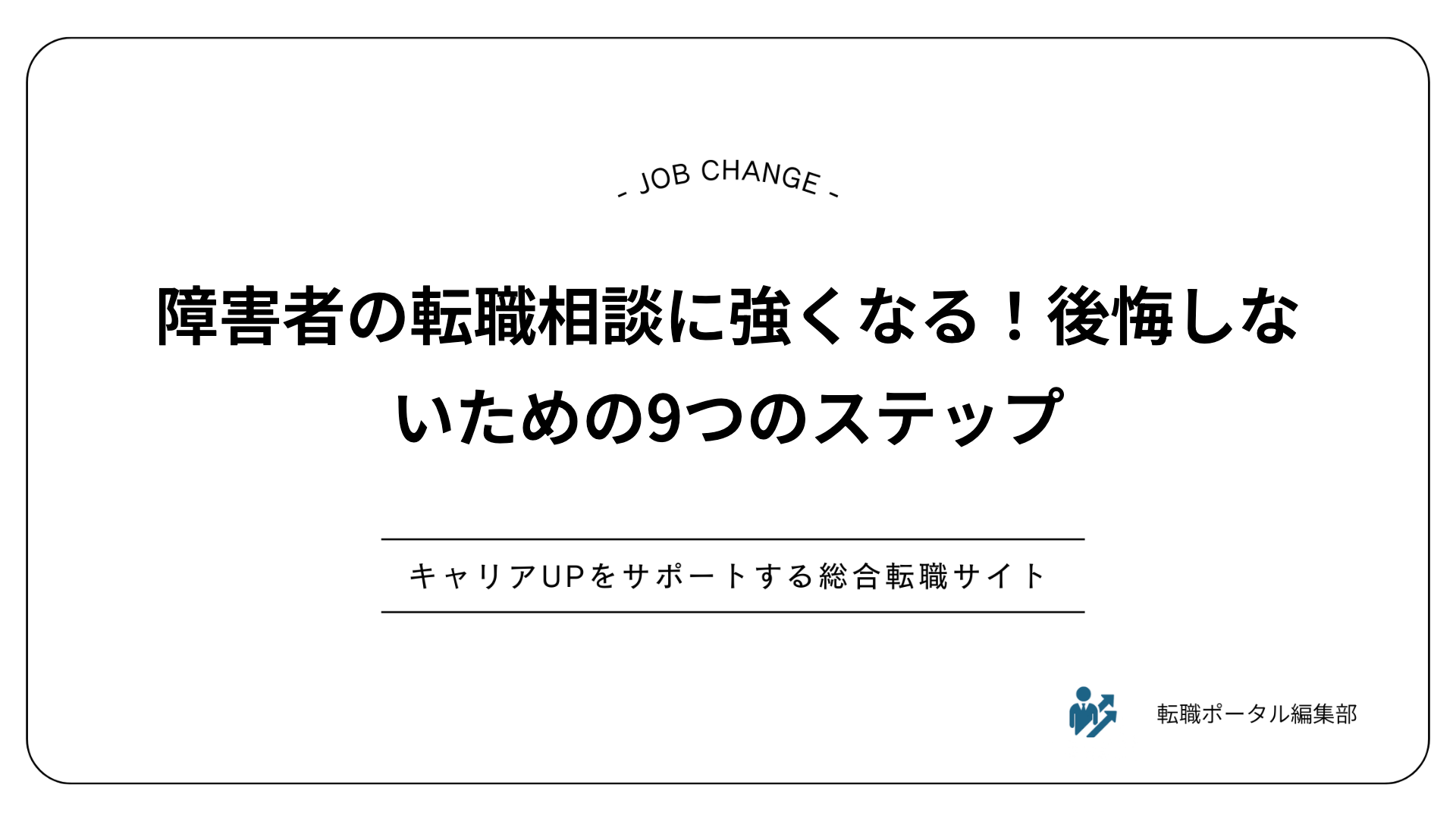障害者の転職に役立つ資格18選と選び方ガイド
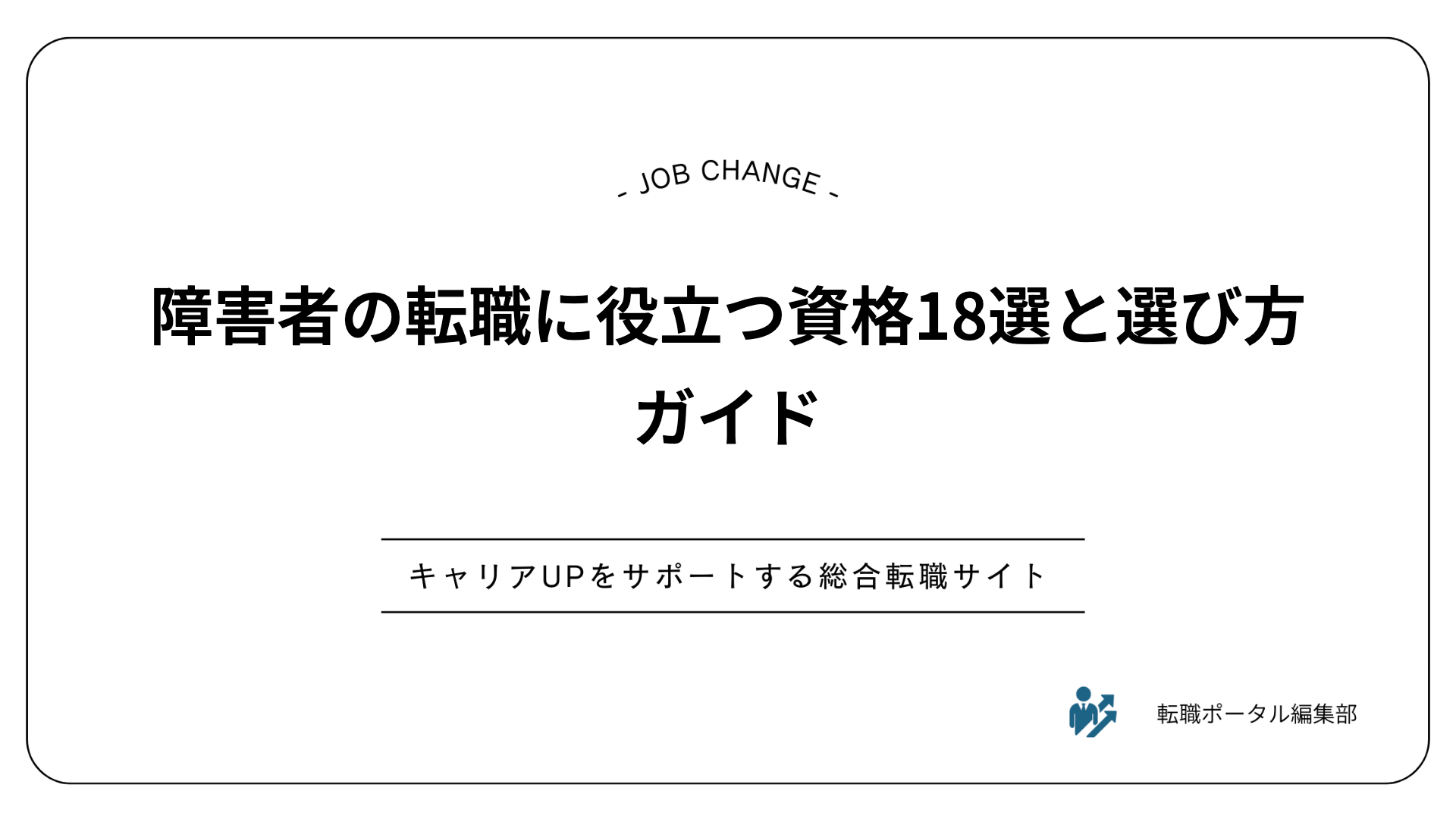
「障害がある自分でも、資格を取れば転職に有利になるのかな…?」そんな不安や疑問を抱えていませんか?
実際、企業は資格を通じて応募者のスキルや意欲を判断しており、適切な資格を持っているだけで書類選考や面接の通過率が大きく変わることもあります。
とはいえ、どの資格を選べばいいのか、どんな支援制度が使えるのか、自分に合った方法がわからずに悩む方も多いはずです。
そこでこの記事では、障害者の転職において特に役立つ資格とその活かし方を、以下のような視点から丁寧にまとめました。
- 企業が評価する資格の特徴とは?
- 業界・職種別のおすすめ資格
- 発達・身体・精神の障害特性ごとの資格選び
- 公的支援制度を使って学習費用を抑える方法
- 資格を活かした履歴書・面接でのアピール術
資格は、あなたの可能性を広げる大きな一歩。ぜひ最後まで読み進めて、自分に合った選択を見つけてください。
資格取得が障害者の転職に与えるメリット
企業が資格を評価する理由

障害者雇用の現場において、資格は応募者の「業務遂行力」を客観的に示す指標となります。
特に未経験職へのチャレンジやスキルの裏付けが求められる職種では、資格の有無が選考結果を左右することも少なくありません。
- スキル証明として、知識や技術の基準を満たしていることが明確になる
- 学習意欲を持っている姿勢を企業側が評価しやすい
- 業務に直結する内容の資格であれば、即戦力と見なされやすい
特に障害のある方は、過去の職歴や実務経験をアピールしにくい場合もあります。
そんなとき資格が「私はこれができます」と語ってくれる、強力な武器になるのです。
給与・キャリアアップにつながる仕組み
資格を取得することは、採用時の評価だけでなく、就職後のキャリアや収入にも好影響を与えます。
企業によっては資格手当や昇進条件に資格保有を明記していることもあり、長期的なキャリア設計にも役立ちます。
- 資格手当として月額5,000円〜20,000円が支給されるケースがある
- 管理職への昇進には特定の資格取得が必須となる企業もある
- 部署異動や職種転換時に資格が判断材料となることも
単に「入社できる」だけでなく、入社後も活躍の幅を広げる鍵になるのが資格なのです。
障害特性を補完するスキルとしての資格
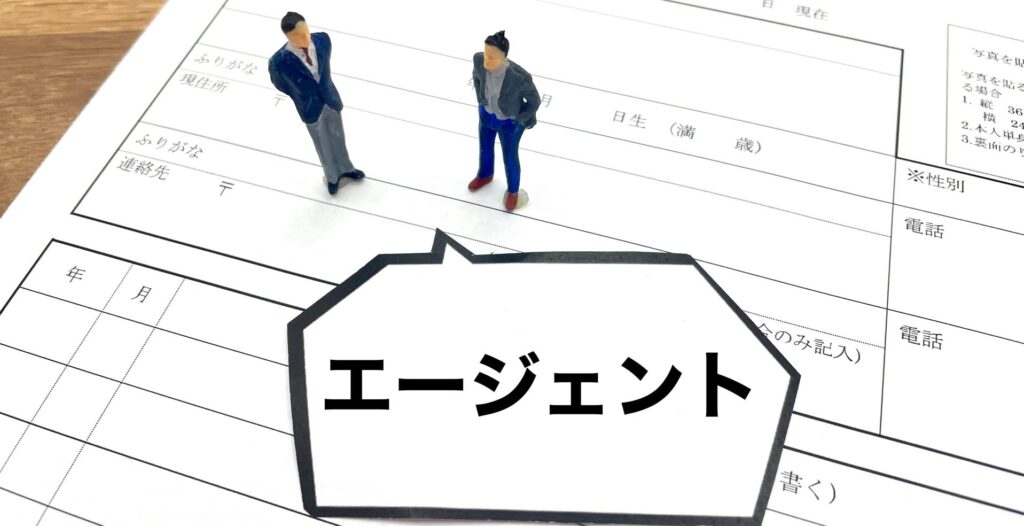
資格はスキルの証明であると同時に、障害によって生じる課題を補う「補完手段」にもなります。
たとえば発達障害の方が「タスク管理が苦手」という課題を補うために、情報整理力や計画力が求められる資格を取得することで、強みに変えることもできます。
また、精神障害のある方がメンタルヘルス系の資格を学ぶことで、自身のストレスマネジメントにも役立つなど、自己理解と成長につながることもあるのです。
つまり資格は、「できない」を補い「できる」に変えるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。
資格選びで失敗しない3つのポイント
適性と興味を見極める方法
資格選びで最も重要なのは、「続けられるかどうか」です。
せっかく時間とお金をかけて学ぶのですから、自分の適性や興味に合っているかを見極める必要があります。
まずは「過去に楽しかったこと」や「苦にならなかった作業」を思い出してみましょう。そこにヒントがあります。
- 事務作業が好き → 簿記・MOSなどの資格
- 人の役に立ちたい → 福祉・相談員系の資格
- マイペースに働きたい → IT・在宅系資格
迷ったときは、適職診断ツールを活用したり、就労移行支援などで専門家に相談するのも有効です。
難易度・費用・学習期間の比較
資格にはさまざまな種類があり、必要な学習時間や受験料、教材費用が大きく異なります。
費用ばかり高くて挫折してしまうのは本末転倒です。自分にとって「現実的なライン」を見極めましょう。
- 費用:テキスト+受験料で1万円以内の資格も多数
- 学習期間:1ヶ月〜6ヶ月で取得可能なものが狙い目
- 難易度:初心者向けの入門資格から段階的に進むのが安全
まずは「短期で取れる+再受験しやすい」資格から始めて、成功体験を積むのが効果的です。
通学・通信・オンラインの学習スタイル

最近ではオンライン学習サービスの充実により、場所や時間に縛られず学べる環境が整っています。
ただし、自宅学習が苦手な方には通学型や就労移行支援を活用する方が継続しやすいこともあります。
- オンライン:Udemy、スタディング、YouTube講座などが人気
- 通信講座:テキスト+添削方式でペースを保ちやすい
- 通学型:対面で質問できるため初学者には安心感がある
ご自身の集中しやすいスタイルを見つけ、無理なく続けられる方法を選びましょう。
業界・職種別おすすめ資格一覧
事務・IT系で評価される資格(MOS・日商簿記など)
事務職やデスクワークを希望する障害者の方にとって、PCスキルや経理知識を証明する資格は大きな強みになります。
中でも、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級は、実務未経験でもアピールしやすい資格として人気があります。
- MOS:WordやExcelの操作スキルを証明
- 日商簿記:経理の基礎を理解している証明
- ITパスポート:情報セキュリティやIT全般の基礎知識
これらの資格は、履歴書に記載するだけで「パソコンが使える」「経理業務も対応可能」と伝えられ、事務職採用に有利に働きます。
福祉・介護系で需要が高い資格(介護福祉士・社会福祉士など)

「人と関わる仕事がしたい」「福祉業界で活躍したい」と考える方におすすめなのが、介護や相談支援に関連する資格です。
介護福祉士や社会福祉士は国家資格であり、専門職としてのキャリア形成にもつながります。
- 介護職員初任者研修:福祉系資格の入門
- 介護福祉士:実務経験と試験が必要な国家資格
- 社会福祉士:相談支援業務に従事する際に必須レベル
身体的な制限がある方でも、支援計画の作成や相談業務といったデスクワーク主体の福祉職種に進む道があります。
技術職・エンジニア向け資格(ITパスポート・基本情報技術者など)
エンジニアやIT関連職種は、リモートワークや柔軟な働き方が可能で、障害者にも人気があります。
技術スキルの証明として活用できるのが国家試験であるITパスポートや基本情報技術者試験です。
特にITパスポートは初学者にも取り組みやすく、就労移行支援事業所でも多く取り入れられています。
「在宅勤務ができる職種に就きたい」という希望がある方にとって、IT関連資格は有力な選択肢になるでしょう。
ビジネススキル系資格(メンタルヘルス・マネジメント検定など)
働く上で必要な対人関係や心の健康についての理解を深めたい方には、ビジネススキル系の資格が役立ちます。
- メンタルヘルス・マネジメント検定:職場のストレス管理を学ぶ
- サービス接遇検定:丁寧な接客・対応力を証明
- ビジネス文書検定:適切な報告・連絡・相談スキルを習得
これらの資格は、職場内でのコミュニケーション能力の高さをアピールできるため、事務や受付職、支援職などで重宝されます。
公的支援に直結する資格(障害者職業生活相談員など)

障害者の就労支援や、職場定着支援を行う側として活躍したい方にとって、公的資格は重要なステップになります。
障害者職業生活相談員は企業の障害者雇用促進にも役立ち、自身の体験を活かして相談支援ができる職種です。
- 障害者職業生活相談員:企業での障害者支援に従事
- 職業能力開発推進者:障害者のスキル習得支援に関連
ご自身が障害当事者である場合、その経験が支援業務において「理解者」として強みになるケースも多くあります。
障害特性別おすすめ資格ガイド
発達障害の方に適した資格
発達障害のある方は、集中力の波やコミュニケーションの困難さなど、個々に特性があります。
そんな中でも、構造的な作業やパターンのある業務が得意な方には、一定のルールで進められる資格学習が向いています。
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
- 日商簿記3級
- ITパスポート
これらはPC作業に特化しており、自分のペースで学習を進めやすいのが特徴です。
また、資格取得の過程で「できた」「わかる」という成功体験が得られることで、自己肯定感の向上にもつながります。
肢体障害の方におすすめの在宅ワーク系資格

肢体に不自由がある方にとって、通勤の困難さは転職活動における大きな課題のひとつです。
そのため、在宅ワークがしやすい職種につながる資格を取得することが、安定した就業への近道となります。
- Webライティング能力検定
- Illustratorクリエイター能力認定試験
- クラウドソーシング検定
これらの資格は、フリーランスや副業としても仕事を得やすく、自宅でスキルを活かす手段として注目されています。
精神障害の方に役立つストレスケア資格
精神障害のある方は、ストレス耐性や環境の変化への適応に不安を抱えるケースが多くあります。
そのような方には、メンタルヘルスに関する資格を通じて、自分自身の心の状態を理解し、セルフケアの技術を学ぶことがおすすめです。
たとえば、メンタルヘルスマネジメント検定やカラーセラピーなどは、心理的な安定と他者理解にもつながります。
資格学習自体が「自分と向き合う時間」となり、再就職の準備期間としても非常に有効です。
資格取得を支援する公的制度とサービス
障害者職業能力開発校の活用術
障害者職業能力開発校は、国や自治体が運営する公的な職業訓練施設です。
障害特性に応じた配慮を受けながら、資格取得や職業訓練を受けられる環境が整っています。
- 少人数・個別指導に対応
- 受講料が原則無料(教材費程度のみ)
- 修了後の就職支援も実施
実技中心の訓練や模擬試験も用意されており、特に初めて資格に挑戦する方には心強い存在です。
教育訓練給付金・助成金の受け取り方

資格取得にかかる費用の負担を減らすには、厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」の活用が効果的です。
この制度を利用すれば、対象講座の受講費用の20%〜70%が戻ってくる可能性があります。
- ハローワークで申請可能
- 初回は雇用保険の被保険者期間が1年以上必要
- 専門実践教育訓練給付なら最大年間56万円の補助
自分がどの講座で給付を受けられるかは、厚労省の「教育訓練給付制度検索システム」で事前に確認できます。
就労移行支援事業所を利用した学習サポート
障害のある方がスムーズに就職活動を行うためには、就労移行支援事業所の活用が非常に有効です。
これらの事業所では、ビジネスマナーや就職活動の指導に加え、資格取得のサポートを提供しているところも増えています。
- 独自カリキュラムによる講座提供(MOS、簿記など)
- 模擬試験・受験対策のサポート
- 学習時間の管理やモチベーション維持も支援
障害特性に応じた配慮を受けながら、無理なく学べる環境が整っているため、初めての資格取得にも安心です。
就労移行支援事業所を探すのにおすすめのサイトはこちら↓
合格までの学習ステップ
試験日から逆算したスケジュール管理

資格取得を成功させるには、試験日から逆算して計画的に学習を進めることが大切です。
「いつまでに何を終えるか」を明確にすることで、モチベーションの維持にもつながります。
- まずは試験日・申込締切日をチェック
- 過去問の演習期間を含めて余裕あるスケジューリング
- 1週間単位の進捗チェックで遅れを防止
GoogleカレンダーやToDoアプリを活用し、視覚的に管理することで、学習ペースが乱れにくくなります。
効率的な教材・スクールの選び方
資格によっては独学で十分なものもあれば、専門のスクールに通ったほうが効率的なものもあります。
費用・時間・支援の質を総合的に比較し、自分に合った方法を選びましょう。
- 通信教材:コスパ重視なら定番(ユーキャン、スタディングなど)
- オンラインスクール:映像授業で学習しやすく復習もしやすい
- 対面講座:理解度に応じた柔軟な対応が期待できる
自治体の職業訓練講座や就労支援施設を通じて、無料や低価格で受講できるケースもあります。
模擬試験とアウトプット学習
知識の定着には「インプット」だけでなく、「アウトプット」の機会をしっかり確保することが重要です。
特に模擬試験は本番の緊張感を体験でき、試験対策として非常に効果的です。
また、学んだ内容を他者に説明したり、問題集で間違えた箇所を解き直すこともアウトプットになります。
「覚えたつもり」を防ぐためには、実践形式の練習を繰り返すことが欠かせません。
資格取得後の転職活動戦略
履歴書・職務経歴書での資格の書き方

せっかく取得した資格も、履歴書や職務経歴書に適切に記載できていなければ、採用担当者にアピールできません。
資格名は正式名称で記載し、職務経歴書では「資格を通じて得たスキル」も具体的に説明しましょう。
- 例:「日商簿記3級」→「仕訳処理や帳簿作成が可能」
- 「MOS Excel」→「表計算、関数、グラフ作成など実務対応可能」
ただ資格名を羅列するのではなく、職種との関連性や実務への活用イメージまで書けると説得力が増します。
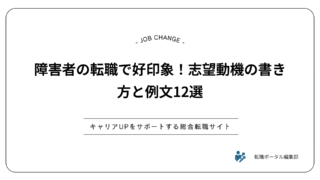
面接で資格をアピールするコツ
面接の場では、単に「資格を持っている」ことを伝えるだけでは不十分です。
資格を通じて得た知識やスキルを、どのように職場で活かせるかを具体的に話すことで、説得力が生まれます。
- 取得の動機:なぜその資格を選んだのか
- 学習の工夫:困難をどう乗り越えたか
- 業務との接点:どの業務でどんな形で役立てられるか
障害特性と絡めて「この資格があるからこそ安心して業務を任せられる」という印象を与えられれば、採用の後押しにつながります。
資格を活かせる求人の見つけ方

資格を取得した後は、それを活かせる求人を探すステップが待っています。
ハローワークや転職サイトに加えて、障害者専門の求人サービスや支援機関を活用するのがおすすめです。
- atGP、dodaチャレンジなどの障害者向け転職サイト
- 就労移行支援事業所からの企業紹介
- 資格名で絞り込める求人検索サイト
職種や業種、働き方(在宅勤務など)を明確にした上で、自分の強みが活かせる職場を見つけていきましょう。
よくある質問
障害者でも取得できない資格はある?
基本的に、身体・精神・知的いずれの障害がある場合でも、取得できない資格はほとんどありません。
ただし一部の国家資格(警察官、自衛官など)や身体機能が必須の資格(航空整備士、運転免許など)では、条件が設けられている場合もあります。
不安がある場合は、試験実施団体に事前相談することで、受験上の配慮が受けられる可能性があります。
複数資格を取るべきか一本に絞るべきか
最初の段階では「1つの資格をしっかり活かす」方が、転職成功率は高くなります。
複数の資格を持っていても、実務と無関係なものばかりでは評価されづらいのが現実です。
まずは1つの資格を軸に実績を積み、次のステップとして補完的な資格取得を考えるのが堅実です。
短期間で取れるおすすめ資格は?

- MOS:2週間〜1ヶ月で取得可能。PCスキルの証明に最適
- 日商簿記3級:3ヶ月以内で合格可能。経理・事務に有利
- メンタルヘルス・マネジメント検定III種:基礎的な内容で初学者にもおすすめ
「すぐに結果を出したい」という方は、こうした短期取得型の資格から始めると達成感も得やすく、転職活動にも早く活かせます。
まとめ:資格を味方に転職を成功させよう
障害者の転職活動において、資格は「自信」と「選択肢」を増やす大きな武器です。
適性に合った資格を選び、無理のないペースで学習し、公的支援制度や専門機関を活用することで、資格取得は現実的な目標になります。
また、取得した資格をどのように活かすかを意識しておくことで、履歴書・面接・実務すべてにおいて好印象を与えることができます。
資格はゴールではなくスタートです。焦らず、あなたの特性と強みに合った道を見つけ、転職成功へとつなげていきましょう。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
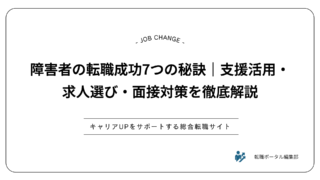
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓