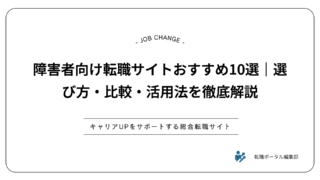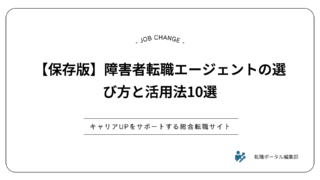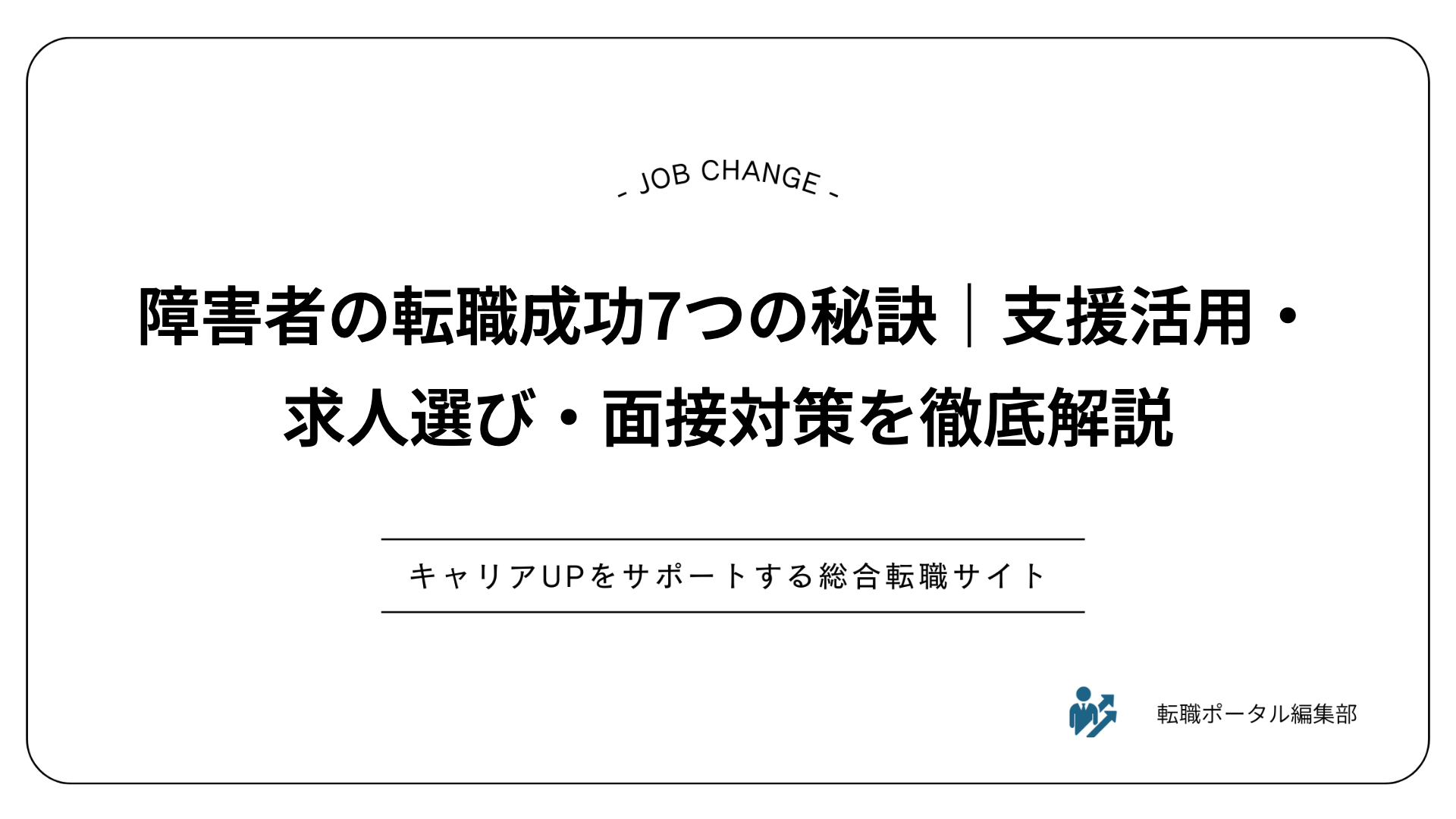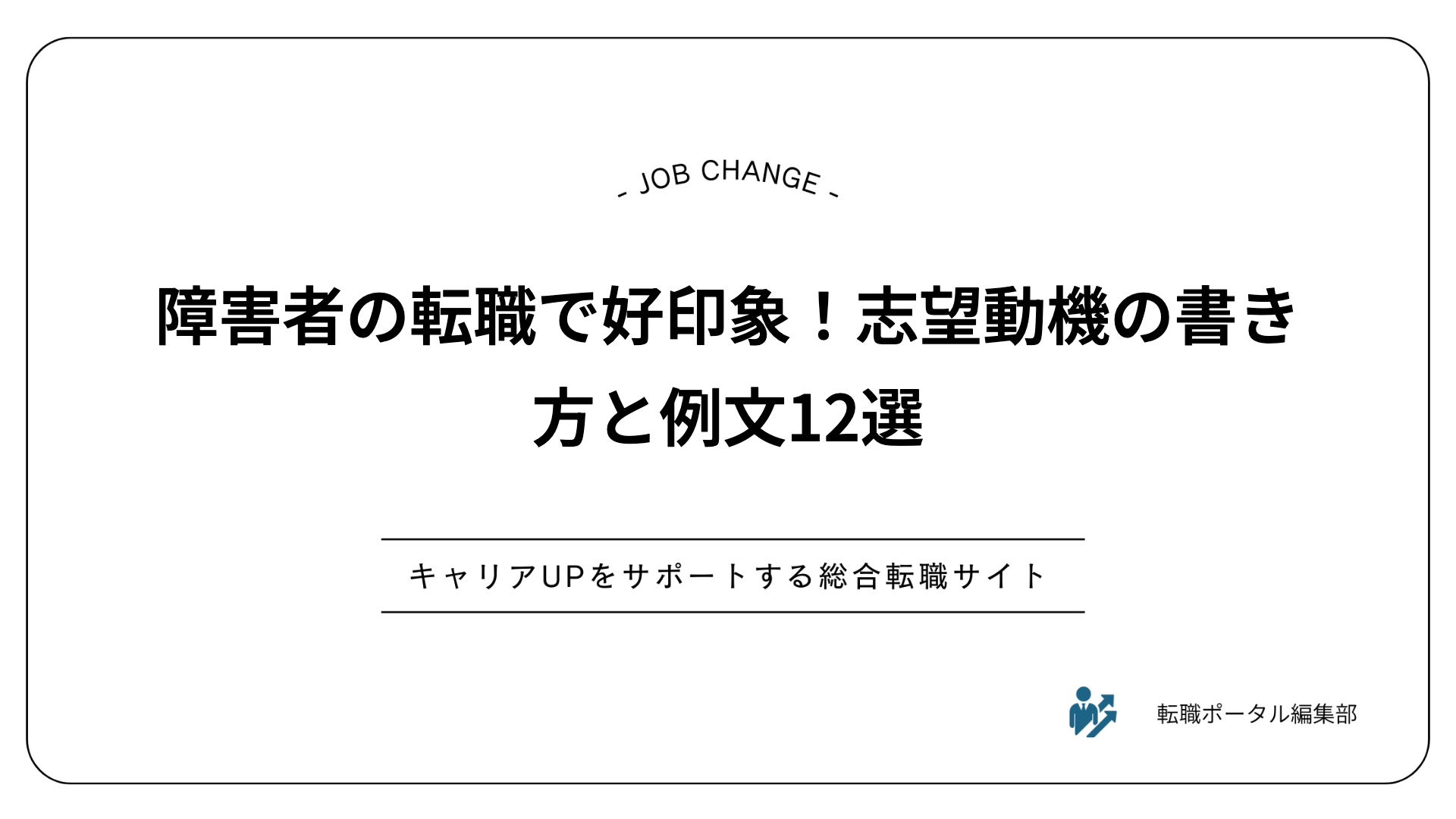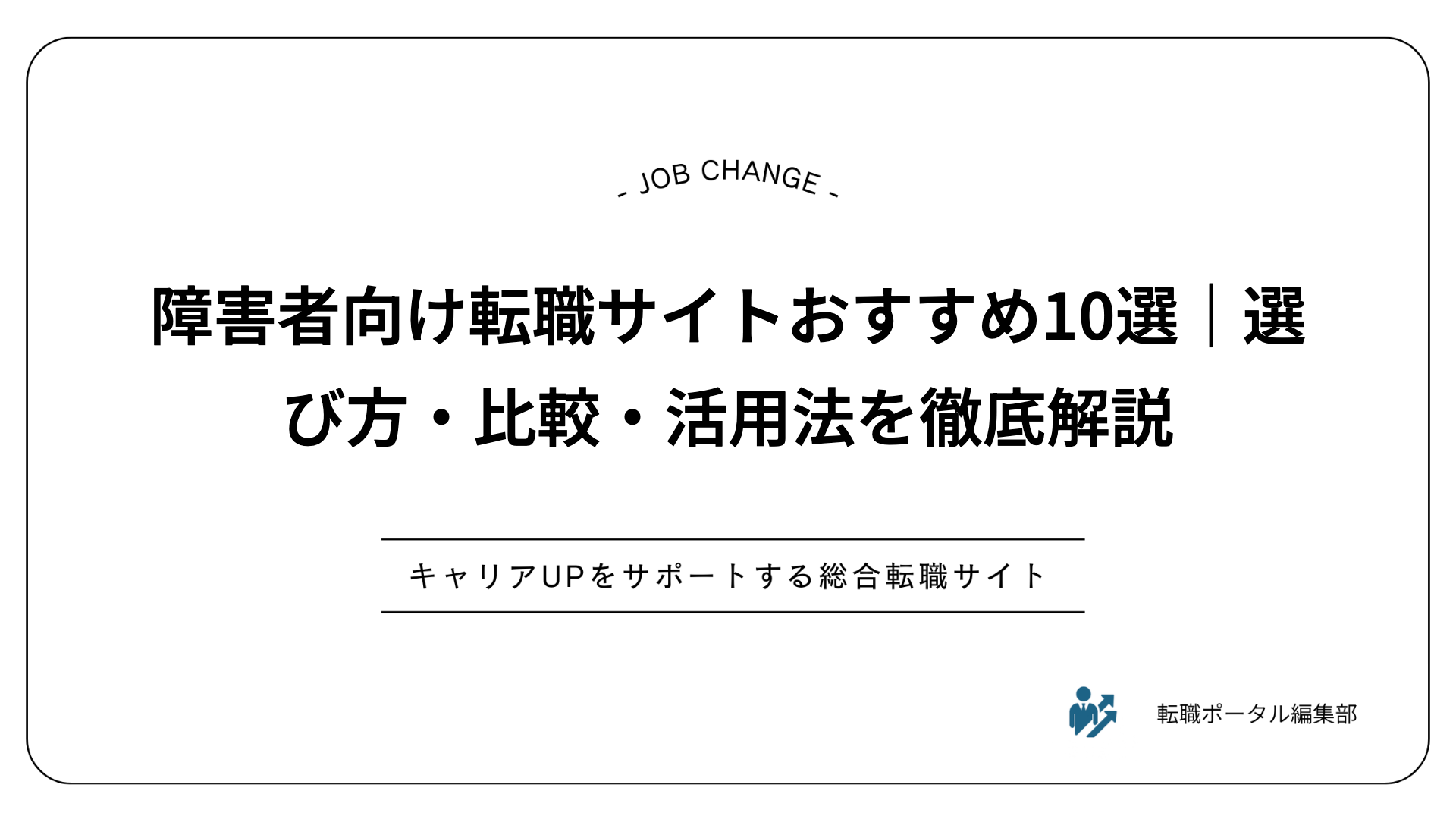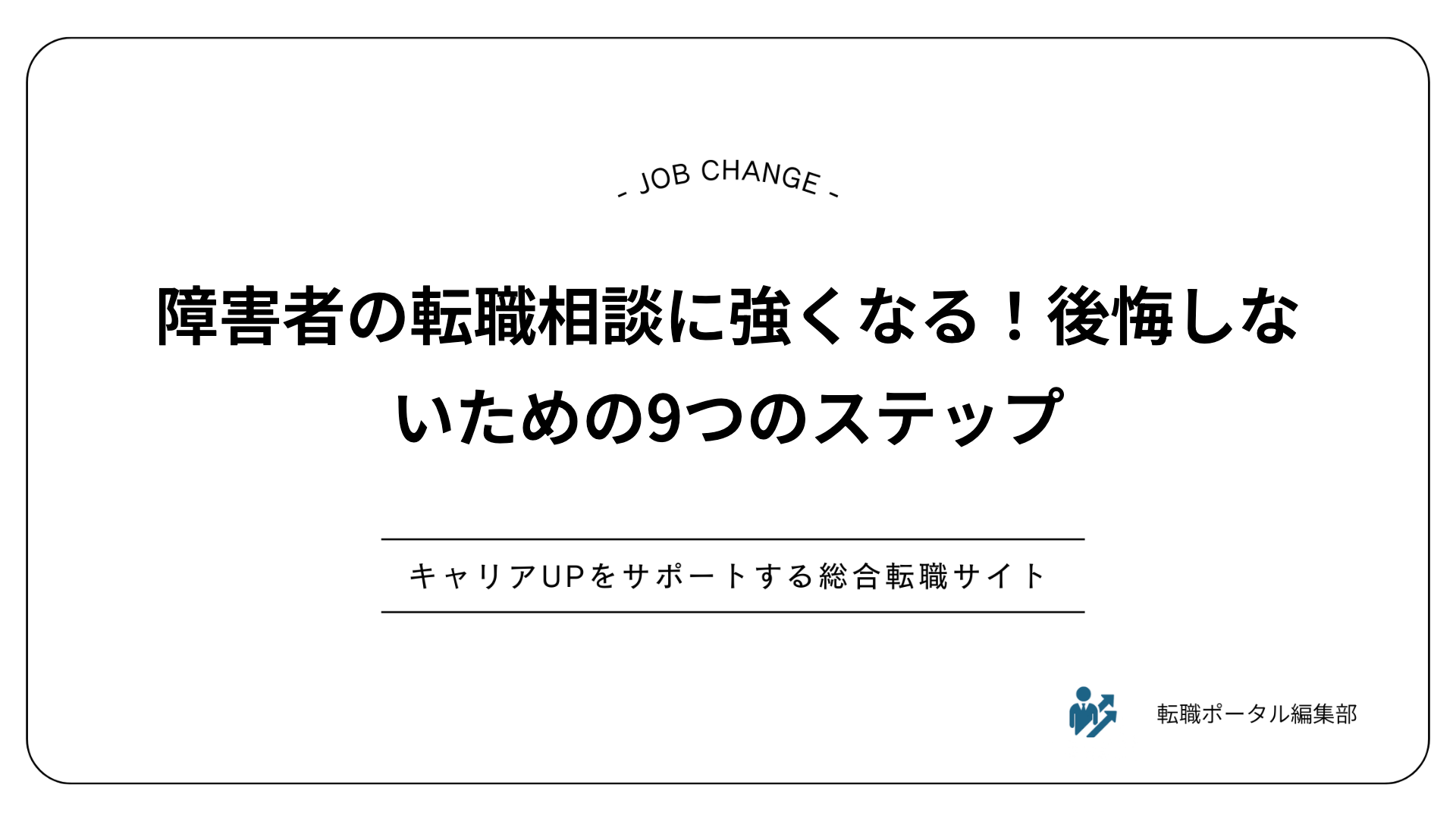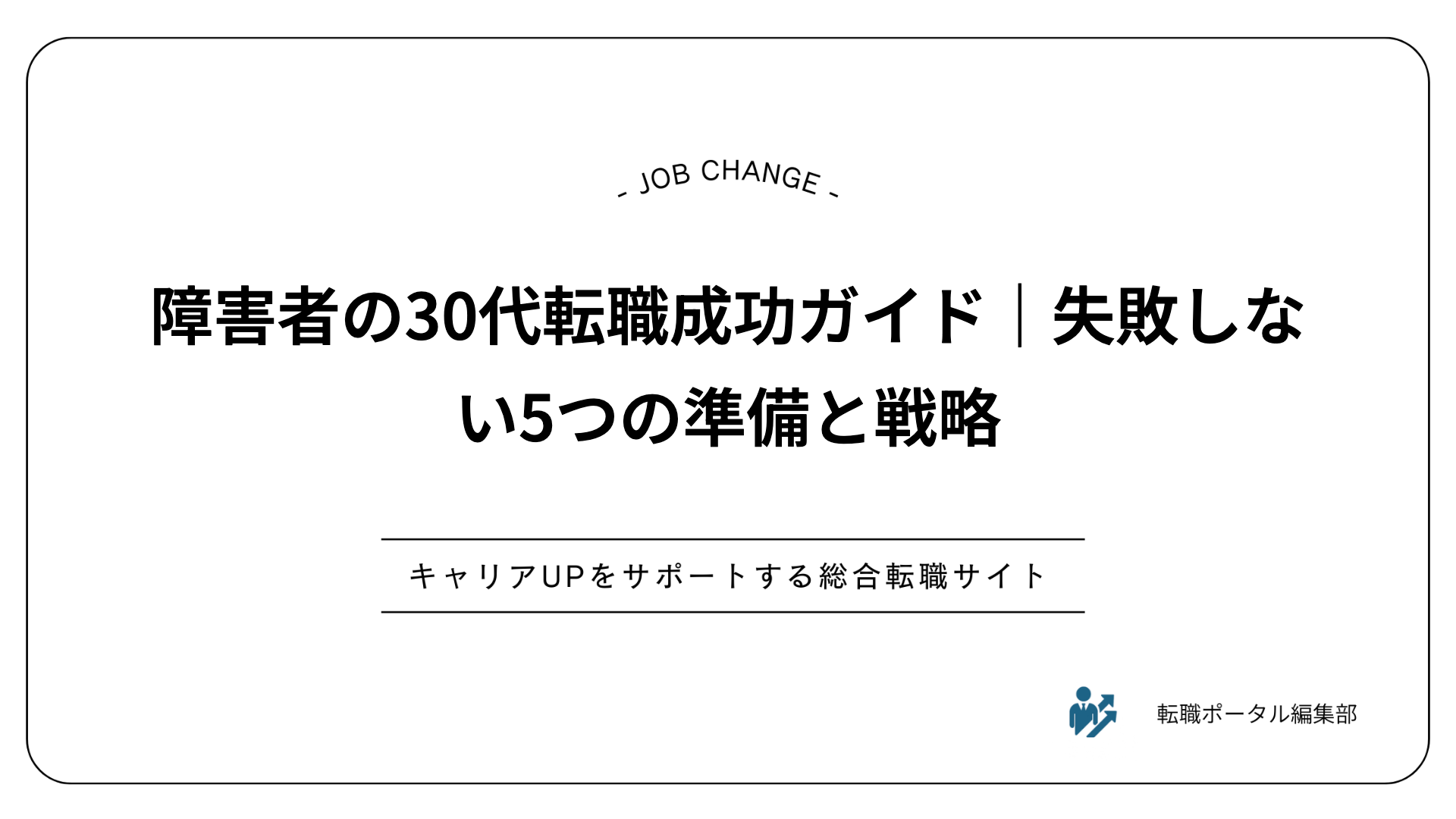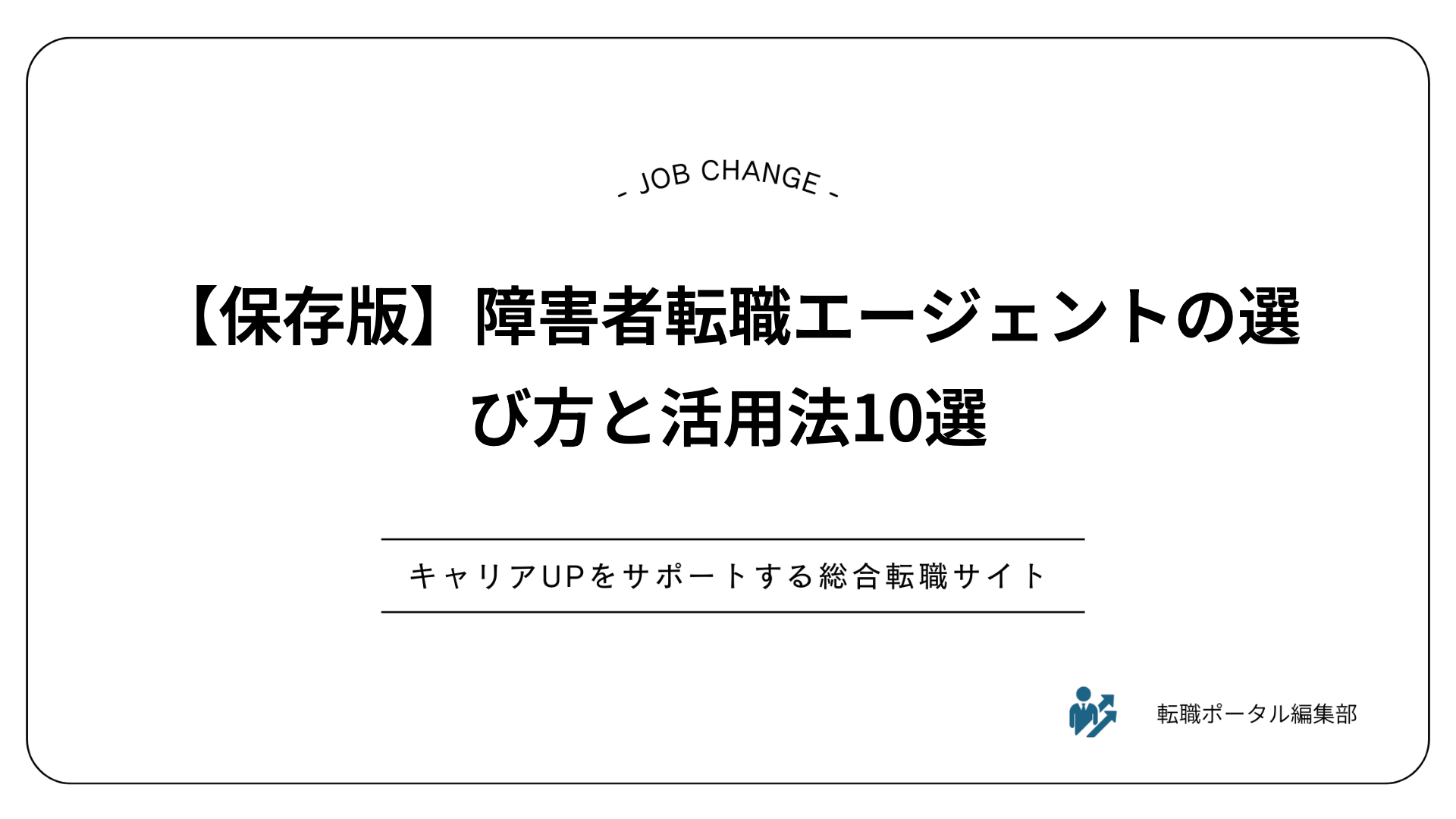障害者の転職が難しい5つの理由と成功への具体策
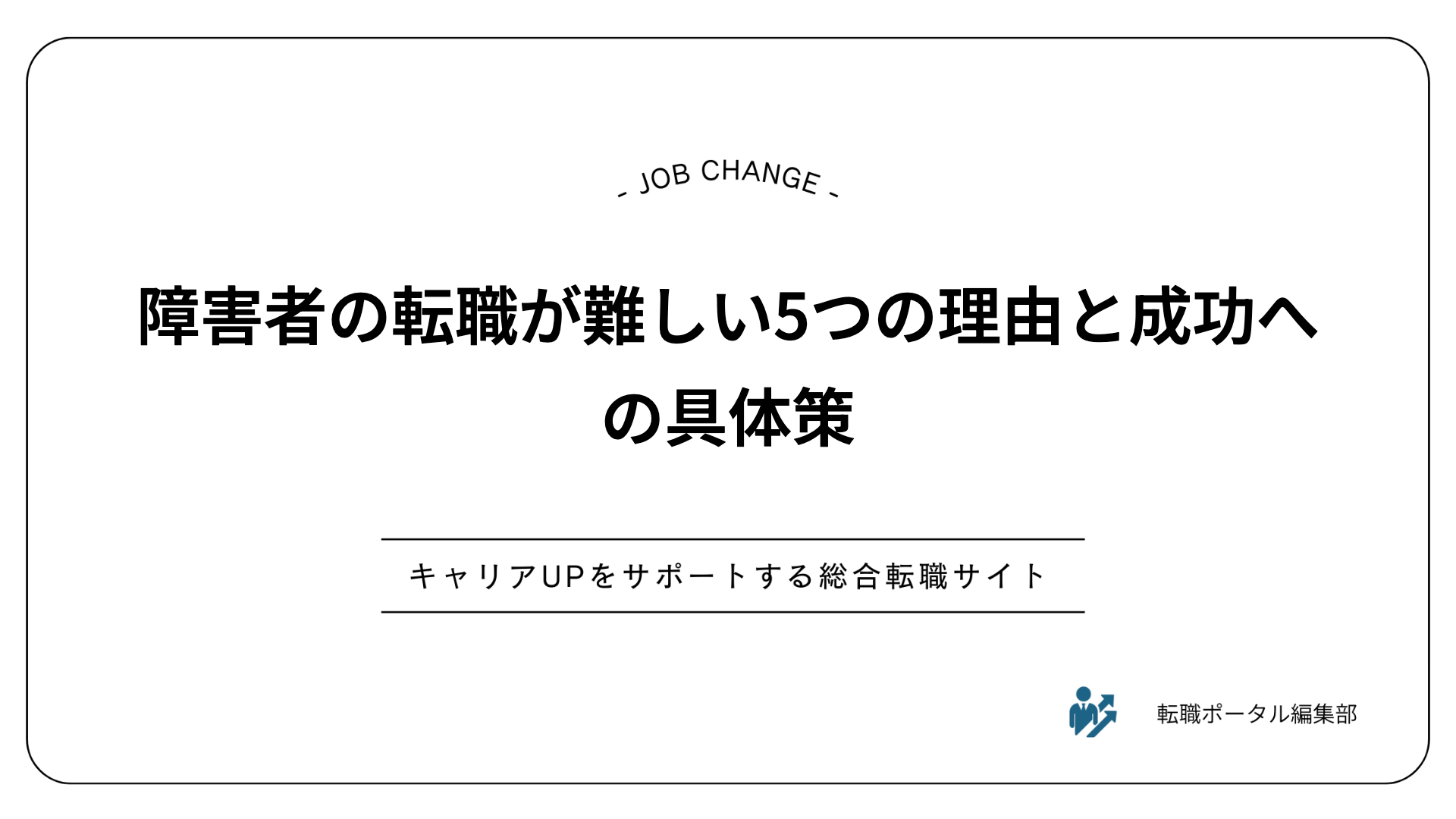
「障害があると転職はやっぱり難しいのかな…」
「応募しても書類が通らない」「体調や職場の理解が心配」など、障害を持つ方が転職活動で感じる不安や壁は決して少なくありません。
特に年齢や障害の種類によって状況が大きく異なる中で、自分に合った働き方や職場をどう見つければよいのか悩む方も多いでしょう。
この記事では、障害者の転職が難しいと言われる理由と、それを乗り越えるための具体的な方法をわかりやすく解説します。
- 転職市場の最新動向と法定雇用率の変化
- 障害種別・年代別に異なる転職の壁と対策
- 転職成功に向けた準備・書類作成・面接対応
- 使えるサポート機関やおすすめの支援制度
- 実際に転職を成功させた体験談
「自分にもできる」と思えるきっかけをつかみたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
障害者の転職市場の現状
法定雇用率と求人動向の最新トレンド

障害者の雇用促進を目的に設けられている「法定雇用率」は、企業が一定割合以上の障害者を雇用する義務を示す制度です。
2024年度からは民間企業の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、特に300人以上の大企業ではその対応が急務となっています。
- 法改正により対象企業が拡大
- 事務系職種を中心に求人が増加傾向
- テレワーク可能な求人も増え、柔軟な働き方が選べるように
こうした環境の変化は、転職を検討する障害者にとって追い風です。
「求人が少ないのでは」と不安な方も、最新情報をキャッチすれば有利に動けるでしょう。
年代別・障害別の就職率データを読み解く
厚生労働省の統計によれば、障害種別や年齢によって就職率には大きな差が見られます。
特に20〜30代前半の若年層や身体障害者は就職率が高く、企業側も即戦力として受け入れる傾向が強まっています。
一方で、精神障害者や高年齢層は定着支援やマッチングの丁寧な工夫が必要とされており、専門機関との連携が重要になります。
「年齢が上がるほど厳しいのでは」と感じるかもしれませんが、対策次第で十分に転職成功は目指せます。
障害者雇用枠と一般枠の違いとメリット・デメリット

障害者の転職活動では、「障害者雇用枠で応募するか、一般枠を狙うか」が大きな判断ポイントです。
障害者枠は職場の配慮が得られやすい一方で、待遇や昇進に限界を感じる人もいます。
逆に一般枠は競争が激しいものの、スキル次第では昇給や昇格の可能性が広がります。
- 障害者枠:働きやすさ・配慮重視
- 一般枠:キャリアアップ・収入増を重視する方向け
どちらが良いかは、その人の働き方やライフスタイル次第です。
「配慮を受けつつ長く働きたい」「チャレンジしてみたい」など、自分の希望を明確にすると選択しやすくなります。
障害者の転職が難しいと言われる主な理由
求人数と職種の限定による選択肢の少なさ
障害者の転職で最も多く挙げられる課題のひとつが「求人数の少なさ」です。
一般の求人と比較すると、障害者枠の求人はまだまだ限定的で、業種や職種も偏りが見られます。
- 求人が集中しやすいのは事務補助・清掃・軽作業など
- 販売・接客・専門職などは数が少なめ
- 地域によっては求人自体が極端に少ないケースも
このように選択肢が限られていると、「本当にやりたい仕事」に就けないと感じる場面もあるでしょう。
しかし最近では、障害者向けのIT職やクリエイティブ系の求人も増えており、スキル次第で活躍の場は確実に広がっています。
企業側の理解不足と配慮体制の未整備
障害者の転職が難しいと言われる背景には、企業側の理解不足も深く関係しています。
法律上の雇用義務があるとはいえ、実際には障害特性に対する知識が乏しく、合理的配慮の内容も曖昧なまま採用が進んでしまうケースがあります。
その結果、働き始めてから環境が合わずに早期離職につながることも。
- 業務量や就業時間に柔軟性がない
- 障害内容を共有できる体制が整っていない
- 「配慮=特別扱い」と捉える風土が残っている
こうした状況では、安心して自分らしく働くことは困難です。
そのため、応募前に企業の障害者雇用実績や職場見学の有無、配属先での受け入れ体制などを確認しておくことが重要になります。
スキル・経験のギャップと即戦力性への不安

「業務経験が少ない」「ブランクが長い」といった理由で、企業側が即戦力として判断できず採用を見送るケースも少なくありません。
特に中途採用市場では、即戦力が求められがちです。
しかしこれは障害のある方に限った問題ではなく、どの求職者にも共通する課題です。
そのギャップを埋める方法としては、以下のような取り組みが有効です。
- 就労移行支援や職業訓練を通じてビジネススキルを補強する
- トライアル雇用制度を利用して、実務経験を積む
- ポートフォリオやスキル証明書で成果を可視化する
「未経験だから無理」と諦めるのではなく、小さな経験の積み重ねで「できる」を証明していくことが大切です。
体調・通勤・職場環境に関する懸念
障害によっては、継続的な通院や体調変動に悩まされることがあります。
また、職場までの通勤距離や交通手段、オフィスのバリアフリー対応など、物理的な環境も大きなハードルになることがあります。
企業側がそれらの事情に十分に理解を持ち、柔軟な対応をしてくれるかどうかが、就職後の働きやすさを左右します。
このような懸念に対しては、以下のような対策が有効です。
- 在宅勤務・時差出勤制度のある企業を選ぶ
- 職場見学で実際の通勤経路・設備を確認する
- 履歴書・面接時に「どのような配慮が必要か」を具体的に伝える
「通えるか不安…」「体調が読めない…」と悩む方は、無理なく働ける環境を最初から選ぶことが転職成功のカギです。
コミュニケーションやビジネスマナー面での課題

障害の特性によっては、職場内のコミュニケーションやビジネスマナーへの不安を抱える方もいます。
特に精神障害や発達障害がある場合、会話のテンポや指示の理解に時間がかかったり、報連相(報告・連絡・相談)が苦手とされることがあります。
そのため「職場になじめるか」「孤立してしまわないか」といった心理的な壁を感じる方も少なくありません。
こうした課題を和らげるには、以下のような工夫が効果的です。
- 自分が得意な伝え方(文章・図解など)を面接で伝えておく
- 就労支援員の定期訪問や面談を活用して職場と橋渡しをする
- 業務マニュアルやタスク管理ツールを使って負担を軽減する
また、企業側もコミュニケーション支援の研修やツール導入を進めており、以前よりも働きやすい環境は整いつつあります。
「人間関係が怖い…」と感じる方も、最初から安心できるサポート体制を持つ職場を選ぶことで不安を最小限に抑えることができます。
年代・障害別に見る転職の壁
三十代前半が直面しやすい課題と乗り越え方
30代前半は「若手」としての可能性がありつつも、即戦力としての実績も求められる中間世代です。
障害の発症が20代後半〜30代前半だった場合、「キャリアのブランク」や「異業種への転向」が転職時の壁となることがあります。
加えて、結婚・子育て・介護など家庭事情との両立に悩む人も多く、柔軟な働き方を希望する声も強まります。
この年代で成功するには、過去の経験を活かしつつ、未来の成長意欲を明確に伝えることが重要です。
- キャリアチェンジの場合は「なぜその職種を選んだか」を論理的に説明する
- 支援機関と連携して書類作成や面接対策を行う
- 時短勤務や週4勤務など、フルタイム以外の選択肢も検討する
「まだ間に合うかな…」という不安を感じる方も、30代は「やり直しやすい最後のチャンス世代」と言えます。行動を早めに起こすことで道は開けます。
企業側の理解不足と配慮体制の未整備
障害者の転職が難しい背景には、企業側の障害理解不足や受け入れ体制の不十分さがあります。
法定雇用率の達成義務があっても、実際には障害種別ごとの特性や合理的配慮のあり方について正しく理解されていないケースが多く見受けられます。
例えば、設備面だけ整っていても、上司や同僚の理解が乏しければ働きにくさは拭えません。
こうした状況では早期離職のリスクも高まります。入社前に企業の雇用実績や配属先の環境確認が重要です。
スキル・経験のギャップと即戦力性への不安

障害者の転職では「ブランクがある」「経験が少ない」などの理由で、即戦力にならないと判断されることがあります。
特に中途採用では、業務の即応力や自主性が求められる場面が多く、その分選考のハードルも上がります。
- 就労移行支援を利用し、実務トレーニングでスキルを補う
- 短期の職場実習やトライアル雇用で経験を積む
- 資格取得やポートフォリオで能力を可視化する
完璧な職歴がなくても「何ができるか」「どんなサポートがあれば活躍できるか」を伝える姿勢が評価されます。
体調・通勤・職場環境に関する懸念
障害の内容によっては体調管理や通勤への配慮が必要です。
特に慢性疾患や精神障害を抱える方にとって、毎日の通勤は大きな負担になることもあります。
- 在宅勤務や時差出勤を導入している企業を選ぶ
- バリアフリー環境や駅からのアクセスを事前に確認する
- 通院・服薬に理解のある企業風土があるかをチェックする
こうした配慮が受けられる職場を選ぶことが、長期的な定着にもつながります。
コミュニケーションやビジネスマナー面での課題

精神・発達障害などの場合、報連相や雑談のタイミングなど、職場内のコミュニケーションが負担に感じられることもあります。
しかし、これは「個性」であり、「苦手」を補う方法は多様に存在します。
自分に合った伝達手段(チャット、文章など)を提案したり、支援員との連携を取ることで職場とのギャップを埋められます。
「コミュニケーションに不安があるから無理かも…」と感じる方も、事前の対話で十分に乗り越えることができます。
四十代で不利になりがちなポイントと対策
40代になると、転職市場では「年齢による即戦力性」や「企業文化との適応力」が重視されやすく、ハードルが上がる傾向があります。
特に障害者枠での転職では、「若い人を育てたい」という企業の意向や、「年齢=経験値」への期待が裏目に出てしまうケースもあります。
しかし、年齢を強みに変える工夫次第で、むしろ企業にとって頼れる存在として活躍できるチャンスは十分にあります。
- 過去の業務経験を棚卸しし、面接でエピソードを交えてアピールする
- 最新のITスキルやビジネスマナーを学び直し、時代に合った柔軟性を見せる
- 職場の中核を担う存在として、後輩のサポートやチーム貢献を意識する
「年齢を重ねたからこその視点や安定感」は、企業にとっても価値ある武器になります。自信を持って臨むことが何よりの対策です。
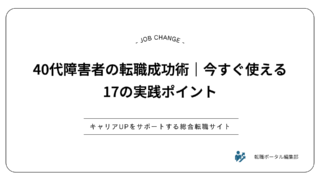
五十代以降に高まる壁と突破法
50代になると転職市場全体でも求人数が減少し、障害者雇用枠においても選択肢がかなり限られてきます。
特に「体力的な負担がある職種を避けたい」「スキルの最新化が追いついていない」といった状況では、マッチする求人を見つけるまでに時間がかかる傾向があります。
しかし一方で、50代は「定着率が高い」「仕事に対して真面目」という評価も得やすく、工夫次第で採用につながる可能性も十分にあります。
大切なのは「何ができるか」を具体的に伝えることと、無理のない勤務条件を企業と丁寧にすり合わせることです。
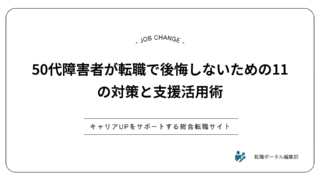
身体・知的・精神障害それぞれの難しさと留意点

障害の種類によって転職活動における課題や配慮の内容は大きく異なります。
- 身体障害:通勤手段や職場のバリアフリー環境の確認が重要
- 知的障害:業務手順の明確化や視覚的サポートが効果的
- 精神障害:体調変動やストレス耐性に対する理解と柔軟な勤務体制が必要
いずれの場合も、自分にとって必要な配慮事項をあらかじめ整理し、履歴書や面接で正確に伝えることが求められます。
また、支援機関と連携しながら進めることで、より自分に合った職場とのマッチングがしやすくなります。
「どの情報をどこまで伝えるか不安…」という場合は、キャリアカウンセラーに事前相談しておくと安心です。
転職を成功させるための準備と対策
自己理解と適職分析を深めるステップ
転職成功の第一歩は、自分自身の理解を深めることです。
どんな職場なら安心して働けるのか、どんな仕事にやりがいを感じるのか。これらを明確にすることで、応募先の選定や面接対策にも一貫性が生まれます。
特に障害がある場合、「できること」「難しいこと」を客観的に把握しておくことが重要です。
- 過去の職務経験を棚卸しして、得意・不得意を整理する
- 障害特性と仕事環境との相性を分析する
- 支援員や専門機関のアセスメントツールを活用する
「向いている仕事がわからない」という方も、一度プロのカウンセラーと一緒に分析することで、思わぬ適職が見えてくることもあります。
スキルアップ・資格取得の具体的戦略

スキルや資格の有無は、転職時のアピールポイントとして大きく影響します。
特に未経験職種へのチャレンジを考えている場合は、基本的な知識やスキルを学んでおくことが評価されることもあります。
とはいえ、無理に難関資格を目指す必要はありません。業界ニーズや自分の興味と重なる内容から、少しずつ実力を積み重ねましょう。
- パソコン操作(Word・Excel・メール)ができると事務職で有利
- 就労移行支援で職業訓練と資格取得を同時に進められる
- MOSや簿記3級、ビジネスマナー検定などは取り組みやすく評価されやすい
「今さら学び直せるかな…」と不安に思う必要はありません。学び直しの意欲自体がプラス評価につながります。
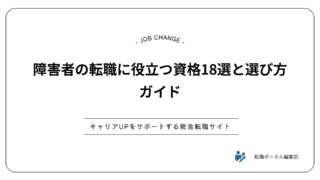
応募書類と面接で伝えるべき配慮事項
障害者の転職活動において、応募書類や面接時にどこまで自分の障害について伝えるかは悩みどころです。
伝えすぎることで不利になるのでは…という不安もありますが、必要な配慮を正しく伝えることは職場定着のためにも欠かせません。
大切なのは「どんな配慮があれば、どのように仕事ができるか」を前向きに説明することです。
たとえば「週に1回の通院がありますが、それ以外は体調安定しています」や「口頭指示よりも、書面での指示があると理解しやすいです」といった伝え方が効果的です。
ネガティブな伝え方を避け、自分の特性に合った働き方の工夫をアピールする姿勢が評価されます。
在職中に転職活動を進めるコツと時間管理
現在の職場で働きながら転職活動を行う場合、体調や時間の管理がより重要になります。
日々の業務に加えて、応募書類の作成や面接準備、求人情報のチェックなどをこなすのは負担も大きくなりがちです。
- 1日30分の転職タイムを決めて無理のない計画を立てる
- 土日を使って集中的に書類作成や情報収集を行う
- エージェントを活用して面接日程の調整を任せる
「毎日疲れていて転職活動どころじゃない…」という方も、少しずつでも行動を始めることが将来の不安解消につながります。
体調管理と働き方シミュレーションのポイント

転職前に必ず行いたいのが「自分にとって無理のない働き方」をシミュレーションしておくことです。
週5フルタイムで働くのが現実的なのか、リモートや時短なら継続できるのかなど、体調と相談しながら見極める必要があります。
就職後すぐに体調を崩してしまっては、再び転職活動を繰り返すことになりかねません。
できれば、支援機関や主治医と相談のうえで、「理想」と「現実」のバランスを取りながら職場選びを進めましょう。
また、あらかじめ想定される困りごとに対して、どのような対処法を持っているかをまとめておくと、企業側も安心して迎え入れやすくなります。
サポートを活用して転職を有利に進める方法
障害者向け転職エージェントの選び方と比較
障害者の転職では、専門の転職エージェントを活用することで求人探しや応募手続き、面接対策をスムーズに進められます。
一般の転職サイトでは自分に合った求人を見つけづらいこともありますが、障害者専門のエージェントなら配慮事項に理解のある企業とのマッチングが可能です。
- atGP:障害内容に応じた専門サポートが手厚く、求人数も豊富
- dodaチャレンジ:大手パーソルグループ運営でサポート体制が充実
- ミラトレ:就労移行支援と連携し、長期的な職場定着を支援
それぞれのエージェントには特徴があるため、複数登録して比較検討するのがおすすめです。
「自分に合う会社がわからない…」という方は、まずはカウンセリングから始めてみましょう。
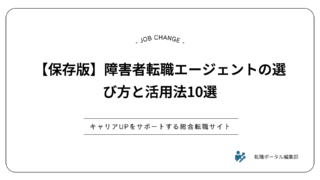
就労移行支援・トライアル雇用の活用メリット

就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための準備機関です。
ビジネスマナーやパソコンスキルの習得、生活リズムの安定、就職活動のサポートまで一貫して支援を受けられます。
また、一定期間企業で働きながら雇用を判断する「トライアル雇用制度」も、実務経験のない方にとっては大きなチャンスです。
制度を活用すれば、いきなり本採用ではなく、環境との相性を見ながら進められるため安心感があります。
ハローワーク・自治体支援を最大限に利用する方法
ハローワークや各自治体も、障害者向けの就労支援に力を入れています。
特別支援窓口では、障害のある方専用の求人情報の提供や職業相談、模擬面接などのサービスを受けることができます。
- 専門の障害者職業相談員が在籍しており、個別対応が可能
- 就労支援機関と連携し、職場体験や見学もサポート
- 生活支援や福祉制度との併用相談にも対応
地域によっては、交通費補助や就労準備講座など独自の支援策も展開されています。自分の住む自治体にどんな支援があるか、ぜひ一度調べてみましょう。
主治医・カウンセラーと連携したキャリア設計
転職を進める上では、主治医やカウンセラーと連携して「働くための体調管理」や「メンタルサポート体制」を整えることも大切です。
医師の意見書や診断書は、配慮事項を明確に伝える手段としても有効です。
また、キャリアカウンセラーや福祉職員との対話を通じて、自分に合った働き方を客観的に見つけることも可能です。
「一人で考えると不安が大きくなる…」と感じたときこそ、専門家と一緒にキャリア設計を進めてみましょう。
実例で学ぶ転職成功ストーリー
四十代身体障害者が事務職へ転職したケース

40代男性、脳梗塞の後遺症による片麻痺を抱え、長年製造業に従事していた方が、事務職への転職を成功させた事例です。
発症後は復職が困難となり、ハローワークを通じて就労移行支援を活用。
パソコンスキルを一から学び直し、1年後に障害者雇用枠の一般企業へ転職しました。
ポイントは、「今できること」に焦点を当てた自己PRと、通院と業務が両立できる勤務体系を面接で丁寧に相談したことです。
結果として、企業側も本人の誠実さと職務適性を高く評価し、安定した職場定着へとつながりました。
精神障害者が在宅ワークでキャリアを再構築したケース
30代女性、双極性障害により通勤が難しい状況が続き、退職後は引きこもりがちに。
支援員と相談しながら在宅勤務可能な求人を探し、Webライターとして再スタートしました。
クラウドソーシングから少しずつ実績を積み上げ、3年後には複数企業と業務委託契約を結ぶまでに。
自分の体調ペースで働ける「在宅ワーク」のスタイルが性に合い、今では収入も安定。自己肯定感も大きく回復したと話しています。
五十代で特例子会社から一般企業へ移ったケース
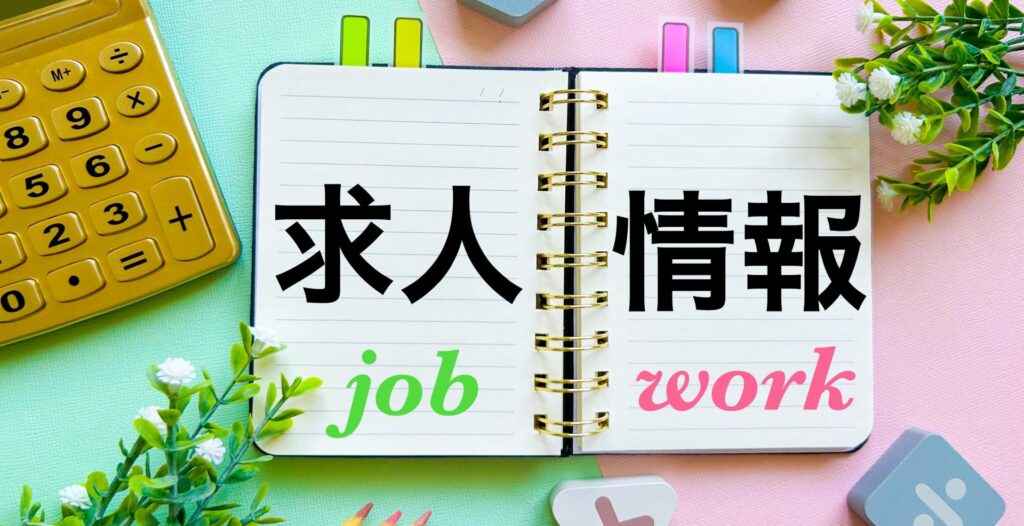
50代男性、知的障害のある方で、長年特例子会社で清掃業務に従事していましたが、「もっとスキルを身につけたい」と就労移行支援に通所。
支援員の協力を受けながら、簡単な事務作業の訓練を積み、応募書類の書き方や模擬面接も繰り返しました。
その結果、一般企業の物流部門で伝票入力業務に従事することに。
「年齢や障害があっても、自分の意欲と準備次第で新しい環境に挑戦できる」と周囲からも大きな励ましを受けています。
よくある質問と回答
障害者雇用枠でも年収アップは可能?
「障害者枠だと給与が低いのでは…」と心配する方は少なくありません。
確かに未経験職やサポート前提の職種では初任給が抑えられることもありますが、必ずしも低賃金とは限りません。
- IT系や外資系企業では年収400万円以上の求人も存在
- 正社員登用制度がある契約社員スタートの求人も増加中
- 実績を積めば昇給・昇進の機会が得られる企業も多い
「年収アップ=一般枠」ではなく、「働き方と将来性をどう描けるか」が大切です。
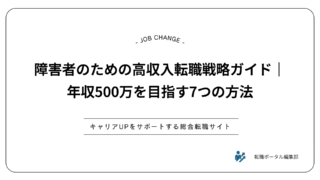
障害を開示するタイミングはいつが最適?
障害者雇用枠での応募であれば、書類段階で開示するのが基本です。
一方、一般枠での応募を検討する場合は、応募時に開示するか、内定後に相談するかをケースごとに判断する必要があります。
「配慮が必要な点」を明確に伝えられるかどうかがポイントです。タイミングに迷ったら、支援機関やキャリアアドバイザーに相談しましょう。
転職回数が多くても不利にならない方法

転職歴が多い場合でも、伝え方次第で印象は大きく変わります。
職場環境の不一致や体調の変動など、やむを得ない理由がある場合は、正直かつ前向きに説明しましょう。
- 「退職の理由」と「今回の転職にかける思い」を一貫して伝える
- 職歴の中で得た経験をポジティブに整理する
- 再発防止のための工夫(通院継続・働き方の工夫)を示す
企業も「人間らしいキャリアの揺れ」を理解してくれる時代です。不安を恐れず、自分の道を前向きに伝えましょう。
正社員求人が少ない場合の代替選択肢
地域や業種によっては、正社員求人が少なく選択肢が限られることもあります。
そんな時は、無理に正社員にこだわらず、契約社員やパートスタートからの実績づくりを検討しましょう。
企業によっては、まずは短時間勤務や有期雇用から始めて、仕事ぶりを見て正社員へ登用するステップも整っています。
安定を求める気持ちも大切ですが、最初は「自分に合った働き方を見つける」ことを優先してみるのも一つの道です。
まとめ:難しさはあるが、障害者の転職は十分に成功できる
障害者の転職は「難しい」とされがちですが、結論から言えば、正しい準備と支援を活用すれば十分に成功できます。
なぜなら、法制度や企業の意識が変化しつつあり、サポート体制も年々整ってきているからです。
この記事では以下のような視点から、転職成功に必要な要素を紹介してきました。
- 法定雇用率の引き上げで障害者の求人が拡大傾向
- 転職の難しさには「職種の選択肢」や「企業理解」の課題がある
- 年代別・障害別に異なる壁とその乗り越え方が存在する
- 転職成功のためには自己理解・スキルアップ・支援活用が重要
- 実際に転職を成功させた事例や利用可能な支援も多い
転職活動には不安もつきものですが、今の自分を受け入れ、未来を変えようとするその一歩が、確実に可能性を広げます。
難しさを「無理」と決めつけず、一つひとつの準備と選択を丁寧に重ねることで、きっと理想の職場に出会えるはずです。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
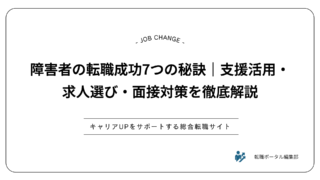
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓