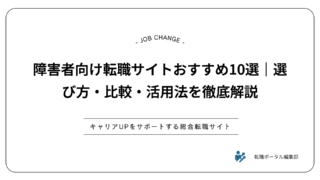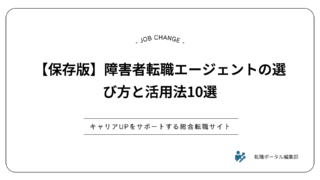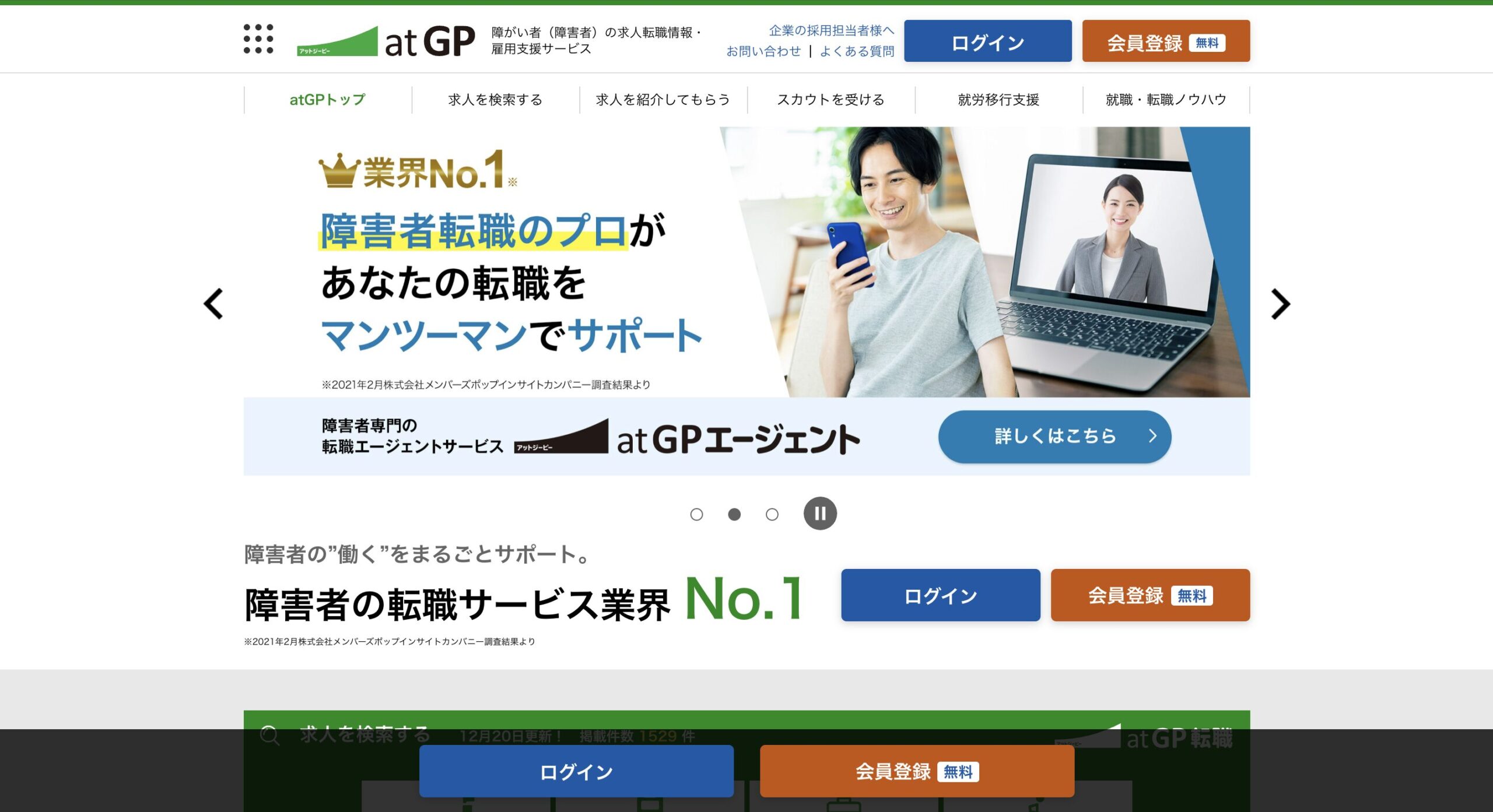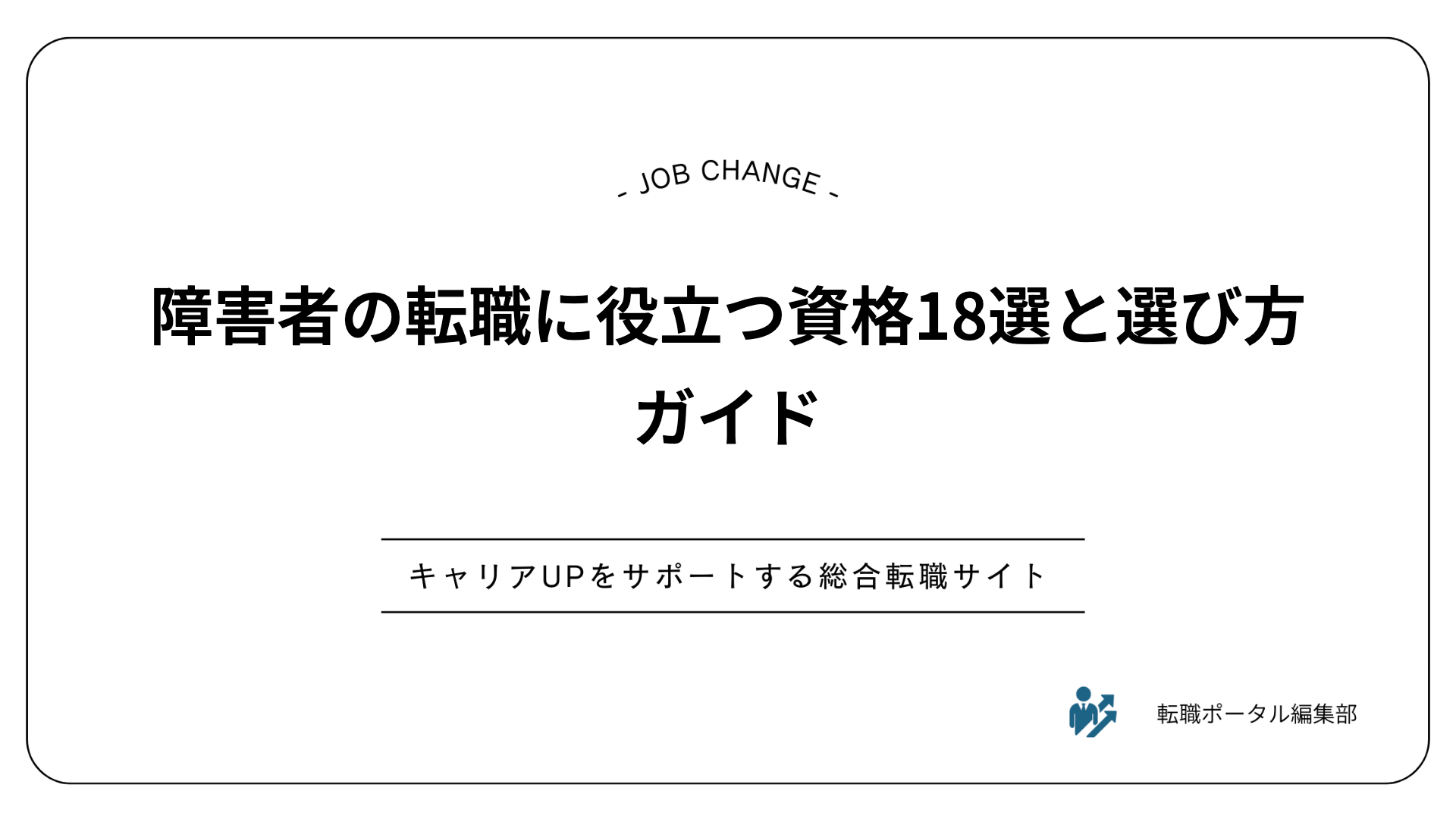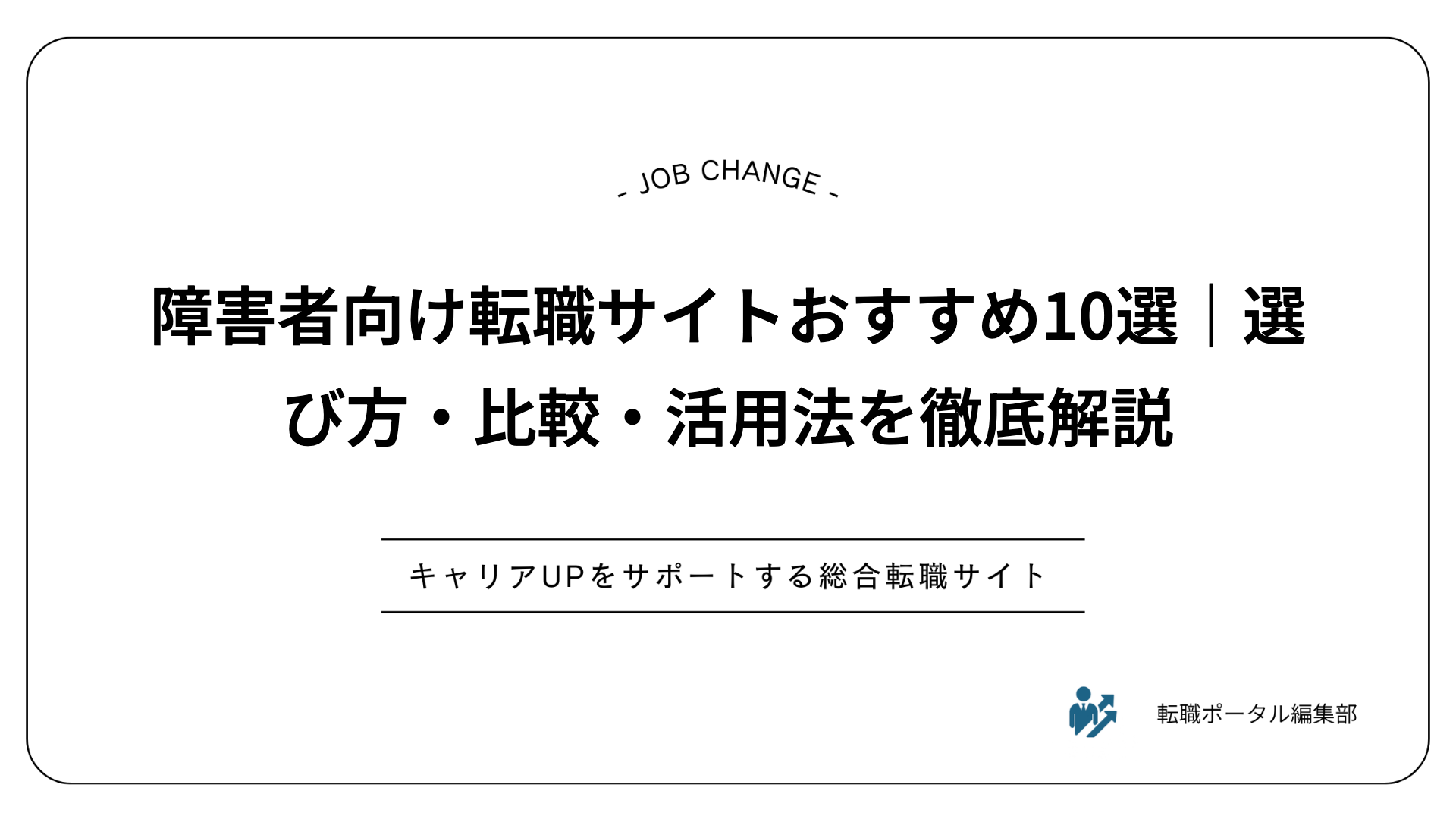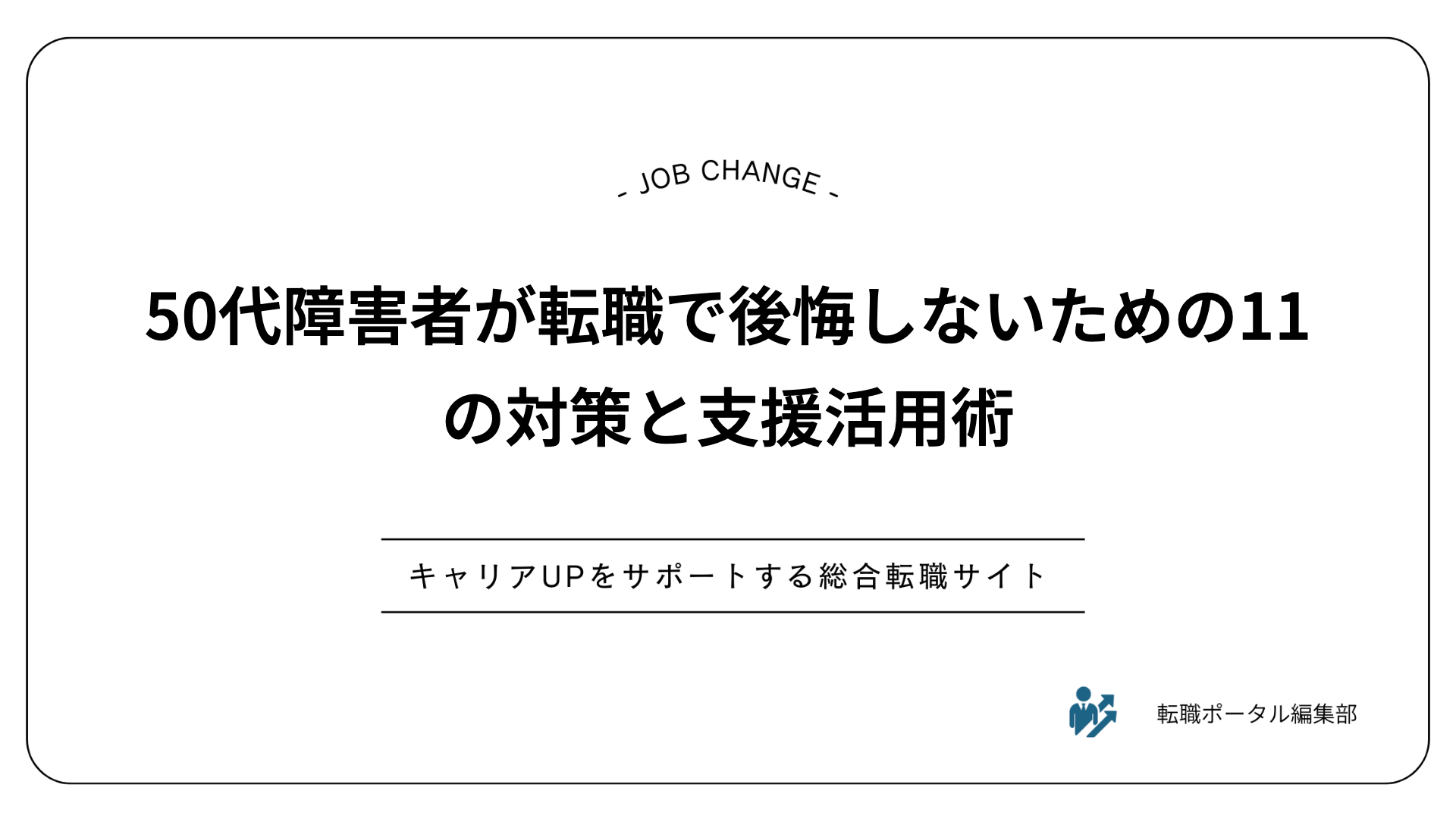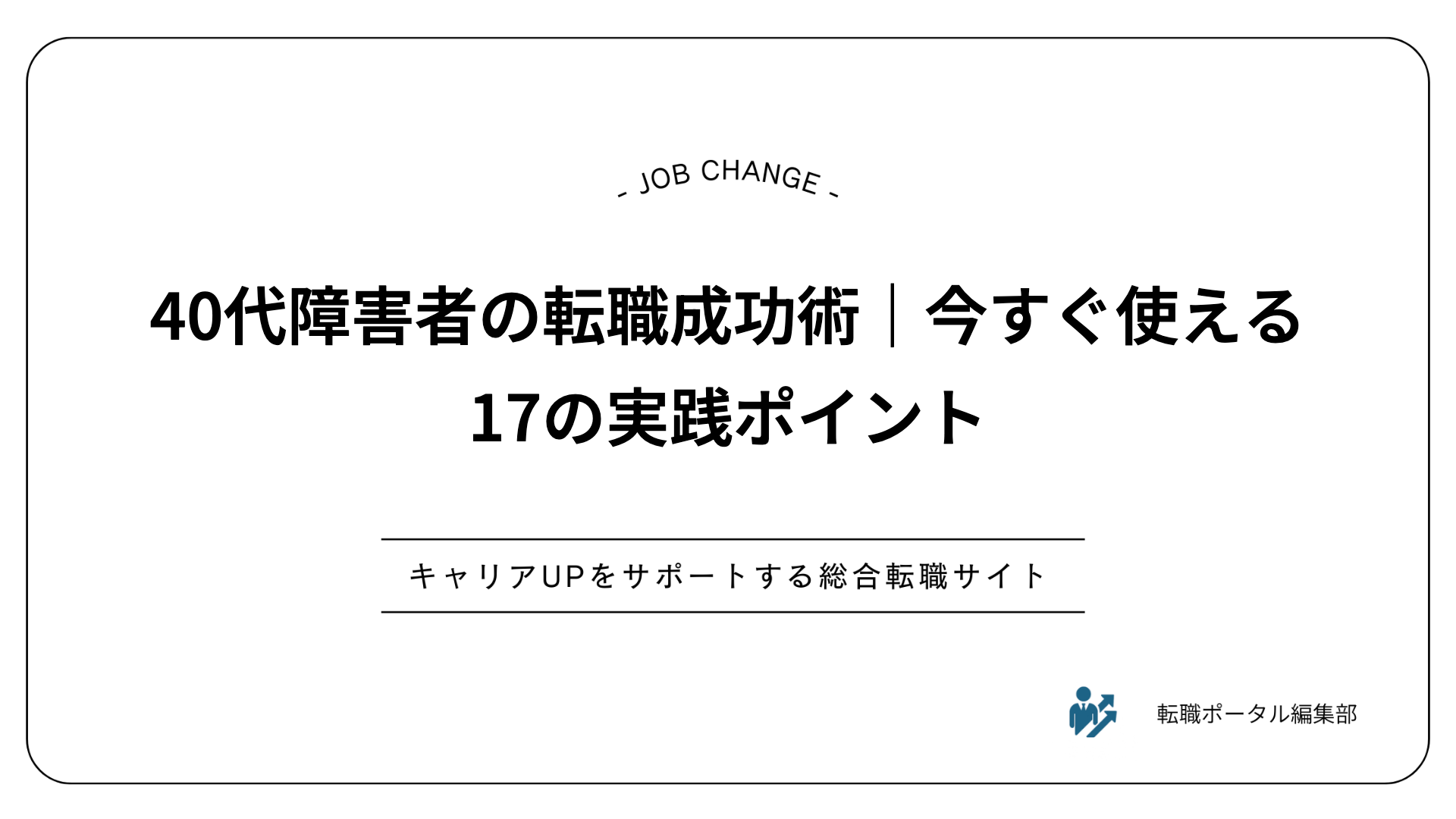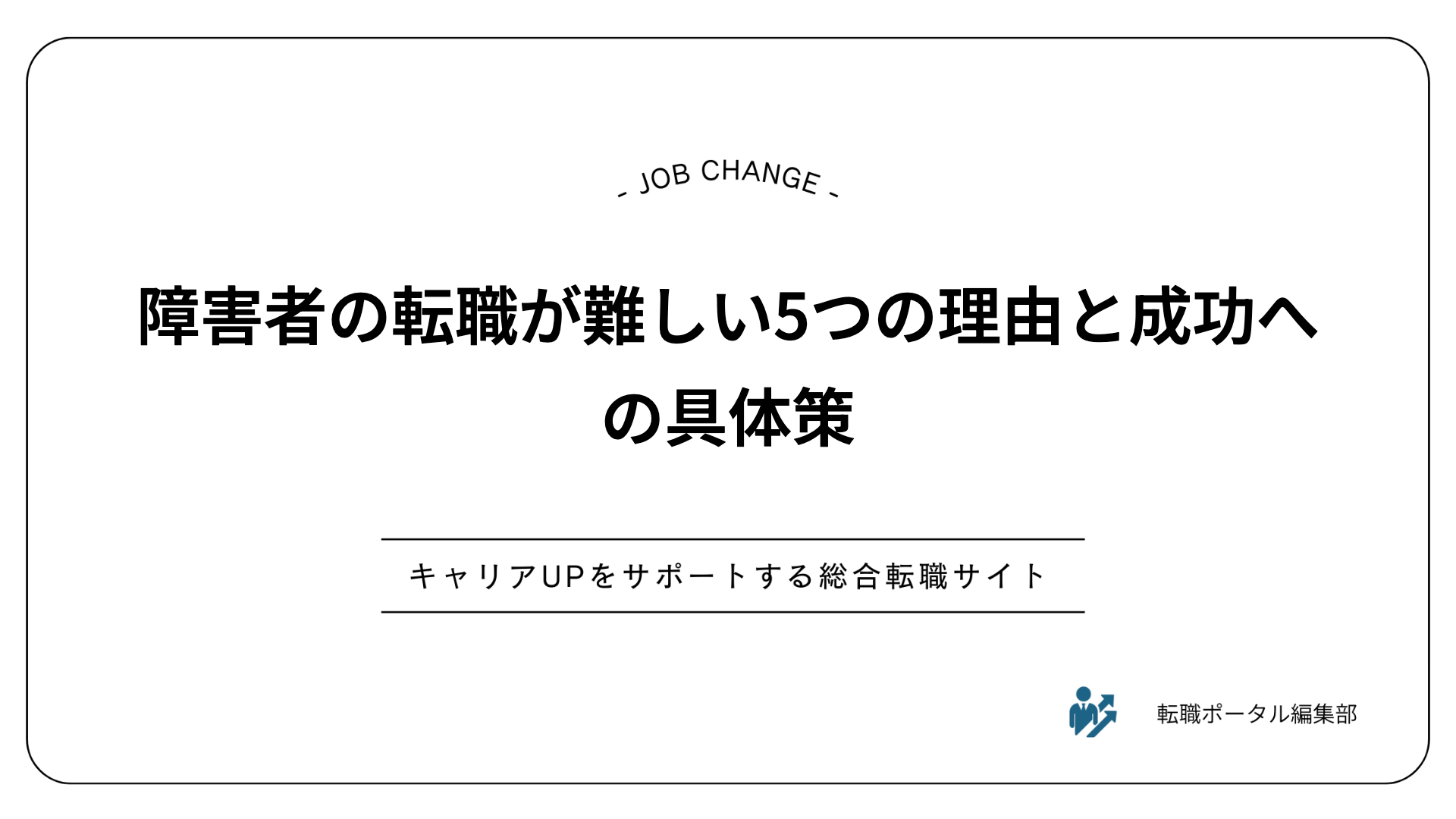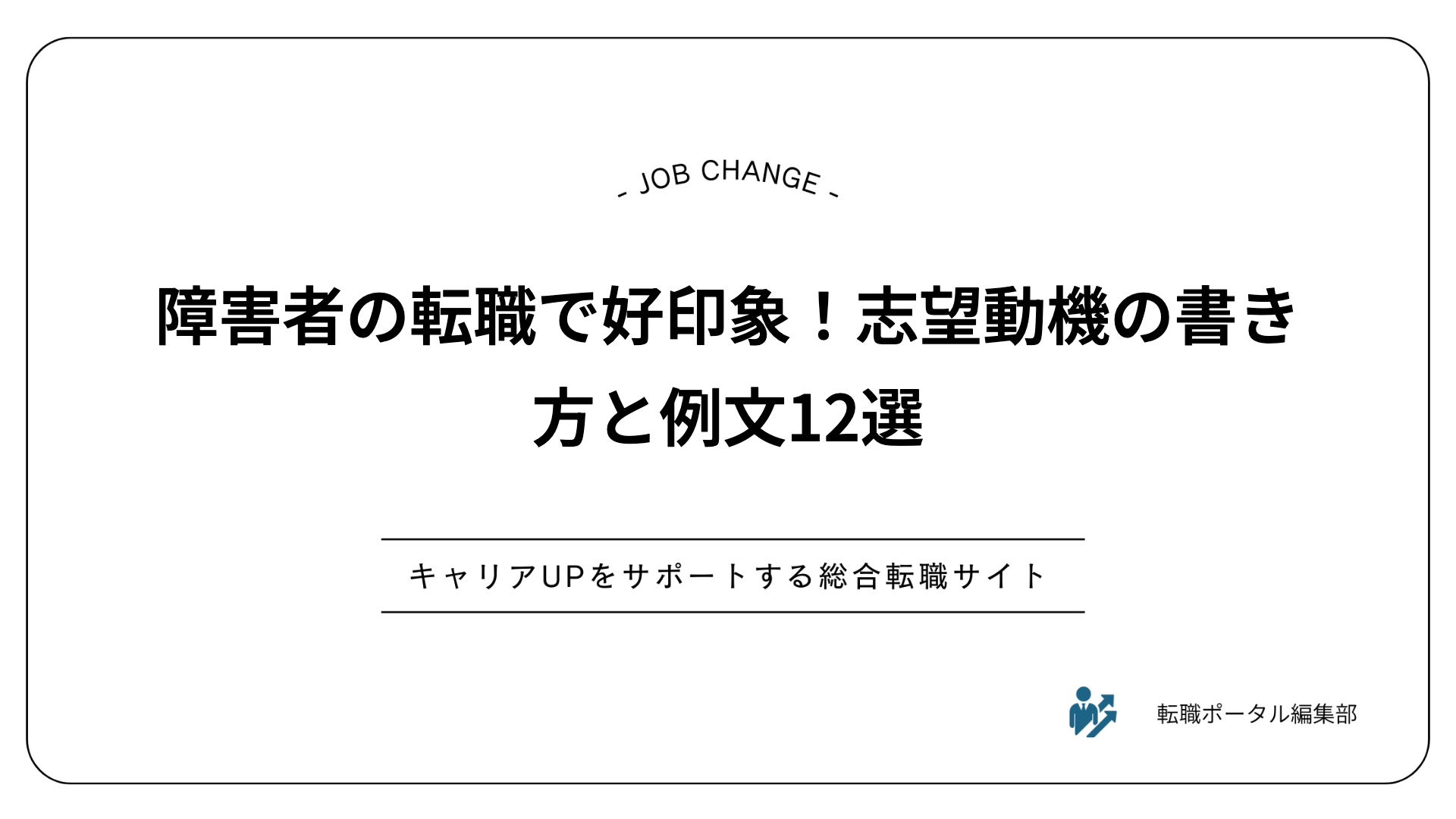障害者の転職相談に強くなる!後悔しないための9つのステップ
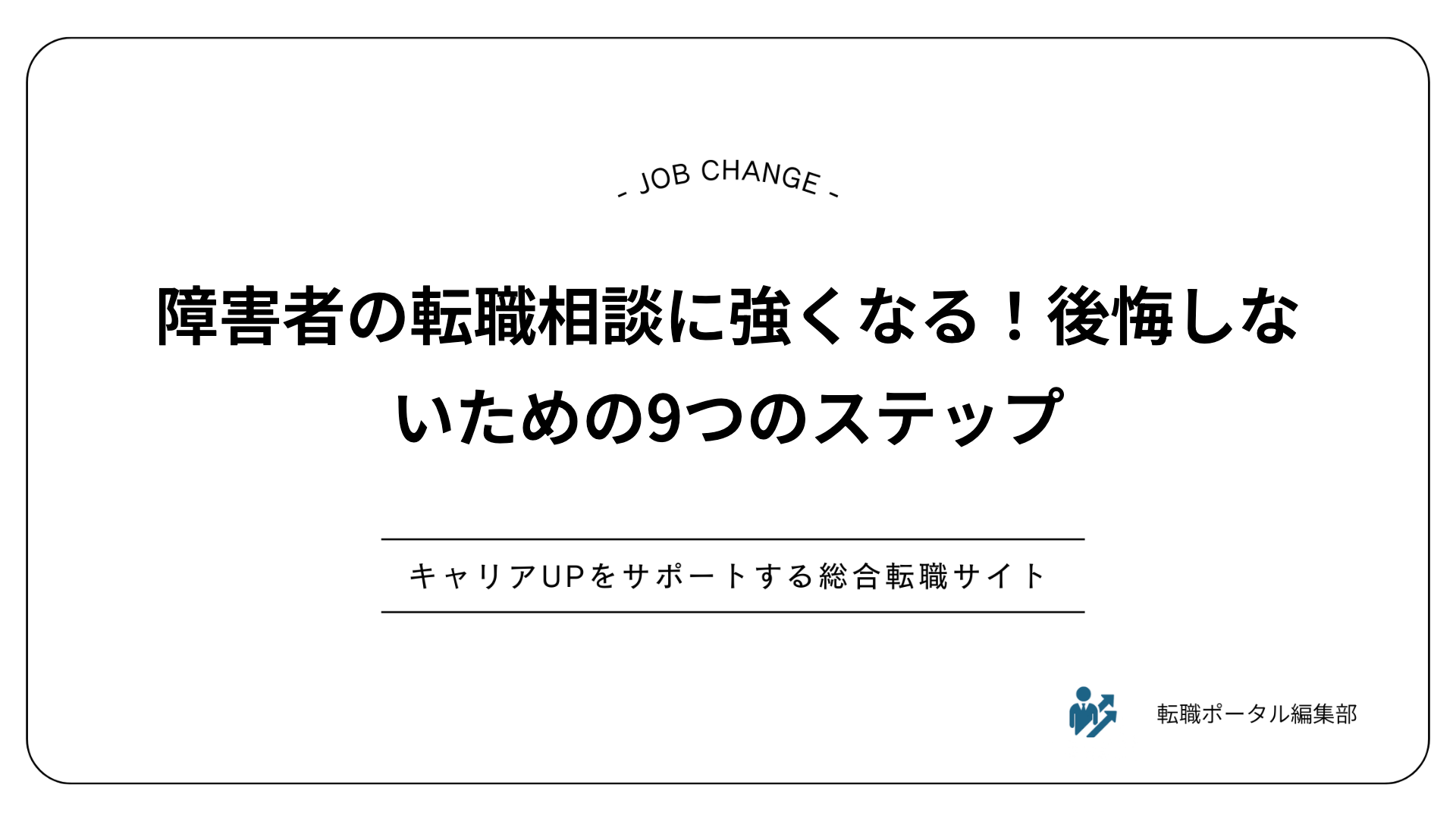
「障害がある状態で転職できるのか不安」「誰に相談すればいいのかわからない」──そんな悩みを抱えていませんか?
障害者雇用の制度や相談先は年々整備されていますが、情報が複雑で迷ってしまう方も多いのが現実です。
この記事では、障害者の方が転職で後悔しないために知っておきたい相談先の種類や、準備の進め方、成功事例などをわかりやすく解説します。
特に以下のような方にとって、この記事は役立つ内容になっています。
- 転職したいけど、何から始めればいいかわからない
- ハローワークとエージェントの違いを知りたい
- 障害を開示すべきかどうか迷っている
- 安心して長く働ける職場を見つけたい
- 在宅勤務や配慮のある職場を希望している
読んだあとには、「自分に合った相談先はどこか」「どのように動けばいいか」がクリアになり、不安を自信に変える一歩が踏み出せるはずです。
転職相談を始める前に知っておきたい基礎知識
障害者雇用市場の最新動向

障害者の転職市場は、近年大きな変化を遂げています。
企業の障害者雇用に対する姿勢は以前よりも前向きになり、選択肢の幅も広がりつつあります。
その背景には、法定雇用率の引き上げやダイバーシティ推進の動きがあり、実際に多くの企業が障害者雇用に積極的に取り組んでいます。
- 法定雇用率が2025年時点で2.5%に設定
- 企業による合理的配慮の義務化
- 在宅勤務やテレワーク求人の拡大
- 就労支援・職業訓練サービスの充実
特に精神障害者の雇用が増加しており、理解のある職場も着実に増えています。
また、求人の幅も広がり、事務職以外にIT、販売、リモートワークなど多様な職種が登場しています。
「自分にできる仕事があるか不安」と感じている方も、今の環境なら自分に合った仕事を見つけやすくなっていると言えるでしょう。
障害者が転職相談を利用するメリット・デメリット
転職相談を利用することで、客観的なアドバイスを受けながら効率的に転職活動を進められるのが大きなメリットです。
とくに障害のある方は、自力で情報収集や応募を進めるのが困難な場合もあるため、専門家のサポートは心強い味方になります。
- 自分に合った求人を提案してもらえる
- 応募書類や面接の準備をサポートしてもらえる
- 企業との連絡や条件交渉も代行してもらえる
一方で、必ずしも希望通りの職場を紹介されるとは限らず、「合わない」と感じることもあるかもしれません。
また、相談員の経験や対応力にはばらつきがあるため、相談先選びは慎重に行う必要があります。
相談を「丸投げ」するのではなく、自分の意思をしっかり持って利用することが成功のカギです。
オープン就労・クローズ就労の違い

障害者雇用では、自分の障害を開示して働く「オープン就労」と、開示せずに働く「クローズ就労」があります。
オープン就労では、職場に配慮をお願いしやすく、通院や体調管理がしやすい環境が整います。
一方、クローズ就労は障害を明かさずに働くため、配慮は得にくい反面、職種や待遇の選択肢が広がる可能性もあります。
たとえば、オープン就労では業務の調整が可能な代わりに、責任あるポジションに就きにくいという面もあります。
クローズ就労では自立性が求められますが、自分のペースを守るのが難しいケースもあります。
どちらを選ぶかは、障害の特性や働き方の希望次第です。転職相談の場でこの点を整理しておくと、後悔のない選択につながります。
障害者の転職相談先の種類と特徴
公的機関(ハローワーク・地域障害者職業センター・JEED)のサービス内容
障害者の転職支援において、もっとも身近で利用しやすいのがハローワークなどの公的機関です。
特に障害者専用窓口では、障害の種類や程度に応じた専門的な相談が可能であり、無料で支援を受けられる点が大きなメリットです。
- 就職・転職に関する個別相談
- 求人情報の提供(障害者枠含む)
- 模擬面接や履歴書の添削
- 職場実習やトライアル雇用の紹介
たとえば地域障害者職業センターでは、就労アセスメントや職業評価を行い、その人に最適な働き方を提案してくれます。
JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)もハローワークと連携しながら、多角的なサポートを提供しています。
「まず何から始めたらいいかわからない…」という方には、最初の相談先として最適です。
民間転職エージェント・転職サイトの活用ポイント
障害者向けの転職をよりスムーズに進めたいなら、民間の転職エージェントや転職サイトの活用も有効です。
特に障害者専門のエージェントは、障害への理解が深く、就職後のフォロー体制も整っているため安心して利用できます。
たとえばatGPやdodaチャレンジなどの大手サービスでは、求人の質・量ともに充実しており、非公開求人も豊富です。
また、カウンセラーが企業側と条件交渉を行い、配慮事項を伝えてくれるケースもあります。
一方で、短期間での転職を促されることもあるため、自分のペースや希望をしっかり伝えることが大切です。
就労移行支援・生活支援センターのサポート内容

一般企業への就職が難しいと感じる方には、就労移行支援の利用も検討に値します。
これは福祉サービスの一環で、障害者が一般就労するための訓練や支援を提供しています。
- ビジネスマナーやPCスキルなどの就労訓練
- 生活リズムの安定やストレス対処の支援
- 企業実習・職場定着のサポート
支援期間は原則2年で、通所型の施設が多く、障害者手帳があれば多くの場合は無料または低額で利用できます。
生活支援センターでは、日常生活や金銭管理、住まいなど就労以外の面も含めてトータルサポートが受けられます。
就職に自信がない方や、まず生活を整えたい方には特におすすめです。
企業内相談窓口や障害者職業相談室を利用する方法
企業によっては、障害者向けの社内相談窓口を設けているところもあります。
入社後に体調の変化や業務の悩みが出た際に、安心して相談できる体制があるかどうかも、職場選びの重要なポイントです。
また、都道府県労働局が設置する障害者職業相談室では、労働環境の問題やハラスメントなどについても相談可能です。
「働き始めたけれど、今の職場で続けていけるか不安…」と感じたときの相談先として覚えておくとよいでしょう。
相談は無料で匿名でも可能な場合があり、一人で抱え込まずに活用することが安定した職業生活につながります。
公的機関を活用した転職相談の進め方
ハローワーク障害者窓口で受けられる支援と手順
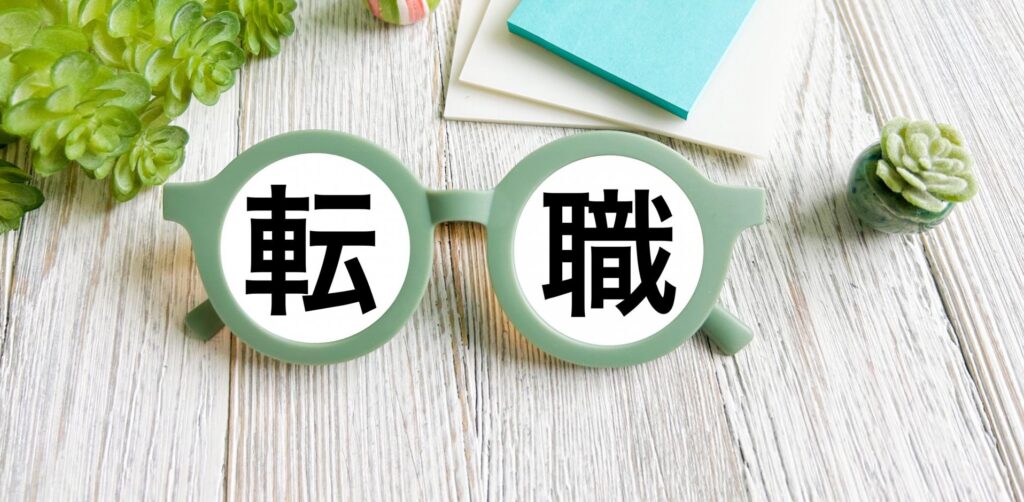
ハローワークには、障害者専用の相談窓口が設置されており、就職活動をサポートするさまざまなサービスが無料で提供されています。
手続きの流れはシンプルで、初回登録時に「障害者窓口を希望」と伝えれば、以降は専門の担当者が一貫してサポートしてくれます。
- 障害特性や希望条件に応じた求人紹介
- 面接対策や応募書類の添削
- トライアル雇用や職場実習のあっせん
- 就職後の職場定着支援
さらに、精神障害者保健福祉手帳を持つ方には、就労支援ナビゲーターによる継続的なフォローが受けられる制度もあります。
求人票には載っていない企業の雰囲気や配慮内容についても教えてもらえる場合があり、安心して応募できる環境が整っています。
「求人票だけでは企業の実態がわからない…」という方にもおすすめです。
地域障害者職業センターによる専門的サポート
地域障害者職業センターは、JEED(独立行政法人)によって運営されており、より専門性の高い就労支援が特徴です。
ここでは職業評価や就労準備性のチェックを通じて、障害のある方に最適な働き方を提案する支援が行われます。
たとえば、「どのような仕事が自分に向いているか」「職場でどの程度の配慮が必要か」などを、専門スタッフと一緒に客観的に把握することができます。
また、必要に応じて職場適応援助者(ジョブコーチ)による現場同行支援や、企業への合理的配慮の提案も実施されています。
ハローワークと連携して求人紹介や職場実習も受けられるため、「就職に向けた準備をしっかりしたい」という方にぴったりです。
自治体・福祉事務所の相談サービスを利用する際の注意点
お住まいの自治体や福祉事務所でも、障害者の就労支援に関する相談を受け付けています。
特に生活保護や障害年金、住宅支援などと絡む相談も可能なため、就労だけでなく生活全体を見据えた支援が期待できます。
- 生活支援と就労支援をワンストップで提供
- 福祉制度・給付制度の申請支援
- 他機関との連携による総合的支援
ただし、自治体によって支援内容にばらつきがあり、対応に時間がかかることもあります。
予約が必要なケースや、担当職員によって対応の質に差があることも少なくないため、他の支援機関と併用することが効果的です。
「制度の使い方がよくわからない」「どこに相談すべきかわからない」と感じたら、まず福祉窓口で相談してみるとよいでしょう。
民間の転職エージェントを活用した相談術
障害者専門エージェントの選び方と比較ポイント

障害者専門の転職エージェントを選ぶ際は、自分の障害特性に合ったサポート体制が整っているかを基準にすることが重要です。
エージェントによって得意とする障害の種類や対応地域、求人の種類が異なるため、複数のサービスを比較するのがベストです。
- 精神障害者のサポート実績が豊富か
- 企業への交渉力や合理的配慮の実績があるか
- 就職後の定着支援があるか
- オンライン面談に対応しているか
たとえば「dodaチャレンジ」「atGP」「エージェント・サーナ」などは、障害別に専任のカウンセラーを配置し、継続的なサポートを行っている点で評価されています。
初めてエージェントを利用する際は、口コミや支援実績も確認しながら、自分に合った1社を選ぶことが大切です。
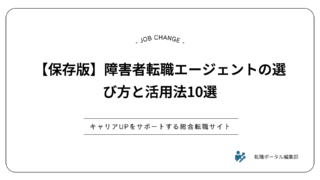
大手総合エージェントとの併用メリットとデメリット
障害者専門エージェントに加えて、リクルートエージェントやマイナビなどの大手総合型エージェントを併用するという選択肢もあります。
これにより、より幅広い求人情報にアクセスできたり、待遇の良い一般求人も検討できる可能性があります。
ただし、大手エージェントでは障害への理解が十分でない場合もあり、配慮内容が伝わりにくいといったリスクもあります。
企業側とのコミュニケーションや支援の質を考えると、障害に特化したエージェントを軸に、必要に応じて大手も活用する「併用型」が理想的です。
「少しでも良い条件で転職したいけど、障害の理解も重視したい」という方にとって、複数サービスの併用は有効な手段です。
エージェント面談前に準備しておくべき情報と書類

エージェントと初回面談をする際には、事前に準備をしておくことで、より具体的で実りある相談が可能になります。
- 履歴書・職務経歴書の最新版(フォーマットは不問)
- 障害者手帳の写し(開示する場合)
- 過去の職場で配慮を受けた内容や対応履歴
- 希望条件(勤務時間、通勤時間、業種・職種、配慮内容など)
さらに、現在の就労状況や健康状態、働く上で不安に感じていることなども整理しておくと、キャリアカウンセラーとの対話がスムーズになります。
「何を話したらいいのか不安…」という方でも、正直に悩みを共有することで、より適切な求人を提案してもらえる可能性が高まります。
エージェントを活用して転職成功した具体的な事例
実際にエージェントを利用して転職を成功させた方の事例を紹介します。
精神障害を抱えていた30代の男性は、一般枠での転職に何度も失敗し、自己流での転職活動に限界を感じていました。
そこで障害者専門エージェントに登録したところ、体調に配慮した勤務形態の企業を紹介され、半年以内に内定を獲得。
現在は週4日勤務・在宅中心で無理なく働き続けられているとのことです。
別の例では、身体障害のある20代女性がエージェントを通じて医療機器メーカーの事務職に就職。
面接時から通勤経路や設備の配慮を交渉してもらい、入社後の定着率も良好との報告があります。
このように、専門的な支援があることで、本人に合った職場環境を見つけやすくなるのがエージェントの強みです。
障害別・状況別におすすめの相談窓口
身体障害のある方に適した相談先とサポート内容
身体障害をお持ちの方には、バリアフリー対応の職場や通勤の利便性を重視した就職支援が欠かせません。
そのため、相談先としては「地域障害者職業センター」や「ハローワーク障害者窓口」が特に有効です。
- 職場環境に関する相談(段差・エレベーター・車椅子対応など)
- 通勤経路や通勤手段の検討
- 職務内容の調整や業務補助の相談
企業側と連携して合理的配慮の提案ができる相談機関を選ぶことで、ミスマッチのない転職を実現できます。
「配慮してもらえるのか不安…」という声もありますが、事前にしっかり相談・準備することで、安心して働ける環境を整えられます。
精神・発達障害のある方に適した相談先と活用方法

精神障害や発達障害のある方には、体調管理や職場での人間関係の不安に寄り添える支援が重要です。
そのため、「就労移行支援事業所」や「精神保健福祉センター」の利用が推奨されます。
たとえば就労移行支援では、模擬職場でのコミュニケーショントレーニングや、ストレスマネジメント講座が提供されており、働くための土台づくりが可能です。
また、精神保健福祉センターではメンタル面の専門的支援が受けられ、主治医との連携もスムーズに行えます。
「就職してもすぐに辞めてしまう…」という悩みがある方には、職場定着支援まで含めたトータルサポートが受けられるこれらの機関が有力です。
20代・30代など年代別で活用したい相談窓口の選び方
年齢によって利用しやすい相談先も異なります。
たとえば20代・30代の方には、「地域若者サポートステーション(サポステ)」や「就職カレッジ」のような若年層特化型の支援機関が適しています。
- キャリアカウンセリングや適職診断
- ビジネスマナーや模擬面接などの研修
- 企業見学・職場体験など実践的なサポート
若年層は職務経歴が少ない場合も多いため、「ポテンシャル採用」に強い相談窓口を選ぶのがポイントです。
「未経験でも応募できる仕事が見つからない」と感じる方でも、こうした窓口なら企業とのマッチング支援を受けやすくなります。
在宅勤務やリモートワークを希望する場合の相談先と求人探しのコツ

近年では障害者雇用においても在宅勤務が広がっており、「通勤が困難」「体調管理が優先」といった方にとって有力な選択肢となっています。
この場合、「民間の障害者専門エージェント」や「テレワーク対応企業に強い転職サイト」を活用するのが効果的です。
求人検索では、「在宅可」「リモート可」「テレワーク導入済」などのキーワードで絞り込みが可能です。
また、ハローワークでもテレワーク求人を紹介してもらえる場合があるので、相談時に希望を明確に伝えることが大切です。
「自宅で働ける仕事なんて少ないのでは?」と感じるかもしれませんが、IT・事務・カスタマーサポートなどを中心に、選択肢は確実に増えています。
転職相談の流れと事前準備
自己分析とキャリアの棚卸しを効果的に行う方法
転職相談を受ける前に、まずは「自分の強み・弱み」「できること・やりたいこと」を明確にしておくことが大切です。
この準備がしっかりできていれば、相談内容も深まり、より的確なアドバイスを得やすくなります。
- これまでの職歴・経験の振り返り
- 仕事で楽しかったこと・辛かったことの洗い出し
- 自分にとっての「働きやすい環境」や「働きがい」
市販のキャリアシートや自己分析ツールを使うのも有効ですが、就労移行支援事業所やキャリアカウンセラーに相談するのもおすすめです。
「自分のことがよくわからない…」と感じる方こそ、外部の視点を借りて整理してみましょう。
履歴書・職務経歴書・障害者手帳など必要書類の準備ポイント
転職活動を円滑に進めるためには、必要書類の準備も欠かせません。
特に障害者雇用では、通常の履歴書・職務経歴書に加えて、障害者手帳や主治医の意見書などが必要になる場合があります。
- 履歴書:形式は自由だが写真や志望動機は丁寧に記載
- 職務経歴書:簡潔かつ具体的に実績・業務内容を記述
- 障害者手帳の写し:開示する場合はコピーを準備
- 医師の意見書:企業から求められた場合に備えて主治医に相談
なお、配慮事項については、書類で伝えるか面談で伝えるかをエージェントや相談員と一緒に判断するのがベストです。
「書きすぎてしまわないか不安…」という場合は、カウンセラーに添削してもらいましょう。
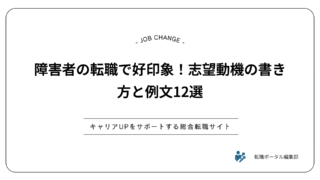
相談予約から面談当日までの具体的な流れ

転職相談の基本的な流れは、以下のようになります。
- ① 相談機関やエージェントへの連絡・Web申し込み
- ② 初回面談日程の調整・予約
- ③ 必要書類の提出・事前アンケートの回答
- ④ 面談当日:希望条件や悩みのヒアリング
初回面談は対面・電話・オンラインなどで行われ、約30〜60分程度が目安です。
担当者からは求人提案がある場合もあれば、「まずはスキルアップから始めましょう」とアドバイスされることもあります。
気負わずに「相談する」ことを目的に臨めばOKです。
相談後に行うべきアクションとフォローアップ方法
面談が終わったら、次のステップに進むためのアクションを明確にすることが重要です。
紹介された求人に応募するかどうかの判断や、職場見学・面接準備など、やるべきことをリストアップしておきましょう。
また、多くの相談機関ではメールや電話でのフォローも可能ですので、「気になることが出てきた」「体調に変化があった」などの場合は、遠慮なく連絡を入れてください。
一度で理想の職場が見つかるとは限りませんが、継続的な相談と行動の積み重ねが、転職成功への近道です。
転職相談を成功に導くポイント
合理的配慮の伝え方と企業への交渉術

転職を成功させるためには、自分に必要な合理的配慮を企業に正しく伝えることが重要です。
伝え方次第で、企業側の理解や対応が大きく変わるため、単に「配慮してください」と言うのではなく、具体的かつ前向きに説明することが求められます。
- 例:「午前中に体調が不安定なため、10時出社を希望します」
- 例:「電話対応は難しいため、メール中心の業務を希望します」
ポイントは、「できないこと」よりも「どうすれば働けるか」を中心に伝えること。
また、エージェントや相談員を通じて企業に伝える方法も有効です。
「直接交渉するのが不安…」という場合でも、第三者のサポートを活用すればスムーズに話を進められます。
障害開示・非開示を判断するための基準と注意点
障害を開示するかどうかは、転職活動において非常に重要な判断です。
一般的には、継続的な配慮が必要な場合は「開示」、短期的な不調など特段の配慮が不要な場合は「非開示」も選択肢となります。
たとえば、通院配慮や通勤時間の調整、業務内容の限定などが必要であれば、あらかじめ開示しておいた方がミスマッチを防げます。
一方で、軽度な症状や体調が安定している場合は、非開示で就職し、その後必要に応じて相談するという形もあります。
どちらの選択も一長一短があるため、信頼できる相談員や主治医と話し合いながら判断するのが安心です。
面接でよく聞かれる質問と回答の組み立て方
障害者雇用の面接では、一般的な質問に加えて「配慮内容」や「体調管理の工夫」などについても聞かれるケースが多くあります。
- これまでの職務経験・得意なこと
- 障害の内容と、仕事に与える影響
- 必要な配慮とその理由
- 再発防止や体調維持の取り組み
回答のコツは、「できないこと」ではなく「こうすれば働ける」という視点で話すことです。
たとえば、「長時間の対人業務は苦手ですが、マニュアル作成や事務作業には集中力を発揮できます」といった形で、代替スキルをアピールしましょう。
緊張しやすい場合は、模擬面接を活用して練習するのも効果的です。
入社後の定着支援を継続的に受ける方法

無事に転職が決まっても、働き続けられるかどうかが次の課題です。
そのためには、入社後も相談機関や支援者との関係を継続し、不安や問題が生じたときにすぐに相談できる体制を整えておくことが大切です。
具体的には、次のような支援を受けるとよいでしょう。
- ジョブコーチによる職場訪問や面談
- 定着支援型の就労移行支援事業所の活用
- 企業内の相談窓口との定期的な面談
問題が起きる前に相談することで、環境調整や業務の見直しがしやすくなります。
「働き続けることに自信がない…」という方でも、定着支援をうまく活用することで、安心して長く働くことが可能になります。
よくある質問と悩みへの回答
転職エージェントとハローワークはどちらを利用すべきか?
転職エージェントとハローワークは、それぞれ強みが異なるため、目的に応じて使い分けるのが理想です。
エージェントは、非公開求人や企業との交渉力に優れており、マンツーマンの手厚い支援が特徴です。
一方、ハローワークは地域密着型で、職業訓練や公共機関ならではのサポートが受けられます。
- 早期に就職を目指すなら→エージェント
- 職業訓練や福祉制度と併用したいなら→ハローワーク
- 両方利用しながら比較検討するのがベスト
「どちらを使えばいいかわからない…」と迷う必要はありません。両方に登録し、併用しながら自分に合った支援を見つけるのが賢い選択です。
転職エージェントのおすすめは以下の記事にまとめています↓
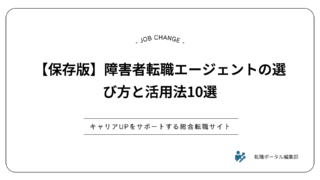
未経験からでも挑戦しやすい職種と探し方
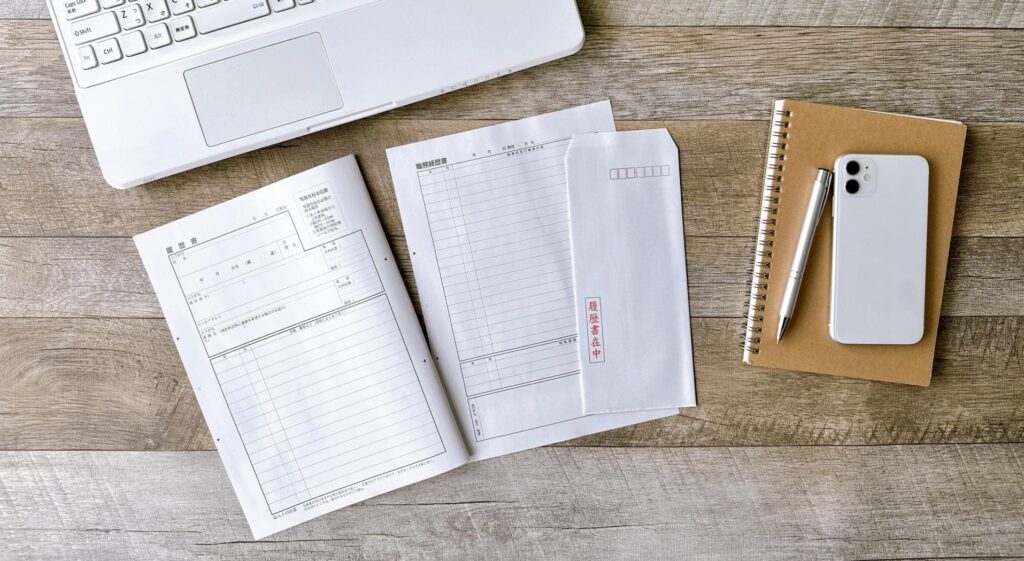
障害者雇用では、未経験OKの求人も多数あります。
特に事務補助・軽作業・清掃・ITサポートなどは、研修制度が整っており、初めての方でも安心して挑戦しやすい職種です。
探し方のポイントは、スキルよりも「働きやすさ」や「体調管理のしやすさ」を基準にすること。
たとえば在宅勤務ができる仕事や、勤務時間の柔軟な職場を選ぶことで、継続して働ける可能性が高まります。
エージェントやハローワークに希望条件を具体的に伝えることで、未経験歓迎の求人を効率よく探せます。
給料アップを目指す際の相談ポイントと注意点
障害者雇用では「給与が低い」と感じる方も多いですが、条件次第では年収アップも十分に可能です。
ポイントは、自分のスキルや経験を的確にアピールすること、そして業界や職種を戦略的に選ぶことです。
- IT・経理・Web制作など専門スキルが活きる職種
- 中小企業より大手・外資系の方が高待遇の傾向あり
- 長く勤務し昇給制度を活用する戦略も有効
「障害があるから給与は仕方ない」と諦めずに、キャリアプランを明確に持つことが、収入向上への第一歩です。
ただし、給与だけに目を向けすぎず、自分の体調や働き方とのバランスも意識しましょう。
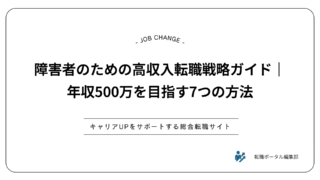
転職活動期間中の生活費や支援制度の活用方法
転職活動中の生活費に不安を感じる場合、活用できる制度や支援があります。
たとえば、就労移行支援を利用することで、訓練を受けながら福祉サービスを通じた生活支援を受けられるケースがあります。
- 失業給付(条件を満たせば受給可能)
- 障害年金や生活保護の申請
- 自治体の住宅・生活支援制度
また、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」など、一定期間の無利子貸付も検討できます。
「収入が途絶えるのが怖い…」という場合は、転職相談と並行して福祉相談窓口にもアクセスしておきましょう。
まとめ:自分に合った転職相談先を活用して、安心できる未来をつかもう
障害のある方が転職を成功させるためには、「自分に合った相談先を選ぶこと」が最も重要です。
その理由は、支援機関やエージェントの特性によって得られるサポートが異なるからです。
どの相談先を選ぶかで、求人の質、面接の支援、職場定着までの流れが大きく変わります。
- 障害特性に応じて公的機関・民間サービスを選び分ける
- 事前に自己分析・書類準備を進めることで相談効果が高まる
- 合理的配慮や配属先への希望は事前に整理しておく
- 障害開示・非開示の判断は専門家と相談しながら決める
- 複数の相談先を併用して視野を広げるのも有効
最終的には、「自分のことを理解してくれる人と出会えるかどうか」が転職成功のカギです。
今すぐに理想の職場が見つからなくても、相談を通じて一歩ずつ前に進んでいけるはずです。
迷ったときこそ、一人で抱え込まず、信頼できる相談窓口に声をかけてみてください。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
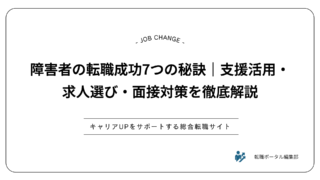
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓