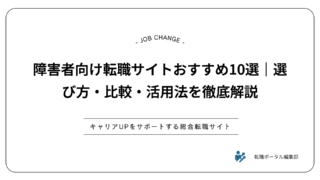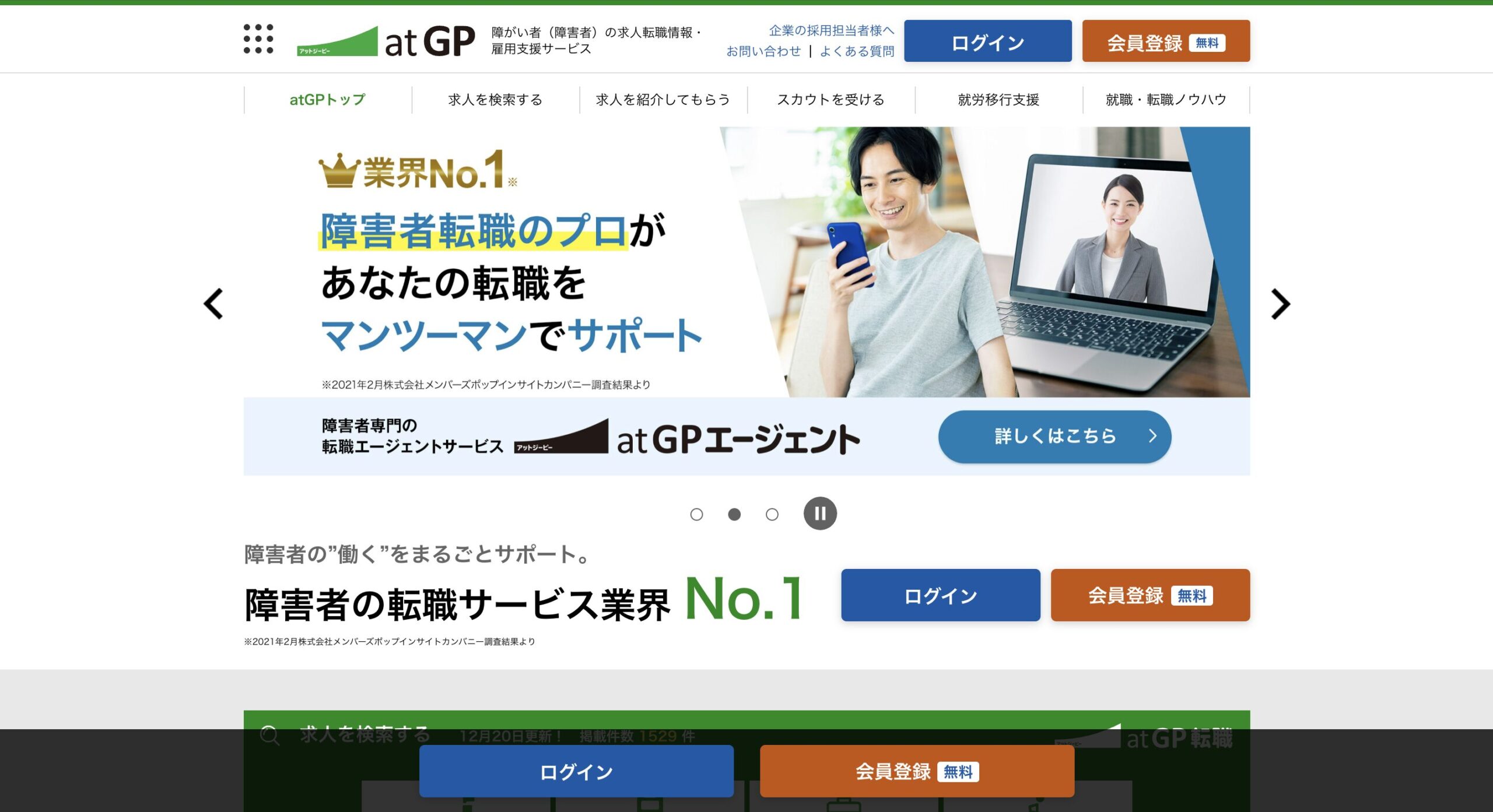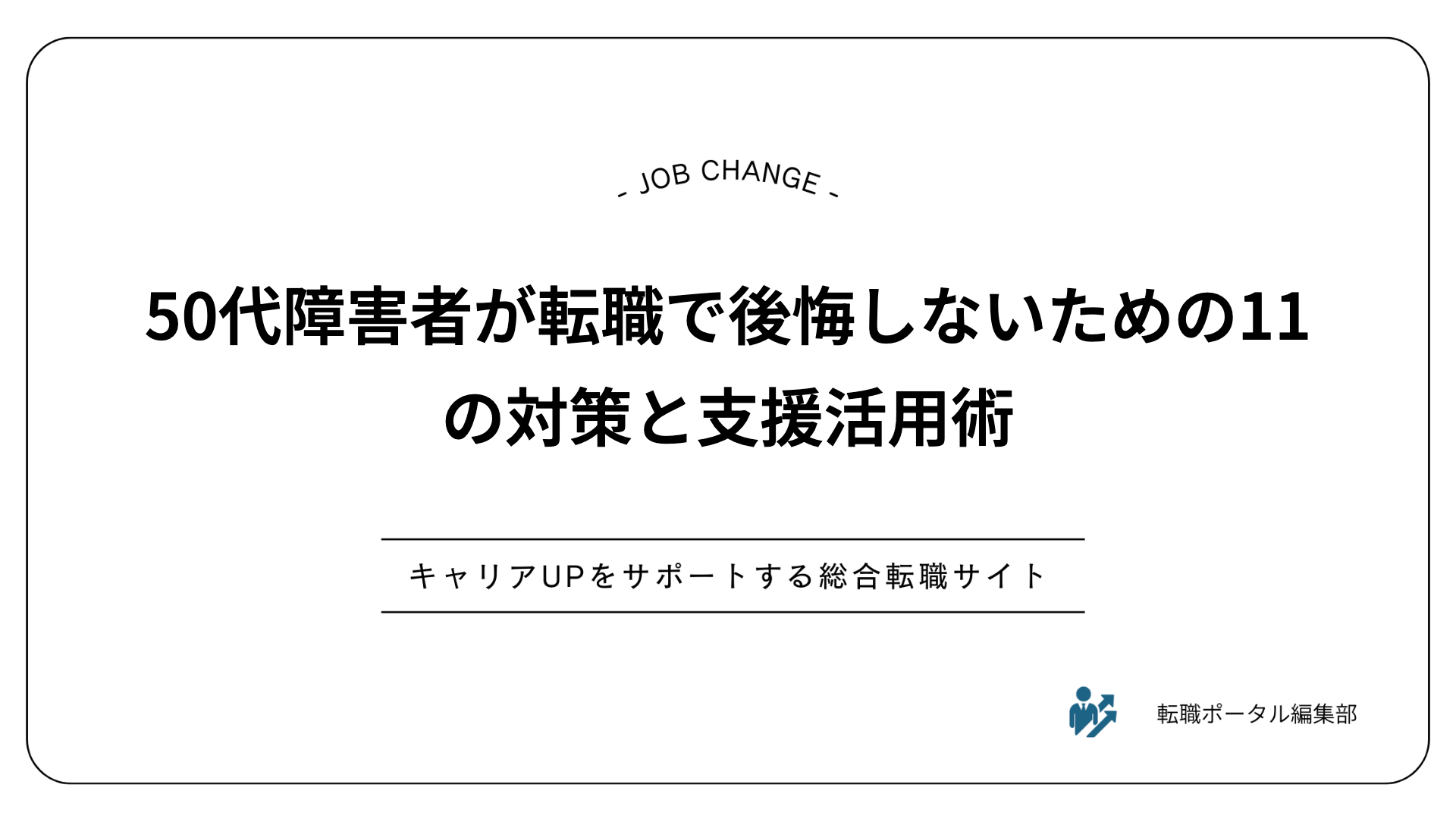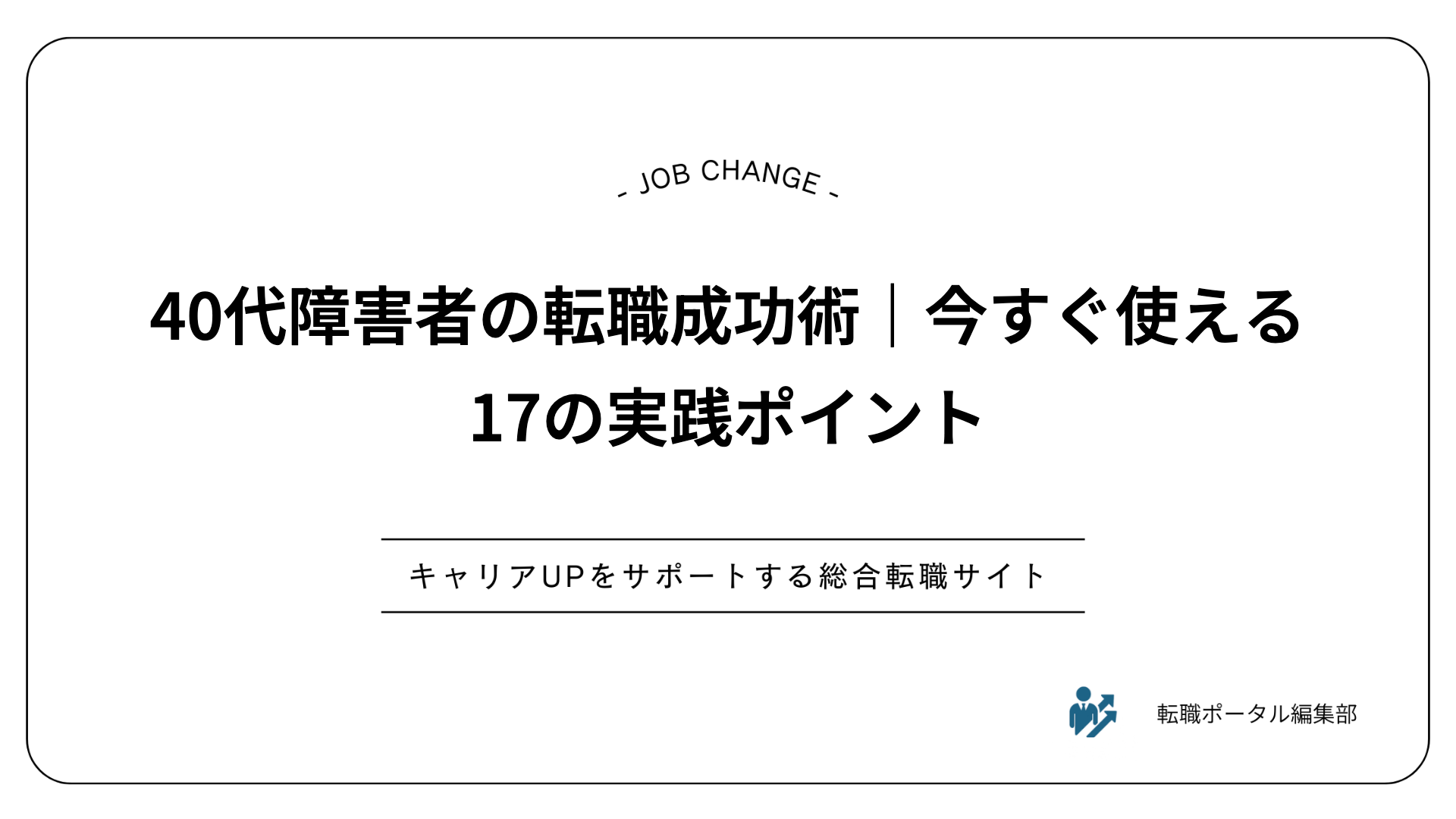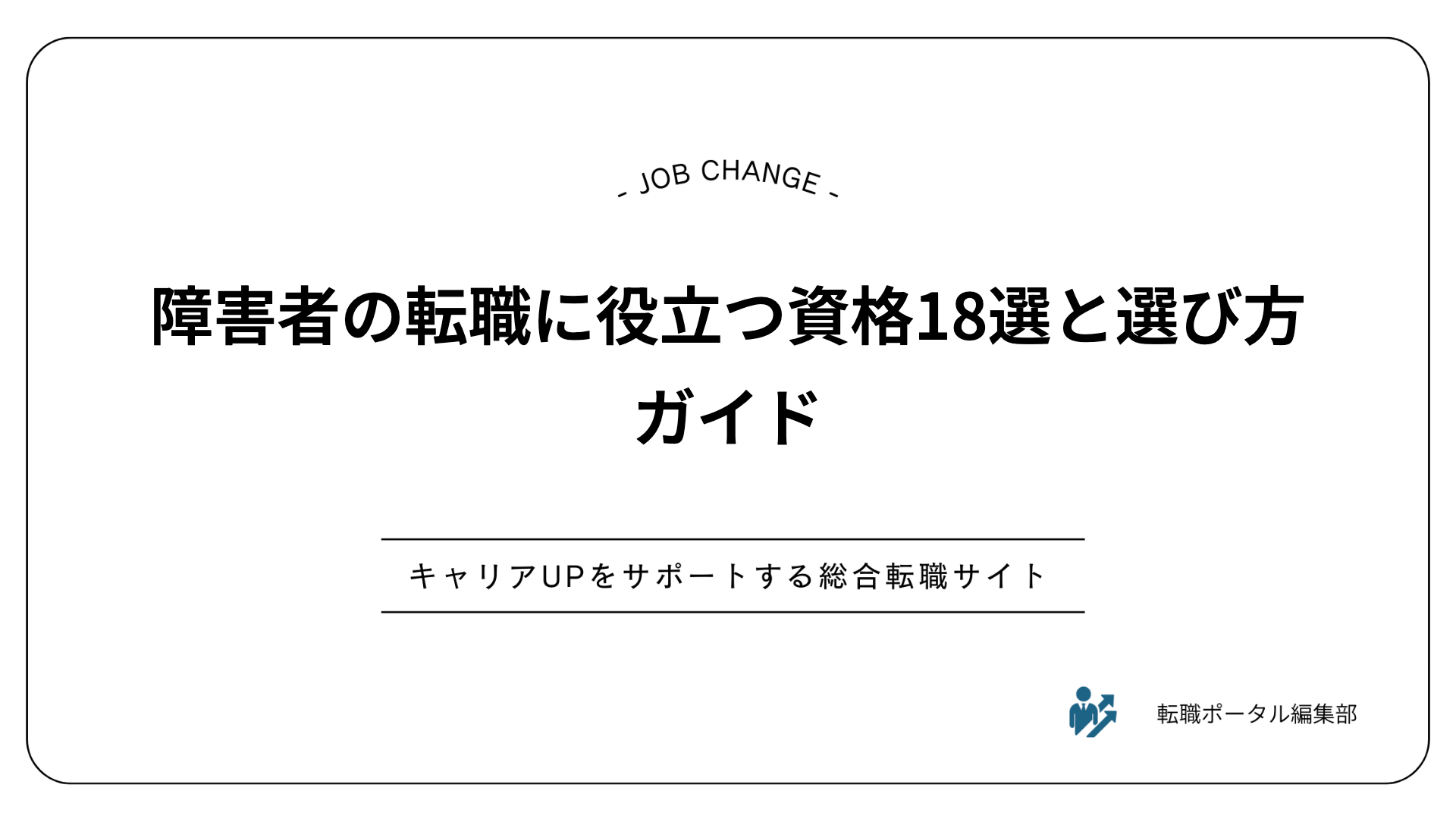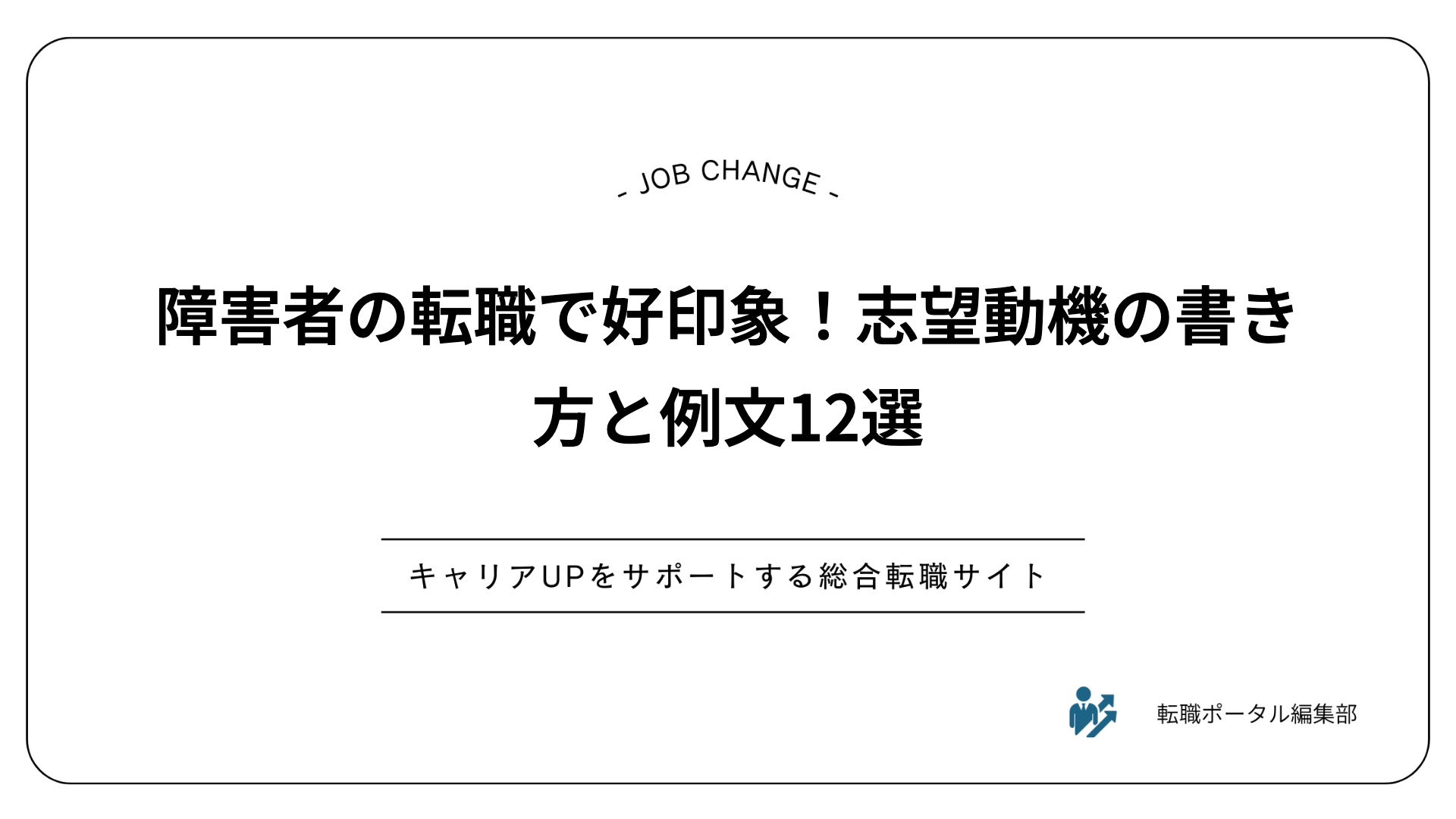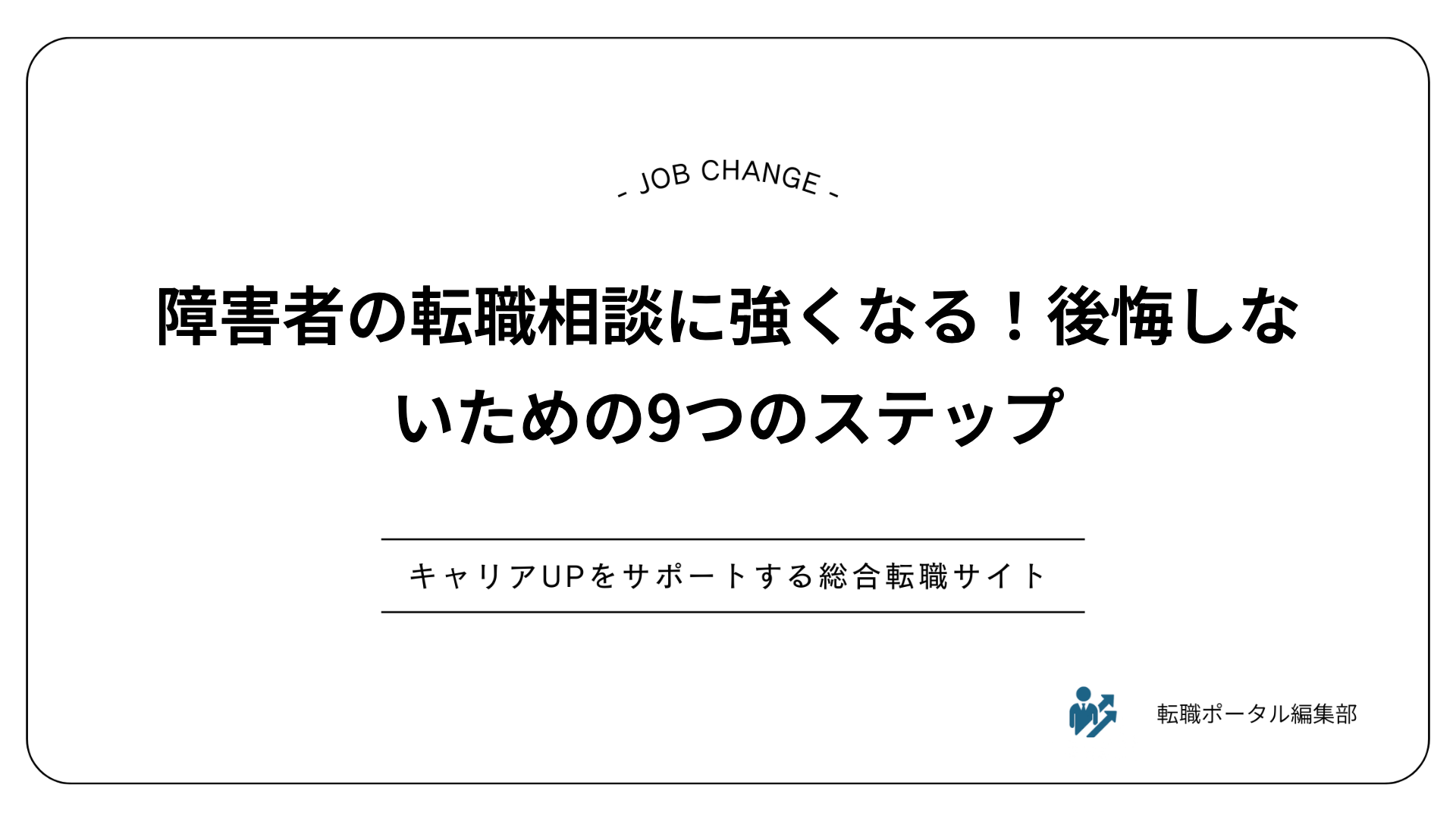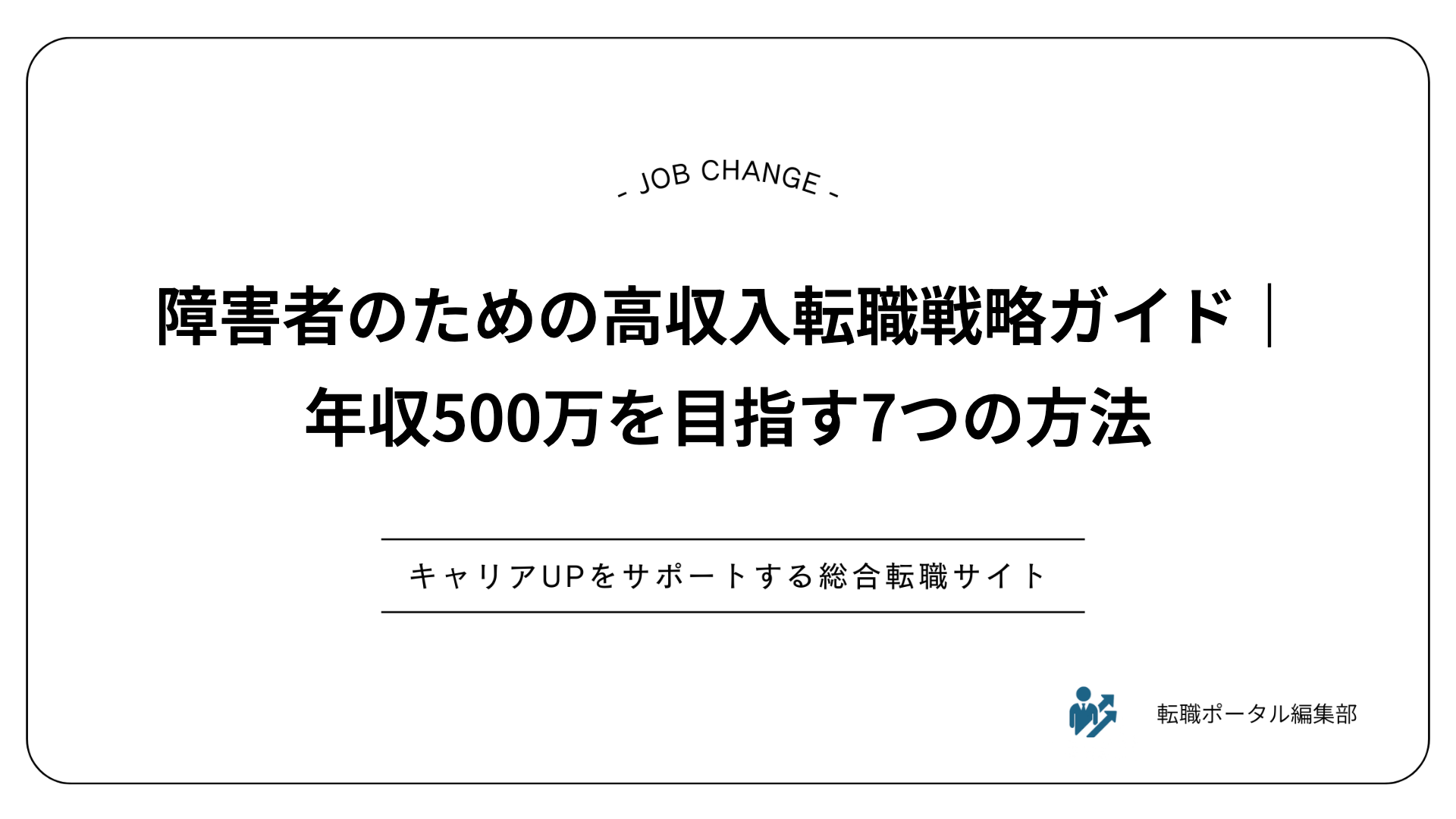【保存版】障害者転職エージェントの選び方と活用法10選
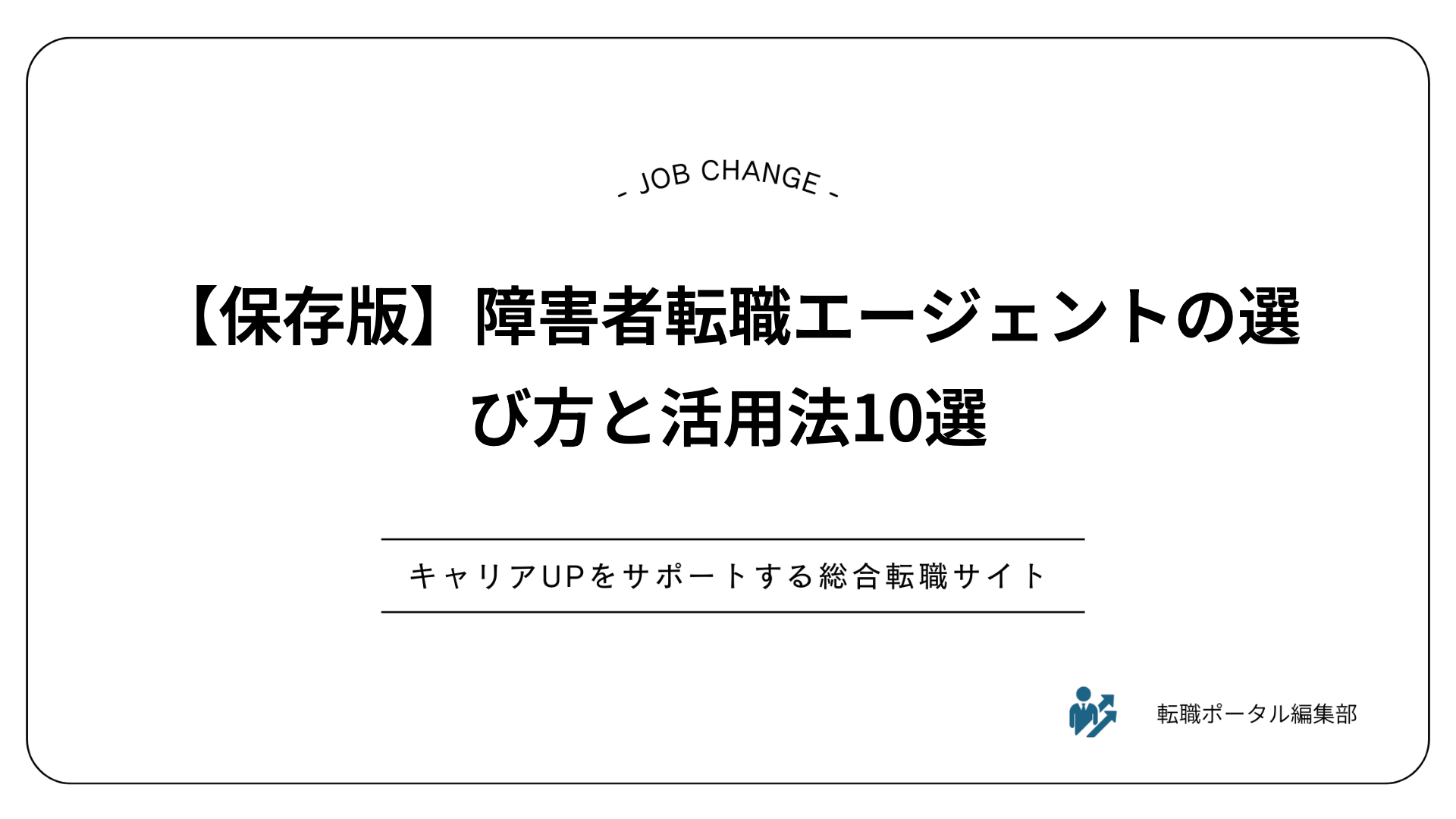
「障害があると、転職って難しいのでは…」そう感じていませんか?
実際に、求人探しで自分に合った職場が見つからなかったり、面接でうまく伝えられなかったりと、悩みを抱える方は少なくありません。
ですが、そんな時こそ頼りになるのが「障害者転職エージェント」です。
この記事では、障害者転職エージェントを活用することで得られるサポート内容から、エージェントの選び方、転職成功のコツまでを詳しく解説します。
こんな悩みや希望を持つ方におすすめの内容です。
- 安心して長く働ける職場を見つけたい
- 自分の障害に理解のある企業に就職したい
- 書類や面接に自信がなくて一人では不安
- 転職サイトでは見つからない求人を探したい
一人で悩まず、プロの支援を受けながら「自分らしく働ける環境」を見つけていきましょう。
障害者転職エージェントとは
サービスの仕組みと特徴

障害者転職エージェントとは、障害のある方が働きやすい職場へ就職できるよう、専門的な支援を提供してくれる無料サービスです。
- 障害者専任のアドバイザーが常駐しており、就職活動の悩みに親身に寄り添ってくれる
- 障害者雇用に理解のある企業とのマッチングに特化している
- 履歴書の添削や面接対策など、内定に向けた具体的なサポートが受けられる
特に民間エージェントは「就労支援A型・B型」とは異なり、一般企業への就職を前提とした支援を行っています。
そのため、福祉的な就労から一歩踏み出し、長期的なキャリアを築きたい方にとって、非常に頼もしい存在です。
「就労移行支援との違いがよくわからない…」という方も多いかもしれませんが、次の段落で具体的にご紹介していきます。
一般枠との違い
障害者雇用枠と一般枠の違いは、大きく分けて「合理的配慮の有無」と「評価基準の違い」にあります。
障害者枠では、選考段階から障害に関する配慮が前提となるため、自身の体調や特性について安心して伝えることができます。
一方、一般枠では健常者と同じ働き方が前提とされ、職場での配慮を得るハードルが高くなる傾向があります。
これにより、たとえば通院や服薬の事情を開示できず、無理な働き方を強いられるケースも少なくありません。
「必要な配慮を伝えて働ける環境がほしい」と考える方にとって、障害者枠の利用は安心できる選択肢と言えるでしょう。
エージェントと転職サイトの違い
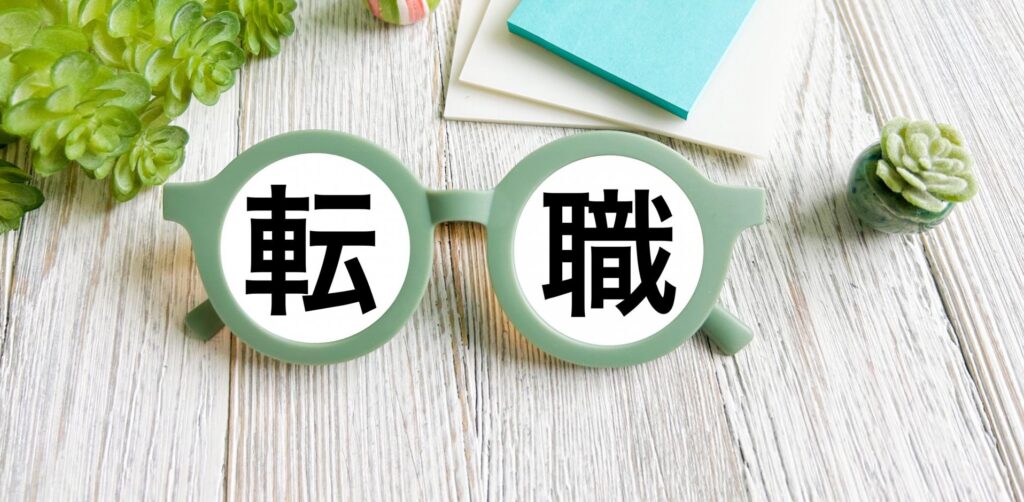
障害者向けの転職支援では、「転職エージェント」と「転職サイト」のどちらを利用するかで転職活動の進め方が大きく変わります。
- 転職エージェントは、専任アドバイザーが企業とのやりとりや選考日程の調整まで行ってくれる
- 転職サイトは、自ら求人を探し、自分の力で応募・面接を進める必要がある
特に配慮事項が必要な場合、自力での求人探しでは情報が不十分なこともあります。
エージェントを通すことで、事前に職場の雰囲気やサポート体制を確認できるため、安心して応募しやすくなります。
「応募しても落ち続けてしまう…」「自分に合った職場が見つからない…」と感じている方には、転職エージェントの利用をおすすめします。
障害者の転職におすすめのサイトを知りたい方は以下にまとめています↓
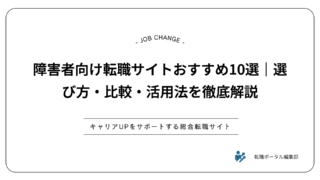
利用するメリットとデメリット
メリット:専門サポートと非公開求人
障害者転職エージェントを利用する最大のメリットは、やはり「個別サポート」と「非公開求人へのアクセス」です。
- 履歴書・職務経歴書の添削や面接練習など、手厚いフォローを受けられる
- 企業と直接やり取りする必要がなく、精神的な負担が減る
- 求人サイトには載っていない非公開求人の紹介がある
特に非公開求人には「障害特性に理解のある社風」「長期雇用前提」「柔軟な勤務体系」といった魅力的な条件が揃っていることもあります。
これにより、選択肢の幅が大きく広がります。
自分一人ではなかなか出会えない求人に巡り合えるチャンスがあるのは、エージェント利用ならではの強みです。
デメリット:アドバイザー依存と求人の偏り
一方で、エージェントには注意すべき点もあります。
まず、アドバイザーの質に差があること。
担当者によって提案内容や対応の丁寧さが変わることがあり、「この人とは合わない」と感じることもあるかもしれません。
また、エージェントが保有する求人は、地域や業種に偏りが出ることがあります。
特に地方在住の方や、在宅勤務を希望する方は、希望条件に合う求人が少ないと感じることもあるでしょう。
そのため、エージェントを1社だけに絞らず、2〜3社を併用して比較するのが安心です。合わない場合は担当者の変更も依頼できます。
「断っても大丈夫?」「しつこく営業されない?」と不安な方もいるかもしれませんが、基本的には無理な提案はないので安心してください。
障害者転職エージェントの選び方
障害特性への理解度

エージェント選びで最も重要なのは、「あなたの障害特性にどれだけ理解があるか」という点です。
たとえば、精神障害をお持ちの方なら「体調の波に配慮できる職場」を探す必要がありますし、身体障害がある方なら「設備面の対応」が欠かせません。
このような事情をしっかり理解したうえで、適切な求人を紹介してくれるかどうかは、面談時の対応や過去の支援実績を見ることで判断できます。
エージェントの中には、障害者雇用に関する研修制度を整えているところや、障害当事者のスタッフがいるところもあります。
「なんとなく違和感を感じる…」「こちらの話を深く聞いてくれない…」という感覚がある場合は、担当変更や別エージェントの検討をおすすめします。
求人の質と量
求人の数や質も、エージェント選びにおいて見逃せないポイントです。
- 大手企業と提携しているか
- 非公開求人や独占求人をどれだけ保有しているか
- あなたの希望業界・職種の求人が豊富かどうか
例えば、事務系やIT系に強いエージェントもあれば、製造や軽作業に特化しているところもあります。
希望する職種が明確な場合は、その業界に強いエージェントを選ぶことで、選択肢の幅が広がります。
数が多くても希望に合わなければ意味がありません。「紹介される求人が毎回ズレている…」と感じたら、他のエージェントに切り替える判断も必要です。
対応エリアと雇用形態

転職エージェントの中には、首都圏や関西圏など都市部を中心に対応しているところが多く、地方や離島ではサポートが限定されるケースもあります。
- 地元での就職を希望する方は、全国対応のエージェントや地域密着型のサービスを選ぶ
- リモートワークを希望する場合は、在宅求人に対応しているかも確認
- 正社員・契約社員・パートなど、希望する雇用形態を扱っているか
面談の方法にも注目しましょう。オンライン面談に対応しているかどうかは、特に地方在住の方にとって重要な要素です。
希望に合わない雇用形態しか紹介されない場合、長く働くことが難しくなるため、事前の確認が不可欠です。
サポート内容と定着率
最後に確認しておきたいのが、サポートの手厚さと就職後の定着率です。
優良なエージェントは、求人紹介だけでなく、以下のような支援も行っています。
- 自己分析やキャリアカウンセリング
- 面接同行やフィードバック提供
- 就職後の定着フォローや相談対応
「内定をもらったらサポート終了」ではなく、「働き始めてからも安心できる関係」であるかどうかが、長期的な就労には欠かせません。
エージェントの定着率は公式サイトで紹介されていることもあるため、参考にすると良いでしょう。
「せっかく就職できてもすぐ辞めてしまった…」というリスクを減らすために、サポート体制の充実度もチェックしておきたいところです。
おすすめ障害者転職エージェント比較
総合型エージェント
総合型の障害者転職エージェントは、幅広い業界・職種・障害種別に対応しており、初めての転職でも安心して利用できるのが特徴です。
- 多様な求人を保有しており、希望に沿った提案を受けやすい
- 全国対応していることが多く、地方在住者にも利用しやすい
- 複数の障害種別に対するノウハウを持っている
たとえば「dodaチャレンジ」「ランスタッド」「アットジーピー」などが該当します。
求人の選択肢が多く、比較検討しながら転職活動を進めたい方におすすめです。
「まだやりたい職種が決まっていない」「色んな可能性を見たい」という方には、総合型からスタートするのが無難でしょう。
障害種別特化型エージェント
一部のエージェントでは、精神障害や発達障害、身体障害など、特定の障害種別に特化した支援を行っています。
- 支援実績が豊富で、障害特性に応じたアドバイスが的確
- 面接での伝え方や配慮の相談がしやすい
- 「同じ障害の方が多く働いている企業」とのマッチングが得意
精神障害向けなら「LITALICOワークス」、発達障害に特化した相談が可能な「エンカレッジ」などが知られています。
「自分の障害について、ちゃんと理解のある担当者に相談したい」と感じている方には、こうした特化型エージェントが心強い味方になります。
地域特化型エージェント
首都圏や関西圏以外での転職を考えている方にとっては、地域密着型のエージェントが有力な選択肢です。
こうしたエージェントは地元企業との関係性が深く、求人の詳細情報や現場の雰囲気まで把握していることが多いです。
特に以下のような方にはおすすめです。
- UターンやIターンを考えている
- 地元で安定して働きたい
- 地域の事情に詳しいアドバイザーに相談したい
具体的には「エージェント・サーナ」「クローバーナビ」などが、地方求人に強みを持つエージェントとして知られています。
在宅・リモート求人に強いエージェント
近年、障害者雇用においても在宅勤務の求人が急増しています。
通勤負担の軽減や、静かな環境で働きたい方にとって、リモートワークは非常に大きな選択肢となります。
在宅に特化したエージェントでは、以下のようなメリットがあります。
- 在宅対応の求人が豊富で、自宅から働ける企業を紹介してくれる
- リモート面接の対策や在宅勤務時の注意点も教えてくれる
- 通勤が困難な方でも、正社員を目指せる機会が増える
「atGPジョブトレIT・Web」や「ミラトレ(パーソル)」では、在宅前提の就労支援を行っているプログラムも提供されています。
「自宅で安心して働ける職場を探したい」と考えている方には、こうしたエージェントが大きな助けになるはずです。
年代・キャリア別おすすめ活用法
20代:初めての転職を成功させるコツ
20代の転職では、まだ職歴が浅い方も多く、「自己PRがうまくできない」「何を基準に職場を選べばいいかわからない」という不安がつきものです。
障害者転職エージェントを利用することで、未経験歓迎の求人や研修制度のある企業に出会える確率が高まります。
- ポテンシャル採用に積極的な企業を紹介してもらえる
- エージェントが「自分の強み」を一緒に整理してくれる
- 就職後も定着サポートが受けられるため、離職リスクが下がる
初めての転職だからこそ、一人で悩まずプロの視点を取り入れることが成功の鍵になります。
30代:キャリアアップと年収アップを狙う方法
30代になると、これまでの職歴やスキルを活かして「ステップアップ転職」を目指す方が増えてきます。
障害者転職エージェントでは、即戦力を求める非公開求人や、マネジメント経験を活かせるポジションの紹介も行われています。
例えば、事務職から人事や総務へのキャリアチェンジ、ヘルプデスクからITスペシャリストへの昇格など、可能性はさまざまです。
「年収を上げたいけど、障害がネックになるのでは?」と感じる方もいますが、実際には年収アップに成功している事例も多くあります。
自分の市場価値を客観的に把握するためにも、複数のエージェントと話してみるとよいでしょう。
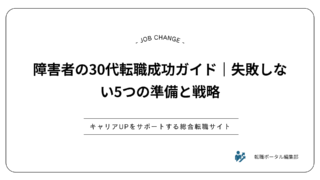
40代・50代:長く働ける職場選びのポイント

40代以降の転職では、「年齢」と「障害」という二重のハードルを感じる方も少なくありません。
しかし、経験を重視する企業や、落ち着いた環境での就業を歓迎する職場も確実に存在します。
- 業務内容が安定していて体調を崩しにくい
- 定年までの雇用継続制度が整っている
- 同世代の障害者が働いている職場
また、ミドル層の転職支援に強いエージェントを活用することで、適切な求人に出会える確率も高まります。
「年齢的に厳しいかも…」と諦める前に、一度エージェントに相談してみる価値は大いにあります。
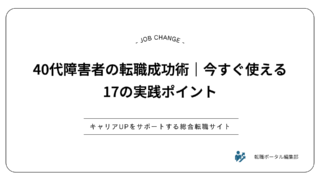
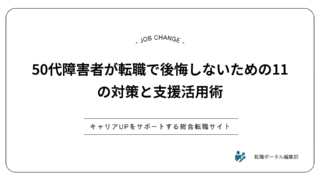
障害種別・配慮内容別の選び方
精神障害向けサポートが充実したサービス
精神障害をお持ちの方には、体調の波やストレス耐性に理解があり、無理のない働き方を支援してくれるエージェントが適しています。
- 通院や服薬のスケジュールを尊重する求人を紹介
- ストレスの少ない職場環境の企業情報が得られる
- 就職後のフォロー体制が整っている
特に「atGPジョブトレ」「LITALICOワークス」などは、就労移行支援と連携したサポートもあり、復職や転職の際に心強い味方となってくれます。
身体障害・車椅子ユーザー向け求人が豊富なサービス

身体障害や車椅子の利用がある方にとって、職場のバリアフリー対応は最も重要なポイントです。
物理的なアクセスだけでなく、トイレや休憩室の構造など、細やかな配慮がある企業を紹介できるかがカギになります。
エージェントでは、実際に職場を見学した上での情報を提供してくれることもあり、安心して応募できます。
「求人票には書かれていない情報が知りたい」と感じている方は、身体障害者向けサポートに強いエージェントを活用しましょう。
発達障害・ASD/ADHDに理解が深いサービス
発達障害のある方は、コミュニケーションやマルチタスクへの配慮が必要なケースが多くあります。
- 得意不得意を整理して適職を提案してくれる
- 自己理解や職場での伝え方のサポートがある
- ASD/ADHDの特性を活かせる職場を紹介してくれる
「エンカレッジ」や「ディーキャリア」などは、発達障害に特化した支援実績が豊富で、特性を前向きに捉える視点からの転職支援を提供しています。
「職場での失敗体験が多くて自信がない…」という方も、一人で悩まず専門家のサポートを受けてみてください。
知的障害向け就労支援が手厚いサービス
知的障害のある方に向けたエージェントは、理解しやすい言葉での説明や、業務指導が丁寧な職場とのマッチングを重視しています。
職場実習制度が整っている企業や、指導担当者が配置されている企業を紹介してくれるため、働きながら仕事に慣れていくことが可能です。
支援機関と連携しているエージェントも多く、定着支援や職場での問題解決にも対応しています。
「安心して長く働きたい」「指導が丁寧な職場がいい」と感じる方にとって、知的障害に理解のあるエージェントは強い味方です。
エージェント利用の流れと準備
登録から面談まで

障害者転職エージェントの利用は、基本的に無料で始められます。最初のステップは、公式サイトからの会員登録です。
- 登録は5〜10分程度の入力で完了
- 障害種別や希望職種、通勤エリアなどの基本情報を入力
- 登録後、エージェントから面談の案内が届く
面談はオンライン・電話・対面から選べるケースが多く、自宅からでも気軽に相談できます。
事前に話したい内容や不安点をメモしておくと、スムーズに進行できます。
求人紹介と応募
面談を通じて希望条件や障害特性を伝えたら、専任アドバイザーがマッチする求人を提案してくれます。
この段階で注目すべきは、「求人票だけではわからない情報の共有」です。例えば、
- 社内に障害者の受け入れ実績があるか
- 業務内容や配慮の範囲はどこまでか
- 定着支援の担当者がいるか
エージェントは企業と直接やり取りしているため、こうした詳細情報を把握しています。気になる点があれば、遠慮なく質問しておきましょう。
面接対策と選考サポート

面接は誰でも緊張するものですが、エージェントでは模擬面接やフィードバックを通じて本番に備えることができます。
特に障害者雇用では、「配慮が必要な点をどう伝えるか」「できる業務と難しい業務をどう表現するか」といった点が重要になります。
アドバイザーはこれまでの事例をもとに、適切な言い回しや伝え方をサポートしてくれるため、安心感があります。
また、面接日程の調整や書類送付なども代行してくれるので、手続きに不安のある方でもスムーズに進められます。
内定後フォローと定着支援
内定が出た後も、エージェントのサポートは続きます。条件面談のサポートや、入社日の調整、必要な配慮の確認などを一緒に行ってくれます。
- 「配属先はどんな雰囲気?」「引き継ぎはあるの?」といった不安も相談可
- 就業開始後のトラブルに対してもエージェントが間に入って調整してくれる
- 一定期間は定着支援の連絡が続き、状況を見守ってもらえる
特に入社直後は環境に慣れるまでの不安が大きいため、相談できる相手がいることは大きな安心材料になります。
エージェントに相談する前にやるべき自己分析
障害の開示範囲を決めるポイント
転職活動において、障害の内容や配慮事項を「どこまで開示するか」は重要な判断ポイントです。
開示の範囲を明確にしておくことで、エージェントとの面談もスムーズに進みます。以下の観点を参考にしましょう。
- 職場で配慮が必要なこと(通院、静かな環境、体力面など)
- 業務上避けたいことや過去の失敗経験
- 自分で対処できることと、支援が必要なことの線引き
「何をどこまで話すべきかわからない…」という方でも、エージェントとの初回面談で一緒に整理してもらえるので安心してください。
希望条件の優先順位付け

求人選びでは、「絶対に譲れない条件」と「妥協してもいい条件」を整理しておくことが重要です。
たとえば以下のような観点で考えると、自分の希望が明確になります。
- 勤務地:自宅から通いやすい範囲か、在宅希望か
- 雇用形態:正社員、契約社員、パートなど
- 業務内容:事務系、軽作業、IT系など
- 勤務時間や残業の有無
すべての条件を満たす求人は少ないため、優先順位をつけておくとミスマッチを防ぎやすくなります。
職務経歴書・履歴書の準備
書類選考に進むためには、職務経歴書と履歴書の準備が必要です。
障害者転職エージェントを利用すれば、書類のテンプレートや記入例、添削サポートも受けられるため、初めての方でも安心です。
職務経歴書では、以下のポイントを意識して書くと効果的です。
- どんな業務をしていたか(具体的に)
- できること・得意なこと
- 工夫したことや成果
「アルバイトしか経験がない」「ブランクがある」という方でも、日常生活で工夫していることや、学んできたことをアピールする方法があります。
エージェントと一緒に整理していきましょう。
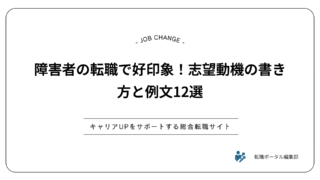
よくある質問(FAQ)
障害者手帳がなくても利用できる?

エージェントによって対応は異なりますが、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。
特に「医師の診断書」や「通院歴のわかる書類」があれば、相談や求人紹介が可能なエージェントも存在します。
- 精神障害の方で、まだ手帳を取得していないが診断はあるケース
- 身体障害の程度が軽度で、今後の取得予定があるケース
ただし、障害者雇用枠での就職を目指す場合は、手帳が求められる企業も多いため、早めに取得を検討することも選択肢のひとつです。
エージェントは何社併用すべき?
基本的には2〜3社を併用するのがおすすめです。
各エージェントによって保有する求人やアドバイザーの視点が異なるため、複数の意見を比較しながら進めることで、より自分に合った職場を見つけやすくなります。
ただし、多すぎると連絡管理が煩雑になったり、エージェント側に伝える情報がバラバラになったりするリスクもあります。
「迷って決められない」という方は、まず1社に登録し、相性を見てから追加するのが安心です。
無料で利用できる理由
障害者転職エージェントのサービスは、利用者側は完全無料で利用できます。
- 企業側が採用時にエージェントへ紹介手数料を支払う仕組み
- そのため、求職者には金銭的な負担が一切発生しない
「無料って逆に怪しい…?」と不安になる方もいますが、これは人材紹介業界では一般的なビジネスモデルです。
安心して利用して問題ありません。
地方在住でもサポートは受けられる?

はい、オンライン面談や電話相談に対応しているエージェントも多く、地方在住でも十分なサポートを受けることが可能です。
また、全国対応型の大手エージェントでは、各都道府県の企業とのネットワークも持っており、地元での求人紹介も対応しています。
在宅勤務の求人を扱うエージェントであれば、勤務地に関係なく選択肢を広げることもできます。
「地元で働きたい」「引っ越さずに就職したい」という方も、まずは一度相談してみましょう。
まとめ:障害者転職エージェントを活用して納得のいくキャリアを築こう
障害を持ちながら働くうえで、自分に合った職場と出会うことは決して簡単ではありません。
だからこそ、障害者転職エージェントという専門サポートを活用することが、転職成功への近道になります。
この記事では、サービスの特徴からメリット・デメリット、選び方やエージェント比較、自己分析のポイントまで幅広く解説してきました。
- 障害特性に理解のある求人を紹介してもらえる
- 応募書類や面接のサポートが受けられる
- 非公開求人に出会える可能性がある
- 内定後のフォローや定着支援が受けられる
- オンライン対応のエージェントもあり、地方からでも相談可能
「一人では限界を感じている」「納得のいく働き方を実現したい」と感じたら、まずは気軽に無料相談から始めてみましょう。
あなたが安心して長く働ける職場に出会えるよう、この記事が一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
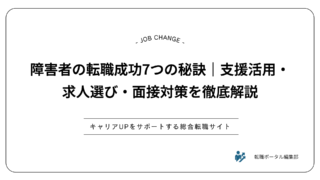
障害者の転職におすすめのサイトはこちら↓