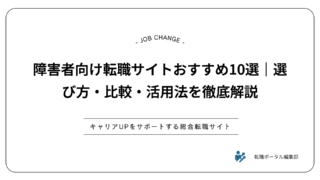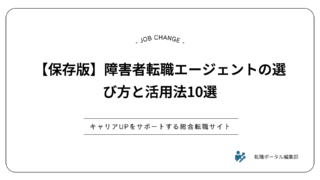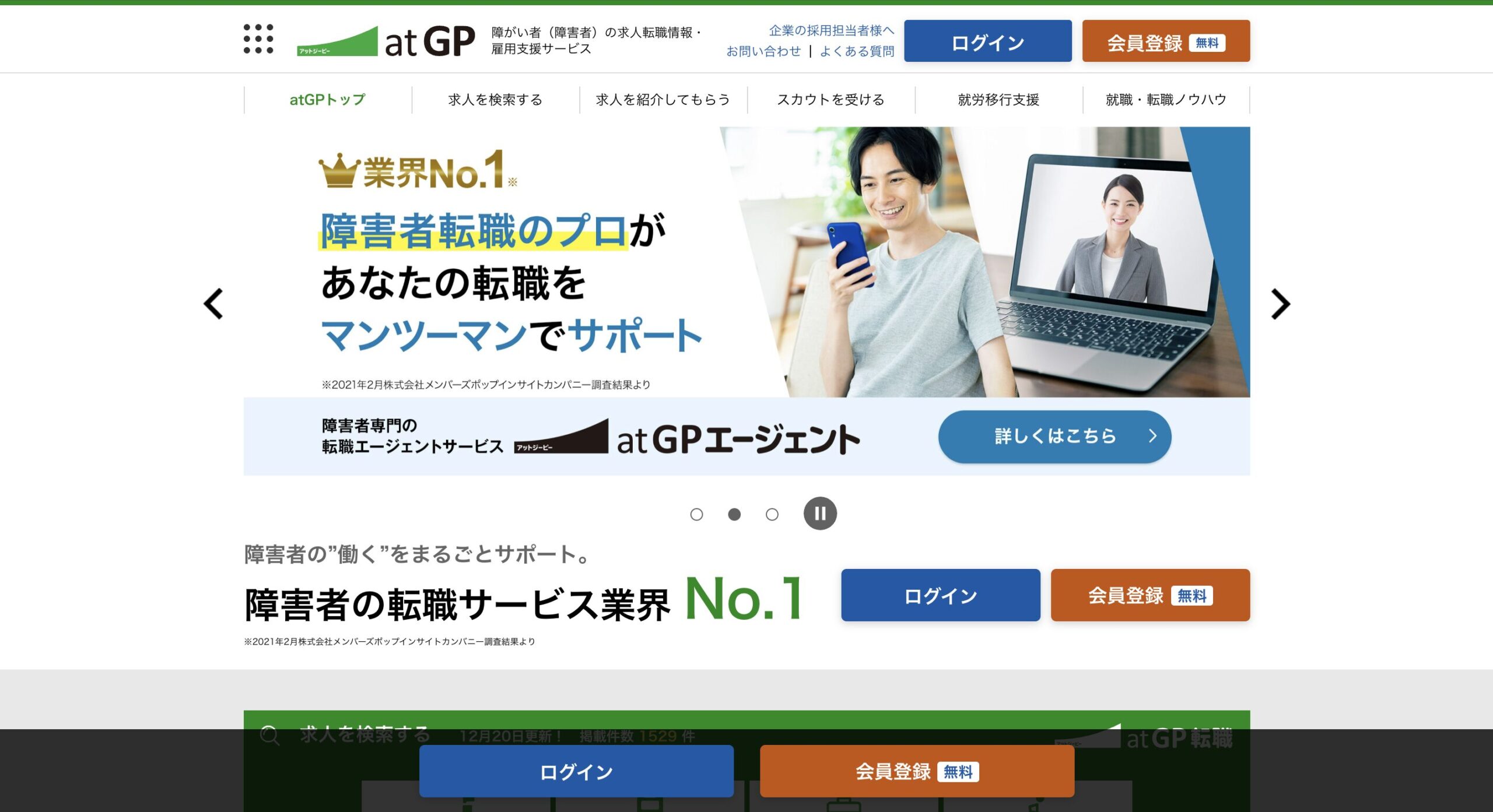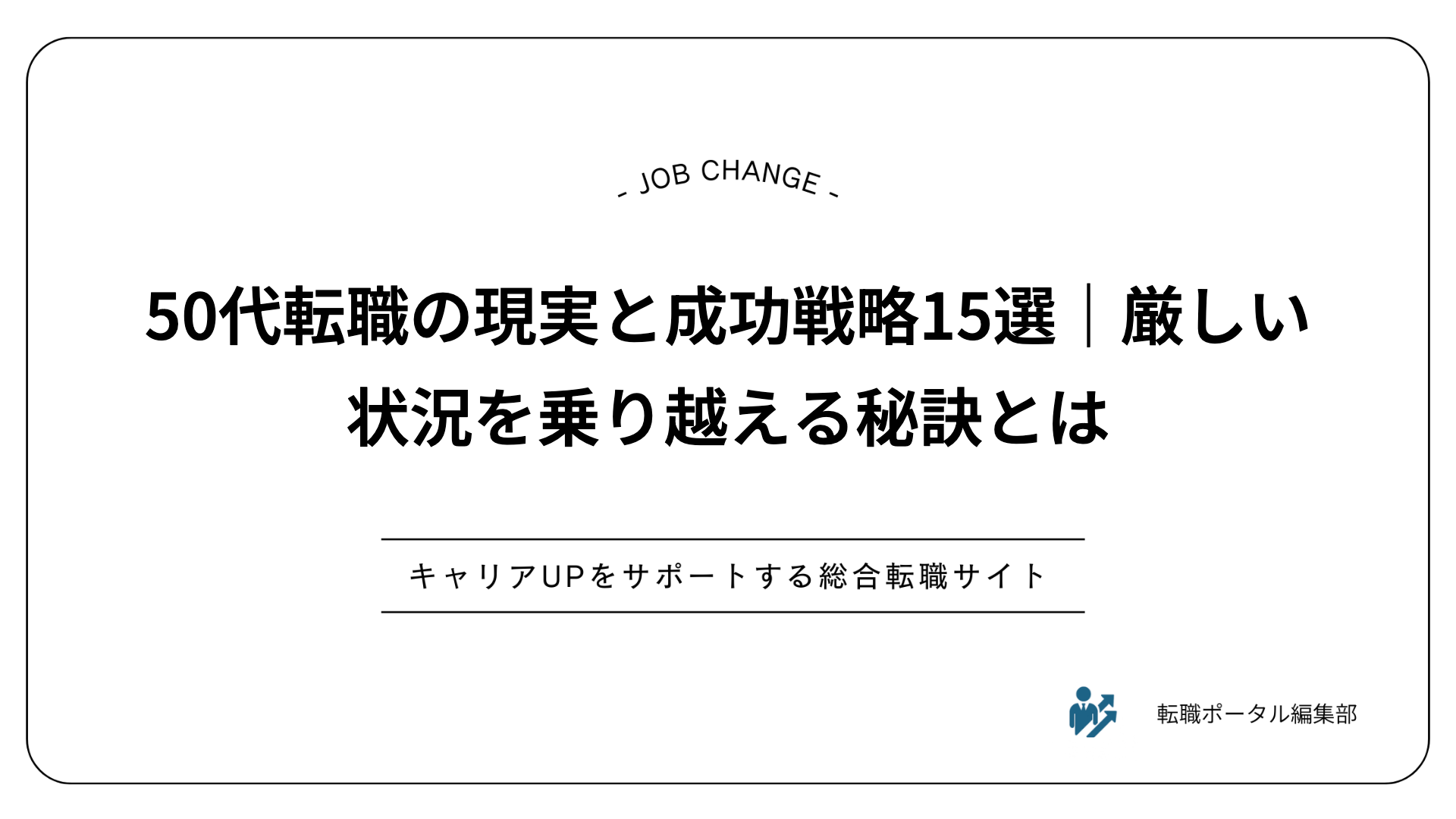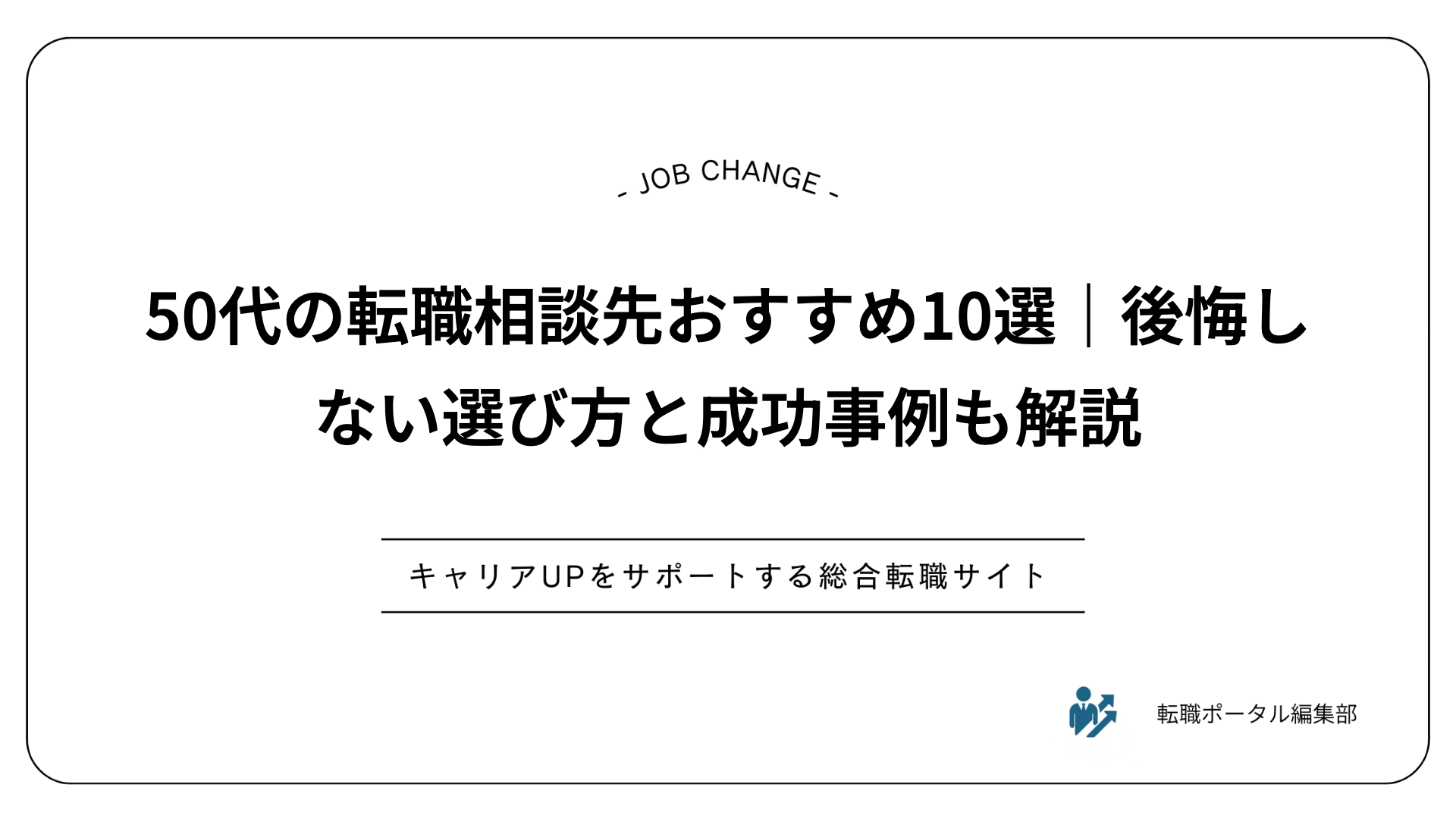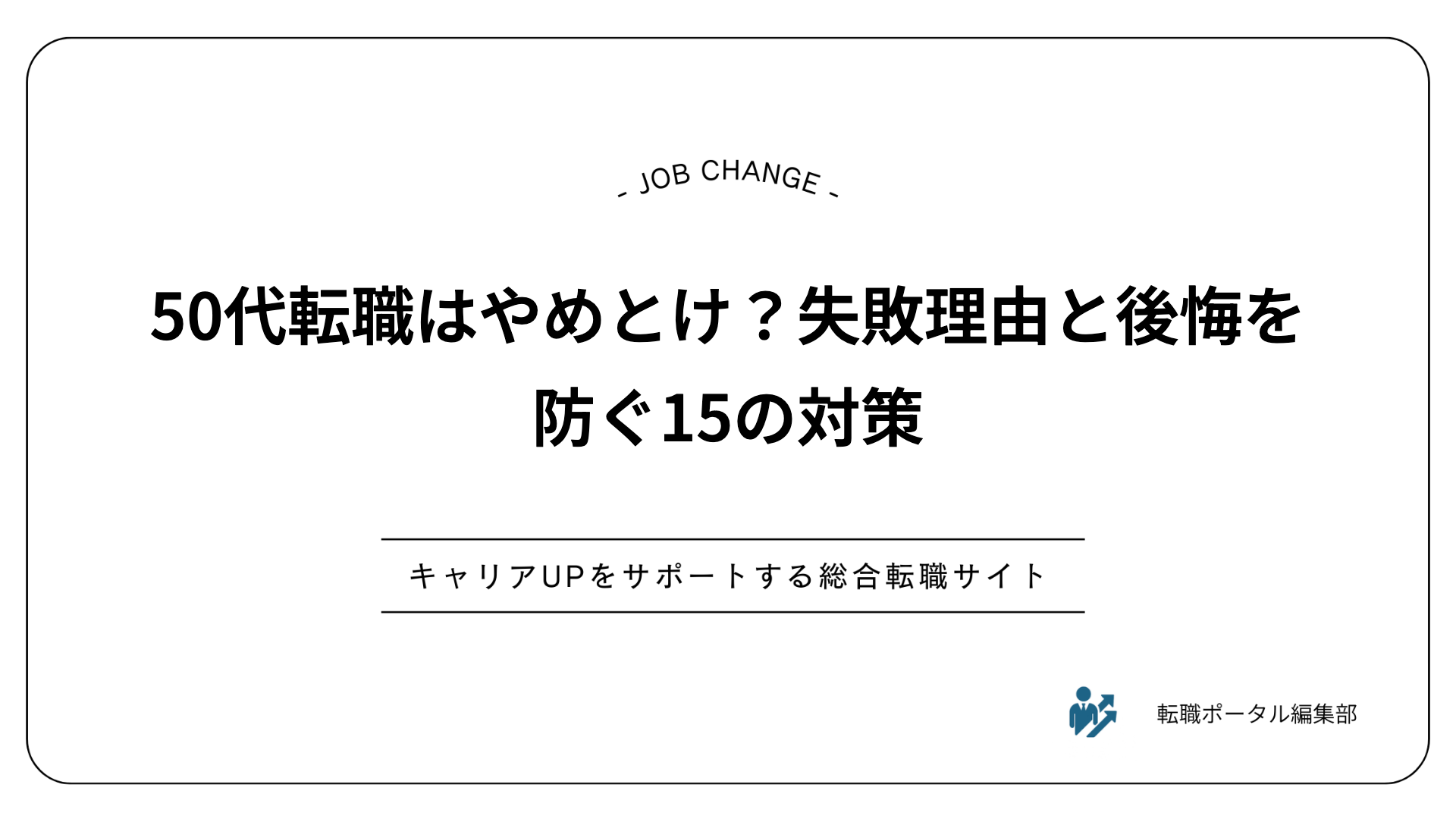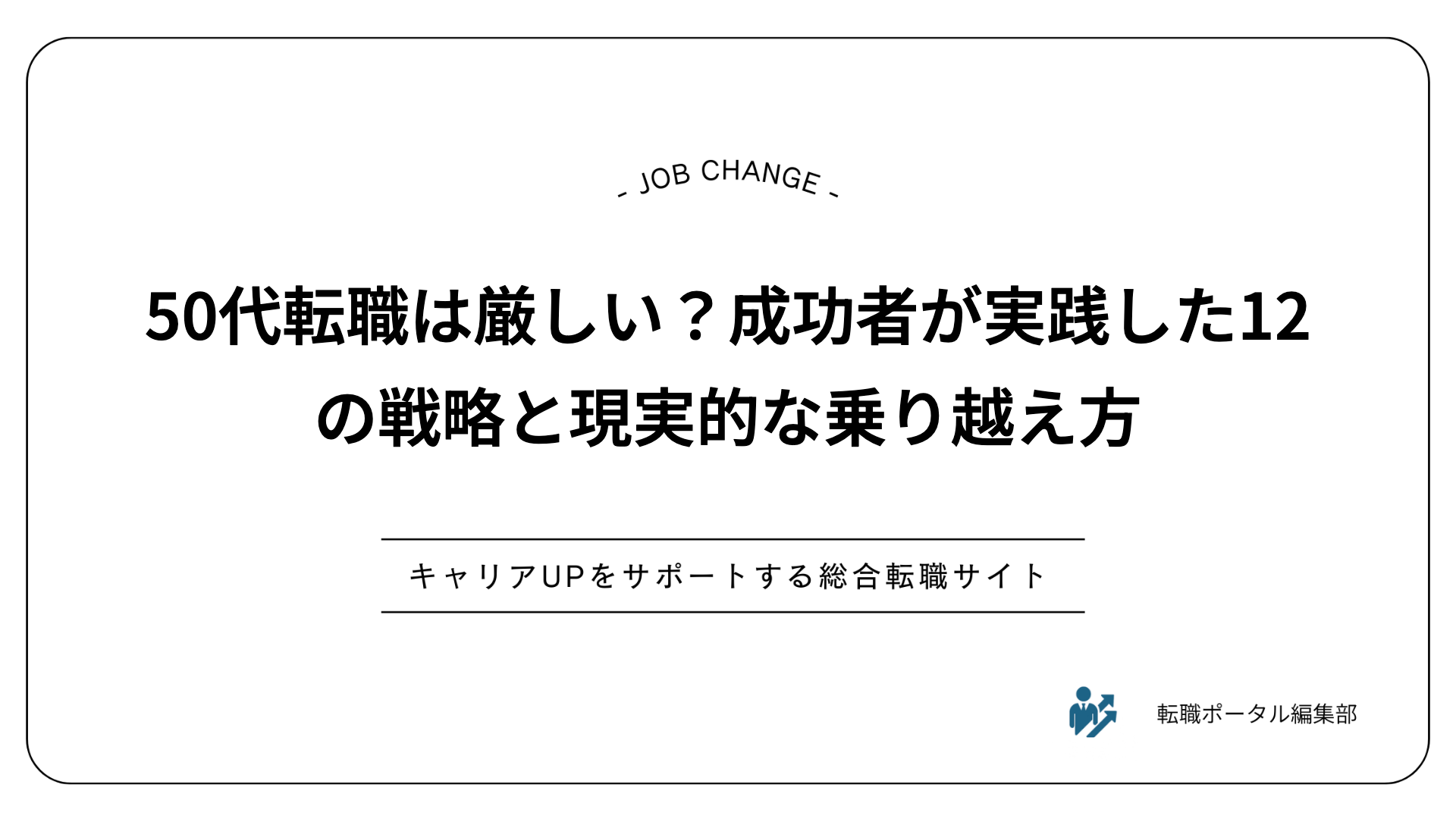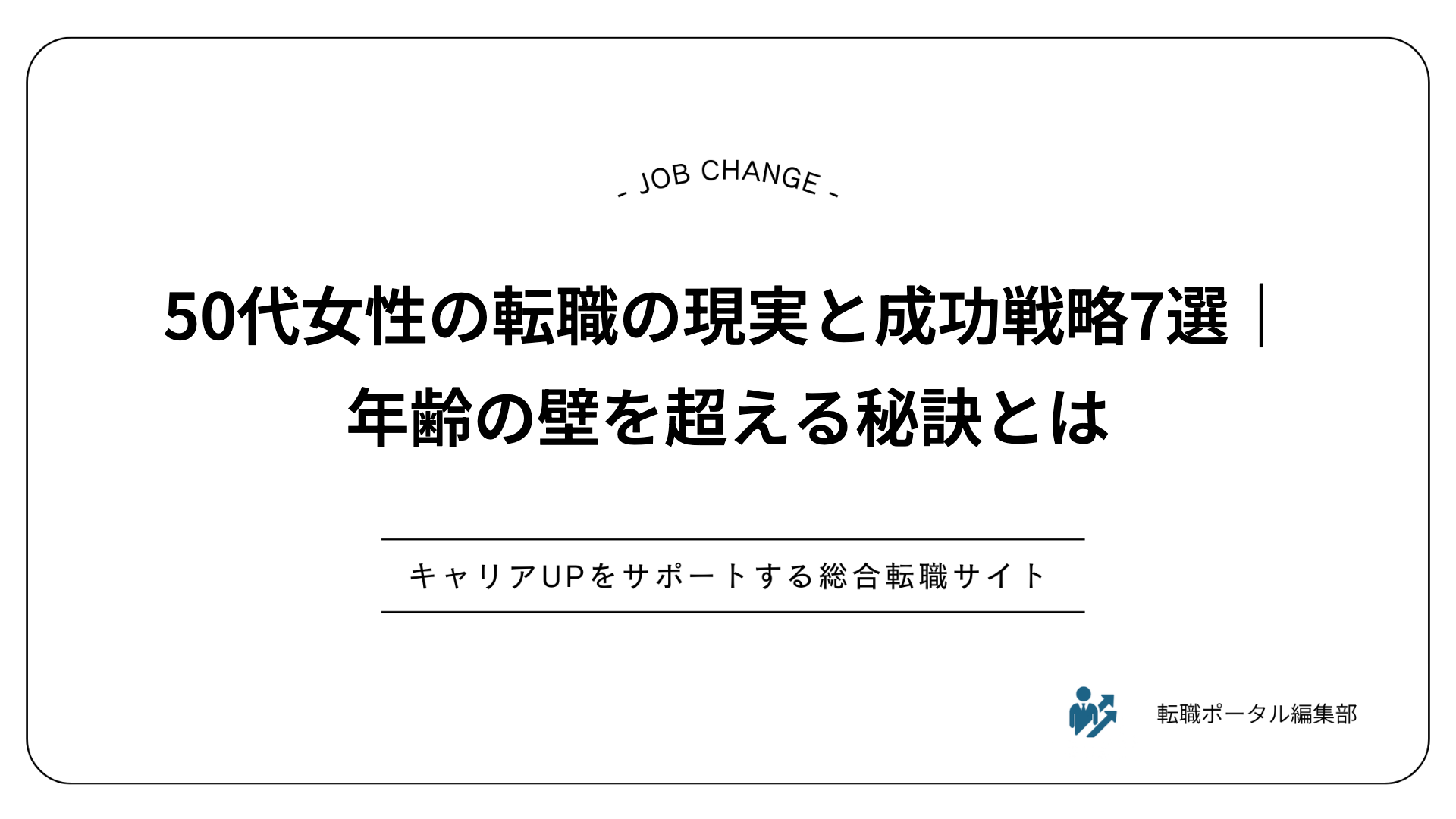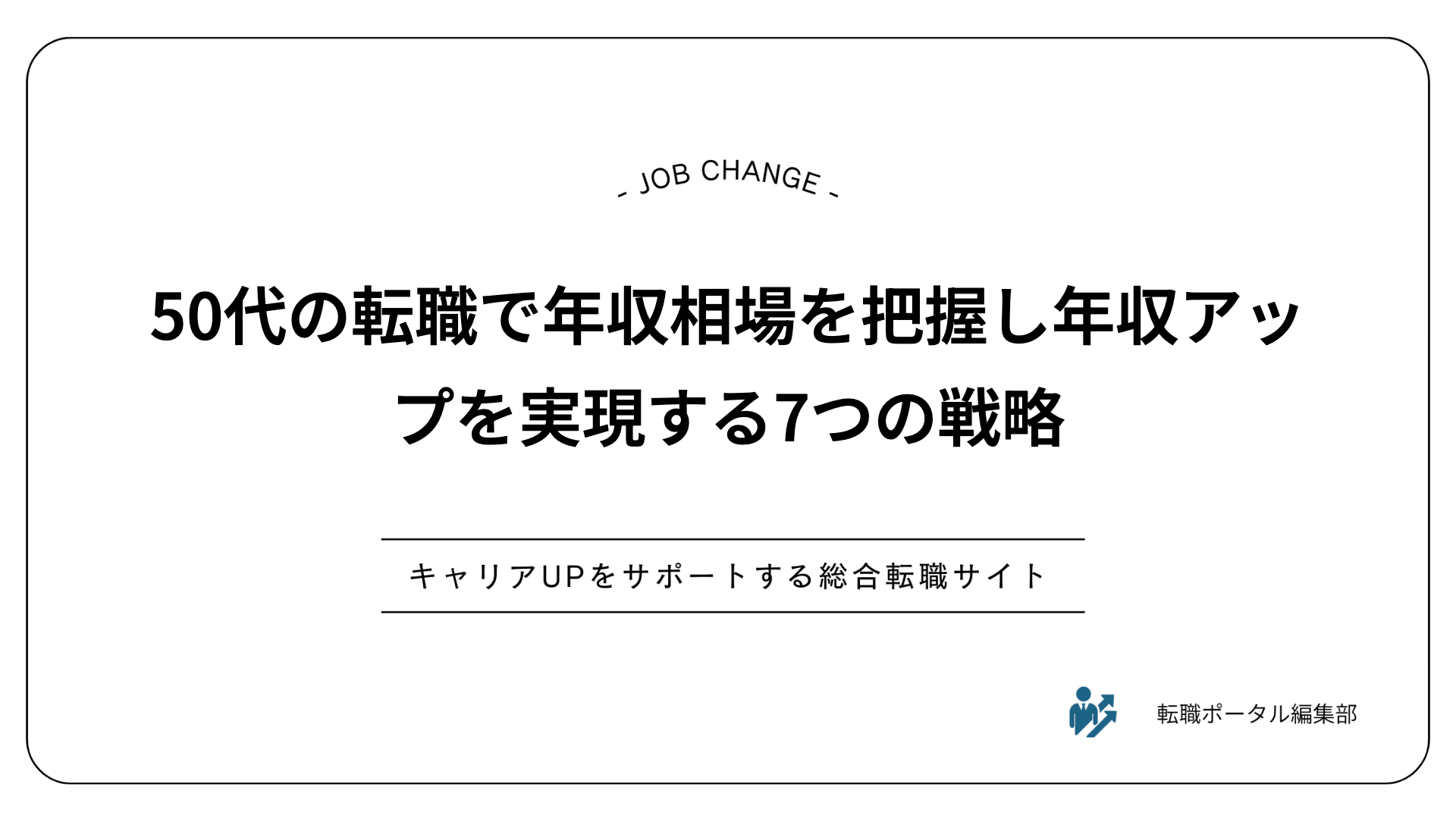50代障害者が転職で後悔しないための11の対策と支援活用術
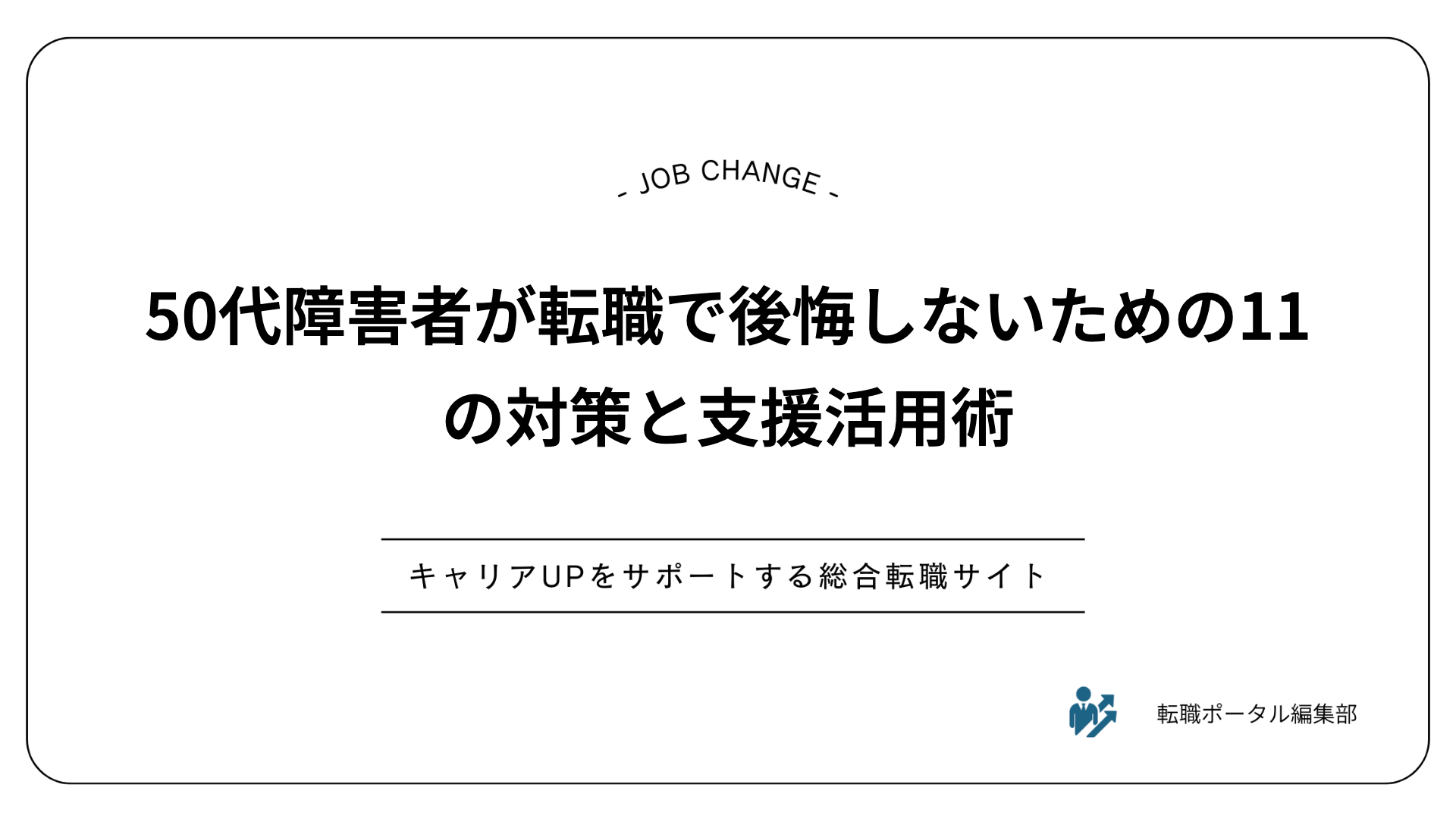
「もう50代だし、障害がある自分に転職なんて無理かもしれない…」
そんな不安を抱えている方は、あなただけではありません。
年齢や障害というハンディを理由に、求人に応募する前から諦めてしまう方も多いですが、実は今、働き方や支援制度は大きく変わってきています。
この記事では、50代障害者の方が転職で「納得のいく一歩」を踏み出せるよう、次のようなポイントを分かりやすく解説しています。
- 50代障害者に向けた最新の転職市場動向と企業ニーズ
- 転職が難しいと言われる背景と現実的な対処法
- 自己分析や求人の探し方、応募のコツ
- 成功事例や支援制度、定着の工夫までを網羅
- 無理なく働き続けるためのキャリア設計と学び直し
「年齢も障害も関係なく、自分らしく働きたい」そう思うあなたにこそ、知ってほしい情報を詰め込みました。ぜひ最後まで読んでみてください。
障害者50代の転職市場の現状
おもな求人動向と法定雇用率の最新データ

50代の障害者にとって転職は決して容易ではありませんが、希望が持てる変化も見られます。
とくに法定雇用率の引き上げと企業の多様性推進が、雇用拡大の後押しとなっています。
- 法定雇用率は2024年より2.5%に引き上げ
- 障害者雇用に取り組む企業数は毎年増加
- 精神障害者の雇用が大企業を中心に拡大
精神障害者の雇用は、2018年の改正法以降とくに伸びています。
その影響で、在宅勤務や短時間勤務といった多様な働き方が認められるようになり、年齢にかかわらずチャレンジしやすい環境が整いつつあります。
「年齢が高いから」とあきらめず、支援制度や求人の変化を味方につけることが、成功への第一歩になるでしょう。
障害種別・雇用形態別に見る就職状況
障害種別や希望する働き方によって、就職のしやすさや選べる職種に違いがあります。
身体障害の場合は事務職や軽作業が中心で、比較的安定した雇用が見込まれます。
一方、精神障害者は短時間や在宅勤務など、柔軟な働き方の選択肢が広がってきました。
知的障害の場合、特例子会社や就労継続支援を通じた雇用が中心となっています。
雇用形態に目を向けると、50代は正社員採用こそ減少傾向ですが、契約社員やパートから実績を積み、正社員へ登用される事例も珍しくありません。
年齢や障害の種別に関わらず、自身の強みと制限を正しく把握し、適切に伝えることが重要です。
50代が直面しやすい課題と企業ニーズ

50代の障害者が転職で直面しやすいのは、体力面やスキルの陳腐化といった課題です。
また、企業側が即戦力や柔軟な対応を求めるケースが多いため、ミスマッチが生じやすいのも実情です。
- 業務スピードや体力への懸念
- ITスキルや最新ツールへの対応力不足
- 年下の上司・若手社員との協働への不安
しかしながら、豊かな社会経験や責任感の強さなど、50代ならではの強みを重視する企業も少なくありません。
とくに人手不足が深刻な業界では、年齢よりも誠実さや安定感を評価する傾向があります。
弱点ばかりを気にするのではなく、自分の「価値を伝える力」を育てることが、転職成功へのカギとなるでしょう。
転職が難しいと言われる理由と背景
障害者雇用枠が限られている背景
障害者雇用枠の求人は、一般求人に比べて数が限られているのが現状です。
その背景には、法定雇用率を最低ラインとして捉えている企業が多く、それ以上の積極採用に踏み切れていないという課題があります。
また、企業側も「どのように配慮すべきか分からない」「体制を整えるコストが読めない」といった理由から、採用に慎重になるケースも少なくありません。
特に中小企業では、障害者を受け入れるための職務設計やサポート体制の構築が難しいとされています。
このような背景があるため、求人数そのものが限られ、応募先の選択肢も狭まりがちなのです。
年齢による体力・健康面の懸念
50代という年齢になると、企業はどうしても健康状態や体力への不安を抱きがちです。
たとえば立ち仕事や反復作業などでは、「継続的に勤務できるのか?」という点が判断基準になります。
また、持病や通院の頻度などがある場合には、勤務スケジュールや業務内容に配慮が必要となるため、企業側が敬遠してしまう可能性もあります。
- 通院のための欠勤や休暇への懸念
- 体調変化による勤務継続リスク
- 長期戦力としての期待のしづらさ
こうした不安に対しては、医師の診断書や職場への希望配慮事項を整理し、安心材料を提示することが有効です。
スキルギャップと即戦力期待のミスマッチ

企業が求める「即戦力」と、50代障害者が持つスキルとの間にギャップがあることも、採用が難しくなる要因の一つです。
特にIT系や事務系の職種では、ExcelやZoomなど最新のツール操作に慣れていることが求められます。
一方、50代の多くは紙ベースでの業務に慣れていたり、独自のやり方を重視する傾向があり、現代のスピード感に馴染めないこともあります。
このギャップを埋めるためには、リスキリングや職業訓練を通じて、実務に近いスキルを習得する努力が欠かせません。
「時代遅れと思われるかも」という不安は、多くの人が感じているものです。
しかし、学び直しによって評価が一変する例も多いため、挑戦する価値は十分にあります。
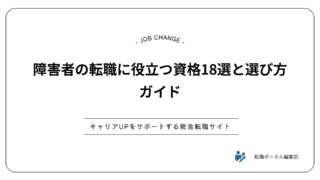
採用側が抱く50代への不安と誤解
企業が50代の障害者に対して抱く懸念には、いくつかの誤解も含まれています。
- 「若い上司と合わないのでは?」
- 「変化を嫌がりそう」
- 「教えても成長しないのでは?」
これらは実際に接してみなければ分からないものですが、履歴書や面接でこうした不安を払拭できるようにすることが重要です。
たとえば、「前職での年下上司との関係性」や「業務改善に取り組んだ経験」などを具体的に伝えることで、柔軟性や協調性をアピールできます。
先入観や固定観念を打ち破るのは容易ではありませんが、自分の強みを正しく届けることで、誤解を減らすことは十分に可能です。
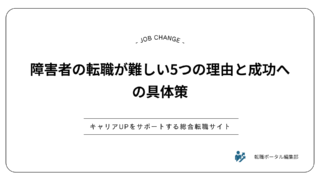
転職成功に向けた自己分析と準備
障害特性と必要な配慮の整理方法
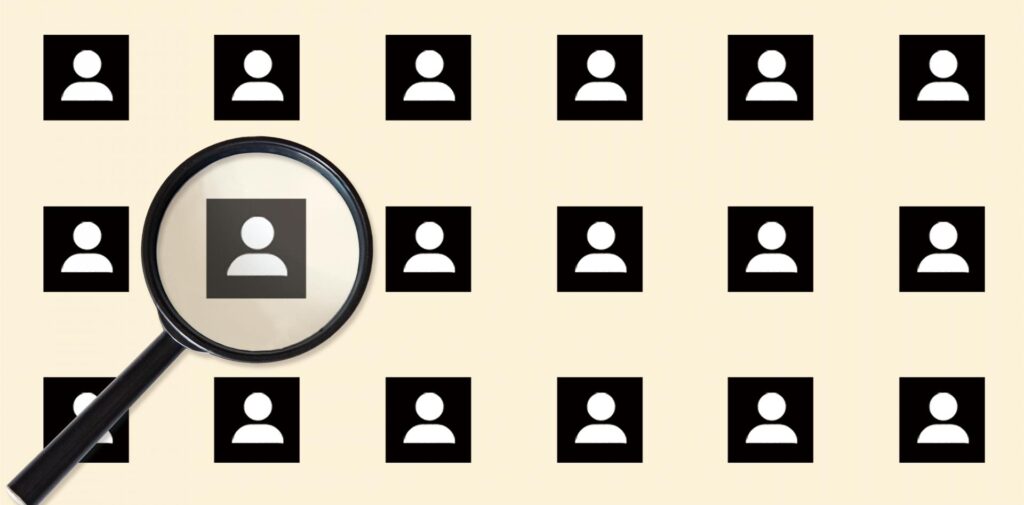
転職活動を成功させるためには、まず自分の障害特性を正確に把握し、どのような配慮が必要かを明文化することが重要です。
たとえば「長時間の集中が難しい」「大きな音に敏感」といった特性がある場合、勤務時間や職場環境に関する希望を整理しておきましょう。
これは面接時や支援機関を通じて、企業側に適切に伝える材料となります。
- 診断書や主治医の意見書の活用
- 自分でまとめた「働きやすい条件リスト」
- 過去の職場で有効だった配慮の具体例
配慮を求めることに遠慮してしまう方もいますが、無理をして働き続けることは結果的に離職につながるリスクを高めます。
自己理解を深めることが、安定就労の第一歩です。
職務経歴・スキルの棚卸しと強みの可視化
年齢に関係なく、過去の職務経験や身につけたスキルは貴重な財産です。
とくに50代は職歴が長く、内容が複雑になりがちなため、棚卸しを通じて強みを言語化する作業が必要です。
たとえば以下のように、経験を「職種・業務内容・成果・スキル」に分けて整理すると伝わりやすくなります。
- 事務職:Excelでのデータ管理、月次報告書作成
- 販売職:接客応対、クレーム対応の経験多数
- 工場勤務:品質検査・軽作業における正確性
これらを具体的なエピソードとともにまとめておくことで、職務経歴書や面接での自己PRに活かせます。
「自分には強みなんてない」と感じている方も、過去を丁寧に振り返ることで新たな魅力を再発見できるかもしれません。
働き方・雇用形態の選択肢を検討するポイント
働き方にはさまざまなスタイルがあり、年齢や障害の状況によって適した選択肢も変わってきます。
正社員にこだわらず、パートや契約社員、業務委託、在宅ワークといった柔軟な形態も視野に入れることで、働くチャンスは広がります。
以下の観点から、自分にとって無理のない働き方を検討してみましょう。
- 勤務日数・時間:週3〜5日、1日4〜6時間などの調整
- 通勤の有無:在宅勤務や近隣エリア勤務の可能性
- 社会保険加入の要件:労働時間や契約内容に応じて変化
「フルタイムじゃないと意味がない」と思われがちですが、無理なく働ける環境こそが長続きのカギになります。
自分らしいペースで働ける職場を選ぶことが、結果として職場定着や収入の安定につながるのです。
求人の探し方と応募チャネル
ハローワークを活用するコツ

ハローワークは、障害者の就職支援に特化した「専門窓口(障害者職業相談窓口)」が設けられており、50代の方でも安心して利用できます。
求人の紹介だけでなく、応募書類の添削や模擬面接、職業訓練の案内まで幅広くサポートしてもらえるのが特徴です。
- 「障害者求人」に絞った検索が可能
- 職業相談員に条件や希望を相談できる
- 応募書類や面接準備まで支援してくれる
自宅から通える範囲や勤務時間、配慮してほしい点などをあらかじめ整理して伝えると、マッチング精度も高まります。
「求人が少ない」と感じる方もいますが、通所して定期的に相談することで、非公開求人などの紹介に繋がるケースも多くあります。
障害者専用転職サイト・求人検索サービスの使い方
インターネットを活用した障害者専用の転職サイトは、近年ますます充実しています。
全国対応のサービスも多く、自宅にいながら求人情報の収集や応募ができるのが大きなメリットです。
代表的なサイトでは、職種・勤務地・雇用形態・障害種別など、細かい条件での絞り込みが可能。
エージェントが間に入ってくれる場合は、応募後のフォローや面接調整もサポートしてもらえます。
気になる求人は「お気に入り」登録しておき、複数のサイトを併用することでチャンスが広がります。
一般求人サイトでの検索テクニックと注意点

一般の求人サイトも利用可能ですが、障害者向け求人を見つけるには工夫が必要です。
- キーワードに「障害者雇用」や「就労支援」と入れる
- 雇用形態や勤務時間で絞り込みを行う
- 企業名で直接検索し、採用ページを確認する
ただし、障害者への理解や配慮の有無は、求人票だけでは見極めが難しい場合もあります。
そのため、応募前には企業の公式サイトや口コミなどを確認することも大切です。
自力での応募が不安な場合は、支援機関やエージェント経由での応募が安心です。
在宅ワーク・テレワーク求人の増加傾向
コロナ禍を契機に、在宅勤務やテレワークを導入する企業が急増しました。これは50代の障害者にとっても、大きな追い風となっています。
通勤の負担がない働き方は、体力や移動に制限のある方にとって理想的な選択肢です。
特に事務・データ入力・コールセンター業務などで在宅求人が多く見られます。
- 勤務時間の調整がしやすい
- 職場の人間関係ストレスが少ない
- 通院や体調管理との両立がしやすい
ただし、在宅勤務には自己管理能力やIT環境の整備も求められます。
面接では「自宅で業務ができる準備が整っているか」を見られるため、事前の確認と対策が必要です。
50代障害者におすすめの転職エージェント
サービス選びの比較基準とチェックポイント
転職エージェントを活用する際は、自分に合ったサービスを選ぶことが成功のカギとなります。
50代という年齢や障害の特性を考慮して、対応の丁寧さや求人の質を重視することがポイントです。
- 障害者雇用に特化した専門エージェントか
- 自分の住んでいる地域に対応しているか
- 面接対策や書類添削の支援があるか
- 50代の転職実績が豊富か
また、担当者との相性も重要です。
相談時に「安心して話せるか」「現実的な提案をしてくれるか」を見極めることで、継続的なサポートを受けやすくなります。
LITALICO仕事ナビの特徴と評判

| 運営会社 | 株式会社LITALICO |
| 求人数 | 4,797件 (2025年/12月更新) |
| 対応エリア | 全国 |
| おすすめ度 | |
| 評判 | 障害のある方の就職・転職情報を掲載し、就職サポートを提供する求人サイトです。 |
| 公式サイト | https://snabi.jp/ |
LITALICO仕事ナビは、全国対応で障害者雇用に特化した転職支援サービスです。
就労移行支援や求人紹介だけでなく、「どんな仕事が合うか分からない」といった悩みにも丁寧に向き合ってくれます。
特に以下のような特長があります:
- 職場体験・職業評価などのプログラムが充実
- オンラインでの相談や求人閲覧が可能
- 障害特性に合わせた就業先の提案が丁寧
口コミでも「初めての転職でも安心できた」「親身になってくれた」といった声が多く、特に支援慣れしていない50代にも使いやすいサービスです。
dodaチャレンジの特徴と評判

| 運営会社 | パーソルチャレンジ株式会社 |
| 求人数 | 約1,500件(公開求人) (2025年/09月更新) |
| 対応エリア | 全国 |
| おすすめ度 | |
| 評判 | 障害者の転職・就職支援でトップクラスの求人数を持ち、パーソルグループのノウハウと豊富な支援実績が高く評価されています。 |
| 公式サイト | https://doda.jp/challenge/ |
dodaチャレンジは、大手人材企業パーソルグループが運営する障害者専門の転職支援サービスです。
登録者数・求人数ともに業界最大級で、幅広い選択肢の中から求人を探せます。
50代の転職者にも対応しており、以下のような魅力があります。
- キャリアアドバイザーが1対1でサポート
- 面接の日程調整や条件交渉も代行
- 自分で求人検索するスタイルも選択可能
「ある程度のキャリアやスキルがある方」「自身の障害特性を説明できる方」にとっては、スムーズに求人応募を進められるプラットフォームです。
その他サポートが手厚いエージェント一覧
LITALICOやdodaチャレンジの他にも、50代の障害者に対応したエージェントは複数あります。
- アットジーピー(atGP)…豊富な求人と転職セミナーが魅力
- クローバーナビ…首都圏中心の求人を紹介、職種も多様
- ミラトレキャリア…職業訓練+就職支援がセットで可能
エージェントごとに得意分野や対応地域が異なるため、2〜3社を併用して比較検討するのがオススメです。
複数登録しておくことで、相性の良い担当者に出会える確率も高まり、納得のいく転職活動につながります。
50代の障害者の方におすすめの転職エージェント・サイトは以下でまとめています↓
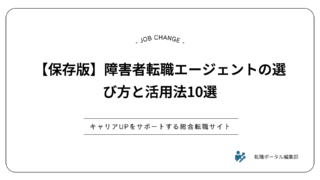
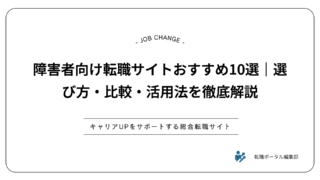
支援機関・制度の活用
就労移行支援事業所を利用するメリット
就労移行支援事業所は、障害のある方が一般就労を目指すための訓練やサポートを受けられる施設です。
50代でも利用可能で、職業スキルの習得やビジネスマナーの学び直しに役立ちます。
- 職場実習や模擬就労で実践力が身につく
- 個別支援計画に基づき、無理のないペースで進められる
- 支援員のサポートにより就職後の定着支援も充実
利用は原則2年間ですが、就職が決まるまで支援を受けられるため、ブランクのある方やスキルに自信がない方にも適しています。
障害者就業・生活支援センターのサポート内容
地域に設置されている「障害者就業・生活支援センター(ナカポツセンター)」は、就労と生活の両面をサポートしてくれる機関です。
50代で転職を目指す際にも、仕事と暮らしを両立するための相談ができます。
具体的には、職場との調整、通勤・生活リズムの安定支援、福祉サービスとの連携など、多方面から支えてくれます。
就労移行支援と併用するケースも多く、地域密着型の支援が特徴です。
自立訓練・リワークデイケアでできること

自立訓練(生活訓練)やリワークデイケアは、就職する前に日常生活のリズムを整えたり、職場復帰への準備を整えるための支援です。
- 生活リズムの安定や対人コミュニケーション訓練
- グループワークを通じた自己理解・ストレス対処力の向上
- 復職後の再発防止を目的とした定期支援
「まだ働ける状態ではないけれど、準備は始めたい」という方には特におすすめです。段階的な回復・準備を進めることで、就労への不安も軽減されます。
各種助成金・給付金の概要と申請手順
障害者が転職・就職する際には、活用できる助成金や給付金制度も存在します。
たとえば「特定求職者雇用開発助成金」や「職場適応援助者(ジョブコーチ)制度」などは、企業が障害者を雇用する際の負担を軽減する制度です。
一方、個人が利用できる制度としては、職業訓練受講給付金や障害年金との両立支給などがあります。
申請にはハローワークや福祉窓口との連携が必要になるため、事前に手続きの流れを確認しておきましょう。
こうした支援制度は、知っているだけで選択肢や就職後の安定性が大きく変わる可能性があります。
面接・職場定着のポイント
障害の開示タイミングと伝え方のコツ

面接時に障害についてどこまで、いつ伝えるべきか悩む方は多くいます。
結論から言えば、「応募時に開示する」のが一般的であり、企業側もそれを前提に採用可否を判断することがほとんどです。
伝え方のポイントは、「できないこと」よりも「配慮があればできること」に焦点を当てることです。
- 診断名よりも「日常で困る場面」と「対応策」を具体的に説明
- 職務に支障のない範囲で働けることを示す
- 過去の成功体験や適応事例も添えて伝える
一方で、障害の内容が業務に大きく影響しない場合は、採用後に必要なタイミングで開示するという選択肢もあります。
状況に応じて、支援者やキャリアアドバイザーと相談しながら判断しましょう。
年下上司との関係構築テクニック
50代で転職すると、配属先の上司が自分より年下というケースは珍しくありません。
年齢差に抵抗を感じる方もいますが、良好な関係を築くには「対等な同僚としての姿勢」が重要です。
謙虚な態度を持ちつつ、過度に卑屈にならず、「教えてもらう」「協力する」というスタンスを取ることで、信頼関係を築きやすくなります。
また、仕事の進め方に違いを感じたときは、感情的にならず、事実ベースで丁寧に話すことが効果的です。
価値観のギャップは対話で埋めることができるのです。
体力・健康面の自己管理と職場配慮の例
50代では、体力の衰えや持病の影響などもあり、継続的に働くには自己管理が欠かせません。
企業側に理解を求めると同時に、自分自身の体調管理にも意識を向ける必要があります。
- 定期的な通院・服薬スケジュールの管理
- 睡眠・食事・運動による基礎体力の維持
- 疲労時のセルフケア方法を持っておく
職場での配慮例としては、「午後に集中する作業を避ける」「静かな環境の席にしてもらう」などが挙げられます。
小さな配慮でも大きな安心感につながるため、必要に応じて遠慮せず伝えましょう。
定着率を高める入社後フォローの活用法
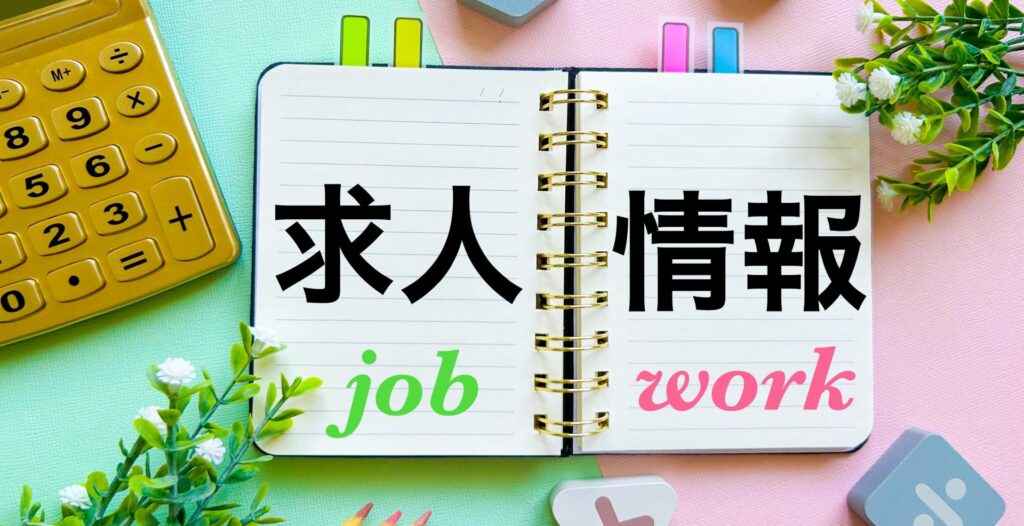
せっかく採用されても、数ヶ月で離職してしまうケースは少なくありません。
長く働き続けるためには、「職場定着支援」の制度やサポートを活用することが有効です。
就労移行支援事業所やエージェントの中には、就職後も定期的に面談を行い、困りごとがあれば仲介や助言をしてくれるところがあります。
こうしたサポートを受けることで、孤立せず安心して働き続けられるようになります。
一人で抱え込まず、支援者を味方に付けることで、職場との関係もより安定したものになるでしょう。
転職成功事例・体験談
事務職に転職した50代身体障害者の事例
Aさん(53歳・下肢障害)は、前職での製造業勤務を退職後、約1年のブランクを経て事務職への転職を実現しました。
転職活動ではハローワークの障害者窓口とdodaチャレンジを併用し、週3日のパート勤務からスタート。
- 通勤時のバリアフリー設備が整った企業を選択
- Excel・Wordの基礎操作を職業訓練校で再学習
- 「正確な事務処理能力」と「勤怠の安定性」が高評価
現在は週5日の契約社員として勤務中で、上司や同僚との人間関係も良好。
勤務形態の相談にも柔軟に対応してくれる企業文化に支えられ、長期的に働ける見通しが立っています。
精神障害を持つ50代女性の在宅ワーク事例

Bさん(56歳・うつ病の診断あり)は、長年の療養生活を経て在宅での仕事を希望。
就労移行支援事業所でPCスキルを習得し、障害者専門求人サイトを通じてWebライターの仕事に応募しました。
業務は完全在宅で、記事の執筆やリライト業務を週20時間のペースで実施。
勤務時間や納期に柔軟性があるため、体調の波とも調整しながら働けています。
「朝起きて仕事がある生活が嬉しい」「無理せず社会とつながれる」という実感が自信につながっており、継続的な収入源としても安定しつつあります。
スキルチェンジで年収アップした50代男性の事例
Cさん(54歳・聴覚障害)は、流通業界での勤務経験を活かし、IT分野へのキャリアチェンジを果たしました。
きっかけはオンラインで受講した職業訓練講座で、基本的なプログラミングスキルを習得。
- 障害者雇用枠での社内SE職に応募
- チャットやメールでのコミュニケーション環境が整備されていた
- 研修期間中にOJTを通じて業務習得
年収は前職比で120万円以上アップ。通院や補聴器利用の事情もきちんと受け入れてくれる企業風土で、安心して長期勤務できる環境が整っています。
長く働くためのキャリアプランと学び直し
60歳以降も見据えたキャリア設計
50代での転職は、単なる「再就職」ではなく、「今後10年以上をどう働くか」を見据えたキャリア設計が重要です。
特に定年延長や再雇用制度が進んでいる今、60歳以降も働き続けることが現実的な選択肢になりつつあります。
体力や家庭状況を踏まえ、フルタイムから短時間勤務への移行や、専門スキルを活かした顧問・サポート業務へのシフトも選択肢となります。
無理をせず、自分の「働き続けられるかたち」を早めに描いておくことが、安心につながります。
リスキリング・資格取得の選び方

新しい分野に挑戦したい、あるいは自分の価値を高めたいと感じる方にとって、リスキリング(学び直し)は有効な手段です。
50代でも遅すぎることはなく、今はオンラインで学べる環境が整っているため、柔軟に取り組むことが可能です。
- MOS(Excel・Word)などのPC系スキル
- 医療事務・福祉住環境コーディネーターなどの事務・福祉系資格
- WEBライティング・SNS運用などの副業向けスキル
ポイントは「資格の難易度」よりも、「求人ニーズがあるかどうか」を基準に選ぶこと。
独学が不安な場合は、就労移行支援事業所や職業訓練も活用してみましょう。
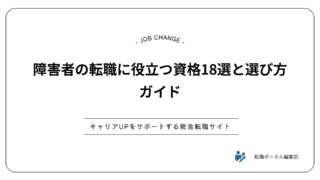
障害者雇用の定年制度と継続雇用の選択肢
多くの企業では定年を60〜65歳に設定しており、その後は再雇用制度により継続勤務が可能となるケースが増えています。
障害者雇用においても、この仕組みが適用されることがほとんどです。
ただし、雇用契約の内容や待遇は企業によって異なるため、早い段階で「定年後どう働き続けたいか」を考えておくことが大切です。
定年を前に一度退職し、新たに「年齢不問の職場」を探す人もいます。
転職エージェントや支援機関に相談しながら、自分に合った働き方を設計していきましょう。
よくある質問(FAQ)
障害者雇用は何歳まで可能?

年齢制限について明確な上限はありません。法律上も「障害者だから◯歳まで」という規定はなく、企業ごとの定年や就業規則に従うことになります。
実際には60代前半までの採用実績もあり、職種や勤務形態によっては70代まで働いている例も存在します。
年齢よりも「健康状態」と「業務に対する適応力」が評価されることが多いため、自信を持って応募してみてください。
障害者手帳がなくても利用できる支援は?
一部の支援機関や転職エージェントでは、医師の診断書や紹介状があれば相談可能なケースもあります。
- 精神科や心療内科での通院歴がある場合
- 就労移行支援の体験利用
- 一般求人への応募+面接での合理的配慮申請
ただし、障害者雇用枠の求人に応募する場合は、障害者手帳の提示が必須となるため、取得を検討している方は自治体の窓口で相談してみましょう。
転職エージェントは複数利用すべき?
はい。複数のエージェントを併用することをおすすめします。それぞれ得意分野や保有求人が異なるため、自分に合った求人に出会える確率が高まります。
また、担当者との相性も重要なため、「この人なら相談しやすい」と思えるエージェントに出会うまでは、遠慮せず比較してみてください。
就労移行支援と転職エージェントの違いは?
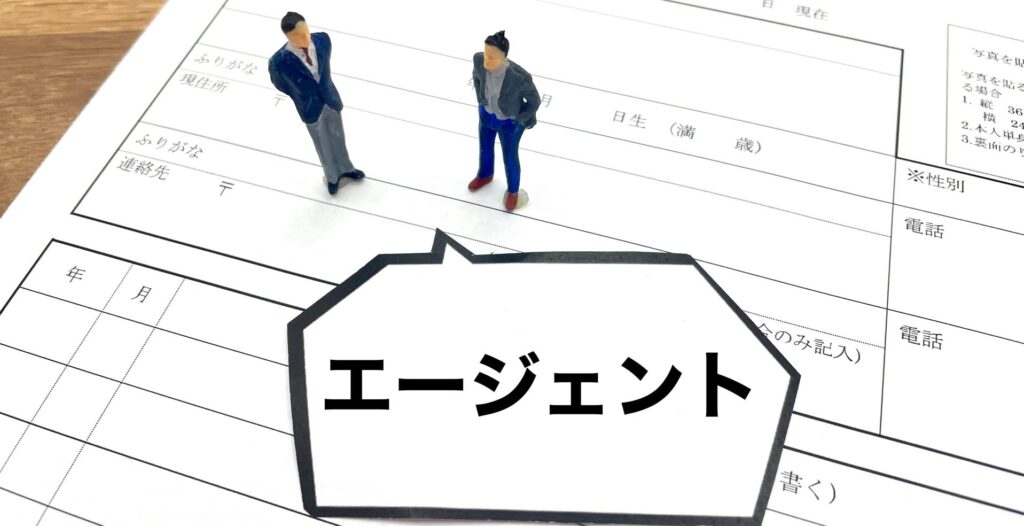
両者は支援の目的と内容が異なります。
- 就労移行支援:働くためのスキルや生活習慣を整える「訓練重視型」
- 転職エージェント:希望に合う求人の紹介や面接サポートを行う「就職支援型」
どちらが良いかは現在の状況によって異なります。ブランクが長い方や体力に不安がある方は、まず就労移行支援から始めると安心です。
まとめ:50代障害者でも「選ばれる人材」になれる時代
50代の障害者にとって、転職は決して簡単ではありません。
しかし、制度の整備や多様な働き方の広がりにより、「今からでも十分に選ばれる存在」になれるチャンスがあるのです。
そのためには、自分の強みや課題を正しく理解し、支援機関や転職エージェントを上手に活用することが不可欠です。
年齢や障害という条件だけで自ら選択肢を狭めるのではなく、現実的に「働けるかたち」を一緒に探す姿勢が重要になります。
- 法定雇用率の上昇と障害者雇用枠の拡大により、求人の選択肢が広がっている
- ハローワーク・転職エージェント・就労移行支援など、年齢に関係なく使える支援が豊富
- 自己分析と配慮事項の整理により、ミスマッチを防ぎながら働きやすい職場を見つけやすい
- 在宅ワークや短時間勤務など、50代に適した働き方の選択肢が増えている
- 年齢や障害の不安は「誠実な姿勢」と「準備」で乗り越えられる
「今さら転職なんて遅い」と思っている方こそ、一歩踏み出して情報を集めてみてください。
年齢や障害の有無にかかわらず、自分に合った働き方がきっと見つかります。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
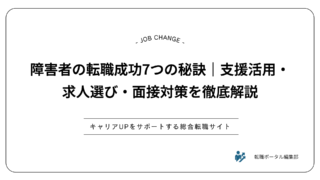
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓