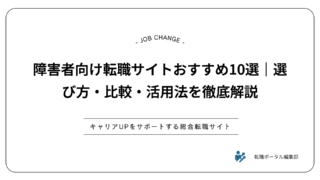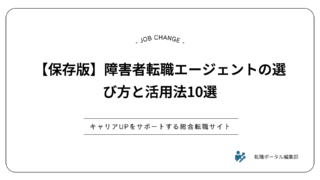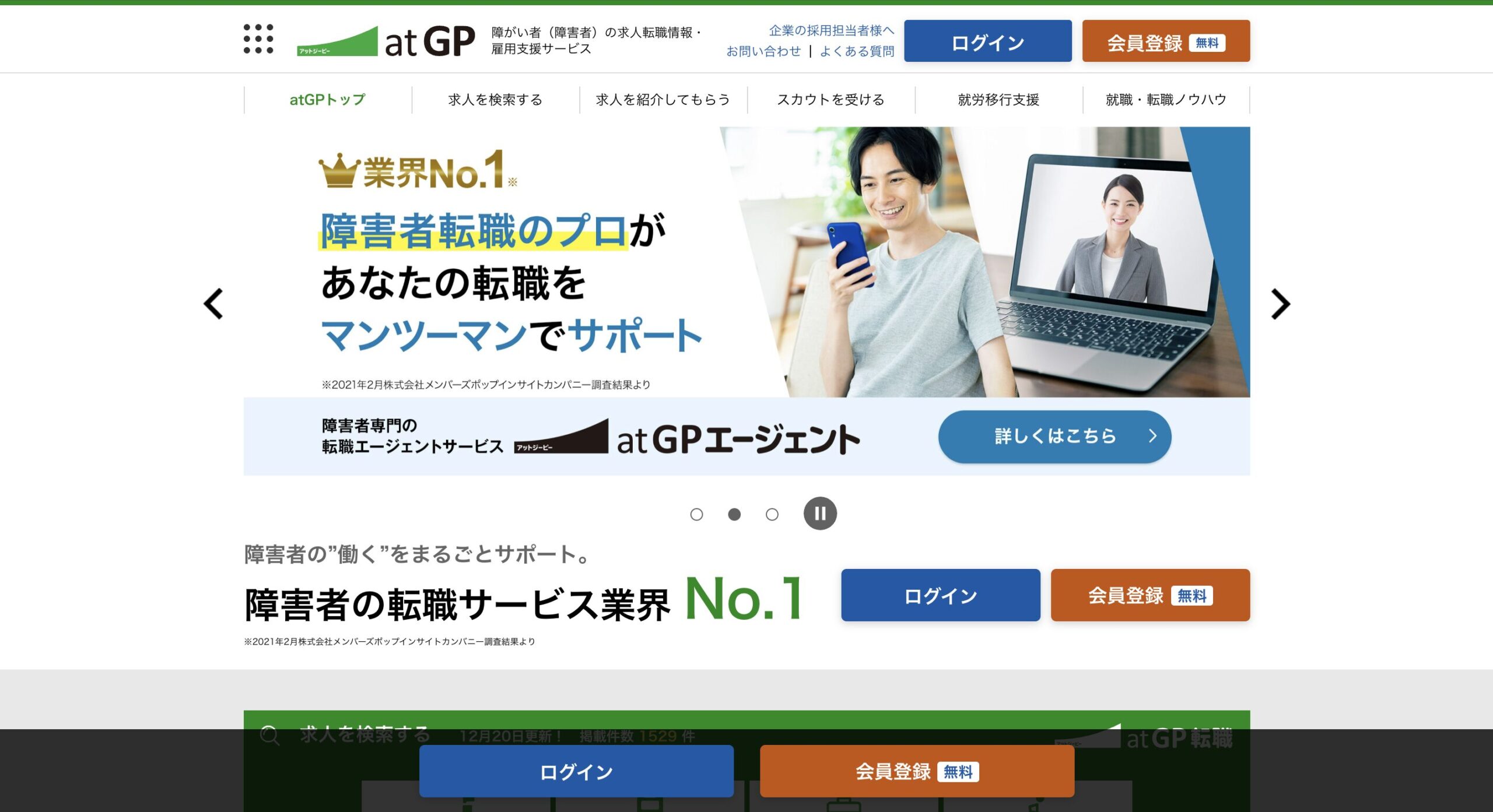40代障害者の転職成功術|今すぐ使える17の実践ポイント
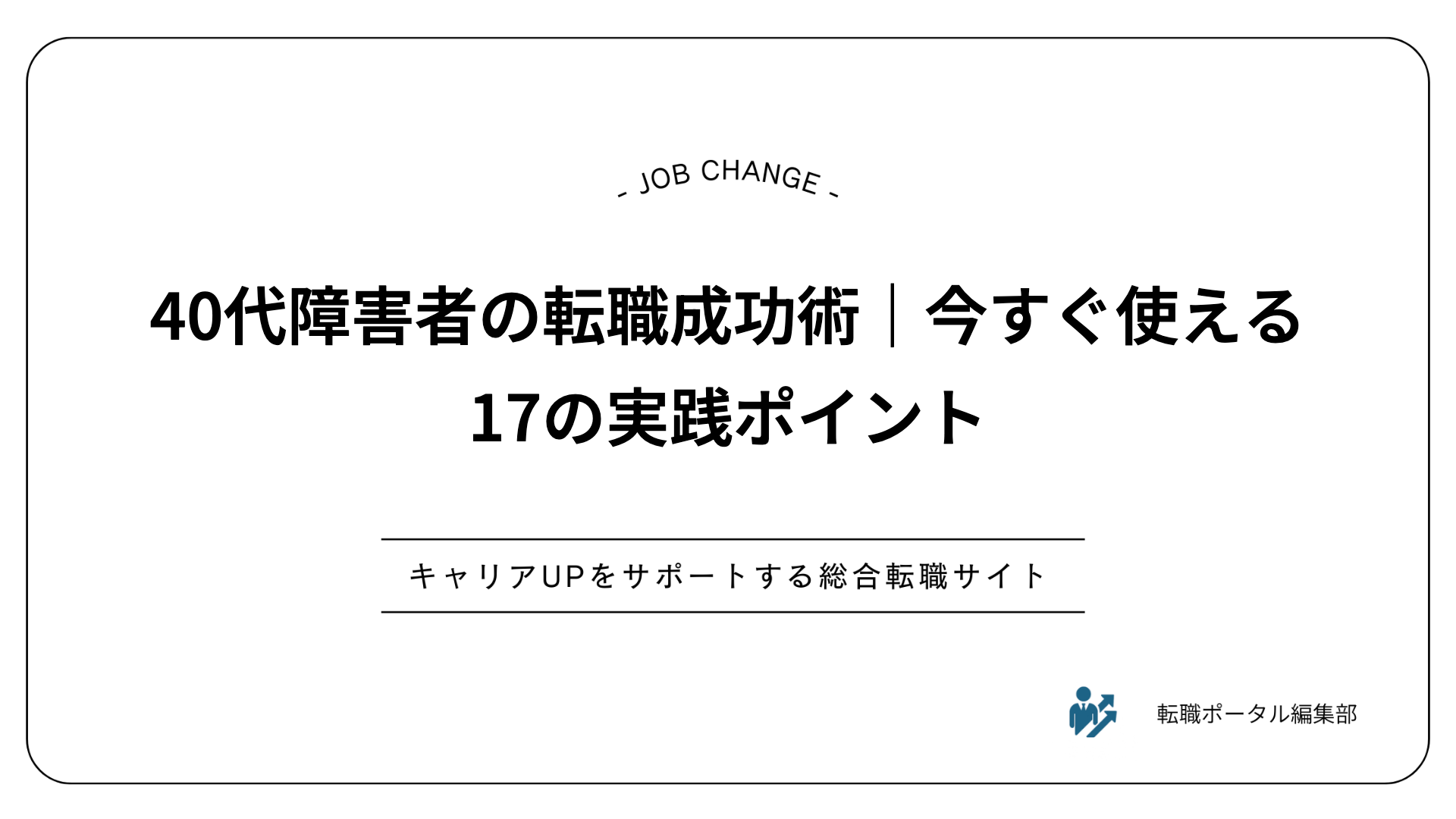
「40代からの転職は難しい」「障害があると選べる仕事が限られてしまう」――そんな不安を感じていませんか?
年齢や障害の有無によって、求人の選択肢が狭まるのではと心配になるのは当然のことです。
しかし、最近では障害者雇用に前向きな企業が増え、働き方の選択肢も広がっています。
実は、40代だからこそ活かせる経験やスキルも多く、しっかりと準備を重ねれば、自分に合った職場に出会うことは十分に可能です。
この記事では、以下のような悩みや疑問を解消する具体的な方法を紹介しています。
- 障害と年齢を理由に書類選考で落ちてしまう
- どの業界・職種なら働きやすいか分からない
- 企業に障害や配慮事項をどう伝えるべきか迷っている
- 支援サービスや制度をどう活用すればよいか知りたい
不安を自信に変えるヒントを、経験・実績・支援の3つの視点からお届けします。
転職市場の現状と障害者雇用の最新動向
障害者雇用促進法と法定雇用率の改定ポイント

結論から言うと、障害者の雇用機会は年々拡大傾向にあります。
背景には、障害者雇用促進法の改正と法定雇用率の引き上げがあり、企業側の受け入れ体制も整いつつあります。
- 法定雇用率は2024年4月より2.5%に引き上げ(2026年には2.7%予定)
- 従業員43.5人以上の企業に雇用義務がある
- 合理的配慮や設備導入に対する助成金が拡充されている
このような制度改定により、企業は障害者の採用を「義務」から「戦力としての活用」へと認識をシフトし始めています。
「自分には雇用枠がないのでは…」という不安を抱える方も多いですが、制度の後押しがある今こそが動き出す好機です。
求人が増えている業界・職種と募集傾向
現在、障害者採用が活発な業界としては、IT業界や製造業、医療福祉分野が挙げられます。
これらの業界は、配慮体制や職種の多様性に加え、柔軟な勤務形態を取り入れている点が魅力です。
- 在宅勤務が可能なIT・Web業界
- 身体障害に配慮した作業環境が整った製造・軽作業
- 精神障害者や知的障害者も働きやすい事務・庶務職
- やりがいのある福祉・医療現場
特に最近では「週3日勤務」「時短勤務」など、働き方に柔軟性を持たせた求人が増えており、採用側も応募者の事情に理解を示す姿勢を強めています。
選択肢が限られていると感じている方も、自分の特性に合った業界に視野を広げることで、思わぬ好条件に出会える可能性があります。
年齢と障害がハードルになる背景を理解する
年齢による選考基準と企業側の視点

40代という年齢は、転職市場において「即戦力」としての期待が高まる一方で、採用に慎重になる企業も少なくありません。
企業側が懸念するポイントとしては以下のような点が挙げられます。
- 柔軟性に欠けるのではないかという先入観
- 業務内容や組織風土への適応に時間がかかる可能性
- 給与やポジションに対する希望が高いというイメージ
しかしながら、40代には「管理経験がある」「実務に精通している」などの強みがあり、障害に関する配慮を明確に伝えられる方は、企業からの信頼を得やすい傾向にあります。
年齢がネックになるのでは?と不安に思う方も、実は職務経歴の整理と自己PRの工夫次第で大きく印象を変えることが可能です。
スキルと職務経験のミスマッチを乗り越える方法
転職活動で壁となりやすいのが、「これまでの経験と求人内容のミスマッチ」です。
特に異業種への転職を目指す場合、このハードルは高く感じるかもしれません。
このミスマッチを乗り越えるには、以下のアプローチが効果的です。
- 過去の経験を「業界共通のスキル」に言い換える
- 数値で実績を示し、成果としてアピールする
- 未経験分野に対する学習姿勢を見せる
たとえば、事務職の経験がある方であれば、「調整力」「正確性」「データ処理スキル」などは多くの職種に通用します。
また、「働きながらPCスキルを習得中」など学習中の内容もアピール材料になります。
ミスマッチを理由に諦めるのではなく、視点を変えて自分の強みを再構成することで、選考通過の確率は確実に上がります。
成功へ導く九つのポイント
障害特性と必要な配慮を言語化する
転職活動では、障害の内容や働くうえで必要な配慮を明確に伝えることが重要です。
これにより、企業側が職場環境を整えるための判断がしやすくなり、ミスマッチの防止にもつながります。
たとえば、診断名や症状の特徴、業務中に困るシーン、それに対して必要な支援内容を具体的に説明できると、企業側の理解が得やすくなります。
「障害があること」自体ではなく、「どのような働き方で能力を発揮できるか」を伝える視点が大切です。
実績を具体的な数字で示して即戦力をアピール

企業は年齢に関わらず、「入社後すぐに活躍できる人材」を求めています。
そのため、過去の実績やスキルを数値や成果で明確に伝えることが、採用担当者の信頼を得る鍵となります。
- 売上を前年比120%に拡大
- 業務改善で作業時間を30%削減
- 3年連続で表彰を受けた
単なる作業経験の羅列ではなく、「結果を出せる人材」であることを伝える姿勢が重要です。
障害のある方でも、適切な環境と支援があれば十分に実績を出せることを、具体的に示すことで選考通過の可能性が高まります。
柔軟な働き方の提案で企業ニーズに合わせる
希望する働き方がある場合、すべてを一方的に提示するのではなく、企業側と協調できる柔軟性を見せることがポイントです。
たとえば「午後からの勤務を希望するが、繁忙期にはフルタイムも検討できる」など、対応可能な範囲を具体的に示しましょう。
企業側も、柔軟な人材には前向きに検討する傾向が強くなっています。「相互理解と歩み寄りの姿勢」が、採用への一歩となるのです。
資格取得や学習で専門性を高める

転職市場において、資格やスキルの有無は選考結果を左右する大きな要素です。
特に40代からの転職では、実務経験に加えて「今も学び続けている姿勢」が評価されるケースが増えています。
たとえば、以下のような学習や資格取得が有効です。
- MOSや日商簿記などの事務系資格
- 障害者雇用に強い「職業訓練校」でのスキル習得
- プログラミングやデザインなどのオンライン講座
また、独学だけでなく、ハローワークの職業訓練や就労移行支援事業所のカリキュラムを活用することで、体系的に学べる環境も整います。
「資格がないから不利」と諦めるのではなく、「これからでも取得可能な資格」を戦略的に選ぶことで、応募書類や面接でも説得力を持たせられます。
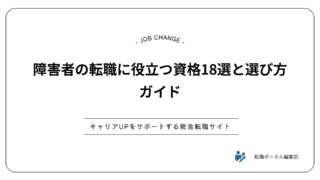
ハローワークや就労移行支援を積極的に活用する
障害者向けの転職活動では、「ひとりで抱え込まない」ことが何より大切です。
そのためには、行政や支援機関のサービスをフルに活用することが重要です。
ハローワークには専門の「障害者窓口」が設置されており、担当者による職業相談や求人紹介、応募書類の添削などを無料で受けられます。
また、就労移行支援事業所では、ビジネスマナーやPCスキルの習得、模擬面接など実践的な支援が提供されます。
自力でうまくいかないと感じたときは、早めにプロの力を借りることで、結果的に早期就職や定着につながるケースも少なくありません。
応募書類と面接で配慮事項をポジティブに伝える
障害に関する配慮を伝える際、どうしても「ネガティブに捉えられるのでは」と不安になる方が多いです。
しかし、伝え方次第で「前向きな自己開示」として企業から高評価を得ることが可能です。
たとえば、次のような伝え方が効果的です。
- 「~という特性があるため、○○のような配慮をいただければ業務に集中できます」
- 「過去の職場では△△の工夫を行い、安定して勤務できました」
重要なのは、「できないこと」を強調するのではなく、「こうすれば力を発揮できる」という視点で伝えることです。
また、障害の程度や症状については正確に、かつ簡潔に説明し、必要に応じて診断書や主治医の意見書なども準備しておくと安心です。
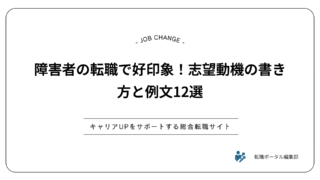
在職中から準備を始めてブランクを防ぐ

転職活動は、退職後に始めるよりも、在職中に情報収集や自己分析を進めておくことで、精神的・経済的な余裕を持って進めやすくなります。
特に40代は、家計や家族との兼ね合いも大きいため、ブランクが長引くことで焦りや迷いが生じやすい年代です。
以下のような準備を在職中から始めると、スムーズに転職活動をスタートできます。
- 履歴書・職務経歴書の作成と見直し
- 転職エージェントとの初回面談
- 希望条件や配慮事項の整理
ブランクを最小限に抑えるためにも、余裕のある時期からの準備をおすすめします。
企業の受容度・サポート体制を見極める
障害者雇用に力を入れている企業ほど、「入社後の配属先での支援体制」や「相談できる担当者の有無」などが整っています。
企業研究の段階で以下のような点を確認しておくと、自分に合った環境かどうかを見極めやすくなります。
- 障害者雇用実績や定着率
- 障害者支援を行う部署・担当者の有無
- 合理的配慮の事例や柔軟な勤務制度
求人情報だけでは分からないことも多いため、面接時の質問や口コミ、エージェントの意見も参考にしましょう。
「採用されたけど働き続けるのが難しかった」とならないために、事前の見極めはとても大切です。
定着支援と長期的なキャリア形成を視野に入れる

転職はゴールではなく、新しい職場で長く安定して働くことこそが本当のスタートです。
そのためには、入社後のフォロー体制や定着支援の有無を事前に確認しておくことが重要です。
たとえば、定着支援のある事業所やエージェントを利用することで、以下のような支援を受けることができます。
- 定期的な職場訪問や本人・上司との面談
- 困りごとのヒアリングと改善策の提案
- 体調面・人間関係に関するアドバイス
また、40代という年代は「今後10年・20年どう働くか」を考えるタイミングでもあります。
目の前の仕事だけでなく、「スキルアップ」「ライフスタイル」「体調とのバランス」なども含めて中長期のキャリア設計をすることが、より良い定着と満足度の高い転職につながります。
まずは数年先を見据えた目標を立てることから始めてみましょう。
転職活動を進める具体的ステップ
自己理解とキャリアの棚卸しを行う
転職活動のスタートは、これまでの自分を整理することから始まります。
特に40代は、過去の経験が豊富な分、強みと弱みを冷静に見つめ直す作業が欠かせません。
- どの仕事でやりがいを感じたか
- どんな支援があればパフォーマンスが安定したか
- 体調や家庭の事情を踏まえた理想の働き方
自分の価値観や環境要因を明確にしておくことで、「自分に合う会社」を見極める軸ができ、応募先選びにブレが生じにくくなります。
求人サイトと検索エンジンの活用術
求人を探す際は、障害者向けの専用サイトだけでなく、一般の転職サイトや検索エンジンも併用することで、幅広い情報に触れることができます。
たとえば、「週3勤務 在宅 精神障害者」といった具体的なワードを組み合わせて検索することで、自分の希望にマッチした求人にたどり着けることもあります。
また、atGPやdodaチャレンジのように、障害者専門の転職支援サービスでは、面接前の相談や条件交渉の代行も受けられるため、安心して活動を進めることができます。
転職エージェントの選び方と連携方法
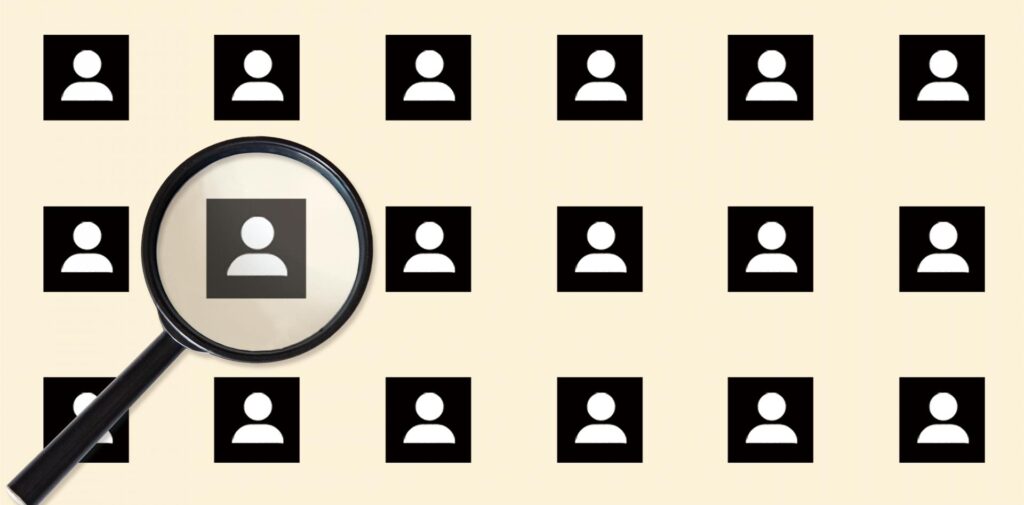
転職活動を効率的かつ安心して進めるためには、自分に合った転職エージェントの活用が鍵となります。
特に障害者雇用に理解のあるエージェントを選ぶことで、配慮事項の伝達や職場選びの不安を大幅に軽減できます。
- 障害者雇用に特化した実績があるか
- 対応が親身で、無理な応募をすすめてこないか
- 障害の特性や職場環境のヒアリングが丁寧か
また、連携する際は「自分ができること」「できないこと」「希望条件」を最初にしっかり伝えることが大切です。
エージェントは「代理交渉役」でもあるため、情報が明確であるほど、企業とのマッチングもスムーズに進みます。
面談時に違和感があれば、複数のエージェントを比較検討して、自分に合うサポーターを見つけましょう。
おすすめの転職エージェントは以下の記事で解説しています↓
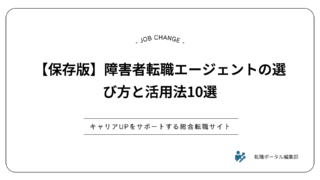
面接対策と企業研究の押さえどころ
面接は、企業と自分との相性を見極める大切な機会です。
ただ受け答えするだけでなく、「どんな職場で、どんな人と、どう働くか」を自分自身でも確認する場として捉えることが重要です。
特に障害がある方の場合、「配慮が必要な場面」「過去に困った経験」「それをどう乗り越えたか」など、エピソードベースで語る準備をしておくと説得力が増します。
企業研究については、公式サイトだけでなく、クチコミサイトやSNSでの社風チェックも有効です。
可能であれば、実際に働いている障害者の声や、定着率なども確認しておくと安心です。
相談先と支援サービスの活用法
ハローワーク・地域障害者職業センターの支援内容

障害者の転職活動において、ハローワークや地域障害者職業センターは、非常に心強い公的支援機関です。
無料で利用できるだけでなく、専門的なサポートが充実しています。
たとえば、ハローワークの「専門援助部門」では、障害者専用の職業相談員が常駐しており、求人紹介・応募書類の添削・模擬面接など、丁寧に対応してくれます。
一方、地域障害者職業センターでは、職業評価やジョブコーチ支援、復職プランの設計など、より専門性の高いサービスを受けられます。
- 職業適性の診断(職業リハビリテーション)
- 精神障害・発達障害などに応じた就労支援プログラム
- 企業への訪問や現場調整も行う「ジョブコーチ支援」
民間サービスと併用することで、より多角的かつ実践的な支援を受けることが可能です。
就労移行支援・定着支援サービスのメリット
障害のある方が一般就労を目指す際に活用できるのが、「就労移行支援事業所」です。
ここでは、ビジネスマナー、職業訓練、実習などを通じて働く力を段階的に身につけられます。
多くの事業所では、生活リズムの安定からスタートし、職場体験や模擬就労など実務に近い訓練も行われるため、未経験の分野にもチャレンジしやすくなります。
また、就職後の「定着支援」では、職場訪問・定期面談・トラブル対応などが行われ、長期的な職場定着に貢献します。
支援内容や雰囲気は事業所ごとに異なるため、事前に見学・体験を申し込むと、自分に合う事業所を選びやすくなります。
就労移行支援事業所を探すのおすすめのサービスはこちら↓
転職フェアやオンライン相談を利用する
転職活動の情報収集や企業との接点を広げるうえで、転職フェアやオンライン相談会の活用は非常に有効です。
障害者専用の転職イベントでは、企業が障害者雇用に積極的であることが前提となっており、対面またはオンラインで企業担当者と直接話すことができます。
- atGPやdodaチャレンジなどの大手による就職フェア
- 自治体やNPO法人が開催する地域限定のマッチング会
- ZoomやLINEを使ったオンライン面談会
応募前に企業の雰囲気や支援体制を直接確認できる点は、通常の求人応募と比べても大きなメリットです。
また、ハローワークなどが提供する「職業相談のオンライン化」も進んでおり、来所が難しい方でも気軽に相談できるようになってきています。
一人で悩まず、こうした機会を積極的に活用することで、自分に合う職場と出会える可能性が高まります。
成功事例で学ぶキャリアチェンジのヒント
キャリアチェンジに成功したケース

異業種への挑戦は不安も大きいものですが、障害者雇用においてもキャリアチェンジに成功した40代の例は数多く存在します。
たとえば、長年接客業に従事していた方が、就労移行支援でパソコンスキルを学び、事務職へと転職。
静かな職場環境で集中できる働き方がマッチし、現在は正社員として安定して勤務されています。
この方のように、「自分の特性に合った環境」を見つけるための学び直しや支援サービスの活用が、成功のカギとなっています。
同業界でキャリアアップしたケース
40代は、これまでの経験を活かして同業界でステップアップする好機でもあります。
障害をオープンにすることで、むしろ信頼を得られることも少なくありません。
- 製造業でライン作業に従事していた方が、職長研修を経て管理補佐に昇格
- 営業経験者が、同じ業界のインサイドセールスへ異動し、体調と業績を両立
企業側も経験者を歓迎する傾向が強く、実績を数字でアピールすることができれば、キャリアアップのチャンスを掴みやすくなります。
在宅勤務への転向で働きやすさを実現したケース

コロナ禍以降、在宅勤務を導入する企業が増え、障害者雇用においても「通勤負担の軽減」「静かな作業環境の確保」などの理由から注目が集まっています。
実際に、通勤ストレスで退職を繰り返していた方が、在宅ワークに切り替えたことで勤務継続が可能になり、現在はライティングやデータ入力業務で活躍中です。
職種や企業の柔軟性にもよりますが、「出社が難しい=働けない」ではなく、選択肢の一つとして在宅勤務を検討する価値は十分にあります。
よくある質問と疑問解消
年収と給与交渉でよくある疑問
障害者雇用では「給与が低くなりがち」との声を耳にしますが、必ずしも一律で待遇が下がるわけではありません。
企業側が慎重になるのは、「長く働けるか」「能力を発揮できるか」などの不確実性です。
これらを払拭できれば、実力に見合った評価を得ることも十分に可能です。
- 面接での実績・スキルの具体的なアピール
- 採用後の働き方の柔軟性や安定性の説明
- エージェントを通じた給与交渉の活用
年収に納得がいかない場合は、条件面だけで判断せず、将来的な昇給制度や評価制度も合わせて確認しておきましょう。
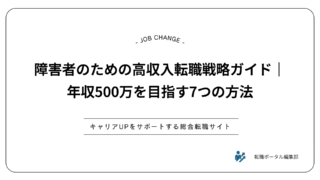
障害者手帳なしで応募できるか
基本的に「障害者枠」の求人は、障害者手帳の保持が前提となっていますが、手帳がない方でも応募できる一般求人や「配慮を必要とする方向け」の求人も存在します。
また、一部企業では「取得予定」であれば選考対象とするケースもあるため、状況によっては事前に問い合わせてみるのも良いでしょう。
ただし、合理的配慮を求めるには、手帳の提示が必要になる場面も多いため、選択肢を広げる意味でも取得を検討する価値はあります。
一般枠と障害者枠のどちらが自分に合うか

どちらの枠で応募するかは、「自分の体調や配慮の必要度」「希望する働き方」「職種の幅」などによって変わってきます。
- 通院や体調の波があり、勤務条件に配慮が必要 → 障害者枠
- 障害の影響が比較的軽く、一般企業と同等の働き方が可能 → 一般枠
障害者枠は柔軟な勤務形態がある反面、職種やキャリアの幅が狭くなることも。
一方、一般枠では実績重視の採用が多いため、無理なく働けるかを見極めることが大切です。
まとめ:経験と配慮を武器に、40代からの転職を成功させよう
40代の障害者の方にとって、転職は「難しい」と感じられるかもしれませんが、正しい準備と戦略を持てば、むしろ今こそが理想の働き方を実現するチャンスです。
なぜなら現在は、法定雇用率の引き上げや在宅勤務の普及など、障害者を受け入れる企業の体制が急速に整ってきており、支援制度も豊富に用意されているからです。
特に以下のような行動が、成功への鍵を握ります。
- 自分の障害特性と配慮事項を明確にする
- 実績やスキルを数値で示し、即戦力としてアピールする
- 支援機関(ハローワーク・就労移行支援等)を積極的に活用する
- 柔軟な働き方を提案し、企業側と相互理解を深める
- 定着支援やキャリア形成も視野に入れて転職活動を進める
40代は、経験という大きな武器を持つ年代です。
そこに「自分に合った働き方」や「継続的な学び」を組み合わせることで、障害があっても自分らしいキャリアを確実に築くことができます。
一歩を踏み出すのに遅すぎることはありません。自分自身と向き合い、理想の職場と出会うための準備を、今すぐ始めてみましょう。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
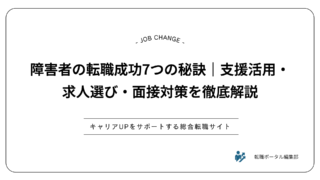
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓