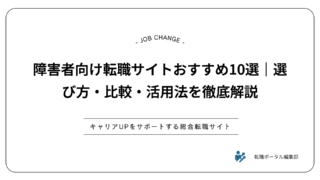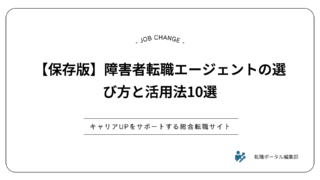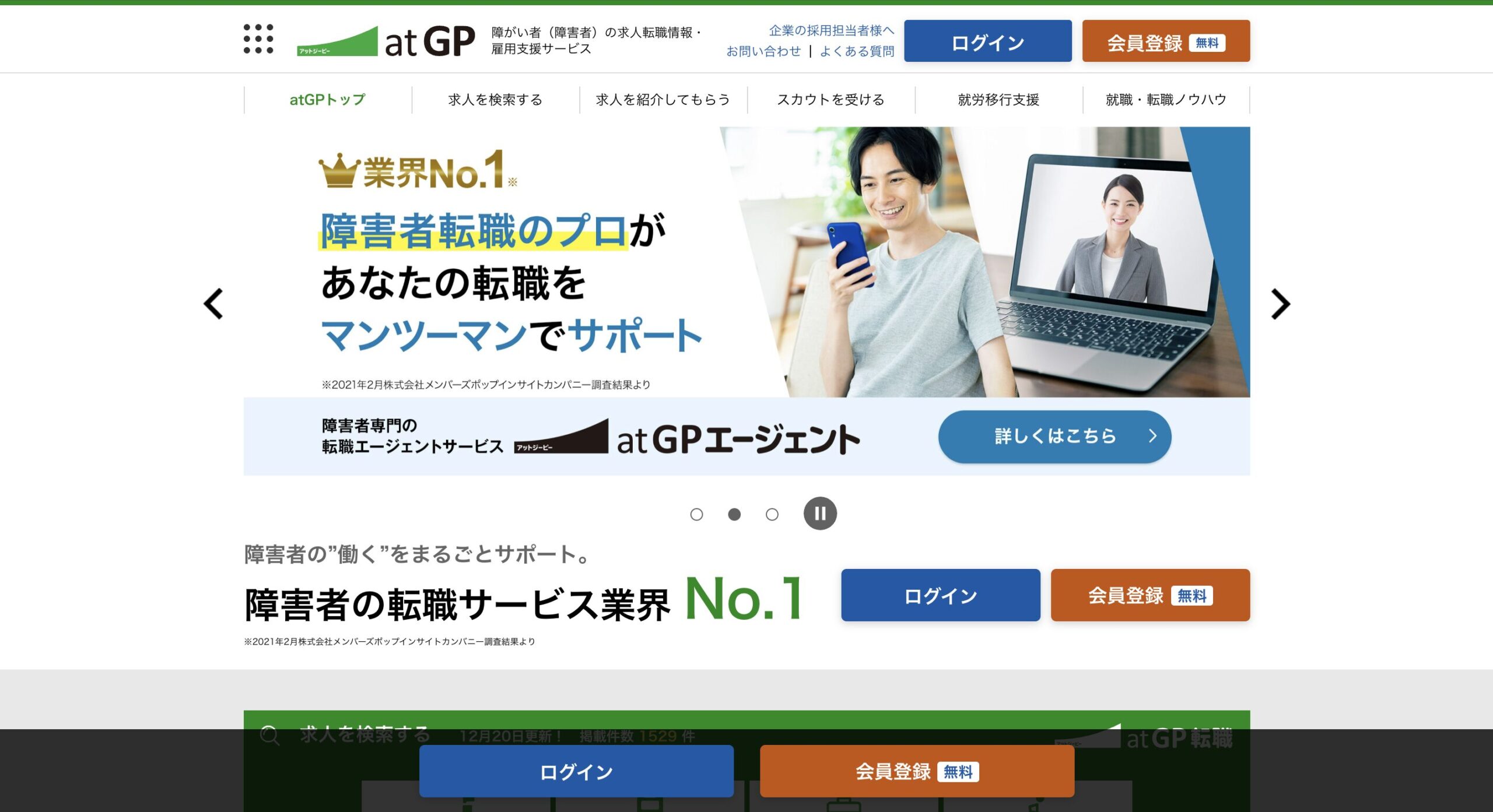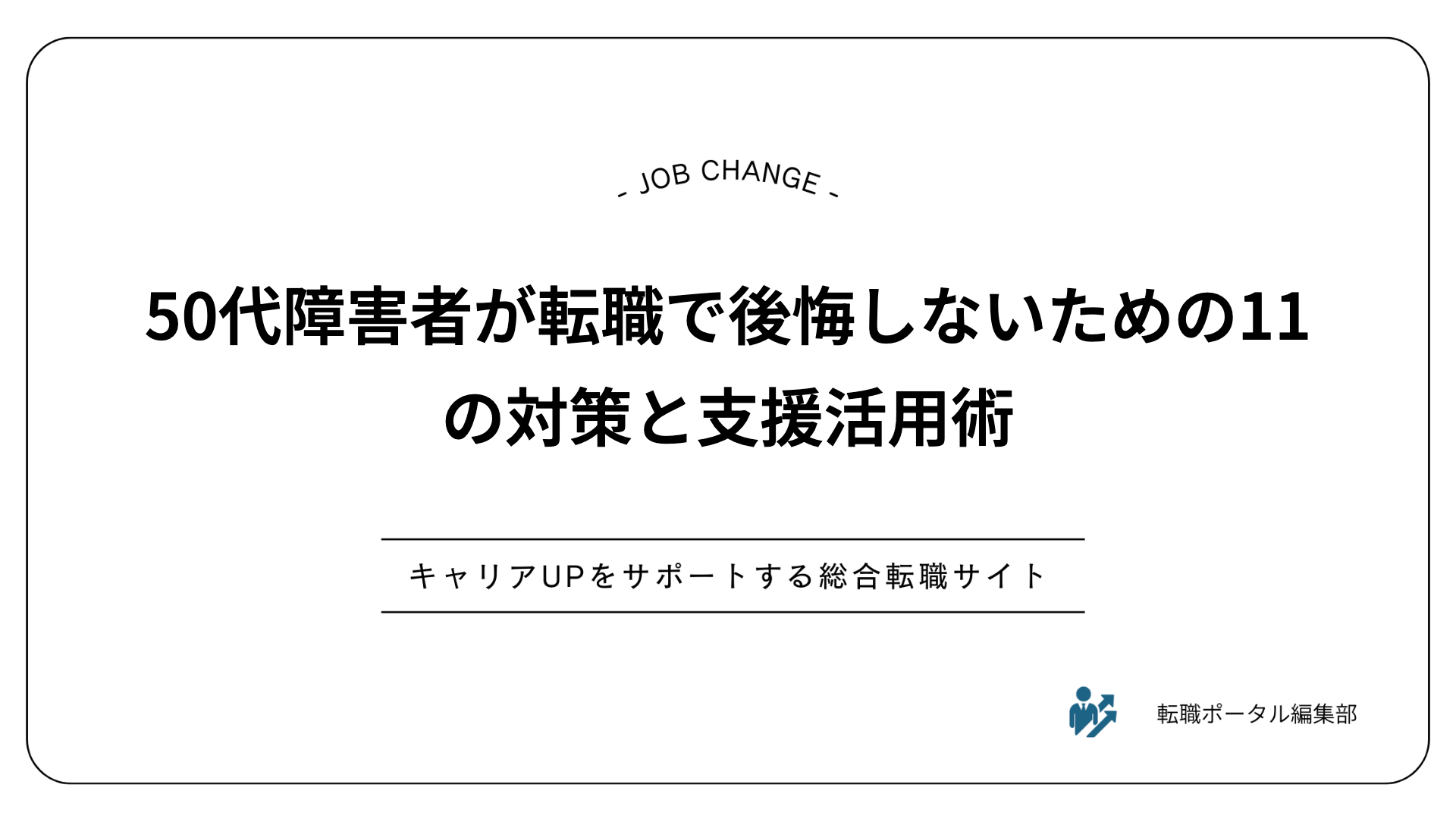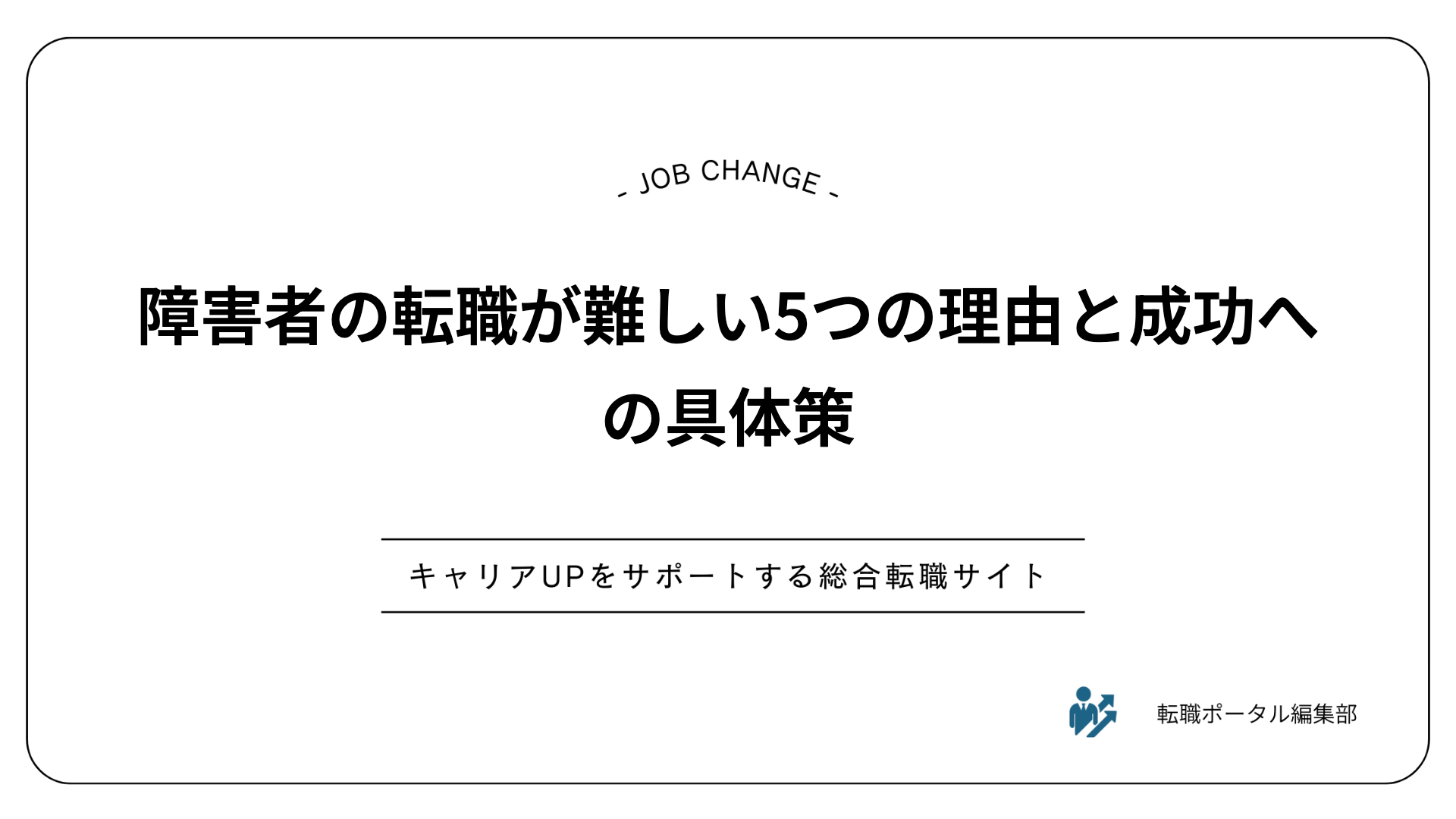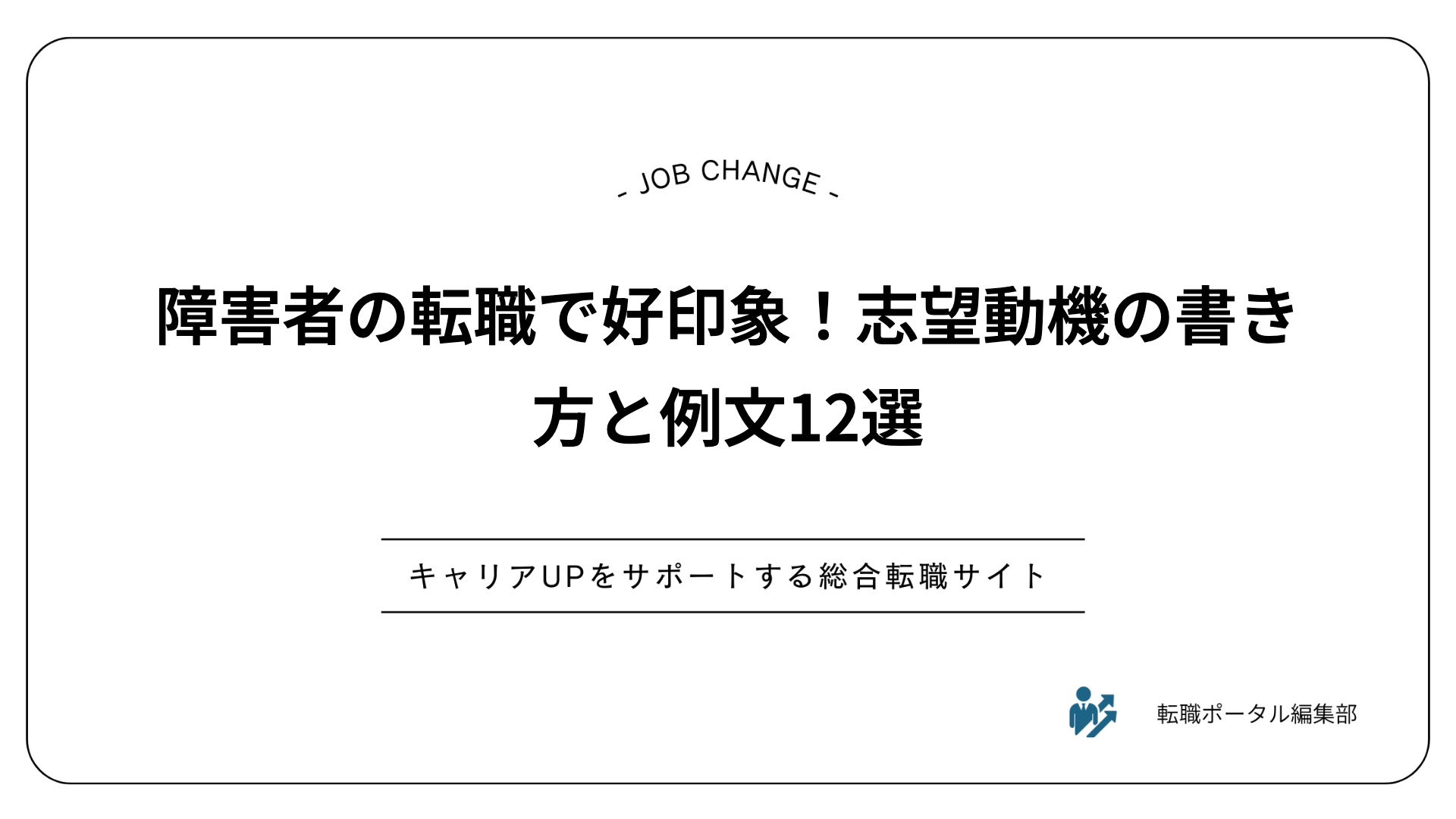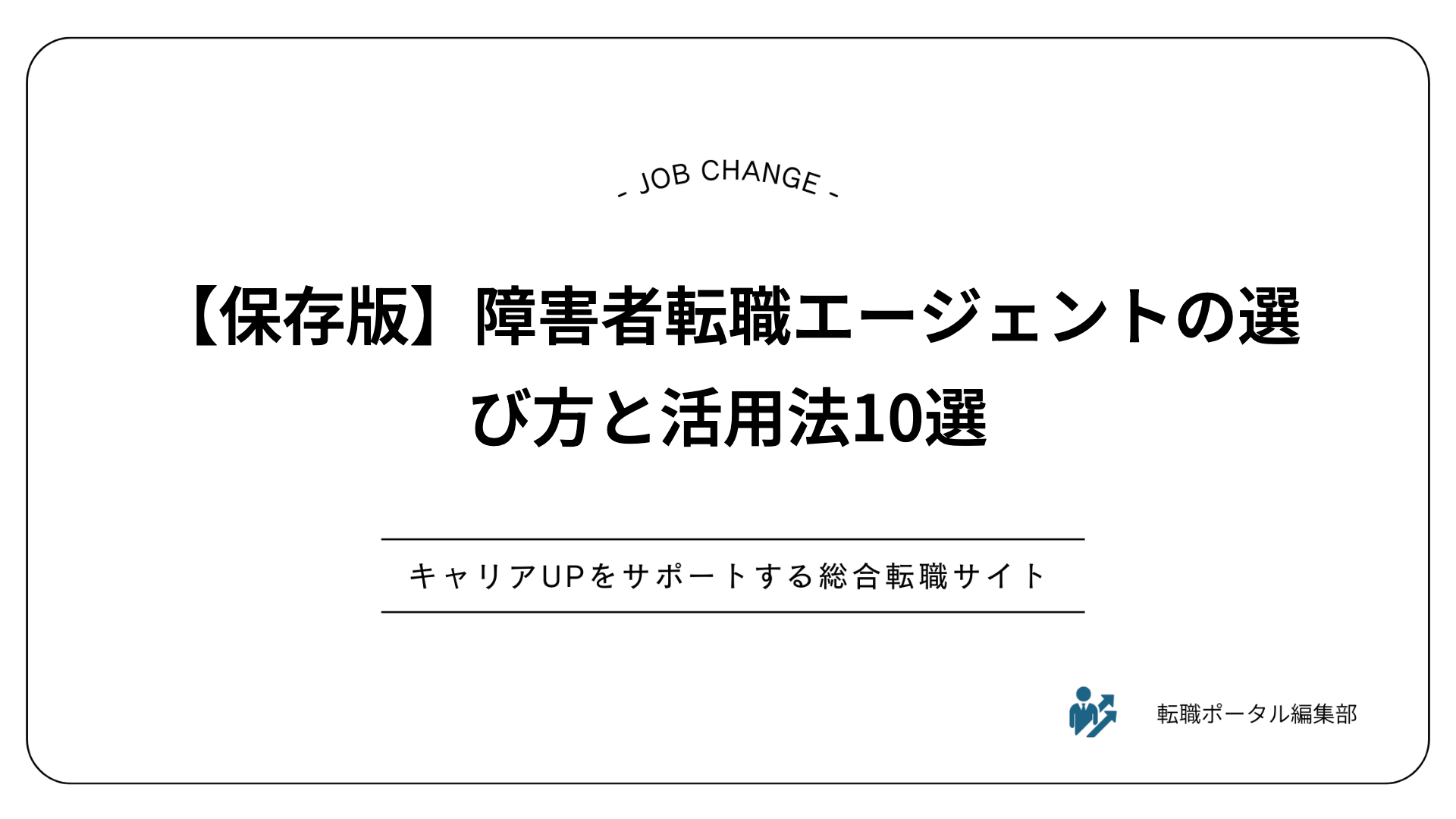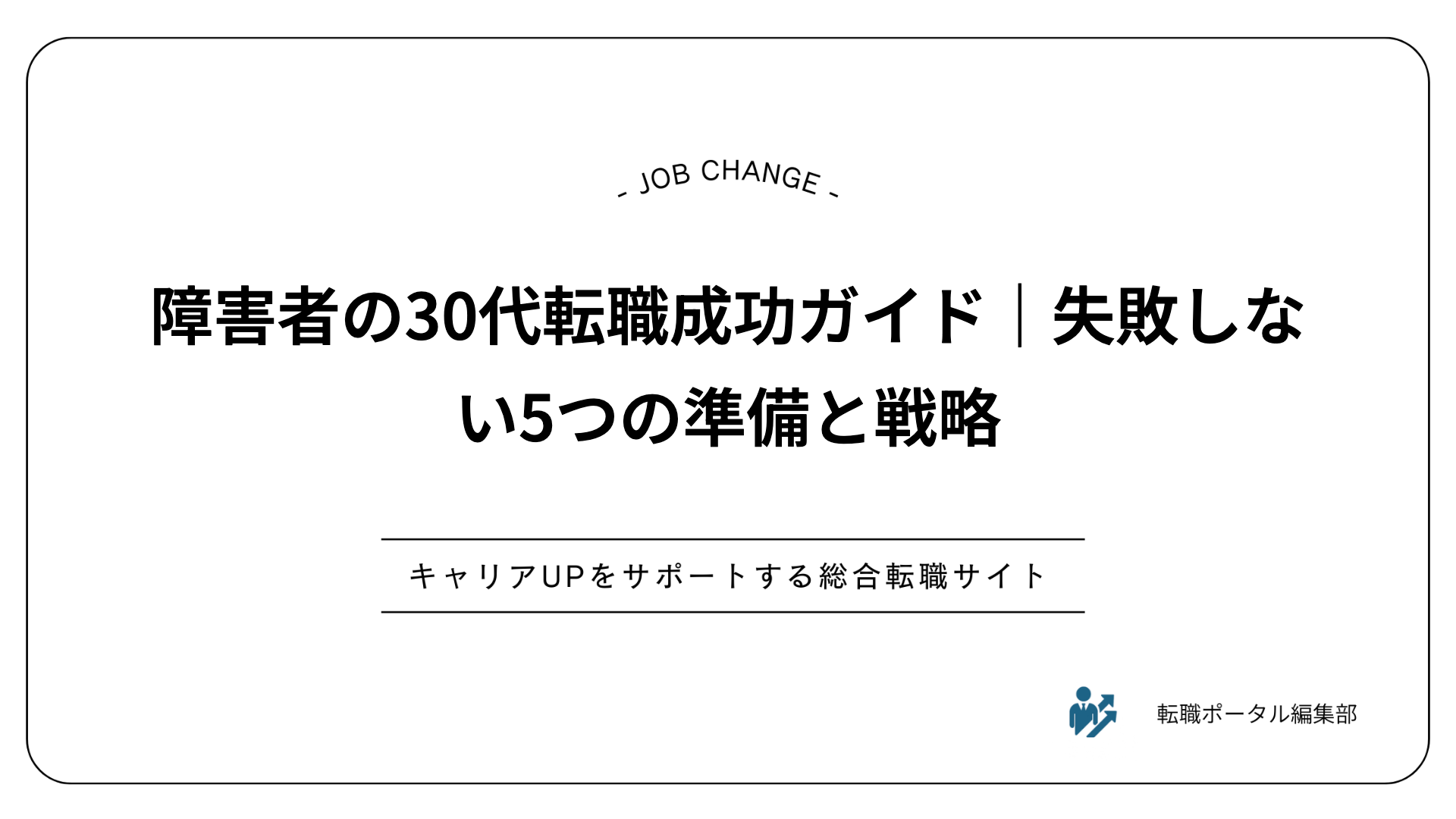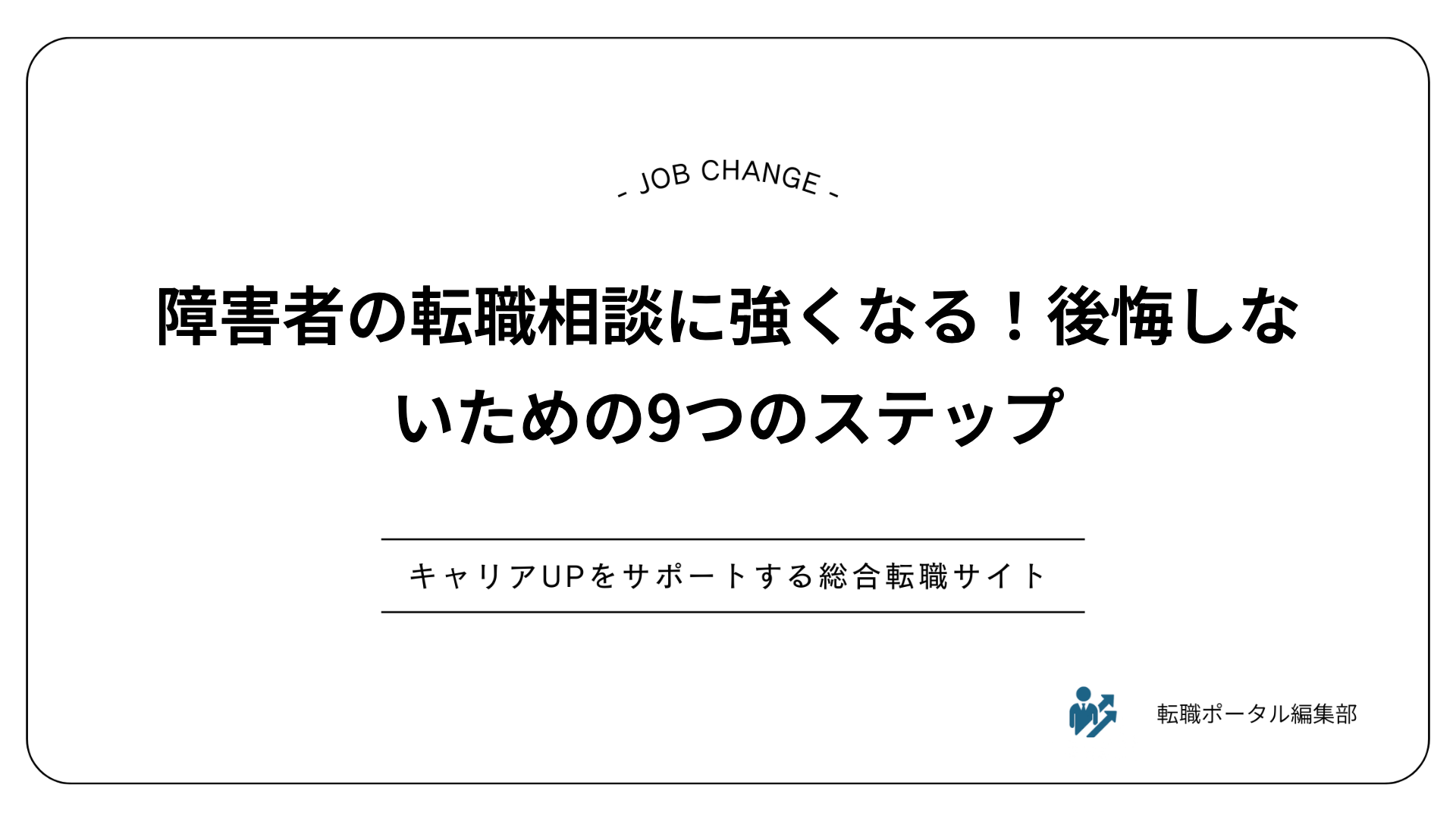障害者の転職成功7つの秘訣|支援活用・求人選び・面接対策を徹底解説
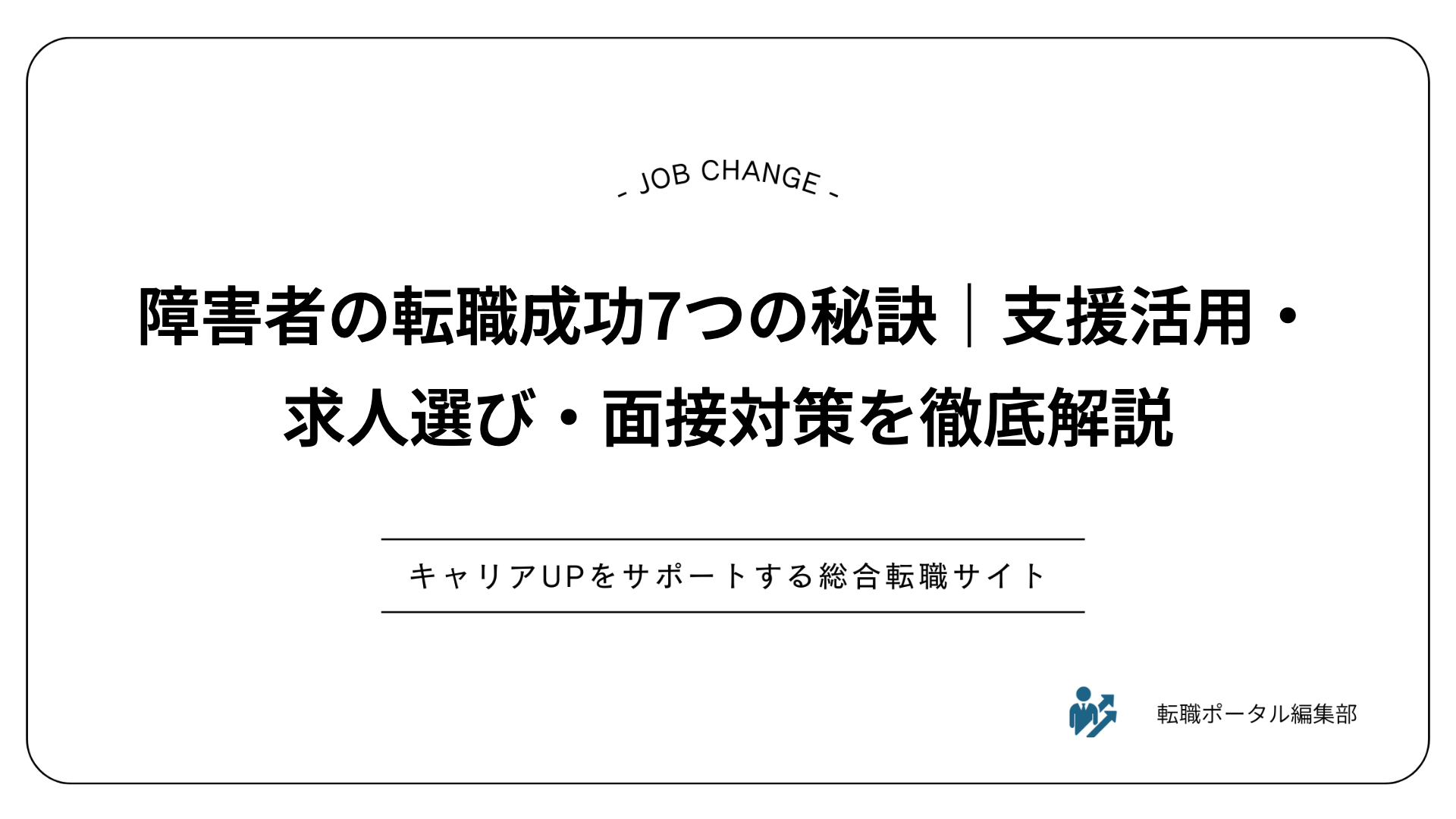
「障害があっても、自分に合った仕事に就きたい」「転職したいけど、何から始めればいいのか分からない」――そんな悩みを抱えていませんか?
障害者の転職には、特有のハードルがある一方で、今は以前よりも多くのチャンスが広がっています。
法定雇用率の上昇や多様な支援制度の整備により、自分らしい働き方を実現できる可能性が高まっているのです。
この記事では、次のような疑問や不安を持つ方に向けて、具体的な情報と解決策をお届けします。
- 障害者雇用と一般雇用の違いを知りたい
- どの転職サイト・支援サービスを使えばいいのか迷っている
- 面接で障害をどう伝えるべきか分からない
- 在宅勤務や時短など柔軟な働き方を希望している
- 年代ごとのキャリア戦略を知っておきたい
この記事を読めば、あなたの現状や希望に合った転職活動の進め方がきっと見つかります。
ぜひ最後まで読んで、自分らしい働き方を一緒に考えてみましょう。
障害者転職市場の最新動向
法定雇用率の推移と企業ニーズ

障害者雇用の現場では、年々「法定雇用率」の引き上げが進み、企業の採用姿勢にも変化が見られます。
2025年現在、民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられており、従業員40人以上の企業は少なくとも1人以上の障害者雇用が義務付けられています。
- 雇用率の上昇により、障害者採用枠が広がっている
- 未達成企業には納付金制度が適用され、対策が急務に
- 身体・精神・知的など多様な障害に対応する職域の拡充が進行中
このように、法定雇用率の引き上げは単なる数字の変更ではなく、企業の人材戦略や社会的責任にも深く関わる重要な要素となっています。
ダイバーシティ推進やイノベーション促進の観点からも、障害者雇用の価値はますます高まっているのです。
障害者雇用枠と一般枠の違い
転職活動を進める際は、「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」の違いを理解しておくことが重要です。
障害者枠では、合理的配慮が前提とされており、勤務時間や働き方に対して柔軟な対応が期待できます。
たとえば、面接回数が少なめに設定されたり、短時間勤務・通院配慮などが実施されたりと、個々の事情に応じた調整が行われやすいのが特徴です。
一方で、一般枠はあくまで健常者と同じ基準での選考や評価が求められます。
「配慮よりも成果やキャリアアップを重視したい」という方には、あえて一般枠で挑戦するのも一つの選択肢となるでしょう。
障害種別・年代別の求人トレンド

近年の求人動向では、精神障害や発達障害の方を対象とした求人が急増しており、障害者向け求人全体の約6割を占めるまでに広がっています。
- 身体障害者向けには、オフィス系の事務職やIT職が多く見られます
- 精神障害者向けには、在宅勤務可能な業務や定着支援付き求人が増加
- 発達障害者向けには、マニュアル化された軽作業やIT業務などが注目されています
年代別で見ると、20代~30代ではベンチャーや柔軟な社風の企業が人気で、40代~50代では安定志向が強く、公的機関や大手企業への応募が目立ちます。
自身の年代や障害の特性に合った求人を見つけるには、専門性の高いエージェントや支援機関の活用がカギになるでしょう。
活用すべき支援サービスと選び方
転職サイトとエージェントの特徴比較
障害者の転職活動では、「転職サイト」と「転職エージェント」のどちらを利用するかで得られる情報や支援内容が大きく異なります。
自分に合った方法を選ぶことで、転職成功率も格段に高まるでしょう。
- 転職サイト:求人検索や応募が自分のペースでできる
- 転職エージェント:応募書類の添削や面接対策など、手厚いサポートが受けられる
- 障害特化型エージェント:配慮事項や働きやすさを重視したマッチングに強い
「自分の希望する業種が決まっている」「スピーディに応募を進めたい」場合は転職サイトが適しています。
一方で、「どんな職場が自分に合うか分からない」「応募書類が不安」という方には、障害者専門の転職エージェントの利用がおすすめです。
おすすめの転職エージェント・サイトは以下の記事でまとめています↓
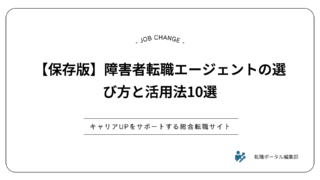
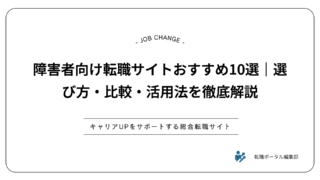
就労移行支援・定着支援の活用方法
障害者の転職を成功させるうえで、就労移行支援と定着支援は非常に有効な手段です。
特にブランクがある方や、職場環境への不安が強い方にとっては、就労前後のサポートが心強い味方となります。
就労移行支援は、就職を目指す障害者に対して職業訓練や面接練習、ビジネスマナーの指導を行うサービスです。
最長2年間、通所しながら準備を進められるため、体調と相談しながら無理なくスキルを高められるのが特長です。
一方の定着支援は、就職後に職場に慣れるまでの数ヶ月~1年間、第三者としてサポートしてくれる制度です。
企業との仲介役として、業務や人間関係の悩みを聞き取ってくれるため、「せっかく就職したのにすぐ辞めてしまう」というリスクを減らせます。
求人フェア・合同面接会のメリット

障害者向けの求人フェアや合同面接会は、企業と直接会える貴重な機会です。
特に「書類選考で落ちやすい」「まずは話をしてみたい」という方には、対面で印象を伝えられるイベント形式が向いています。
- 多くの企業担当者と一度に会える
- 書類選考なしで面接に進めるケースがある
- 企業ブースでリアルな雰囲気や人柄に触れられる
一度に複数の企業を比較できるため、「どんな会社が自分に合いそうか」を短時間で把握できるのもメリットの一つです。
「履歴書を送っても返信が来ない…」と感じている方ほど、こうしたフェアに参加することで突破口が見えてくるかもしれません。
おすすめ障害者転職サイト&エージェント比較
総合型サービスの強み

障害者の転職支援を行う総合型サービスは、全国の求人を幅広くカバーしている点が魅力です。
業種や職種の偏りが少なく、身体・精神・知的といった各種障害の方に向けた案件も網羅されているため、「とにかく選択肢を増やしたい」という方に適しています。
- 多数の企業と提携しており、非公開求人も豊富
- 全国対応で地方在住でも利用しやすい
- 支援員の数が多く、面談対応や書類サポートが充実
特に「dodaチャレンジ」「atGP」「ランスタッド」などは知名度も高く、企業との太いパイプを活かしたマッチングに定評があります。
「どのサービスを使えばよいかわからない」という方は、まずこのような総合型サービスからスタートしてみるのが安心です。
精神障害向け特化サービスの選択基準
精神障害をお持ちの方にとって、転職活動には体調や人間関係の不安がつきものです。
そんな中、精神障害に特化した転職支援サービスは、医療や福祉に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、より深い理解をもとにサポートを受けられるのが特徴です。
たとえば、「働く時間を少しずつ増やしたい」「配慮事項をどう伝えるべきか悩んでいる」といった声に丁寧に対応してくれるため、長期的な就業継続にもつながりやすくなります。
「LITALICOワークス」や「サーナ」などのサービスは、精神・発達障害に特化しつつ、本人の希望と職場の環境を丁寧にすり合わせてくれるので安心感があります。
在宅勤務・IT系求人に強いサービス
働き方の多様化が進むなか、在宅勤務可能な求人やITスキルを活かせる職種の需要も高まっています。
特に通勤負担の大きい方や集中環境を重視したい方にとっては、在宅求人に特化したサービスの活用が有効です。
- ITエンジニア・Webデザイナー・カスタマーサポートなどの職種が多い
- リモート前提の求人では、出社義務がない働き方も可能
- PCスキルや資格があれば、未経験からでも狙える求人もある
「atGPジョブトレIT・Web」や「Green」などは、特に在宅IT職のサポートが手厚く、オンライン面接や研修も完備されています。
「人と会うのが苦手」「地方に住んでいても働きたい」などのニーズにも柔軟に対応してくれます。
地方求人に強いサービス
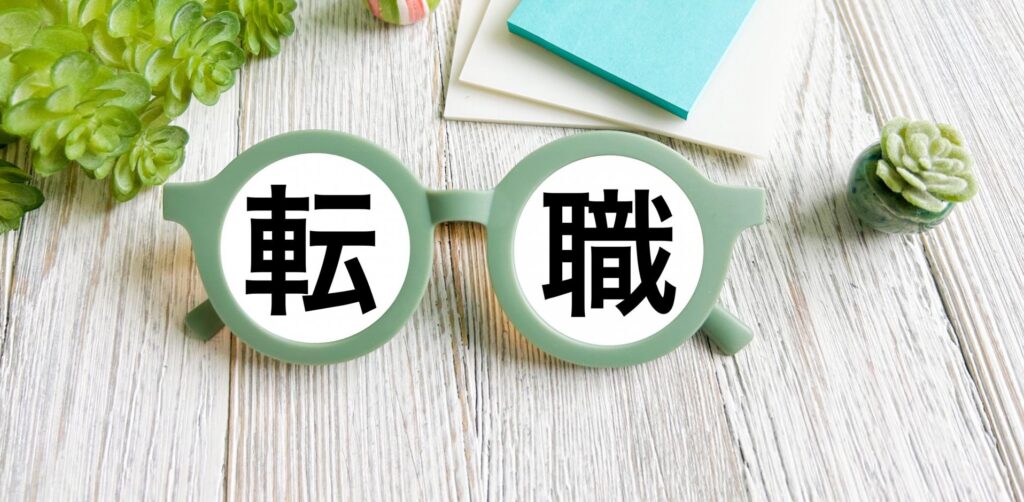
都市部に比べると、地方の障害者求人はまだまだ選択肢が限られています。
しかし、全国展開している転職エージェントや、自治体と連携した地元密着型のサービスを活用することで、地方でも安定した就職が可能です。
たとえば、ハローワークや地域若者サポートステーション、または地域特化型の障害者支援NPOなどと連携しているサービスでは、地元企業との信頼関係が構築されており、マッチング後の定着率も高めです。
「通勤距離を短くしたい」「地元で腰を据えて働きたい」といった希望がある方は、複数のエージェントと並行して、地域に根ざした情報源も活用すると良いでしょう。
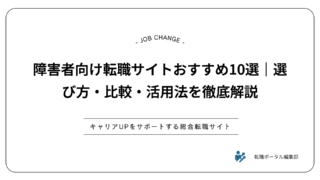
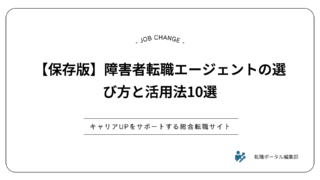
転職成功までのステップと準備
自己理解と配慮事項の整理方法
転職活動を成功に導く第一歩は、「自分自身を深く知ること」です。
障害の特性や体調の波を理解し、どのような職場環境や業務内容であれば無理なく働けるのかを明確にしておくことで、ミスマッチを防ぐことができます。
- 過去に困難だった勤務条件(例:長時間労働、人間関係のストレスなど)を振り返る
- 得意な作業スタイル(例:集中力が続く時間帯、得意分野)を洗い出す
- 通院頻度や服薬、副作用などを踏まえた勤務条件をまとめる
これらの情報は「配慮事項」として企業に伝える際の基礎資料になります。
「自分に何が必要か分からない…」という方は、就労移行支援やエージェントのカウンセリングを活用するのも一つの方法です。
応募書類の書き方とポイント

履歴書や職務経歴書は、採用担当者にとっての第一印象を決定づける重要な資料です。
特に障害者枠での応募では、配慮事項とスキルの両立をアピールすることが鍵になります。
ポイントは、「配慮は必要だが、仕事への意欲や能力は十分ある」という姿勢を伝えること。
障害名を書くことよりも、具体的な業務上の工夫や実績に焦点をあてましょう。
また、職務経歴書では単なる業務内容の羅列ではなく、工夫した点や達成できた成果を「数字」「行動」「変化」で表現すると説得力が高まります。
「配慮を求める=負担になる」と誤解されないように、前向きかつ冷静なトーンで伝えることが大切です。
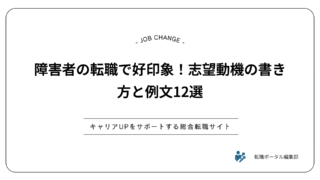
障害開示のタイミングと伝え方
「いつ、どの段階で障害を開示すべきか?」というのは、転職活動において多くの方が悩むポイントです。
結論から言えば、基本的には応募書類提出時点か、面接の初回段階での開示が望ましいとされています。
早期に開示することで、企業も面接や配属の段階から配慮を準備しやすくなります。
逆に、選考後半や内定後に伝えた場合、企業側との信頼関係に影響を与えてしまうリスクも。
伝え方としては、障害名そのものよりも「日常生活や業務上での工夫」「必要な配慮内容」に焦点を当て、事実ベースで簡潔に伝えることが重要です。
感情的・抽象的な説明は避け、冷静かつ論理的にまとめましょう。
面接対策と配慮事項の交渉術
面接では、スキルや人柄だけでなく、障害についての理解とコミュニケーション力も評価の対象になります。
特に障害者雇用枠では、「この人と一緒に働けそうか」「職場にどんな配慮が必要か」を確認する場でもあります。
- 配慮内容は事前にメモして準備しておく
- 「できないこと」だけでなく「できること」もセットで伝える
- 企業側の質問には具体例を交えて誠実に回答する
交渉の際は、遠慮しすぎず、かつ柔軟な姿勢を持つことがポイントです。
たとえば「週に1度の在宅勤務が可能か」といった要望を出す場合でも、代替案や譲歩可能な点を添えて話すことで、建設的な合意に近づけます。
「言いにくいことだけど、伝えることで働きやすさが変わる」と考えて、自信を持って臨みましょう。
職種・働き方別の求人選び
事務・バックオフィスで求められるスキル

障害者雇用枠の中でも特に人気が高いのが、事務・バックオフィス系の職種です。
書類作成やデータ入力、電話対応など、比較的体力的な負担が少なく、ルーティン業務を中心に構成されている点が選ばれる理由です。
- 基本的なPCスキル(Word、Excel、メール対応など)
- 正確性や丁寧さを意識した作業
- 簡単なビジネスマナー(電話応対や報連相など)
特別な資格が必要なわけではありませんが、「日商簿記」「MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)」といった事務系資格を持っていると、選考で有利になるケースもあります。
「パソコンは得意だけど何から始めれば良いかわからない」という方は、無料講座や職業訓練も積極的に活用してスキルを可視化しておくと安心です。
ITエンジニア・テクニカル職の可能性
障害の有無を問わず、ITエンジニア職は人材不足が続いており、スキルのある方であれば高年収や在宅勤務も可能な職種です。
特に発達障害や精神障害のある方の中には、黙々とした作業や論理的思考に適性を持つケースも多く、向いている職種として注目されています。
プログラミング(JavaScript、Pythonなど)やインフラ知識、システム運用など幅広い職域があり、未経験でもスクールやeラーニングで学びながらスキルを身につける道が開かれています。
ただし、業務の変化スピードが早い分、自己管理能力やリモートでの報連相など一定のビジネススキルも必要となるため、支援体制のある職場を選ぶのが成功のポイントです。
接客・販売職で活きる強み

「人と関わるのが好き」「笑顔で接するのが得意」という方には、接客・販売職も有力な選択肢となります。
店舗勤務や受付、インフォメーションなどの職種では、コミュニケーション力や気配りのスキルが評価されやすい傾向があります。
- 来客応対・レジ業務・商品案内など、現場での柔軟な対応力
- 明るい挨拶や丁寧な接遇スキル
- 清掃・品出しなど軽作業を含むマルチタスク能力
体力やストレス耐性も求められる職種ではありますが、職場によっては配慮のもと短時間勤務や担当業務の限定などが行われているケースもあります。
「接客は好きだけど体調が心配」という方は、支援機関と連携しながら働き方を調整していくことが重要です。
フルリモート・時短勤務の求人事例
近年では「場所や時間に縛られずに働ける」働き方の需要が高まり、障害者向けの求人でも在宅勤務や時短勤務を導入する企業が増えています。
特に通院や体調変化のある方にとっては、生活リズムを保ちながら無理なく働けるメリットがあります。
例としては、
- 在宅でのカスタマーサポート業務
- リモートでのデータ入力・WEBマーケティング補助
- 週20時間からの時短勤務対応求人
これらの求人は「フルリモート可」「時間帯応相談」と記載されていることが多いため、検索の際にはキーワードを工夫すると見つけやすくなります。
「子育てや介護と両立したい」「外出が難しい」などの事情がある方にとっても、選択肢の幅を広げてくれる働き方です。
年代別キャリア戦略
20代がキャリアを築くコツ
20代はキャリア形成の土台を築く重要な時期です。障害の有無に関わらず、最初の職場選びや経験が今後の働き方に大きく影響します。
「やりたいことが分からない」という悩みも多い年代ですが、まずは社会経験を積むことを優先して考えましょう。
- 就労移行支援を活用し、職業体験や実習で適職を探る
- 障害者専門のエージェントに相談し、企業とのマッチングを支援してもらう
- 最初から完璧を目指さず、無理なく働ける環境からスタートする
若手人材は企業側からのニーズも高く、「育成前提」で採用されることも多いのが特徴です。
スキルが未熟でも、「成長意欲があること」を伝えられれば十分にチャンスがあります。
30代のキャリアチェンジ戦略

30代は「やりたいこと」と「できること」のバランスを見直すタイミングです。
経験やスキルがある一方で、体調や家庭環境の変化により働き方を見直したくなる時期でもあります。
未経験職種へのチャレンジも可能な年代ですが、何かしらの強みや実績をアピールできることが重要です。
また、企業側も即戦力を期待する傾向があるため、スキル証明や業務理解のある応募が求められます。
「今までの経験を活かして働きたい」「より働きやすい環境に転職したい」と考える方は、障害者枠と一般枠の両方を視野に入れて選択肢を広げるのも一つの方法です。
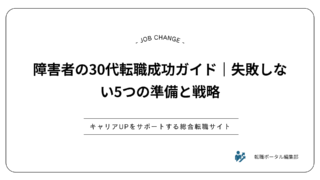
40代・50代が避けたい落とし穴
40代以降の転職では、「過去の実績」に頼りすぎることがリスクになる場合があります。
「年齢=即戦力」という先入観を持たれやすいため、自己PRや希望条件の整理が不十分だと、企業とのミスマッチが起きやすくなります。
- これまでの経験が応募先でどう活かせるかを明確に説明する
- ブランクがある場合は、体調回復やスキル習得などの取り組みを伝える
- 「環境重視」「安定重視」の場合は、定着支援付き求人を優先的に探す
また、再就職準備給付金や障害者向けの再就職支援制度など、年齢に関わらず活用できる制度もあるため、ハローワークや地域支援機関の相談窓口をうまく利用することが成功の鍵になります。
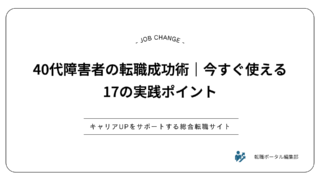
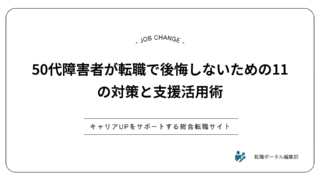
給与・キャリアアップの現実と事例
給与水準と年収アップ交渉術

障害者雇用枠での給与水準は、一般的に初任給がやや抑えられている傾向があります。
ただし、近年は成果やスキルに応じて給与を見直す企業も増え、長期的に見れば一般枠に近い水準を目指すことも可能です。
- 業務内容・経験・スキルによって給与設定に幅がある
- 昇給制度がある企業では、半年~1年単位で見直しの機会がある
- 入社時に配慮事項とともに業務貢献の見込みも伝えて交渉を
給与交渉では、「年収を上げたい」だけでなく、「こういう成果を出すのでこの条件を希望します」というロジックが重要です。
数字や具体例を使って説明することで、説得力を持たせられます。
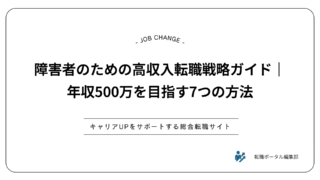
スキルアップ・資格取得の効果
キャリアアップを目指すなら、スキルの見える化が大切です。職務経験だけでなく、資格や研修歴は「学び続けている人材」であることの証明になります。
特に評価されやすいのは次のような資格です:
- MOS(Microsoft Office Specialist)
- 日商簿記検定(3級〜2級)
- 基本情報技術者、ITパスポートなどのIT系資格
資格は自信にもつながりますし、職場での業務幅を広げる後押しにもなります。
「就職してから資格を取った」「ブランク中にeラーニングで学習した」などの姿勢は、企業からも高く評価されるポイントです。
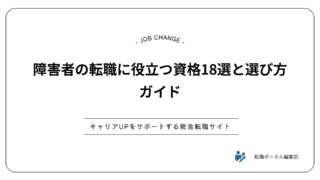
昇進・管理職を目指すためのステップ
障害者雇用枠でも、キャリアを重ねれば昇進・管理職を目指すことは可能です。
実際に、チームリーダーや部門のサブマネージャーに就任している事例も少しずつ増えてきています。
そのためには、単に与えられた業務をこなすだけでなく、業務改善の提案や新人教育の補助など、組織に対して「価値を提供している」姿勢を見せることが重要です。
また、管理職になると体調管理やストレス対策も重要になってきます。
必要であれば産業医や社内カウンセラーに相談する体制を整えておくことも、長期的に活躍するうえで欠かせません。
転職活動でよくある質問(FAQ)
複数の転職サイトを併用すべきか

結論から言えば、複数の転職サイトやエージェントの併用は非常に効果的です。
それぞれに取り扱う求人や得意とする業界が異なるため、併用することで出会える求人の幅が広がります。
- サイトAでは見つからない非公開求人がサイトBにあることも
- エージェントとの相性によってサポートの質が変わる
- 情報収集や自己理解のためにも複数視点を得られる
ただし、管理が煩雑にならないように「連絡手段をまとめる」「応募の進捗を記録する」といった工夫は必要です。
「一つに絞るべき?」と悩むより、まずは試してみて合うところに絞っていくのが現実的です。
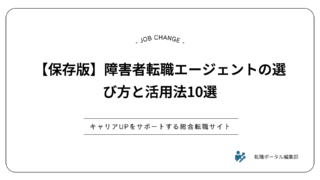
障害手帳がない場合の転職方法
障害手帳を持っていない場合でも、一般枠での転職はもちろん、職場に配慮を求める形での就職も可能です。
ただし、障害者雇用枠を利用するには基本的に手帳の提示が必要とされます。
そのため、手帳がない状態で配慮を受けたい場合は、「オープン就労(障害を開示する)」という形で企業と相談する必要があります。
この場合、医師の診断書や通院歴の提示を求められることもあるため、事前に主治医とも相談しておくと安心です。
「手帳申請中」「通院はしているが手帳取得に至っていない」などのケースでも、個別対応してくれる企業は少なくありません。
エージェントを通じて企業に事情を説明してもらうのも有効な方法です。
障害開示で不採用になるケースへの対策

残念ながら、障害を開示することで不採用になるケースがあるのも事実です。ですが、それは「相性の良くない企業を避けられた」という見方もできます。
重要なのは、開示の仕方とその内容です。
- 「できないこと」だけでなく「こうすれば働ける」工夫を伝える
- 感情的にならず、冷静で具体的に説明する
- 企業の理解度や雰囲気を面接で観察する
また、不採用が続く場合は、履歴書の見直しや面接練習を行うことで改善できるケースもあります。
「開示=不利」ではなく、「伝え方次第で印象が変わる」という視点を持ち、必要に応じて支援機関のフォローを受けましょう。
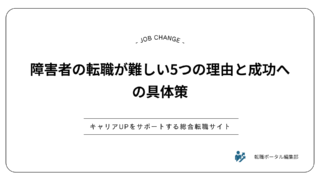
まとめ:障害があっても「納得できる働き方」は選べる時代
障害者の転職は、制度やサポートの充実により年々チャンスが広がっています。
大切なのは「自分に合った情報源と支援を活用し、自分らしいキャリアを選び取る」ことです。
この記事では、転職市場の動向から、活用できる支援制度、職種別の選び方、年代別の戦略までを網羅的に解説しました。
これらを踏まえて、転職活動で特に意識しておきたいポイントは以下の通りです。
- 法定雇用率の引き上げにより、障害者の採用ニーズは年々高まっている
- 支援サービスやエージェントを使うことで、自己理解や書類作成、面接対策の質が大きく向上する
- IT・在宅勤務・短時間勤務など、ライフスタイルに合った求人も増加中
- 年齢や障害の種類に応じた「選び方の戦略」がある
- 障害開示の仕方や交渉の仕方で、採用結果も大きく変わる
障害のある転職者にとって、選択肢は想像以上に豊富です。
「自分には無理かも」と感じた時こそ、情報を正しく整理し、前向きな一歩を踏み出してみてください。
あなたにとっての「働きやすさ」と「やりがい」の両立は、きっと実現できます。
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓