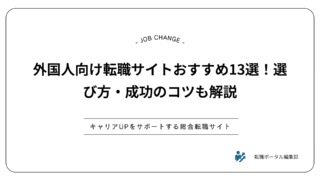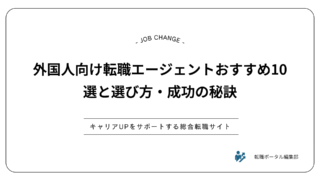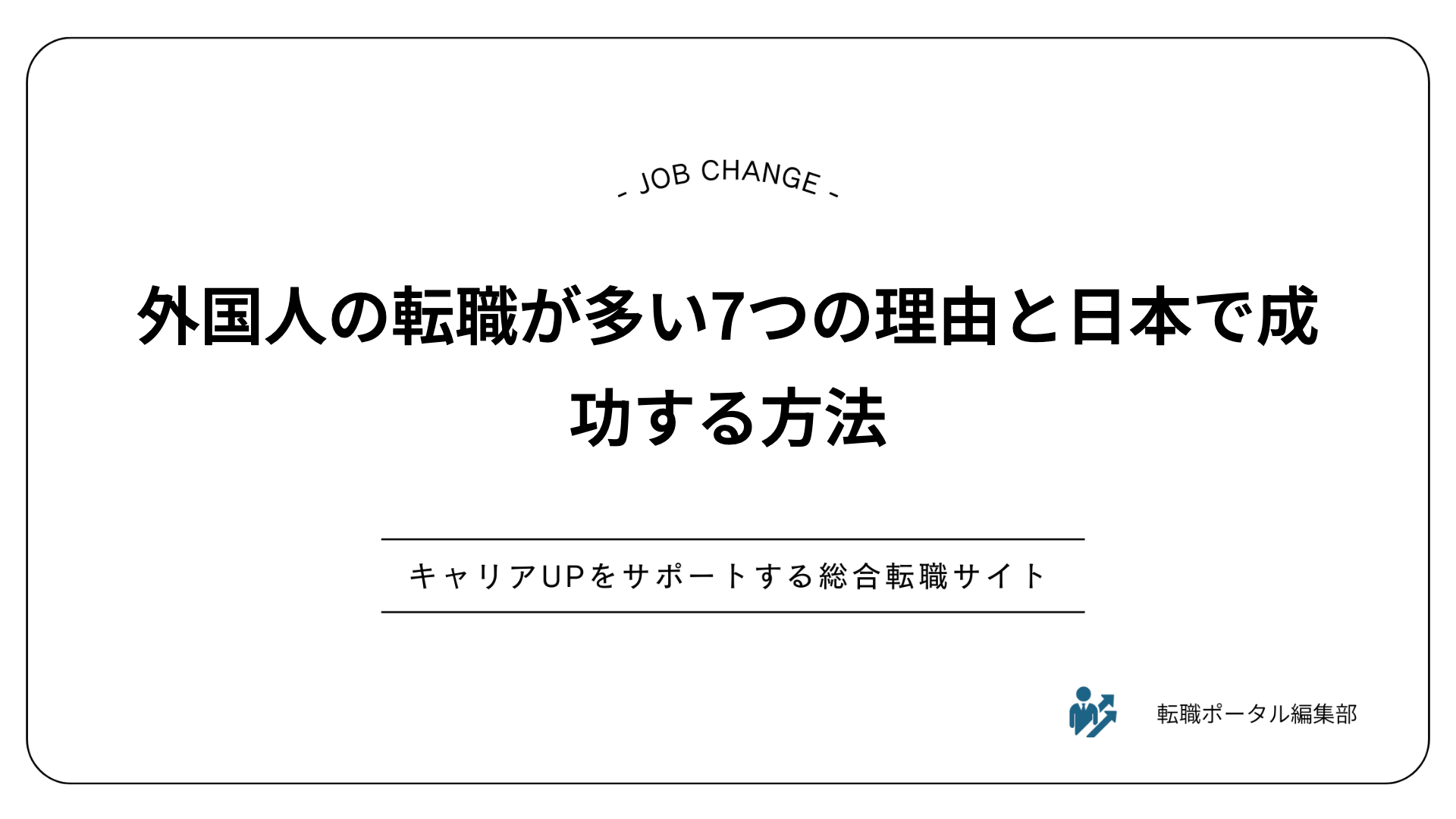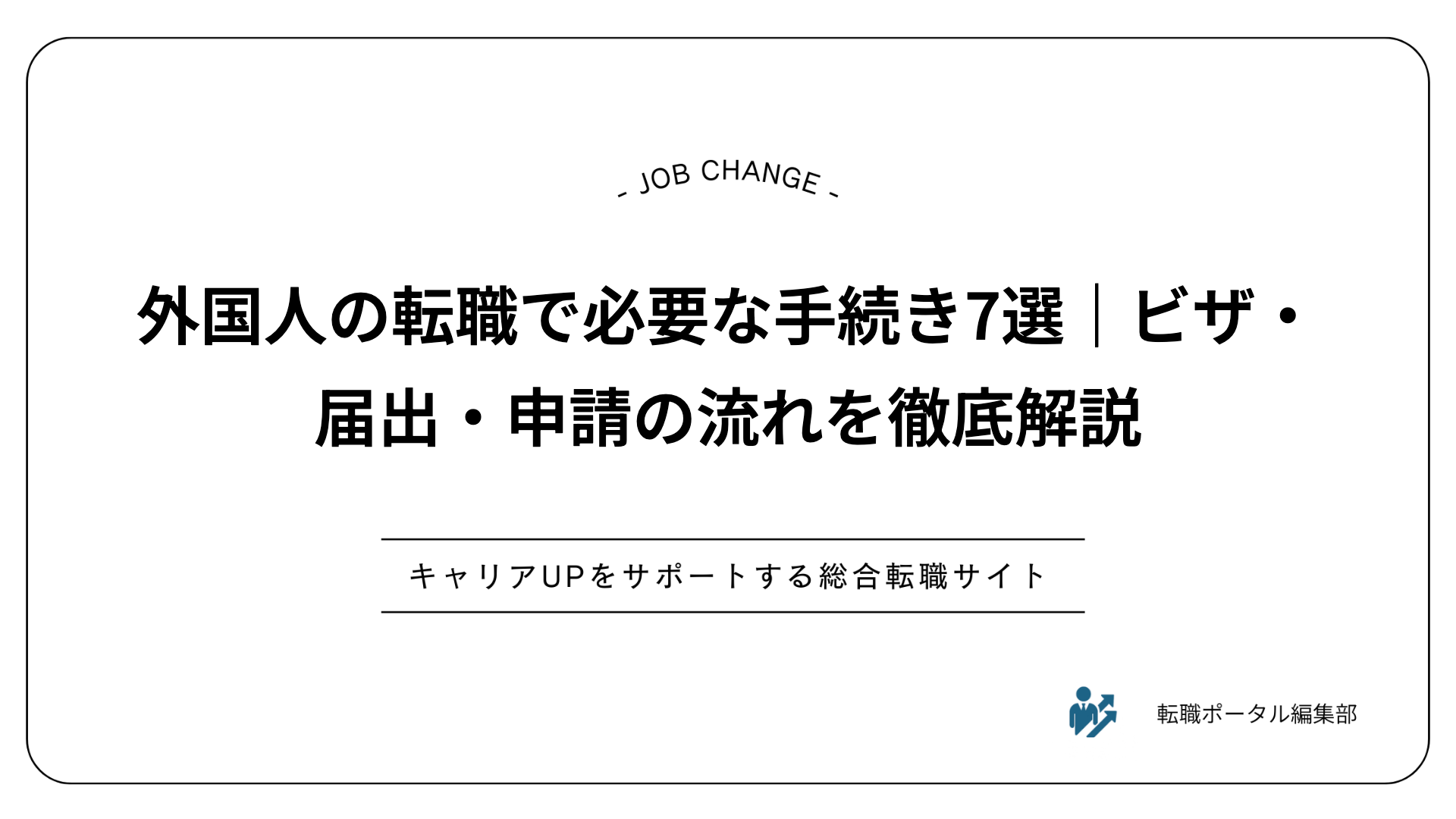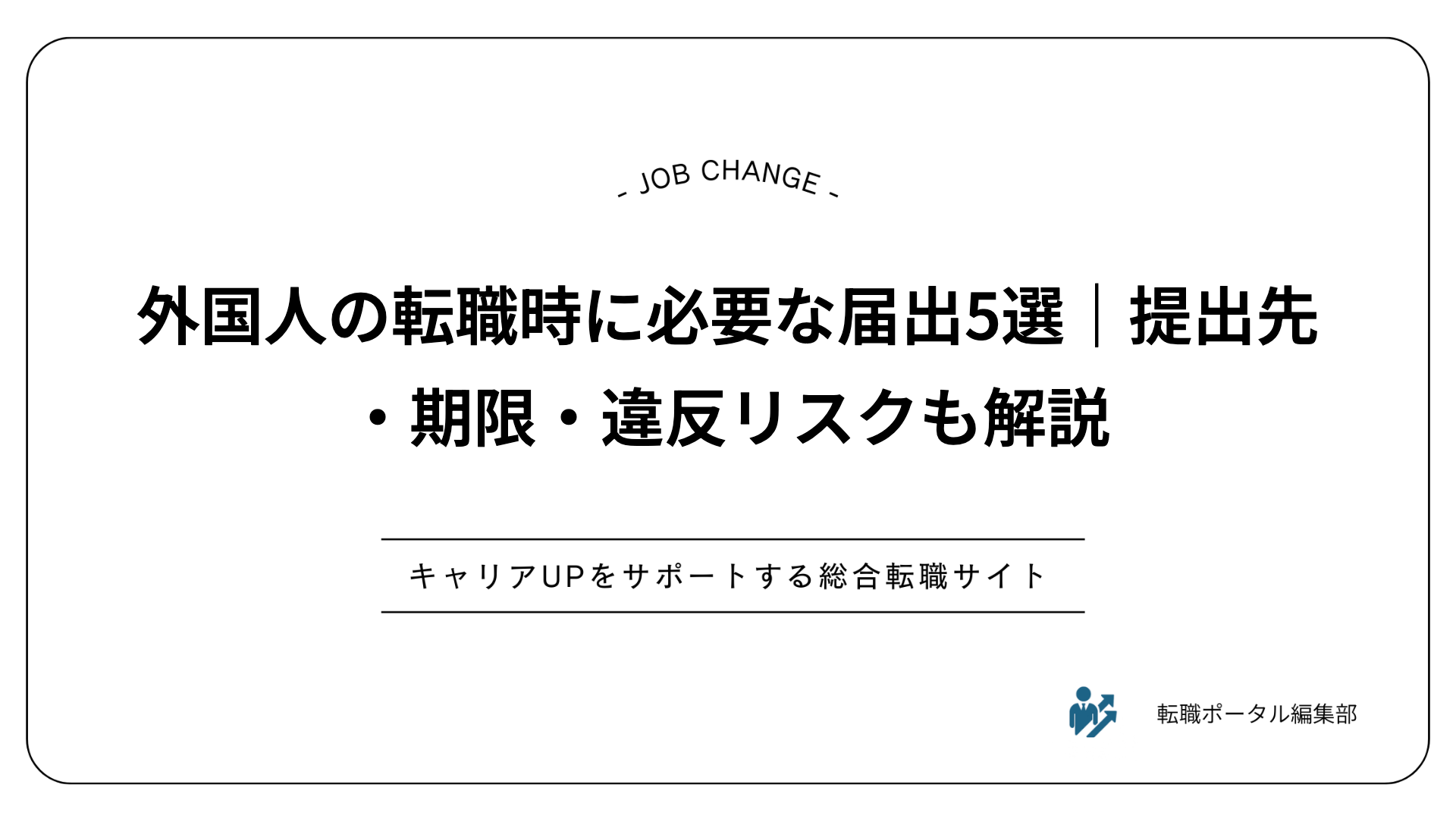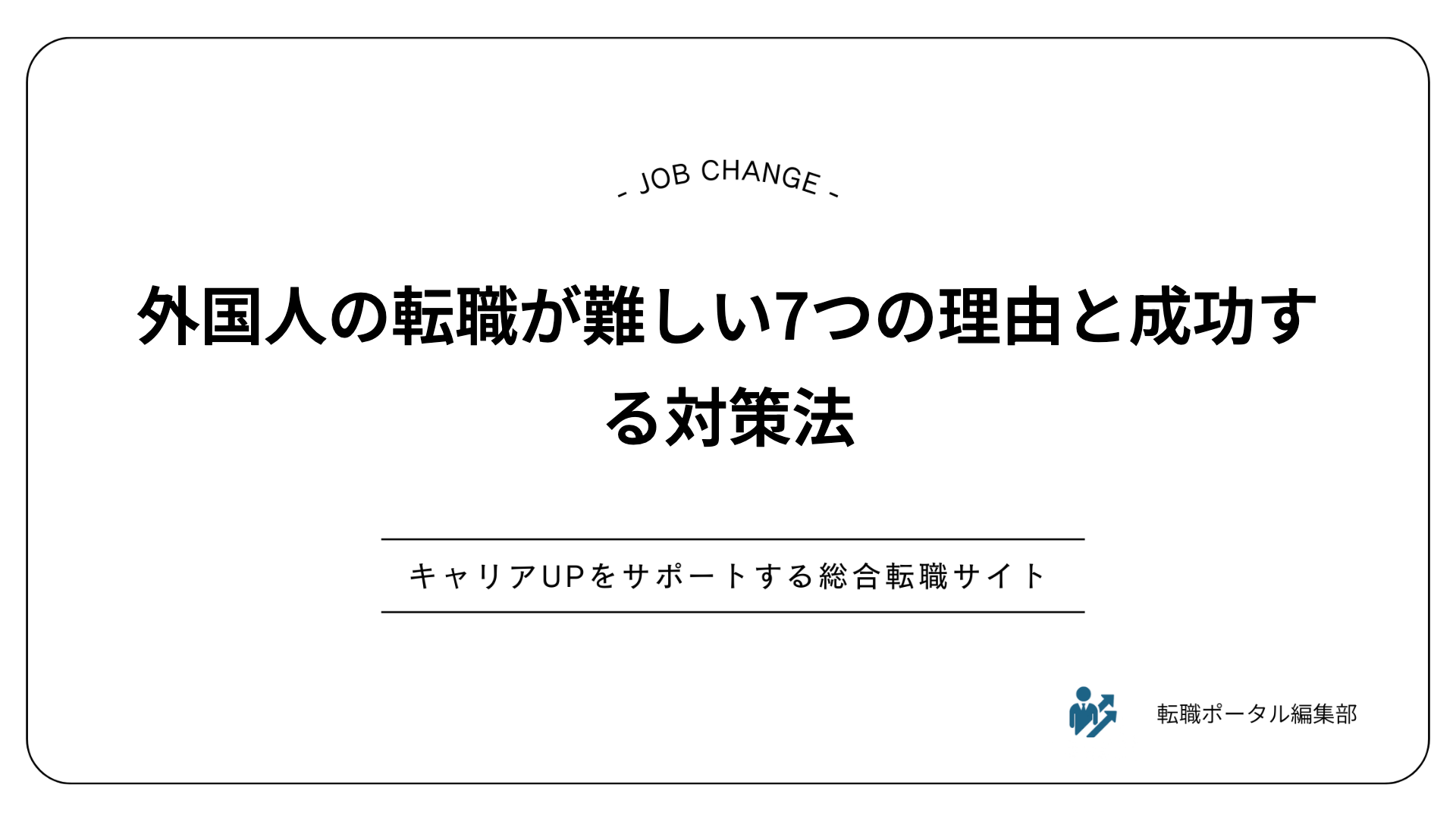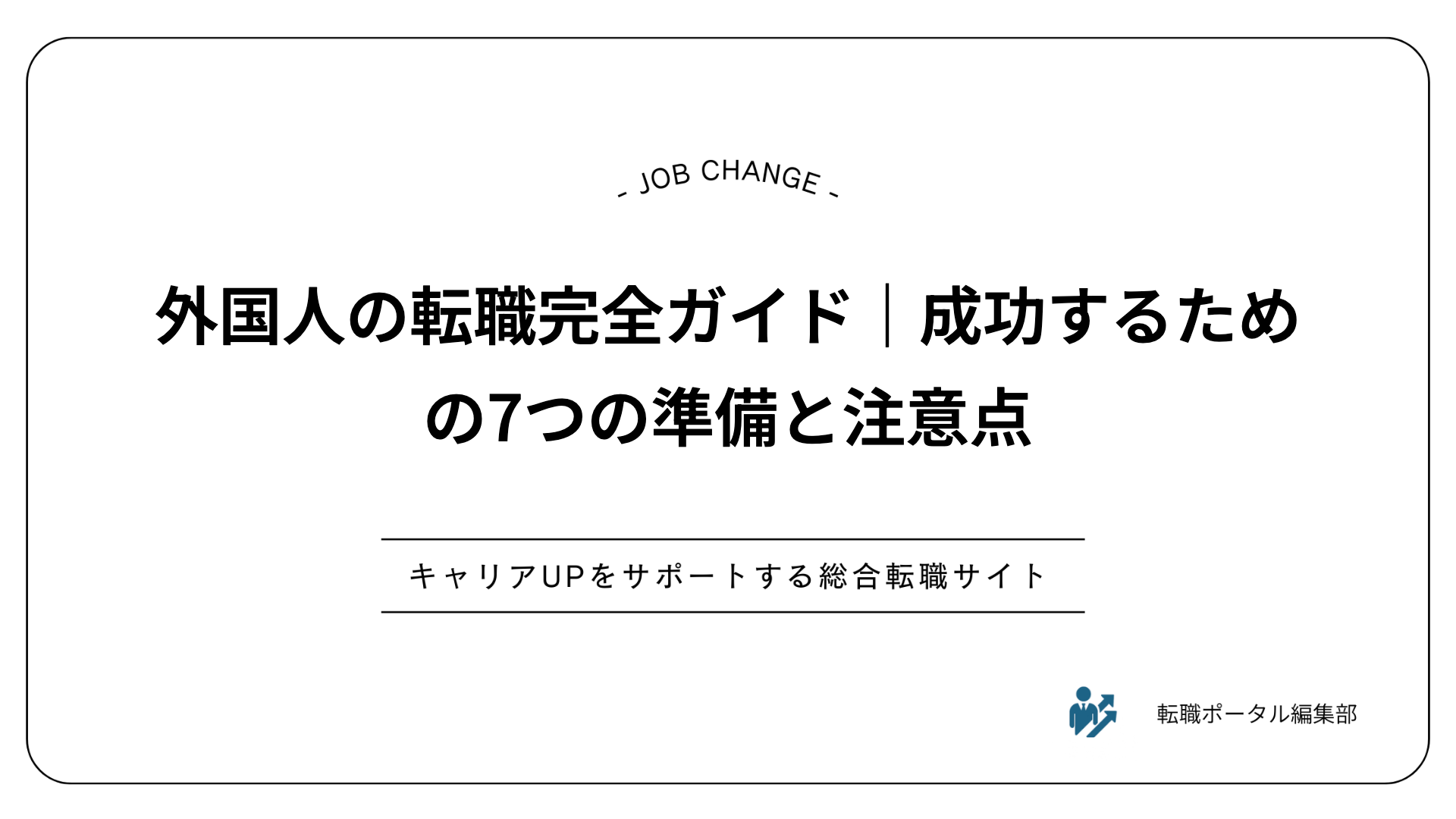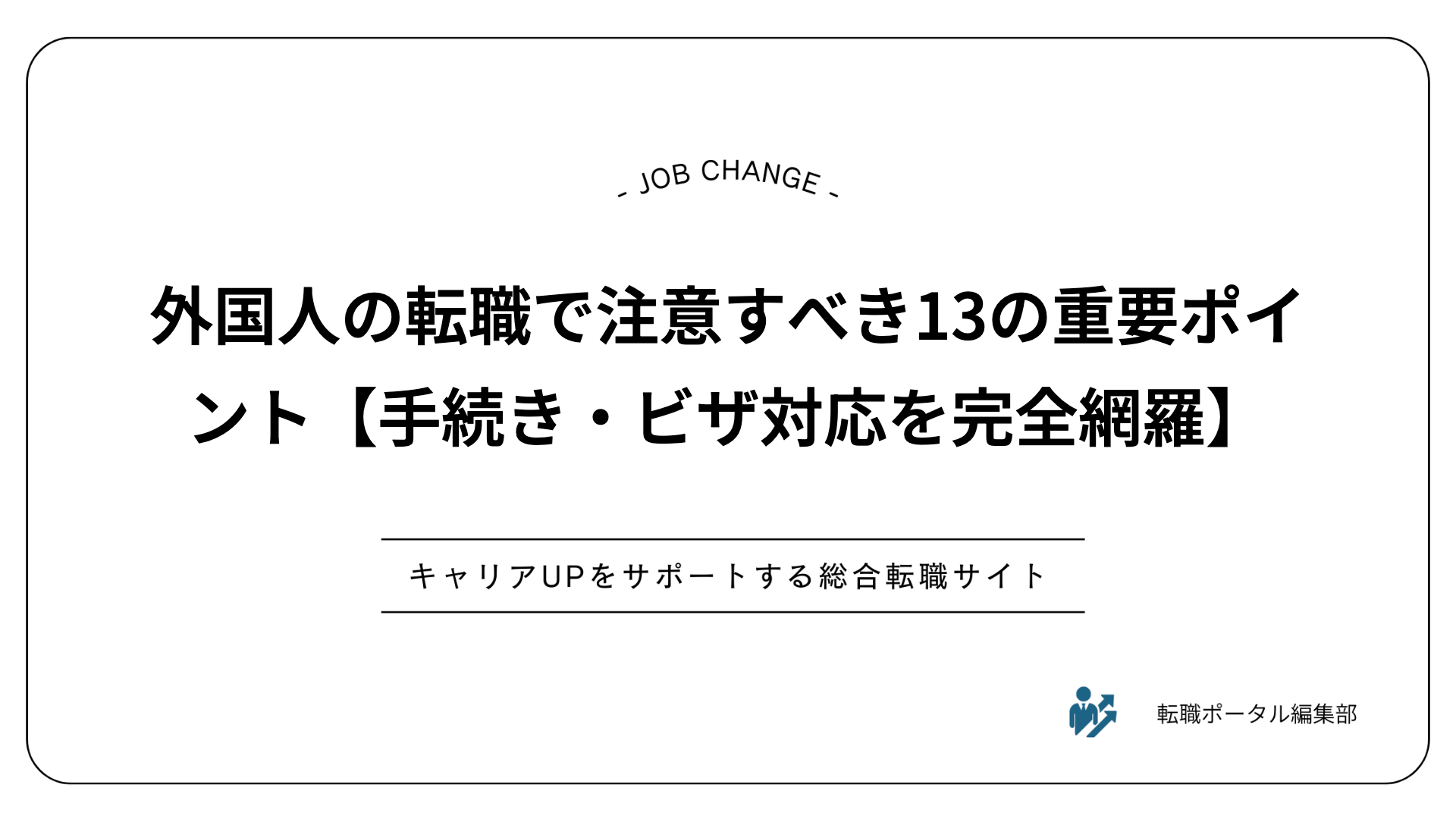外国人の転職とビザ手続き完全マニュアル|7つの注意点と届出・変更の流れ
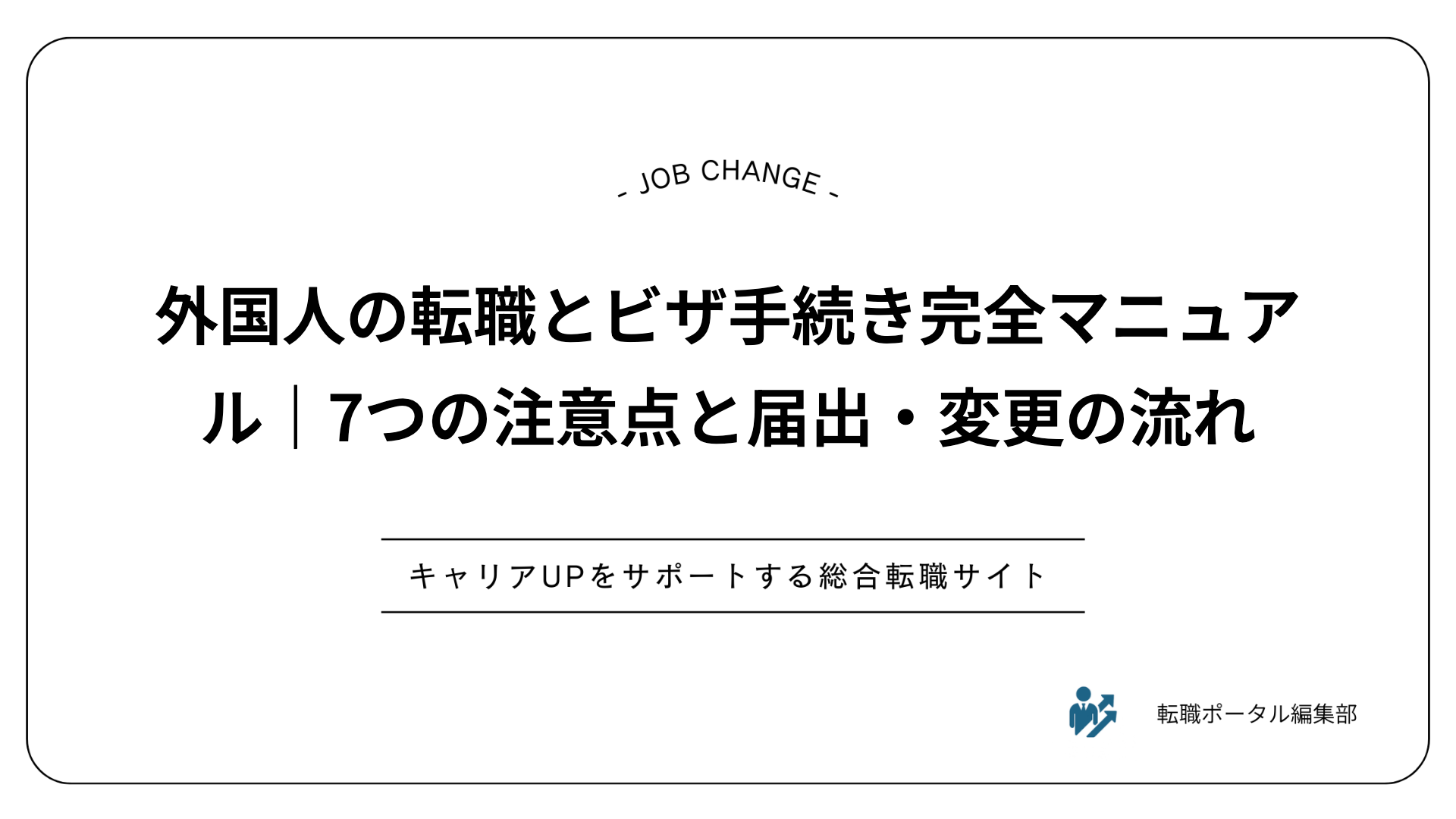
「日本で転職したいけど、ビザの手続きってどうすればいいの?」「転職したら在留資格って変えなきゃいけないの?」
外国人として日本で働いている方にとって、転職はキャリアアップのチャンスである一方、ビザや届出のルールが分かりにくく、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな不安を解消するために、外国人の転職にともなうビザの変更・届出・注意点などをわかりやすくまとめています。
- どんな在留資格なら転職が可能か
- 転職後に必ず必要な3つの届出
- ビザ変更が必要かどうかの判断ポイント
- 企業が採用時に気をつけるべき手続き
- 就労資格証明書の取得方法とメリット
転職を検討している外国人本人はもちろん、外国人を雇用する企業担当者にとっても役立つ内容です。
正しい手続きで安心して次のステップに進みましょう。
就労ビザ保持者は転職できる?基本ルールと前提
転職が認められる在留資格の種類(技人国・特定技能など)

外国人が日本で就労するためには、原則として就労可能な在留資格(いわゆる「就労ビザ」)が必要です。
そのなかで転職が認められる在留資格として、次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国):一般的なオフィスワークに対応
- 高度専門職:研究や経営など高度な職種に対応
- 特定技能:人手不足分野での就労が可能
- 企業内転勤:グループ企業内の異動に対応
これらの資格では、在留期間中であれば一定の条件下で転職が可能です。
たとえば技人国ビザでIT企業に勤務していた場合、同じ職種・業種への転職であれば、在留資格の変更は必要ないケースが多いでしょう。
まずは、自身のビザがこれらに該当するかを確認することが転職の第一ステップです。
転職が制限される在留資格と例外条件
一方、自由な転職が認められていない在留資格もあります。
- 技能実習:原則として転職不可
- 留学・家族滞在:就労活動自体が限定的
- 研修:受け入れ機関の変更が主で、転職とは扱われない
これらの資格では、基本的に企業の変更や業務内容の変更は認められていません。
ただし、技能実習生が不当な労働環境から保護される場合などには、例外的に「特定技能」への変更を通じて就労継続が可能になることもあります。
「今のビザでは転職できないかも…」と思ったら、専門家に相談して道があるかどうかを探ってみましょう。
在留期間中でも転職できるかを判断するポイント
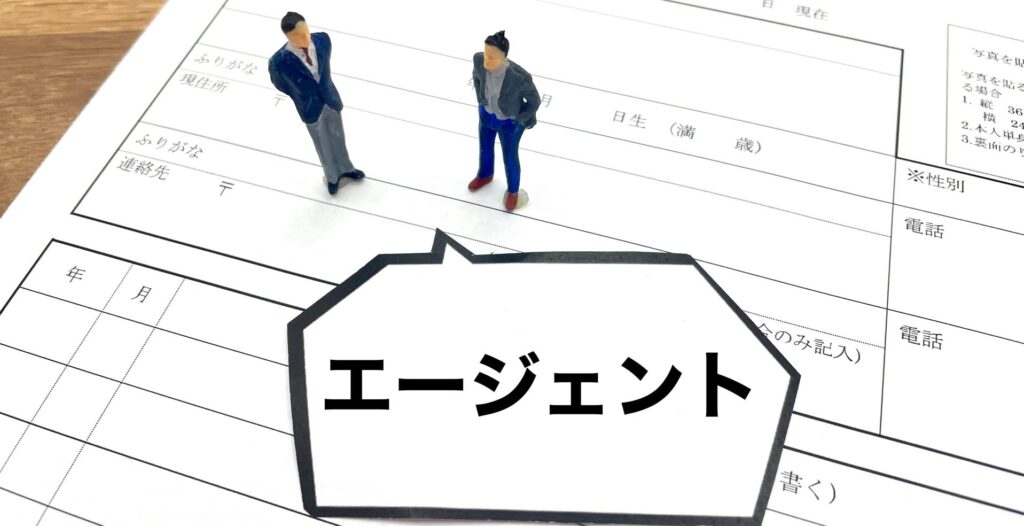
在留期間内だからといって、常に転職が自由とは限りません。
転職可否の判断には、以下のような観点が重要です。
- 職務内容が同一分野であるか
- 現在の在留資格で行える業務に該当しているか
- 在留期間が3か月以上残っているか
例えば、マーケティング職から経理職への転職など、職務のカテゴリーが異なる場合は、資格変更が必要になる可能性があります。
また、在留期限が近い場合は、審査の難易度が上がることもあるため、なるべく早めの行動がカギとなります。
「あと2か月あるし余裕でしょ」と思っていると、思わぬ落とし穴になることもあるので注意しましょう。
転職時に必ず行う3つの届出手続き
契約機関に関する届出(14日以内)の提出方法
外国人が転職をした際には、「契約機関に関する届出」を14日以内に行う必要があります。
これは法的な義務であり、提出を怠ると在留資格の更新や変更時に不利になる可能性があります。
この届出は、出入国在留管理庁へ提出します。手続きはオンラインと郵送のどちらでも対応可能ですが、以下の情報が必要です。
- 退職日または就職日
- 新たな勤務先の名称・住所・業種
- 本人の在留カード番号
オンラインでの手続きには、マイナンバーカードと「在留カード読み取り対応スマートフォン」もしくはICカードリーダーが必要です。
「会社を辞めただけだから、特に何もしなくていい」と思ってしまいがちですが、これは重大なミスになります。期限を守って届出を行いましょう。
外国人雇用状況の届出―企業側が行う義務
外国人が転職する際、転職先企業にも法的な義務があります。その中でも重要なのが「外国人雇用状況の届出」です。
この届出は、雇用主(会社)がハローワークに対して行うもので、外国人を新たに雇ったとき、または退職したときに、それぞれ14日以内に届け出る必要があります。
なぜこの手続きが必要かというと、政府が外国人労働者の就労実態を正確に把握するためです。
届出を怠ると、雇用主に対して30万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際の手続きでは、雇用契約書や在留カードのコピーなどが必要になり、書式はハローワークまたは厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。
企業としては「忘れていた」では済まされない義務なので、外国人を採用した場合は速やかに対応を進めましょう。
「この手続きは本人がやるものじゃないの?」と思うかもしれませんが、これは企業が行う義務なので要注意です。
退職報告書の提出フローと必要書類

外国人本人が退職した場合に行うべき手続きとして、「退職に関する届出」も必要です。
正式には「契約機関に関する届出」と同じ手続きの一部ですが、退職した事実のみを届け出る場合をこう呼ぶこともあります。
- 退職日とその企業名を記載
- 在留カード番号
- 提出先は出入国在留管理庁
郵送の場合は「契約機関に関する届出書」を印刷して記入し、在留カードのコピーを添付の上、入管に送付します。
オンラインでも提出可能ですが、マイナンバーカードやICリーダーが必要です。
退職日から14日以内に行うことが義務となっており、これを怠ると将来のビザ更新や変更審査に悪影響を及ぼすことがあります。
退職直後は忙しくなりがちですが、この手続きは忘れずに済ませておきましょう。
さらに詳しく、必要な届出について解説した記事はこちら↓
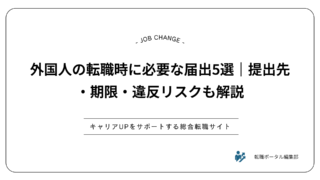
ビザ変更が必要か判断するチェックリスト
職務内容がビザの活動範囲外へ変わるケース
転職にあたって、職務内容が大きく変わる場合は、現在の在留資格では対応できず、ビザ変更が必要になる可能性があります。
たとえば「通訳・翻訳業務(技人国)」から「飲食店の接客業務」へ転職する場合、在留資格の範囲を超えるため、新たに「特定技能」などへの変更が求められます。
この判断は非常に重要で、変更を怠ったまま就労を続けると「資格外活動」に該当し、在留資格取消や強制退去処分を受けるリスクがあります。
不安がある場合は、転職先の職務内容が自分の在留資格に該当するかどうか、入管や行政書士など専門家に必ず確認するようにしましょう。
「似た業界だから大丈夫だろう」と思い込む前に、法律上の区分を明確に知ることが大切です。
在留期限が3か月未満の場合の注意点

転職を検討している際に、在留資格の残存期間が3か月を切っている場合は特に注意が必要です。
なぜなら、在留期間が短い状態では、就労資格証明書の取得や在留資格変更申請に十分な時間が確保できず、結果として転職先で働けないリスクがあるからです。
転職活動を開始する時点で、少なくとも在留期間が3か月以上残っているかを確認しましょう。
また、在留期限が迫っていると、入管審査で「転職の継続性」や「就労の安定性」が疑われる可能性があるため、審査が厳格になる傾向があります。
そのため、転職と在留期間更新を同時並行で進める場合には、専門家のサポートを受けながら計画的に動くことが求められます。
「まだ更新の時期じゃないから放っておこう」と考えていると、いざ転職するタイミングで手遅れになる可能性もあるので、早めの確認と準備が肝心です。
高度専門職・特定技能など特殊ビザからの転職パターン
高度専門職ビザや特定技能ビザなど、特定の活動に限られた在留資格で働いている外国人が転職を希望する場合には、より複雑な条件が関わってきます。
- 高度専門職はポイント制で許可されるため、転職後も70ポイント以上の基準を満たす必要がある
- 特定技能は分野が決められており、業種を跨いでの転職は原則不可
- 一部の特定技能では「業務区分」内での転職は可能
たとえば「特定技能(外食業)」の資格を持つ人が「宿泊業」に転職する場合、在留資格の変更申請が必要となります。
一方で、高度専門職であれば、転職後の企業が自分のキャリアや学歴を活かせる職種であり、年収や勤務条件が基準を満たしていれば、そのまま継続できる可能性もあります。
ただし、こうした判断は非常に繊細であるため、自己判断せずに行政書士や入管窓口での事前相談をおすすめします。
在留資格変更許可申請の流れと必要書類
申請前に準備する書類一覧(雇用契約書・履歴書・説明書など)
在留資格の変更申請を行う際は、事前にいくつかの重要な書類を用意しておく必要があります。
- 新たな勤務先との雇用契約書
- 履歴書・職務経歴書
- 活動内容に関する説明書(職務内容を記載)
- 勤務先企業の登記簿謄本や決算書
- 在留カード・パスポートのコピー
このうち、特に重要視されるのが「職務内容説明書」と「雇用契約書」です。
これらは、転職後の業務が現在または変更予定の在留資格に合致しているかどうかを判断するための資料となります。
企業が中小規模であっても、法務省が提示する要件(安定性・継続性)を満たしていることを示すための資料が求められる点にも注意しましょう。
「書類の準備が不十分だったせいで審査に時間がかかった…」というケースは多いため、抜け漏れなく整えることが重要です。
就労資格証明書交付申請のメリットと取得手順

転職にともなって在留資格は変わらなくても、念のため「就労資格証明書」の交付を受けておくと安心です。
この証明書は、現在の在留資格で新しい職場での業務が適法であることを出入国在留管理庁が認める文書で、取得しておくことで将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
- 手続き先:最寄りの出入国在留管理局
- 提出書類:雇用契約書、在留カード、パスポート、申請書
- 申請費用:無料(証明書の交付に手数料は不要)
証明書は就労資格に関する行政の「お墨付き」として、転職後の在留期間更新や将来的な永住申請でも有利に働くことがあります。
「ビザは変わらないから別に必要ないでしょ」と思いがちですが、実際には取得しておくことでリスクを回避できる重要な手続きなのです。
審査期間と結果通知までのタイムライン
在留資格変更許可申請を行った場合、審査から結果通知までは平均して1〜3か月ほどかかるのが一般的です。
ただし、申請内容や申請先の管轄入管の混雑状況によって前後するため、必ず余裕を持って行動することが大切です。
通知は「はがき」で届くケースが多く、その後、入管に出頭して新しい在留カードを受け取る手続きへと進みます。
なお、申請中に現在の在留資格が切れる場合でも、「特例期間(最大2か月)」が与えられ、在留継続が認められることがあります。
ただし、この特例を過信するとリスクが高まるため、転職活動と申請準備は在留期限よりもかなり前から始めておくべきでしょう。
「申請したけど、いつまで待てばいいの?」と不安になる方もいますが、申請から1か月経っても通知が届かない場合は、管轄の入管に状況を確認するのも一つの方法です。
ビザ変更が不要でも就労資格証明書を取得すべき理由
証明書が転職後のリスクを減らす仕組み

就労資格証明書は、転職後に「不法就労」と判断されないための予防線となります。
特に、同じ在留資格のまま転職した場合でも、新たな職務が現在の資格に合致しているかは自己判断では確定できません。
この証明書を取得しておけば、後日入管から「資格外活動」だと指摘される可能性を大きく減らせます。
また、企業側にとっても「雇用リスクを軽減する証拠」となるため、採用活動時に安心材料として活用できます。
「資格は変わらないのに、どうしてこんな書類が必要なの?」と思うかもしれませんが、後からトラブルになるよりも、先に確認しておく方がずっと安全です。
申請から受領までのステップ
就労資格証明書の取得は比較的シンプルな手続きです。以下のようなステップで進みます。
- 申請書に記入(出入国在留管理庁のサイトでダウンロード可能)
- 雇用契約書・職務説明書・在留カードなどを準備
- 最寄りの入管へ申請書類を提出
- 1〜2か月後に交付通知を受け取り、入管で証明書を受領
なお、就労資格証明書の申請は転職からすぐ行うことが望ましく、可能であれば就業開始のタイミング前に取得できるように準備するのが理想です。
「申請しなきゃダメ?」と思う人も多いですが、法的義務ではなくても取得することで得られるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
転職前後で気を付けるポイントとNG行動
アルバイト・副業の制限と罰則
現在の在留資格が認めている職務範囲を超えたアルバイトや副業は、「資格外活動」に該当し、重大な罰則を受ける可能性があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人は、契約している会社で定められた職務のみに従事することが原則です。
副業やアルバイトをするには、入管に「資格外活動許可」を申請・取得しなければなりません。
- 無許可の副業は不法就労と判断され、退去強制や再入国禁止の対象に
- 副業の内容が在留資格と一致する場合でも、許可なしでの活動は違法
- 勤務時間や報酬に関係なく違反と見なされることがある
「ちょっとだけなら大丈夫」と軽く考えるのは危険です。副業を考えるなら、事前に許可を得てから始めましょう。
失業期間が発生した場合の在留資格の扱い

転職の合間に失業期間が発生した場合、その期間の扱いにも注意が必要です。
在留資格が「就労目的」である以上、一定期間無職の状態が続くと、「活動実績なし」と判断される可能性があり、在留資格の更新や変更が困難になる場合があります。
目安としては「退職後3か月以内に再就職先が決まっていない場合」、入管から事情説明や在留資格取消の警告を受けることがあります。
このリスクを避けるためにも、退職後は速やかに「契約終了の届出」を行い、転職活動中であることを証明できる書類(求人への応募履歴や面接記録など)を残しておくと安心です。
「ちょっとの間ならバレない」と放置すると、今後のビザ審査に響くため注意が必要です。
手続きを怠った場合の不許可リスクと対処法
転職や退職にともなう届出や申請を怠ると、将来的な在留資格の更新・変更が不許可になる可能性が高まります。
例えば、契約終了後に14日以内の届出をしていなかったり、転職後の業務が資格外活動に該当していた場合などは、ビザ更新時に厳しい指摘を受ける可能性があります。
不許可通知を受けた場合でも、すぐに帰国を迫られるとは限りませんが、以下の対応が必要です。
- 不許可理由の説明を受ける
- 必要に応じて行政書士などの専門家に相談
- 内容を是正して再申請を行う
過去の不備は履歴として記録され、将来の審査に影響することもあるため、初動の対応が非常に重要です。
「手続きに自信がない…」という方は、専門家に依頼して早めに対処するのが安心です。
さらに詳しい注意点はこちら↓
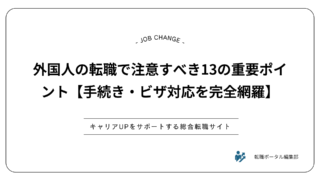
企業が外国人転職者を受け入れる際の義務と手続き
採用前に確認すべき在留資格と活動範囲
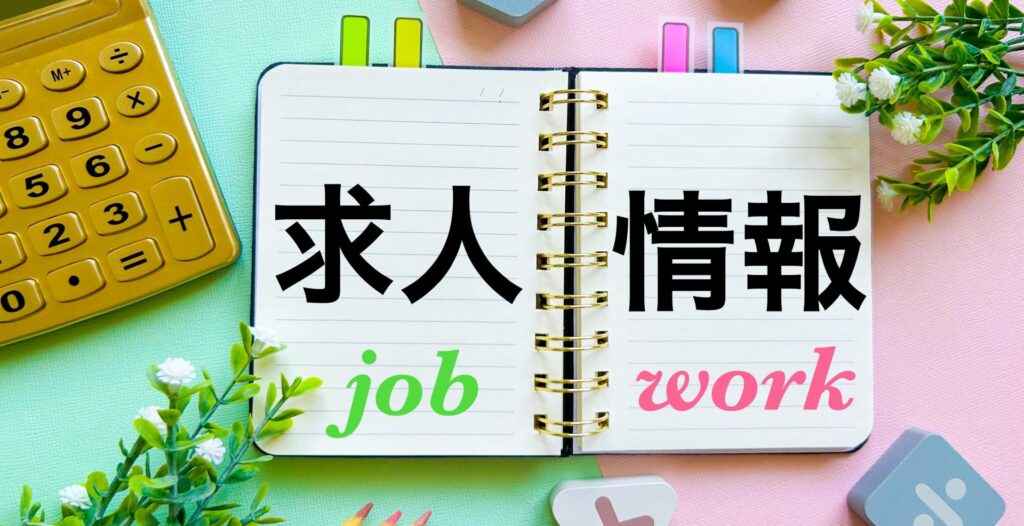
企業が外国人を採用する際には、まず「その外国人が保有する在留資格が、自社での職務に適しているか」を確認する必要があります。
たとえば、技術職のポジションに応募してきた外国人が「特定活動」ビザを所持している場合、そのままでは従事できないケースもあります。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 在留カードの在留資格と在留期限
- 現在の活動内容と自社業務の整合性
- 資格外活動許可の有無(必要に応じて)
特に中小企業では、「ビザがあるから大丈夫だろう」と誤認して採用してしまい、後から問題が発覚するケースもあります。
採用の初期段階で在留資格の適合性を確認することは、企業・本人双方のリスクを回避する第一歩です。
受入れ企業が行う届出・書類管理のチェックリスト
外国人を受け入れる企業には、雇用後にもいくつかの法的義務があります。これらを怠ると、企業側に罰則が科されるリスクがあります。
具体的に企業が行うべき対応を以下に整理します。
- 外国人雇用状況の届出(ハローワークに提出・採用後および離職時)
- 在留カードの有効期限や在留資格の確認と記録の保管
- 在留資格が許容する業務内容と実際の業務内容の整合性のチェック
- 雇用契約書の保存と更新記録の管理
これらの対応は単なる事務処理ではなく、企業のコンプライアンス維持の要でもあります。
「うちはまだ小規模だから…」と軽視すると、行政指導や処罰の対象になるおそれもあります。
罰則事例に学ぶコンプライアンス対応
実際に企業が適切な対応を怠ったことで、罰則を受けた事例も少なくありません。
たとえば、在留資格の確認を怠って技能実習生を適用外の職務に就かせた結果、雇用主が不法就労助長罪に問われたケースや、外国人雇用状況の届出を怠ったことにより、30万円以下の罰金処分を受けたケースも報告されています。
これらの事例から学べるのは、「知らなかった」や「うっかり」は免責にならないという点です。
正しい知識と適切な運用を徹底し、社内ルールとして明文化しておくことが、安全な外国人雇用の第一歩と言えるでしょう。
「外国人採用は不安…」と感じる場合は、社会保険労務士や行政書士と連携することで、スムーズに対応できます。
よくある質問(FAQ)
転職後すぐに海外出張はできる?

はい、基本的には可能です。
ただし、出国前に「転職に伴う届出(契約機関に関する届出)」を済ませていない場合、再入国時にトラブルになるリスクがあります。
特に在留カードに記載されている勤務先情報と実際の勤務先が異なっていると、不審に思われる可能性があります。
出張前に届出を終え、できれば就労資格証明書も取得しておくと安心です。
「忙しくて後回しにしてしまった…」では済まされない場面もあるので、早めの対応を心がけましょう。
配偶者ビザや永住ビザへの切り替えは可能?
はい、条件を満たしていれば可能です。
配偶者ビザへの切り替えには、日本人や永住者と正式に結婚していることが前提となり、結婚の実態や生活実態に関する証明書類が求められます。
永住ビザの場合は、原則10年以上の在留歴、日本での安定した収入、納税状況、素行などが審査対象です。
どちらのビザも在留資格変更申請が必要となるため、必要書類を事前に確認し、専門家と相談のうえ進めるとスムーズです。
不許可になった場合の再申請方法と注意点

在留資格変更や更新が不許可になった場合でも、再申請は可能です。
ただし、再申請前に不許可理由をきちんと確認し、それを是正した上で書類を整える必要があります。
以下のようなポイントに注意しましょう。
- 不許可通知書に記載された理由を確認
- 不足・不備がある書類を補完する
- 専門家(行政書士など)に添削・確認を依頼する
再申請での審査はより慎重になる傾向があるため、準備を怠らず万全な状態で臨むことが成功のカギです。
「不許可=もう終わり」ではないので、冷静に立て直して再チャレンジしましょう。
まとめ:外国人の転職とビザ手続きを正しく理解し、安心してキャリアを築こう
外国人が日本で転職する際には、在留資格の種類や職務内容に応じて、適切な届出やビザの確認・変更が必要です。
これらの手続きを正しく理解し、期限を守って対応することで、在留資格の維持や将来のビザ更新・永住申請にも有利に働きます。
- 転職可能な在留資格(技人国・特定技能など)を確認
- 退職・就職後14日以内の届出を忘れずに実施
- ビザ変更が必要かを職務内容・在留期限で判断
- 就労資格証明書の取得はリスク回避に効果的
- 企業側も適切な確認・届出・管理が求められる
実際に必要な手続きは多岐にわたりますが、それぞれのポイントを押さえておけば、転職による不安やリスクを最小限に抑えることができます。
「面倒そうだから後回しにしよう」と思わず、転職前後の行動を計画的に進めることで、日本でのキャリアを安心して継続していきましょう。
外国人の転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
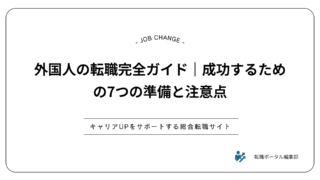
外国人の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓