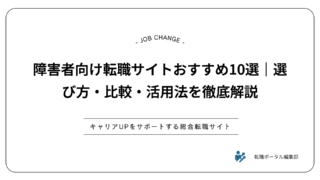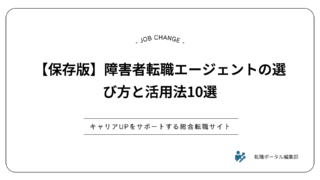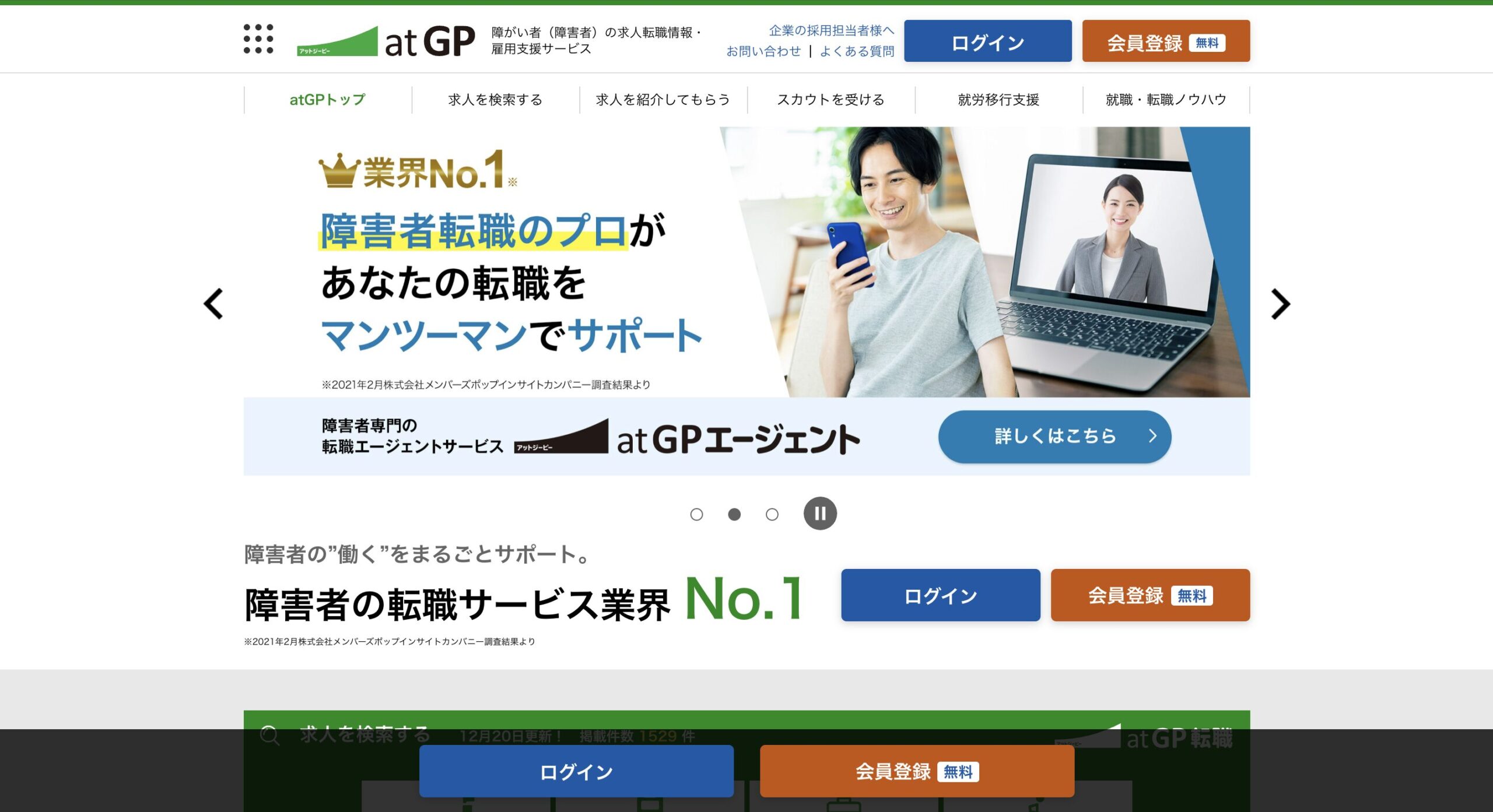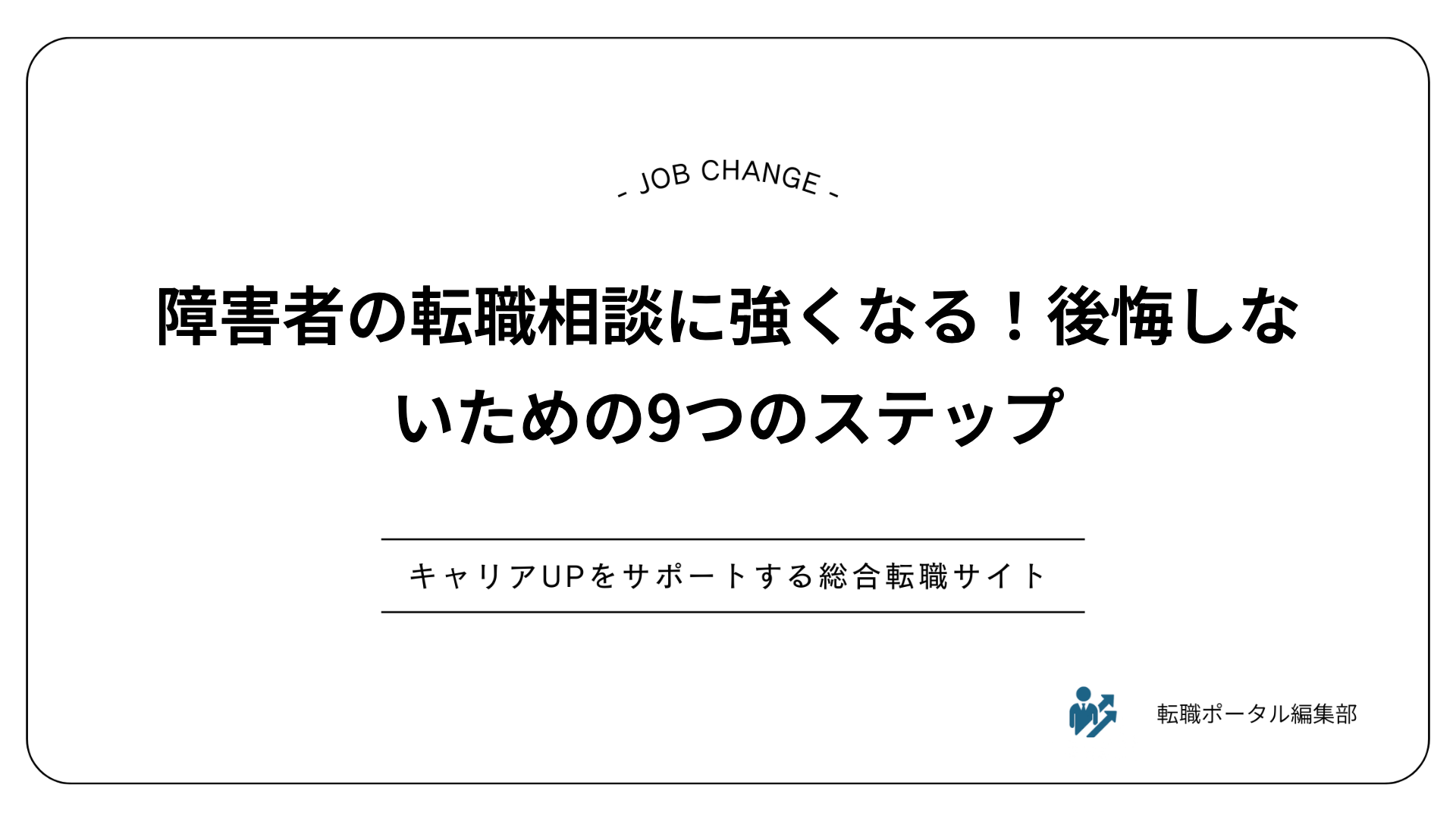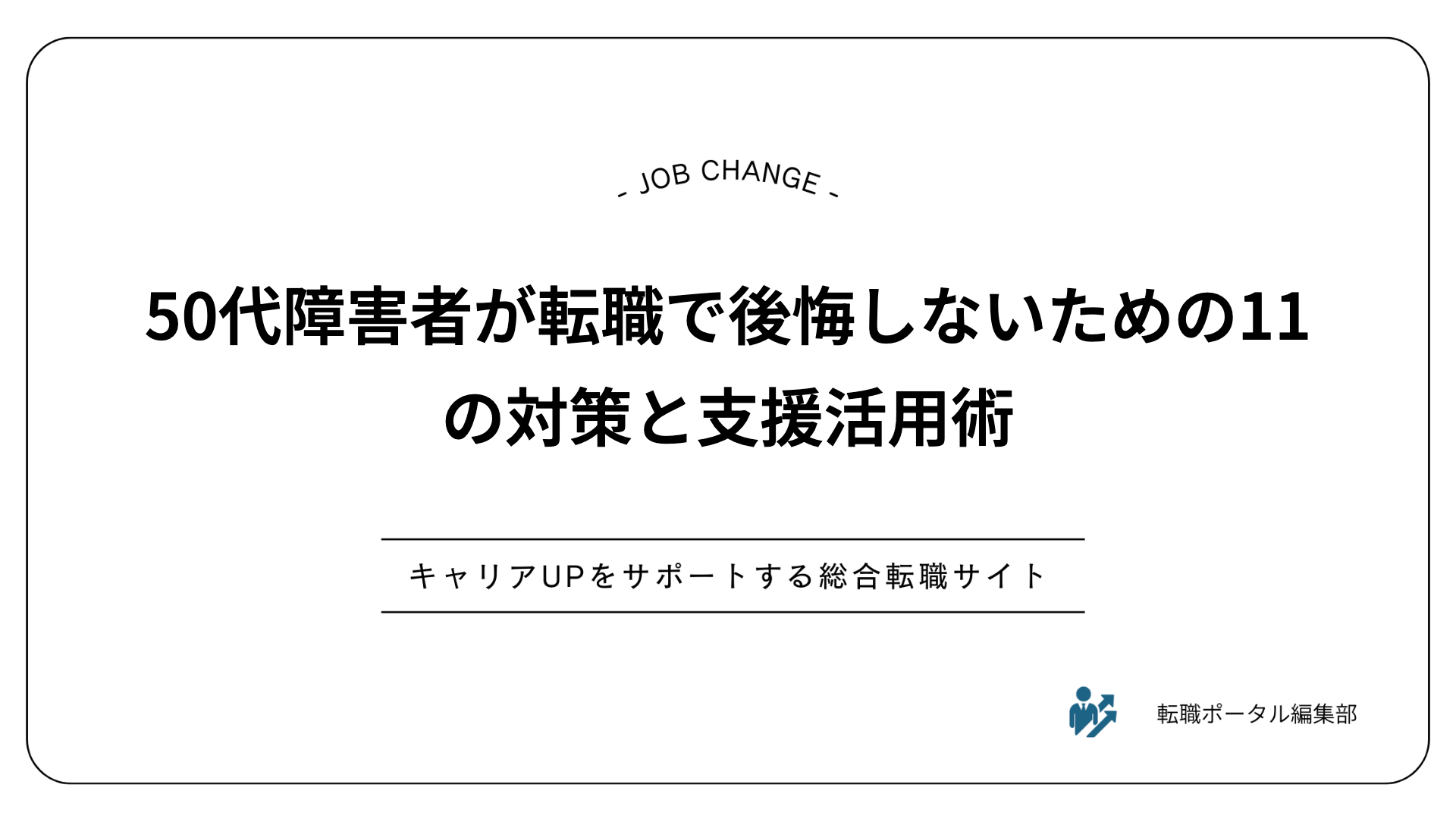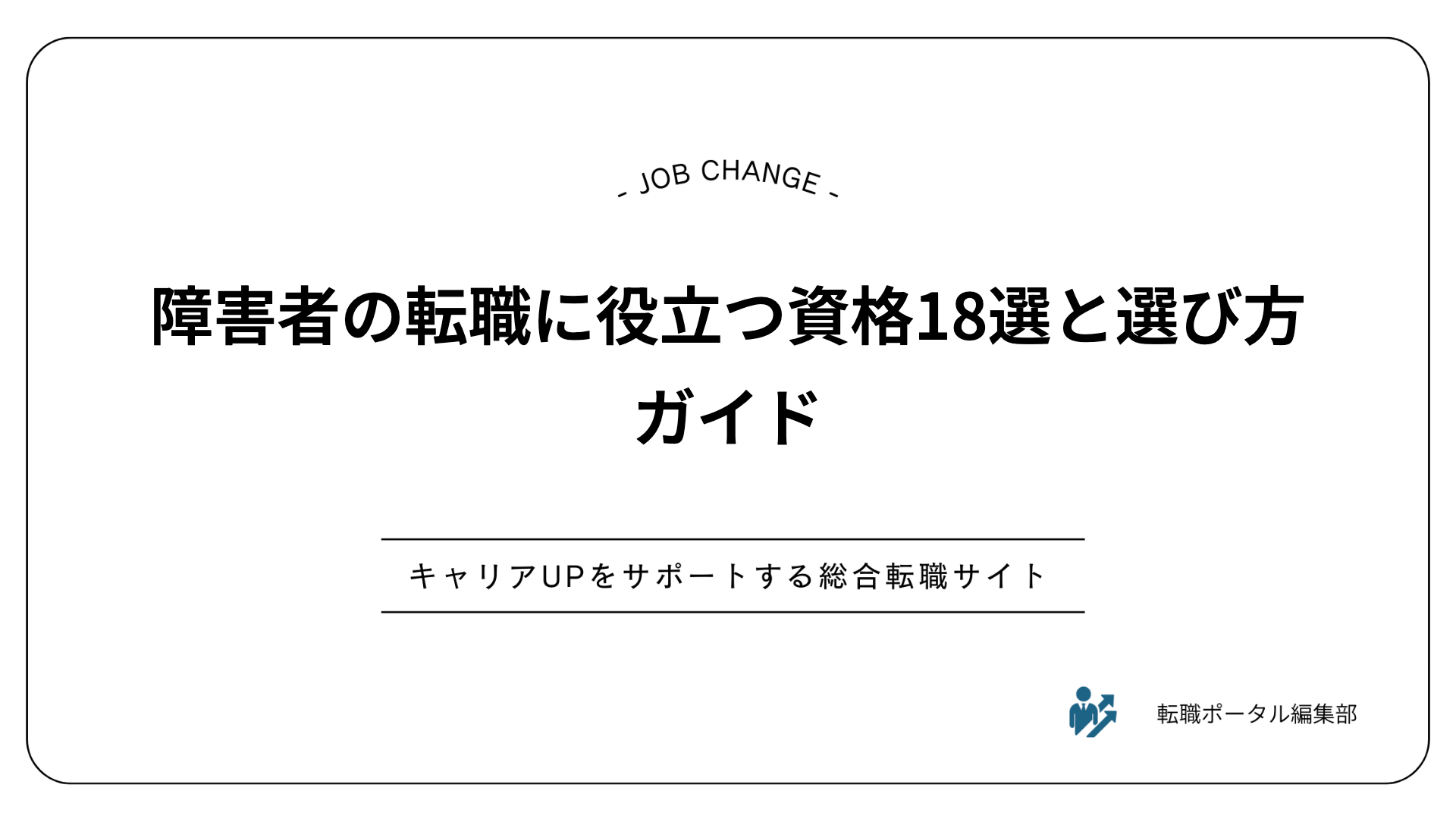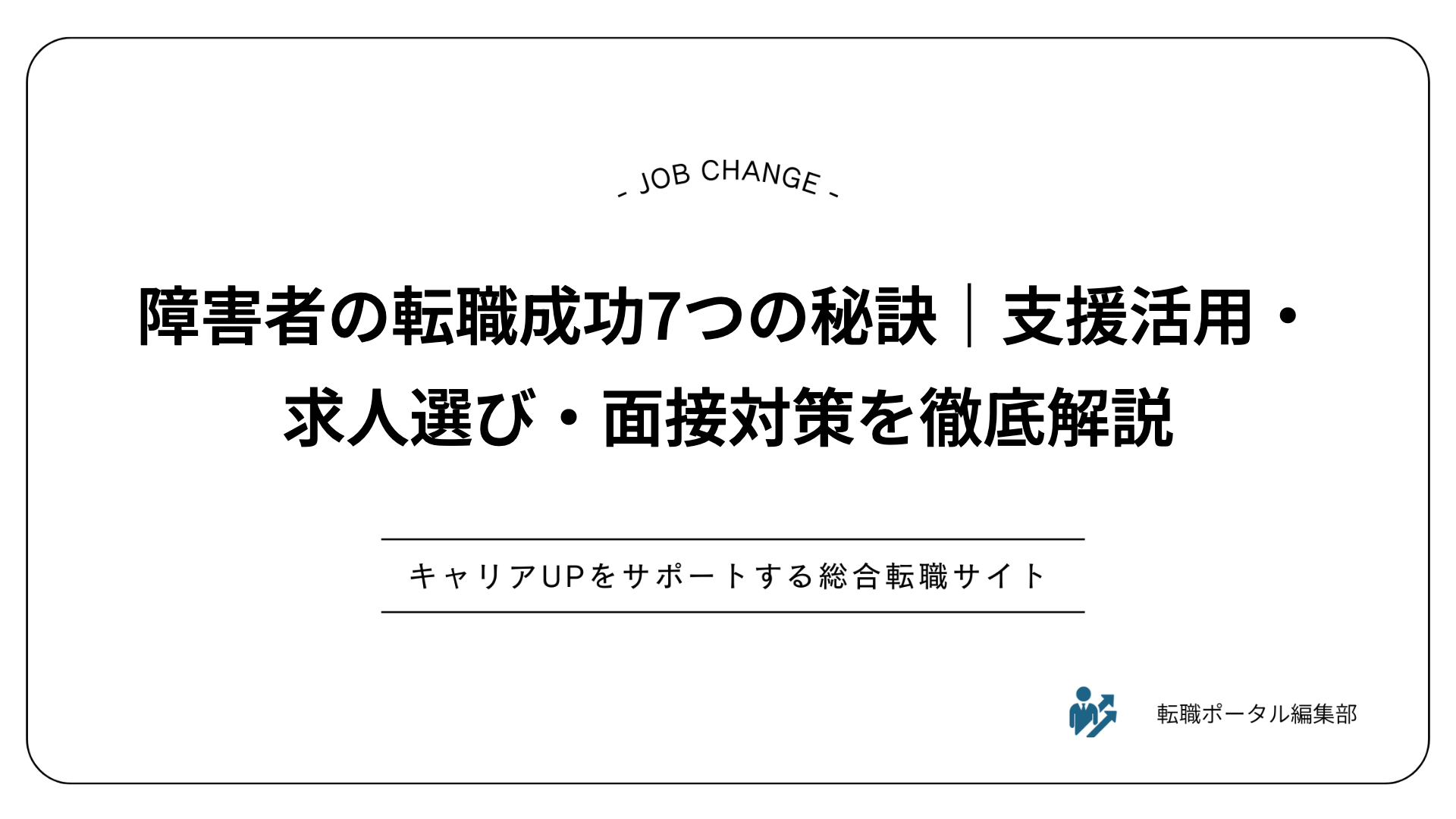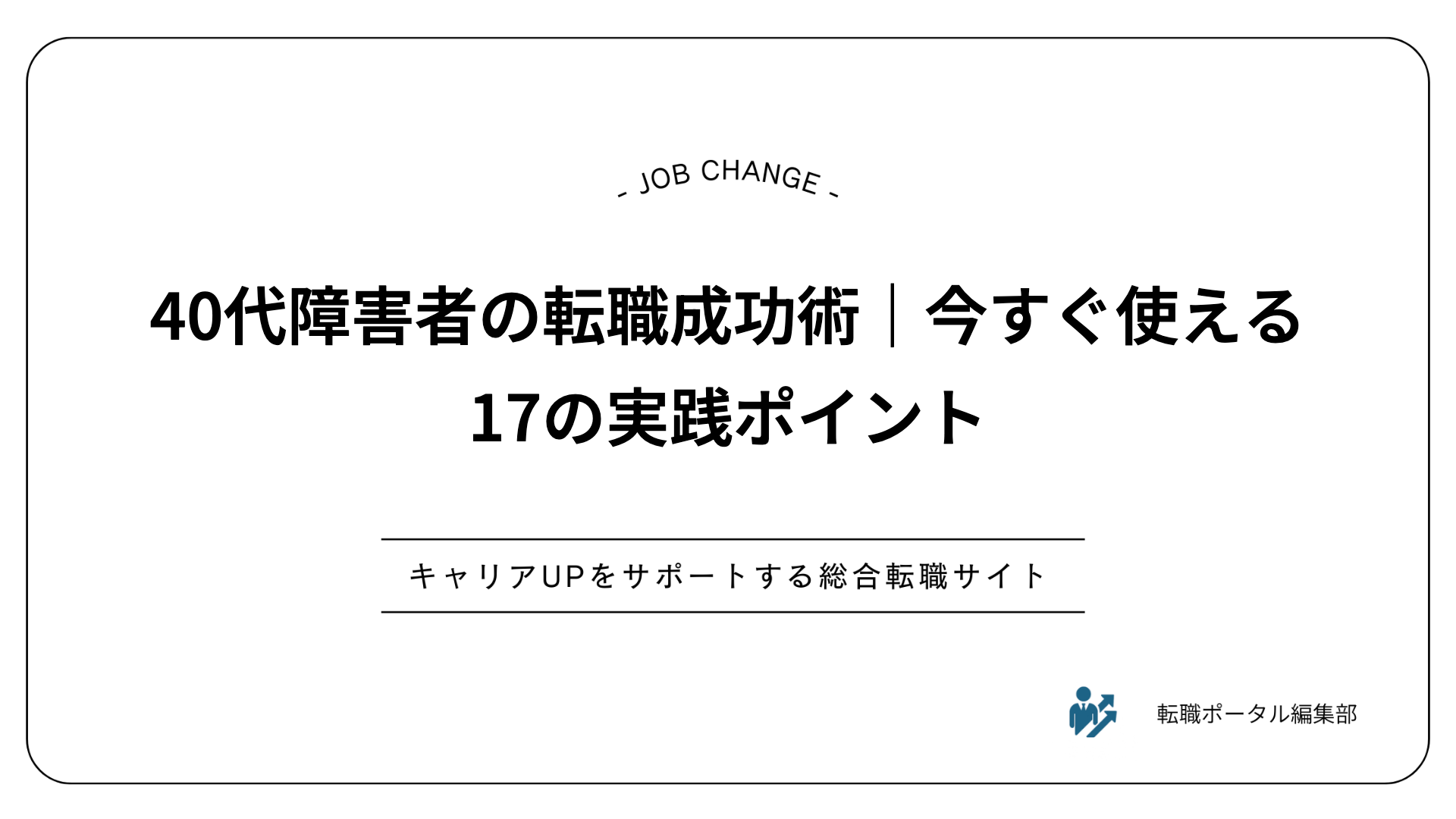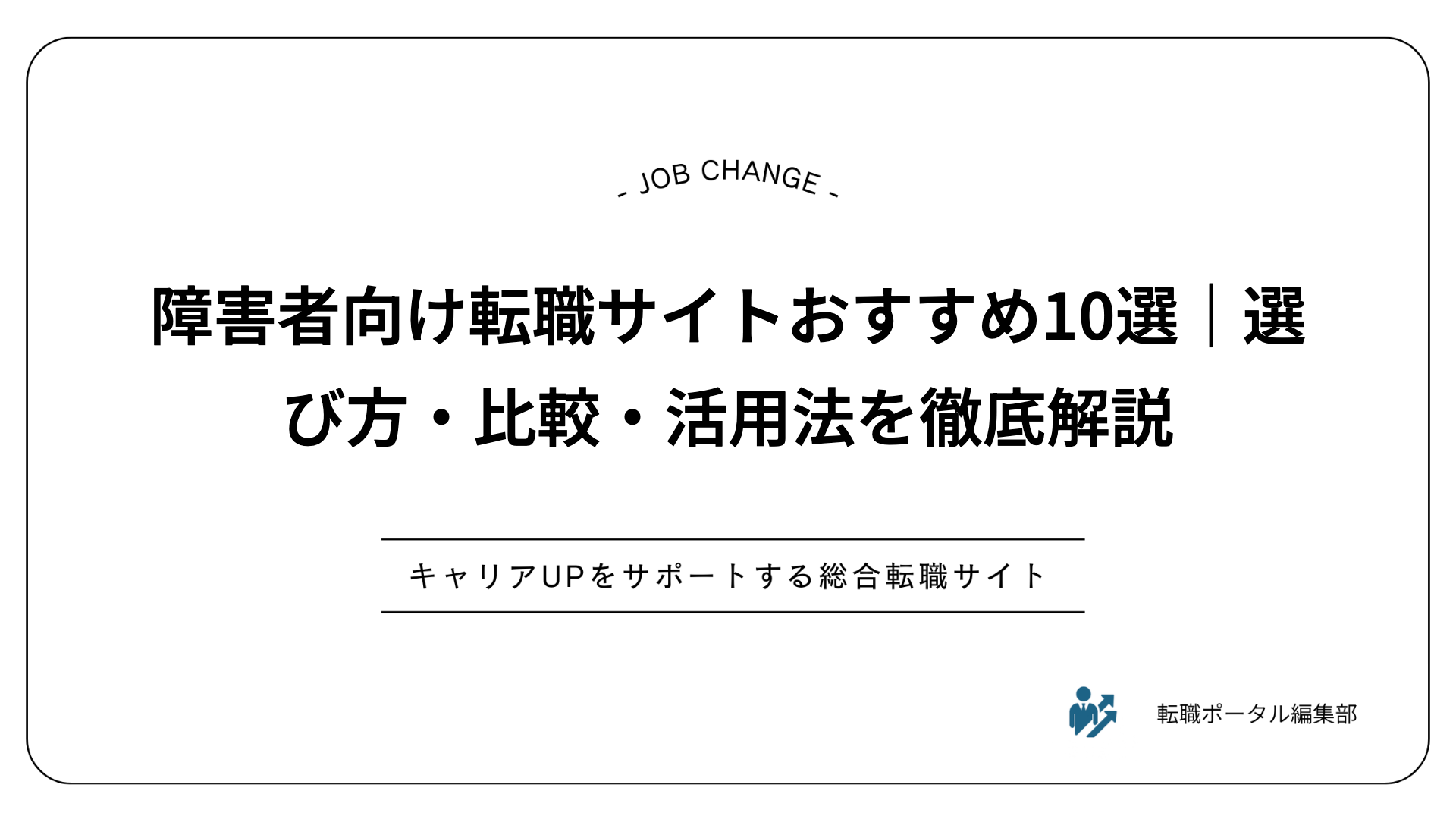障害者の30代転職成功ガイド|失敗しない5つの準備と戦略
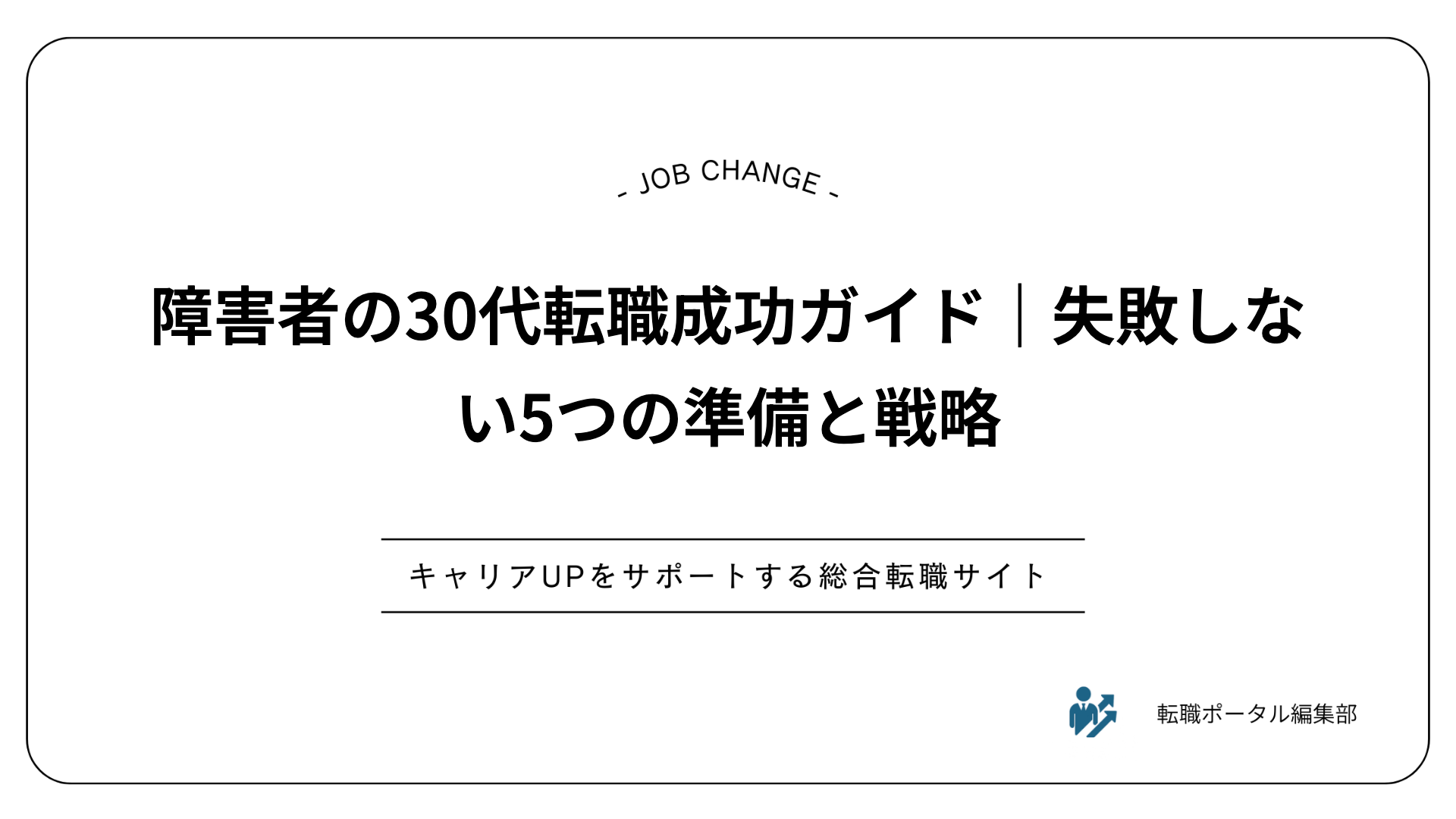
「30代になってからの転職って遅いのかな…」
「障害がある自分に合った職場が見つかるのか不安…」そんな悩みを抱えていませんか?
30代は、これまでの経験と障害への理解を活かして「自分らしい働き方」を実現できるチャンスの年代です。
とはいえ、転職活動では次のような壁にぶつかることも少なくありません。
- 求人の探し方がわからない
- 障害をどう伝えればいいのか悩む
- 面接や応募書類に自信が持てない
- 転職後に長く働けるか不安がある
本記事では、30代の障害者が転職を成功させるために必要な準備・応募のコツ・定着のポイントまでを丁寧に解説します。
この記事を読めば、「自分に合った職場選び」が見えてきて、不安を希望に変える第一歩が踏み出せます。
30代障害者の転職市場の現状
最新の求人動向と雇用率

結論から言えば、障害者の30代転職市場は「ゆるやかに好転している状況」です。
近年、政府の取り組みにより障害者雇用は進展しており、法定雇用率の引き上げにより企業の採用意欲も上がっています。
特に30代は「即戦力」として期待されやすい年代であり、安定的に働ける方へのニーズは高まりつつあります。
- 障害者雇用率は2024年時点で2.5%、2026年には2.7%へ引き上げ予定
- 30代の障害者転職者数は前年比で約110%増
- IT・事務職など障害者向けの求人も増加傾向
たとえば、精神障害者手帳を持つAさんは、障害者雇用枠で大手金融機関の事務職に就職。
職場の配慮とリモート勤務を活かして定着し、2年後にはリーダーポジションに昇進しました。
つまり30代は「経験を活かせる+配慮が得られやすい」世代として注目されているのです。
「自分にはもうチャンスがないのでは…」と不安になる方もいますが、求人傾向を見れば逆です。今こそ積極的に動くべきタイミングといえます。
一般雇用と障害者雇用枠の違い
転職活動を始める前に、「一般雇用」と「障害者雇用枠」の違いを理解しておくことは非常に大切です。
障害者雇用枠は法的な保護の下で配慮を受けながら働ける一方、業務内容や給与、昇進のスピードには一般雇用とは異なる特徴があります。
一般雇用は、障害の有無に関係なく通常の採用選考を受けるスタイルで、職場での配慮は期待しづらい場合が多いです。
一方、障害者雇用枠では、通院や業務内容への配慮が前提として設計されています。
また、給与面では障害者雇用枠の方がスタート時点ではやや低めに設定されるケースもありますが、近年では昇給制度が整った企業も増えています。
30代が転職で求められるスキル・経験

30代の障害者が転職を成功させるためには、「社会人としての基礎力」と「安定して働ける環境作り」が不可欠です。
特に以下のようなスキルや姿勢は、企業から高く評価される傾向にあります。
- 基本的なビジネスマナー(報連相や文書作成など)
- PC操作の基礎(Word、Excelなど)
- チームで働くうえでの協調性
- 自身の体調・障害特性を理解し、安定して就業する力
たとえば、発達障害を持つBさんは、前職での事務経験とExcelスキルを活かして在宅勤務のある職場に転職。
業務内容やコミュニケーションスタイルに配慮を受けながら、安定して活躍しています。
このように、自分の障害特性や強みを言語化できることも、転職成功においては非常に重要です。
転職成功のための事前準備
自分の障害特性と配慮事項を整理する
転職活動を始める前に、最も重要なのが「自己理解を深めること」です。
結論として、障害特性や必要な配慮を整理しておくことで、面接や職場選びの際にミスマッチを防げます。
具体的には以下のようなポイントを明確にしておきましょう。
- 体調の波や通院の有無
- 得意・不得意な業務内容
- 配慮してもらえると助かる点(作業環境、業務量など)
- 過去の職場での成功パターン・苦手パターン
たとえば、聴覚に障害のあるCさんは「電話対応が苦手」という点を明示し、チャットやメールでのコミュニケーション中心の職場を選択。
結果的にストレスなく業務を遂行でき、定着率も高まりました。
「言いづらいかも…」と感じるかもしれませんが、事前に伝えておくことが自分を守るための大切な一歩になります。
キャリアの棚卸しと強みの言語化
転職の準備では、自分の「これまでの経験」と「自信を持てること」を整理しておくことが重要です。
30代になると、何らかの業務経験がある方が多いと思います。それを武器として活かすには「具体的に何ができるか」を言葉にする必要があります。
たとえば、事務職であれば「Excelで請求書作成を月100件対応していた」「5年連続で無遅刻無欠勤だった」など、数字を使って具体的に伝えましょう。
また、業務内容だけでなく「周囲との協調性」や「困難への対処力」といったソフトスキルも、企業は重視しています。
「自分の強みがわからない」という方は、前職の上司や同僚にフィードバックをもらうのもおすすめです。
転職目的とライフプランの明確化

転職活動をスムーズに進めるためには、「なぜ転職したいのか」と「転職後にどうなりたいのか」を明確にしておくことが重要です。
目的が曖昧なままだと、選考で話がブレたり、転職後にミスマッチを感じて後悔する可能性もあります。
- 今の職場に対する不満は何か(例:配慮がない、業務が合わないなど)
- どんな働き方を目指したいか(在宅、通院配慮、残業の有無など)
- 将来的にどんなキャリア・生活を築きたいか
たとえば、在宅勤務を希望するDさんは、「通院しながら働き続けたい」という明確なライフプランを立てた上で転職活動をスタート。
その結果、在宅と出社を組み合わせた柔軟な勤務制度のある企業に内定し、満足度の高い転職を実現しました。
「生活の安定を優先したいのか」「収入アップを狙うのか」「長く働ける職場を探したいのか」──あなたの軸をはっきりさせておくことが、正しい企業選びにつながります。
求人の探し方と応募戦略
ハローワーク・求人サイトの活用法
障害者の転職活動では、求人媒体の選び方によってチャンスの幅が大きく変わります。
結論から言えば、「複数のサービスを併用し、情報を比較しながら進める」のがベストです。
- ハローワーク:地元企業や未経験OKの求人が多く、支援員のサポートも活用可能
- 障害者専門の求人サイト(例:dodaチャレンジ、atGP):障害特性への理解がある企業が中心
- 一般の転職サイト:スキルや経験次第で一般枠応募も可。スカウト機能も便利
たとえば、聴覚障害のあるEさんは、dodaチャレンジ経由で自分の特性に合った求人を見つけ、ハローワークで書類添削を受けて応募。
複数の求人媒体を活用したことで、選択肢が広がりました。
求人サイトだけに頼るのではなく、「支援機関と併用」することで、より納得のいく選択がしやすくなります。
30代に強い転職エージェントの選び方

30代の障害者にとって、転職エージェントの利用は非常に有効です。
特に「キャリアの方向性に迷っている人」や「希望条件が明確な人」には心強い存在です。
おすすめの選び方は、次の3点をチェックすることです。
- 障害者転職に特化しているか(専任アドバイザーがいるか)
- 非公開求人を保有しているか(特に30代向けの事務・IT系など)
- 面談や書類添削などのサポートが丁寧か
たとえば「dodaチャレンジ」や「atGP」などは、障害内容に応じた専任サポートがあるため、安心して利用できます。
登録は無料で、求人紹介だけでなく、履歴書・職務経歴書の添削や模擬面接もしてもらえます。
「1人では心細い…」と感じる人にとって、強力な味方になるでしょう。
スカウトサービス・非公開求人を狙う
最近では、スカウト型の転職支援サービスも増えてきており、企業側から「ぜひ面談したい」というオファーを受けられることがあります。
特に30代は「即戦力+長く働ける人材」として見られるため、スキルや経験がある方ほどスカウトされやすくなります。
スカウトサービスのメリットは以下の通りです。
- 自分では見つけられない非公開求人と出会える
- 事前に自分の特性や希望を伝えられる
- 企業の障害者雇用への理解度が高い
Fさんは、スカウトサイトにプロフィールを丁寧に登録したことで、年収アップ&在宅勤務OKの求人から声がかかり、2社から同時に内定を獲得。
自分で探すよりもスムーズに進んだと話しています。
プロフィール登録時には、スキルの棚卸しと、希望する配慮事項をしっかり明記しておくのが成功のポイントです。
おすすめのスカウト型転職支援サービスはこちら↓
その他のおすすめ転職エージェントは以下にまとめています↓
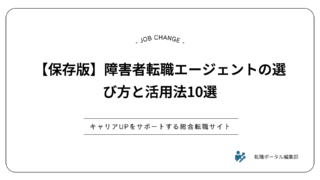
応募書類の作成ポイント
職務経歴書でアピールすべき要素
職務経歴書は、あなたの「これまでの実績とスキル」を企業に伝えるための重要な書類です。
30代の障害者においては、特に「安定的に仕事ができるか」「どんな強みがあるか」を明確に伝えることがポイントです。
- 過去の職務での成果(例:ミスゼロ、月〇件の対応など数字を含める)
- 障害があっても工夫しながら業務を遂行したエピソード
- 勤務継続年数や通院管理の安定性
例えば、「精神的な安定を保ちながら5年間継続勤務し、Excelを使った請求処理を毎月100件以上対応」など、具体性のある実績を記載すると、企業は安心して選考に進めやすくなります。
応募する企業に応じて内容を微調整するのも忘れずに行いましょう。
障害配慮を伝える自己PR例

自己PRでは、ただスキルや長所を並べるだけでなく、「自分の障害とどう向き合いながら仕事に取り組んでいるか」を伝えることが鍵となります。
たとえば、注意力に波がある方であれば「業務をリスト化し、チェック体制を強化する工夫をしてきた」と伝えることで、前向きな印象になります。
また、障害について触れるときは、過度にネガティブにせず、「現状」と「工夫」の2点をバランスよく記載するのがポイントです。
企業は「業務がどこまでできるか」「どんな配慮があれば長く働けるか」を知りたいと考えています。
あくまで安心材料として伝えられるよう意識しましょう。
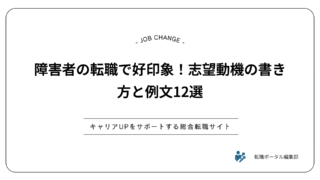
応募書類で避けたいNGパターン
せっかくのアピールがマイナス評価になってしまうのは避けたいところです。次のようなNGパターンには注意しましょう。
- 障害内容を必要以上に詳細に書きすぎる
- 前職を批判的に書いてしまう(例:「配慮がなかった」など)
- 志望動機がどの企業にも通じる抽象的な内容
また、書類全体に統一感がなく、読み手に「整理されていない印象」を与えると選考通過率が下がってしまいます。
文章に自信がない場合は、転職支援サービスで添削を受けるのも有効です。
少しの工夫で、印象が大きく変わります。焦らず丁寧に仕上げましょう。
面接・選考突破のコツ
よく聞かれる質問と回答例

障害者枠での面接では、一般的な質問に加え、障害に関する内容が問われるケースが多くあります。
準備不足だと伝え方に迷い、緊張してしまいがちですが、事前に回答例をイメージしておけば安心です。
- これまでの業務経験について教えてください
- 現在の体調や通院状況について教えてください
- 職場で必要な配慮はありますか?
- 当社でどのように働いていきたいと考えていますか?
たとえば、「週1回の通院がありますが、事前に調整すれば勤務に支障はありません」といった前向きな伝え方が効果的です。
ネガティブな印象を与えず、誠実に答えることを意識しましょう。
配慮事項の伝え方と交渉術
選考の段階で「どこまで配慮事項を伝えるべきか」は多くの方が悩むポイントです。
結論としては、「採用後に困らない範囲で、必要なことは事前に伝える」が最も良いバランスです。
例えば、過集中による疲労が出やすい方であれば「作業を連続して行うより、区切って対応できる環境が望ましい」と伝えます。
これは交渉ではなく、情報共有として伝える意識を持つとスムーズです。
企業にとっても「配慮すべき点」が明確な方が、安心して採用判断ができます。
あらかじめ伝えるべき配慮事項を紙に整理し、面接で活用するのも一つの方法です。
オンライン面接で注意すべき点
オンライン面接が増えている今、通信環境や話し方に注意を払うことが重要です。
特に以下のような点を意識しましょう。
- 背景や照明を整えて顔が見えやすい環境を準備する
- パソコンの通知音やスマホを事前にオフにしておく
- 回答が聞き取りやすいよう、ゆっくりと話す
また、聴覚や発話に不安がある場合は、事前に「チャット機能を併用したい」と伝えておくことで対応してもらえるケースもあります。
面接の内容だけでなく、オンラインならではの「印象」にも気を配ると、評価は大きく変わります。
支援機関・制度の活用
就労移行支援の仕組みと利用方法

就労移行支援は、障害のある方が一般企業へ就職するためのトレーニングやサポートを受けられる福祉サービスです。
20代〜30代の利用者も多く、転職前の準備として活用することで就職率・定着率が高まる傾向にあります。
利用方法は、お住まいの地域の障害福祉課や相談支援事業所に相談するのが第一歩です。通所型の事業所が多く、以下のような支援を受けられます。
- ビジネスマナーやパソコンスキルの訓練
- 履歴書・職務経歴書の作成サポート
- 企業実習や面接同行
- 就職後の定着支援(最長3年)
無料で見学・体験ができる事業所も多く、初めて利用する方でも安心です。
「ブランクがあるけれど就職できるかな…」と感じている方にとって、就労移行支援は非常に頼れる存在です。
地域障害者職業センターのサポート
地域障害者職業センターは、ハローワークと連携して障害者の職業準備や職場定着を支援する公共機関です。
特徴的なのは、専門の職業カウンセラーやジョブコーチによる個別支援が受けられる点です。
具体的には、以下のような支援が提供されます。
- 職業評価(どんな職種が向いているかを分析)
- 模擬職場による訓練(疑似就労体験)
- 企業との調整・定着支援
たとえば、Gさんは「自分に向いている仕事がわからない」と相談し、職業評価と模擬訓練を経て適性がわかったことで、自信を持って就職活動を進めることができました。
全国に設置されているため、まずは最寄りのセンターを検索してみましょう。
助成金・給付金など公的制度

障害者が安心して働けるよう、さまざまな公的制度や給付金が用意されています。
転職活動や就労にあたって活用できる代表的な制度は以下の通りです。
- 障害年金(一定の条件を満たすと在職中も受給可能)
- 自立支援医療(精神通院医療費の自己負担軽減)
- 就労支援機関への利用費支援(移行支援やB型事業所など)
また、企業側にも「障害者雇用納付金制度」や「雇用促進助成金」などがあるため、積極的に採用されやすい背景もあります。
こうした制度を理解しておくことで、経済的な不安を減らしながら転職活動を進めることができます。
「何を使えるかよく分からない…」という方は、市区町村の福祉窓口か障害者就業・生活支援センターでの相談が有効です。
障害種別の転職アドバイス
身体障害のある30代向けポイント
身体障害のある方にとって、転職活動では「物理的な環境への配慮」が最も重要なポイントとなります。
結論として、通勤・業務遂行に支障がない職場環境を選ぶことが、長く働き続けるためのカギです。
- バリアフリーなオフィスか(エレベーター・手すり・段差の有無)
- 在宅勤務制度が利用できるか
- トイレ・移動時の導線に不安がないか
たとえば、下肢に障害のあるHさんは、在宅勤務と週1出社のハイブリッド制度を導入している企業に転職。
出社時もバリアフリーな環境が整っており、ストレスなく勤務を続けられています。
見学や面接の際には、オフィス環境について具体的に確認することがとても大切です。
精神障害・発達障害のある30代向けポイント
精神障害や発達障害のある方にとっては、「安定して働けるペース」と「対人関係の配慮」が特に重要です。
結論として、業務の見通しが立てやすく、コミュニケーションに柔軟な理解がある職場を選ぶと、職場定着につながります。
以下のようなポイントを確認しておくと安心です。
- 仕事内容が明確で、ルーティンが中心であるか
- 感情労働(接客・電話対応など)の頻度が低いか
- 相談しやすい上司やジョブコーチがいるか
たとえば、発達障害のIさんは、スケジュールの見通しが立てにくい業務に苦手意識がありましたが、「日次ルーチンが中心で1人作業多め」の求人に転職。
業務量も明確で、安心して働けているそうです。
自己理解を深めたうえで、マッチする職種や職場環境を選びましょう。
内部障害・難病のある30代向けポイント

内部障害や難病のある方は、見た目では障害が分かりにくいため、周囲とのギャップを感じやすいという声も多くあります。
このため、転職時には「定期的な通院や体調の変動に理解のある職場」を選ぶことがとても大切です。
重要なチェックポイントには、以下のようなものがあります。
- 通院配慮(勤務時間の調整や有休取得のしやすさ)
- フレックスタイム制度や在宅勤務の可否
- 定期的な体調報告を許容する文化
Jさんは腎臓に疾患を抱えており、週に数回の通院が必要でしたが、出勤時間を柔軟に調整できる企業に就職。
配慮を得られたことで長期的な就労が実現しました。
内部障害や難病こそ、「理解のある環境」とのマッチングが大きなカギになります。
成功事例から学ぶ
IT業界への転職成功ストーリー
30代で障害を抱えながらも、IT業界へ転職し活躍している事例は増えてきています。
特にプログラミングやWeb制作など、在宅ワークと相性が良い職種では、スキルと努力次第で大きな成果を出せるチャンスがあります。
たとえば、精神障害を持つKさんは、就労移行支援で基礎からプログラミングを学び、在宅可のWeb制作会社に内定。
入社後もスケジュール管理のサポートや業務の見える化によって安定して活躍しています。
IT業界はスキルさえあれば成果で評価されるため、「対人関係の不安がある方」や「通勤が負担になる方」にとっても可能性の高い分野です。
完全在宅ワークで活躍する事例

在宅勤務は、障害の特性により「外出や通勤が困難な方」にとって非常に有効な働き方です。
- 通勤による体力的・精神的負担がない
- 体調に合わせて柔軟に業務を調整できる
- 自宅環境に合わせた業務遂行が可能
Lさんは難病の影響で疲労感が強く、通勤が困難でしたが、求人サイト経由で完全在宅のカスタマーサポート職に応募し、現在はフルリモートで勤務。
職場とのチャットでのやりとりが中心で、無理なく業務に取り組めています。
近年は障害者雇用でも在宅可の求人が増えており、自分の生活リズムを崩さずに働ける選択肢として注目されています。
管理職ポジションに挑戦した事例
障害があっても、経験と信頼を積み重ねて管理職へキャリアアップしていく事例もあります。
特に30代は、「プレイヤーからマネジメント」へと役割が広がるタイミング。
適切な職場と巡り合えれば、障害を理由にキャリアを諦める必要はありません。
Mさんは、精神障害を開示したうえで大手メーカーに入社し、5年の現場経験を経てチームリーダーに昇格。
週1回のフォロー面談と業務調整により、無理なくマネジメント業務も担えるようになりました。
管理職を目指すうえでは、「自分から相談できる関係性」や「体調を把握してもらえる職場文化」があるかも重要です。
これらの成功事例の多くはエージェント経由での転職よるものです。ぜひ自分に合ったサービスを以下の記事から見つけてください↓
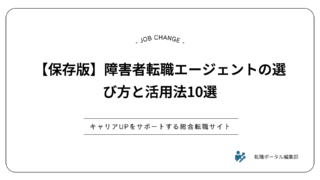
転職後に定着・キャリアアップする方法
入社後6か月のフォローアップ対策
転職後の最初の6か月は、環境への適応や業務習得において最も重要な期間です。
結論から言えば、「職場との連携」と「自分の状態の把握」が定着成功のカギとなります。
- 定期的な上司との1on1面談を依頼する
- 体調や不安がある時は早めに報告する
- 業務内容の進捗や困りごとをこまめに共有する
たとえば、入社後すぐに不安定な時期があったNさんは、ジョブコーチを通じて企業に状況を共有し、業務量を一時的に調整。
復調後は本来のパフォーマンスを発揮し、上司からも高評価を得られました。
「できないこと」を責めるのではなく、「相談できる関係」を築くことが大切です。
スキルアップと資格取得の計画

30代からのキャリアアップには、着実なスキルの積み上げが効果的です。
転職後に安定して働けるようになったら、次のステップとして「できる業務を広げる」「業界内での強みを持つ」ことを目指してみましょう。
おすすめのスキルアップ方法としては、以下のような手段があります。
- 通信講座・eラーニングでの学習(例:MOS、簿記、Pythonなど)
- 社内研修への積極的な参加
- 資格試験へのチャレンジ
Oさんは、事務職で入社後に「MOS Excel資格」を取得し、業務効率化に貢献。その結果、社内表彰や給与アップの評価にもつながりました。
「できることを少しずつ増やす」ことが、将来の選択肢を広げる一歩になります。
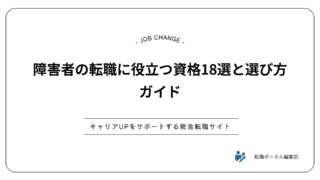
合理的配慮を継続的に受けるコツ
転職後も合理的配慮を継続して受け続けるには、「定期的な振り返り」と「職場との対話」が欠かせません。
一度決まった配慮内容も、業務や体調の変化によって再調整が必要になることがあります。
そのため、以下のような習慣を取り入れることをおすすめします。
- 月に1回、自己チェックの時間を設けて体調・業務負荷を振り返る
- 配慮内容に変化が必要な場合は、上司に報告して話し合う
- 相談しやすい関係性や雰囲気づくりを意識する
実際に、Pさんは入社後3か月を経て業務内容が変わり、「集中力が落ちやすくなった」と感じたため、週1回の業務分担見直しミーティングを提案。
結果として無理なく仕事を続けられています。
配慮は一方通行ではなく、「企業と一緒に作っていくもの」と捉えることが、安定した働き方につながります。
まとめ:30代だからこそ障害と向き合い、自分らしい転職を実現しよう
30代の障害者にとって、転職はキャリアを再構築する大きなチャンスです。
障害があっても、「自己理解・事前準備・適切なサポートの活用」を行うことで、自分らしい働き方と安定したキャリアを築くことができます。
本記事では以下のようなポイントを押さえてきました。
- 30代は即戦力として期待される年代で、障害者雇用市場も拡大中
- 自己理解とキャリアの棚卸しが転職成功の土台になる
- 支援機関や転職エージェントの活用でミスマッチを防げる
- 障害種別ごとに異なる転職戦略を取ることが大切
- 転職後も定着とキャリアアップには継続的な工夫と対話が必要
30代という年齢は、「経験」と「柔軟さ」のバランスが取れた強みを活かしやすい時期です。
不安を抱えすぎず、まずは一歩踏み出すことが、未来の選択肢を広げる第一歩になります。
あなたの経験と特性を活かし、無理なく自分らしく働ける職場は、きっと見つかります。
障害者からの転職を成功させる詳しい方法はこちら↓
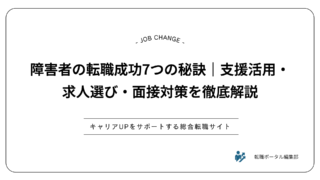
障害者の転職におすすめのサイト・エージェントはこちら↓